刻々と状況が変わり続ける現代において、どのような生き方や仕事をしていくべきかヒントを教えてくれるビジネス本。
この記事では、各界で活躍する読書好きビジネスパーソンに教えてもらった「おすすめのビジネス書」を、お金・時間術・経営・人間関係の悩み解決・自分を変える方法などのジャンルごとに52冊ご紹介します!
様々な観点から役に立つ情報や知識を教えてくれる本ばかり。特に新しい学びの多い20,30,40代の社会人は必読です!
目次
お金・投資についての知識が身につく
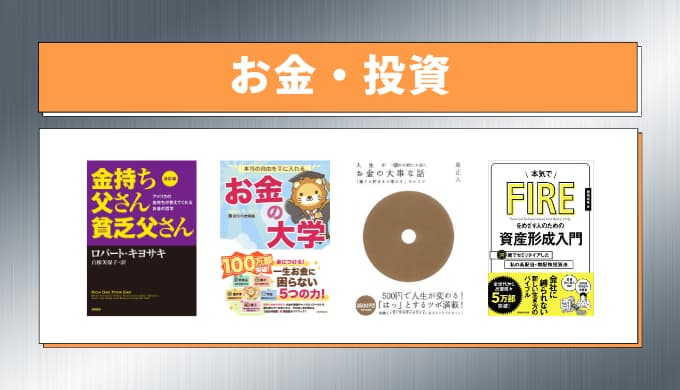
1位『金持ち父さん貧乏父さん』ロバート・キヨサキ
 Hi
Hi
学校教育だけをし続けていても社会に出たときにお金をうまく活用することができないことがほとんどで、それについては自分で学んでいかなくてはならない。
働くこととお金の関係性はどうなのか?お金に関して学ぶとなったら真っ先に読むべき1冊!
 ケン
ケン
自分が働いた分だけ、自分の価値に応じてお金をもらえる(時間を切り売り)貧乏父さんの考えと、お金を生み出すシステムや仕組みを所有することで、自分が働かなくてもお金を稼げる金持ち父さんの考え方の違いがよくわかる。
その上で自分が進みたい方向を定めることができる。
この本は…金持ちになるためにはたくさん稼ぐ必要があるという「神話」をくつがえす。持ち家が資産だという「信仰」を揺るがす。資産と負債の違いをはっきりさせる。お金について教えるのに、学校教育があてにできないことを親にわからせる。そして、お金について子供たちに何を教えたらいいかを教えてくれる。
2位『本当の自由を手に入れる お金の大学』両@リベ大学長
 effort_gogo
effort_gogo
筆者は学生時代に起業し、30代の若さでミリオネアの地位を揺るぎないものにしている両学長。
そんな両学長が「お金のプロ」として、お金にまつわるすべての知識を惜しみなく提供してくれます。
貯金、投資術、節約術、必要な保険等、とにかくお金にまつわるあらゆるノウハウが詰まっています。
本書こそ、全人類に必携の書です。
お金を無駄に垂れ流すことも、「投資は危ない」という妄言に惑わされることもなくなります。
私は本書の通り実践したところ、1年で資産が2倍になりました。
お金に困っている人も、漠然とお金を貯めないといけないと思っている方も、ぜひ手に取って試してみていただきたいです。
貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う―一生お金に困らない5つの力が身につく実践型ガイドブック。
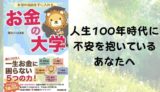 『本当の自由を手に入れる お金の大学』あらすじと感想【人生100年時代に不安を抱いているあなたへ】
『本当の自由を手に入れる お金の大学』あらすじと感想【人生100年時代に不安を抱いているあなたへ】
3位『お金の大事な話』泉正人


「お金を増やす能力は、運動神経と同じもの」
学校教育では誰も教えてくれないお金の正しい扱い方について丁寧に詳しく説明されているハウツー本です。
資産と負債の違いや、キャッシュフローの重要性など、知っているだけで得する知識から、お金が働く仕組みを作りだす為のマインドセットの方法まで、この1冊で「お金」の大枠を掴めるようになっています。
投資をしてみたいけど踏み出せない方や、貯蓄が上手く出来なくて困っている方は一度手に取って読んでみてください。
知識よりも、テクニックよりも、あるコツをつかむこと。500円で人生が変わる、「はっ」とするツボ満載。
4位『本気でFIREをめざす人のための資産形成入門』穂高唯希


「Financial Independent and Retire Early」、つまり「働かなくてもお金に困らない状態を人生の早期に実現する」という意味です。
莫大な土地を持っていて、アパートからの家賃収入だけで生きているとか、ああいう人たちのことです。
本書の著者・穂高唯希氏は、莫大な資産を持っていたわけでもないにも関わらず、わずか30歳でFIREを達成しというツワモノです。
「そんなの高給取りにしかできないだろう」と思われるかもしれません。
確かに穂高氏は三菱系のサラリーマンであり、給与は高そうです。
しかし、彼のすごいところはその徹底的な節約術にあります。
彼は毎日会社に飲み物と弁当を持参、ジムに通う代わりにエレベーターを使わず階段を利用していました。
極めつけは恋人とのデートは公園でのピクニックデート(もちろんお弁当持参)がほとんどだったそうです。
とにかく徹底的に節約をし、浮いたお金でせっせと米国の高配当株を購入していたんだとか。
そうして購入した株から毎年振り込まれる配当金が生活費を超えている=働かずして経済的に自立、というわけです。
節約術と、米国高配当株の投資商品としての魅力をしっかり理解できる一冊になっています!
初心者から本気でFIREしたい人まで、日本版FIREムーブメントの先駆者が、誰でもできる投資法、教えます!FIRE→労働に縛られない新しいライフスタイル。
時間の使い方が上手くなる
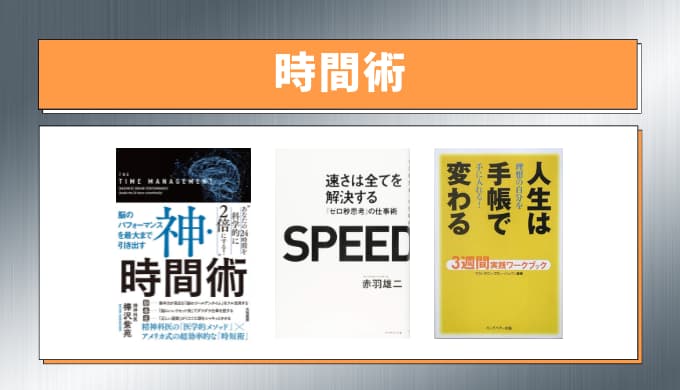
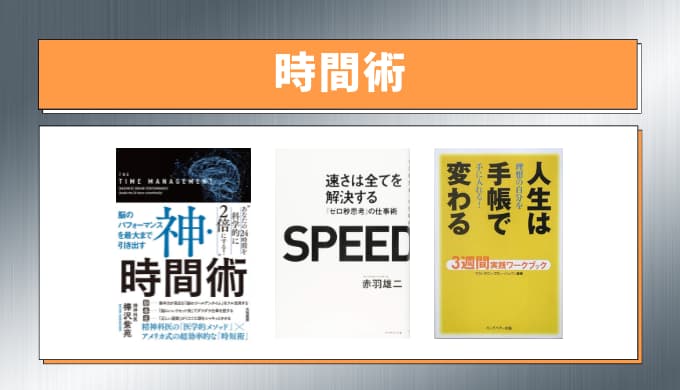
1位『神・時間術』樺沢紫苑


本書は意図的にパフォーマンスを向上させる本です。
「朝起きてから2.5時間が脳のゴールデンタイムであり、睡眠直前の思考が定着しやすいため、人格に影響する」など、自分の脳を客観視して、上手く付き合っていくそんな本です。
限りある時間を有効に使いたい人におすすめです。
これが、“最高の生産性”を叩き出す極意! 精神科医が明かす、「脳科学に基づく集中力の使い方」×「アメリカ仕込みの時間術」で、あなたの24時間を2倍に増やす最強メソッド! 「時間の使い方」は、あなたの「人生の使い方」だ!
2位『速さは全てを解決するゼロ秒思考の仕事術』赤羽雄二


プレゼンに失敗したのは、準備する時間を確保できなかったから。
契約を取れなかったのは、営業トークを磨いている時間が取れなかったから。
大好きなあの人と結婚できなかったのは、ゆっくりコミュニケーションを取る時間がなかったから。
本書は「時間がない」が口癖の現代人の業務の実態に、鋭利なナイフで切りこんでくるようなビジネス書になっています。
なぜ仕事が遅いのか?
では仕事をとっとと終わらせるにはどうすればいいのか?
仕事のスピードを各段に上げるノウハウを、世界最強のコンサルティングファーム・マッキンゼー出身の著者が超ロジカルに教えてくれます。
机上の空論ではなく、「単語登録しまくれ」「メールは速攻返せ」のような、細かなビジネステクニックが書いてあるのでめちゃくちゃ参考になります。
本書で紹介されているテクニックをちゃんと実践すれば、17:00退社も夢ではありません!
マッキンゼーで14年間活躍した著者が明かす、仕事のスピードを極限まで上げる哲学とノウハウ。
3位『人生は手帳で変わる』フランクリン・コヴィー・ジャパン


ブレない自分軸と、理想の自分を見つけ出すことができる。
毎日を何となく生きている人や、将来に希望が見出せていない人は絶対にやるべき。
あなたが理想の自分を手に入れるための、タイム・マネジメントのポイントを3週間で学んでいくワークブック。
リーダー・経営者なら読んでおきたい
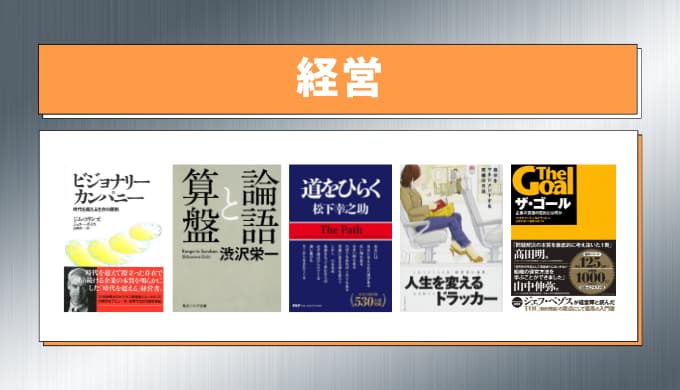
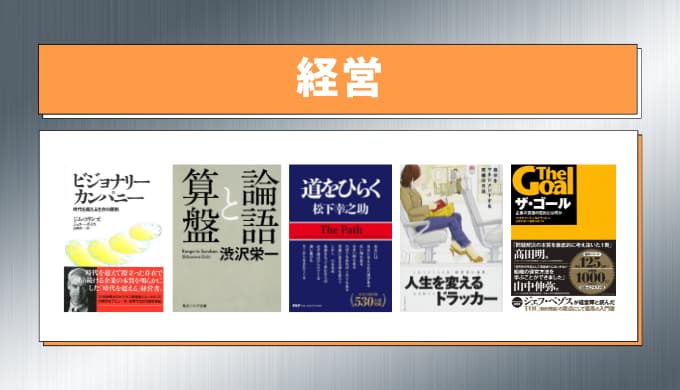
1位『ビジョナリー・カンパニー』ジム・コリンズ


「時代を超える生存の原則」の副題の通り、サバイブする企業の条件を徹底して突き詰めた経営者のバイブル的ベストセラー。
1995年に書かれた”古典”ですが、長く成功した企業に共通するものは今も変わっていません。
変化しないとそもそも成長は起きませんが、全てを変化させるのではなく、理念以外を変化させることが大事。
新しい価値を創造するには既存の問題を乗り越えるジレンマが伴いますが、そこでありがちな二者択一ではなく、「両方正解を追い求める姿勢が大事」というのは目を見張らされる考え方です。そして、従業員にその理念を徹底させることも大切。
ビジネスを新たに興したい人やビジネスに従事する人はもちろん、投資を始めたい人も得られるものがあるでしょう。
本書は、アメリカの主要企業のCEOから採ったアンケートによって選び出された18社の歴史に対する6年間の調査から生み出されたレポート。企業を組織する人間が企業内に活力を生み出すのは、カネでは計れない動機づけにあるというシンプルな「真理」が、ライバル企業と比較された各社の資料、エピソードから浮き彫りにされる。
2位『論語と算盤』渋沢栄一


多くの有名企業の草創期に関わってきた明治期の伝説的人物・渋沢栄一。
彼の経営方針は、「道徳と経営は合一すべきである」というシンプルなもの。
「算盤」は文字通り、利益を追求する資本主義経済を示す一方、儒家・孔子の「論語」は利益に偏りすぎない道徳を表します。
その証拠に渋沢は約500の会社の設立に関わるだけでなく、約600もの社会福祉事業にも携わっていました。哲学者ガブリエルの”倫理資本主義”の思想を100年前に先んじ、実践していたのです。
利益追求に溺れるあまり、非人道的な差別や不祥事にまみれ、腐敗した日本企業の精神を正すための必読書。
ビジネスを成功させる秘訣は論語にある。日本実業界の父が語る必読の名著。
3位『道をひらく』松下幸之助
#累計400万部超


「経営の神様」と謳われた伝説的人物、松下電器の創業者・松下幸之助による名言録。
数ある名言がひとこと形式で載っているため、いつでもどこでも読みやすいのが特徴です。
この本に一貫するのは「人を大事にすること」の大切さ!最近の合理主義一辺倒の冷徹なビジネス書と一線を画しているのは、そうした”心”が随所に感じられるところです。
愛と思いやりに溢れた熱く優れた想いこそが、当時の貧しい日本を引っ張っていく原動力になったことがよく分かります。なにより同じ日本人の言葉であるというのは大変勇気づけられますね。
自信を失ったとき、困難にぶつかったとき、新しい挑戦のとき、この本は珠玉の一冊となるでしょう!
事業の成功者であり、それ以上に人生の成功者である松下幸之助であればこそ、その言葉には千鈞の重みがある。あらゆる年代、職種の人に役立つ、永遠の座右の書である。
4位『人生を変えるドラッカー』吉田麻子


OLや営業マン、カフェのオーナー達が読書会に参加します。『経営者の条件』を読み、お互いに学びや刺激をもらいながら、各人のフィールドで実践し成長していくお話です。
仕事のノウハウを理解できることに加えて、読み終えた後に具体的にどう行動すれば良いか、イメージしやすいと思います。
仕事を通じて、あなたも登場人物と一緒に成長しませんか?
社長に叱られ自信喪失のOL青柳夏子、成績不振に悩む営業マン杉並柊介、脱サラ起業がうまくいかずキリキリ舞いの堀川徹…それぞれの壁を、彼らはどう乗り越えたか?ドラッカーの世界的名著『経営者の条件』が、小説仕立てでやさしくわかる!
5位『ザ・ゴール』エリヤフ・ゴールドラット


現代のほとんどの必需品が工場で大量生産される以上、ほとんどのビジネス分野に関わり、向き合う必要のある「生産管理」について取り上げられています。
日本企業の牽制のために和訳が禁止されていたことから伺える通り、内容の本質さはほとんど”教科書”であり、あまりに王道でスタンダードな手法が書かれています。
専門用語も飛び出しますが、要は効率性を上げるにはボトルネック(詰まっている箇所)の手当てが肝心だという話です。
工場以外のビジネス構造でも応用が効く理論で、今となってはもはや足枷になっている部分でもありますが、いずれにしても必読でしょう。
小説仕立てなので、ガチガチのビジネス書が苦手な方にもとっつきやすいのも魅力的です。
主人公アレックス・ロゴは、ある機械メーカーの工場長。長引く採算悪化を理由に、突然、本社から工場閉鎖を告げられる。残された時間は、わずかに3か月。それまでに収益体制を改善しなければ、工場は閉鎖され、多くの人が職を失ってしまうことになる。半ば諦めかけていた彼だったが、学生時代の恩師ジョナに偶然再会したことをきっかけに、工場再建へ向けて意欲を燃やし始める。ジョナは、これまでの生産現場での常識を覆す考え方で、彼の工場が抱える諸問題を次々に科学的に解明していく。そのヒントをもとに工場の仲間たちとたゆまぬ努力を続け、超多忙な日々を過ごす彼だった。だが、あまりにも家庭を犠牲にしてきたため、妻であるジュリーは彼の前から姿を消してしまう。仕事ばかりか、別居、離婚という家庭崩壊の危機にもさらされたアレックスは…。
世界の大手企業からビジネスの最先端を学ぶ
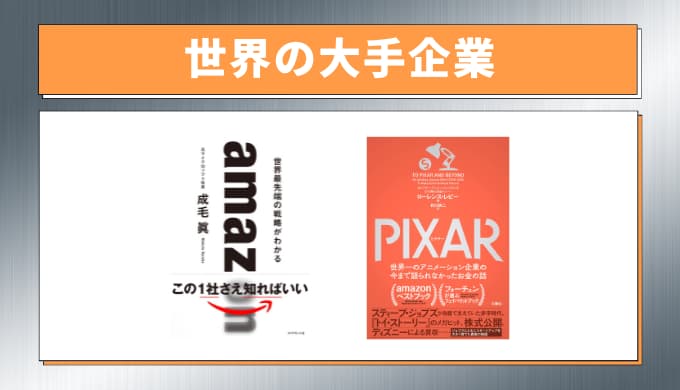
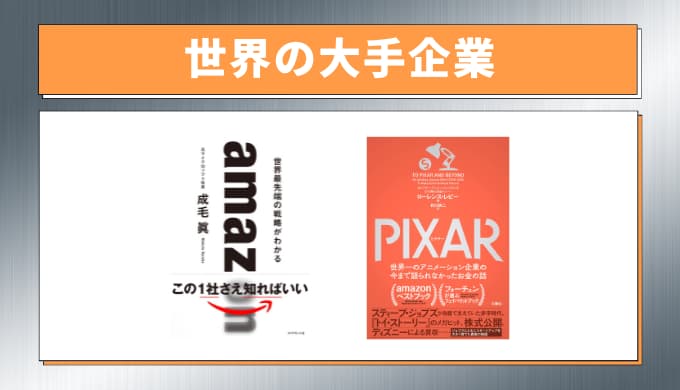
1位『amazon 世界最先端の戦略がわかる』成毛眞


数年後、Amazonの荷物は空から降ってくる?
アメリカ「GAFA」の一角のAmazonがもたらした革命。普段何気なく使うAmazonは、今後もライフスタイルに溶け込んでくる。
なぜアメリカでは4人に1人がプライム会員に入るほどの支持があり、なぜCIAやNASA、政府機関までもがAmazonの顧客となっているのか?
プライムサービス、クラウドサービスを可能にする仕組みとは?
Amazonの戦略は今後の日本にも革命を起こしていく。
「何が勝って、負けるのか」ビジネスの基礎知識も身につく!この一社を知ることは、最新のビジネス感覚を身につけることと同じ。
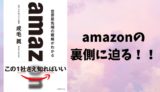
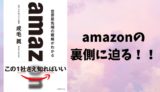
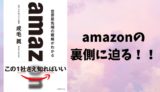
2位『PIXAR 〈ピクサー〉』ローレンス・レビー


数あるディズニー映画のなかでも『トイ・ストーリー』などのピクサーCG作品に親しんだ人は少なくないでしょう。
その点で敷居が低く、読んでいるうちに自分が社屋に立ち入った気分になれる稀有なビジネス書が本作です。
というのも、1994年からピクサーの経営戦略に携わった著者の生々しい実体験が読みやすい筆致で書かれているから。
テーマはズバリ「創造性と現実にどう折り合いをつけるか」!
いくら高い理想を掲げても、現実には果たさなければいけない商業的目標とのジレンマがあります。
紆余曲折と創業メンバーたちの葛藤、誰も予想し得なかったほどの成功を経て、著者はついに「中道」の思想を見出します。仏教精神がカリフォルニアで再発見されたことに驚くことでしょう。
アップルを追放されたスティーブ・ジョブズとともに、スタートアップを大きく育てた真実の物語!
イノベーションを起こす方法が知りたい
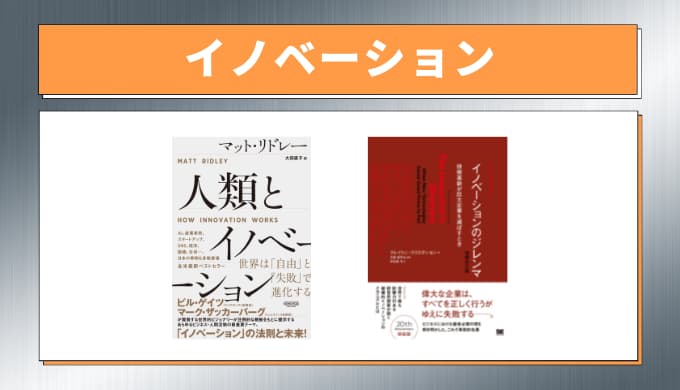
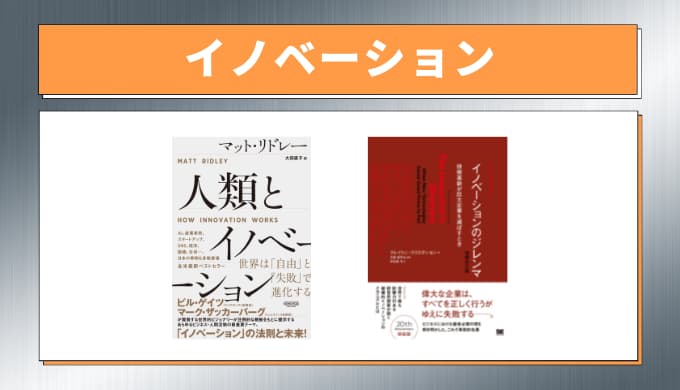
1位『人類とイノベーション』マット・リドレー


「我が社は一丸となってイノベーションを目指します」すっかり当たり前に使われるようになった代表的な横文字ですが、そもそもイノベーションの本当の意味がわかっている人は少ないでしょう。
イノベーションはラッキーパンチのような偶然のまぐれ当たりや天才の閃きではなく、多くの人の無数の失敗と試行錯誤の積み重ねの結果で、いわば生物進化のようなもの。そのシビアな泥臭さを理解しないと、とんでもない方向に行く。
近年のイノベーションの代表例、EV・AI・ワクチンをとっても、それぞれの分野で50年以上の苦難の歴史がある。だから、”人類”とイノベーションなのです。
あらゆるビジネス・人間活動における最大の課題「イノベーション」の本質と未来を解き明かす!
2位『イノベーションのジレンマ』クレイトン・クリステンセン


新たな発明と経済発展、それは必ずイノベーションとともに起こるもの。
では、なぜイノベーションはなかなか起きないのでしょうか?イノベーションが起きるにはどのような条件が必要なのでしょう?
また、大企業よりベンチャー企業のほうがイノベーションを起こしやすいのはなぜなのか?
こうした疑問にシンプルに答え、GAFAの台頭をも予見していたのが1997年に刊行されたこの名著です。
保守的な大企業にとって、目ぼしいアイディアの種は過小評価されるだけでなく、既存事業の脅威に映ることさえあり、そのジレンマを解決しなければならないと著者は主張します。
あらゆる分野に応用可能であり、日本経済がなぜ停滞したままなのか、理由がよくわかるでしょう。
「偉大な企業はすべてを正しく行うが故に失敗する」業界トップ企業が、顧客の意見に耳を傾け、新技術に投資しても、なお技術や市場構造の破壊的変化に直面した際、市場のリーダーシップを失ってしまう現象に対し、初めて明確な解を与えたのが本書である。
人間関係やコミュニケーションの悩みを解決したい
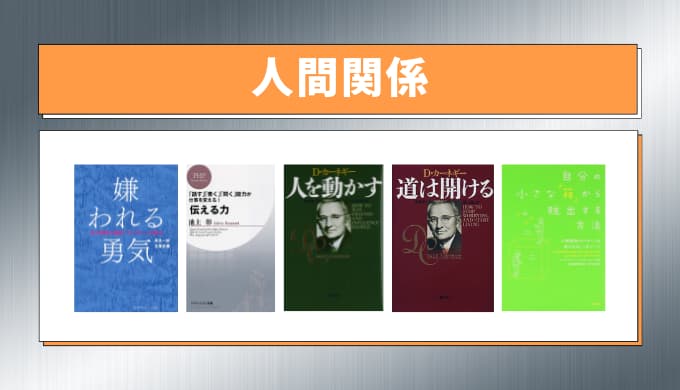
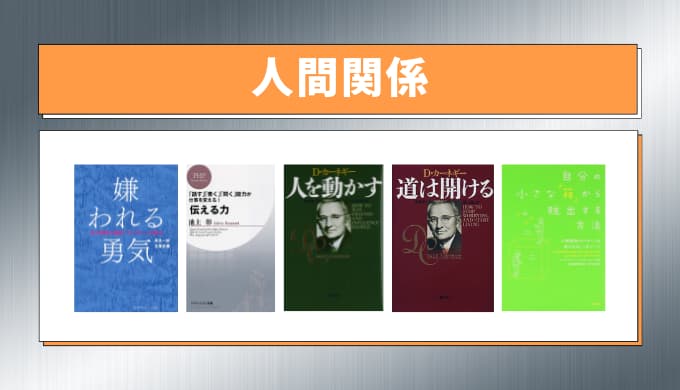
1位『嫌われる勇気』岸見一郎/古賀史健


最近では、「好きなことで生きていく」というフレーズがよく使われるようになりました。
でも、自分の好きなことで生きていくにもハードルがいくつかあります。金銭面的な問題であったり、精神面的な問題であったりなど。
本書は精神面、とくに「こんなことしたら周りはどう思うかなー」と周りの目を気にする人に読んでもらいたい本です。
あなたがどんなことをしても、それを「良い」と思う人もいれば、「悪い」と思う人もいます。でも、そのような感想はあなたの問題ではなく、相手の問題です。
相手の問題は変えられません。というようなことが本書で述べれており、実践できればストレスフリーの生活ができると思います。


誰もが抱く対人関係の悩みをぶった切る。
青年と哲人の対話形式によって、心地良いリアル感を出してくれています。
「劣等感」や「承認欲求」を否定し、自分らしく生きるにはどうすれば良いのか?アドラーの言葉を哲人が丁寧に紐解き、教えてくれます。
青年の抱える悩みは普遍的で感情移入がしやすいので、自分ごと化しやすく、すぐに思考や行動を改めることができます。
自分の考え方を変えるだけで世界はまるで違う。人は皆幸せになれる。幸せになりましょう!
本書は、フロイト、ユングと並び「心理学の三大巨頭」と称される、アルフレッド・アドラーの思想(アドラー心理学)を、「青年と哲人の対話篇」という物語形式を用いてまとめた一冊です。欧米で絶大な支持を誇るアドラー心理学は、「どうすれば人は幸せに生きることができるか」という哲学的な問いに、きわめてシンプルかつ具体的な“答え”を提示します。この世界のひとつの真理とも言うべき、アドラーの思想を知って、あなたのこれからの人生はどう変わるのか?もしくは、なにも変わらないのか…。さあ、青年と共に「扉」の先へと進みましょう―。
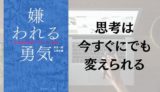
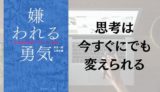
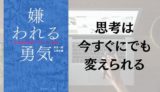
2位『伝える力』池上彰


今の日本において、話のわかりやすさで池上彰の右に出る者はいないでしょう。
政治・経済・法律・国際社会、地理や歴史、社会問題、新型コロナウイルスなど最新サイエンスに至るまで、難しい内容を平たくかみ砕く能力はピカイチ!
本書では惜しむことなくその奥義を披露し、効果的な伝え方や、伝えるべきポイントを徹底的にわかりやすく指南してくれます。
「相手の話をよく聞くこと」「まず自分が納得すること」が大事だという指摘は至極うなづけます。
この本のワザをものにすれば、明日から学校や職場であなたのプレゼンがわかりやすくなること間違いなし!
相手を惹きつける、ビジネス文書を書く、文章力をアップさせるなど、本書の秘訣を習得すれば、仕事が楽しく、やりやすくなること間違いなしだ。
3位『人を動かす』デール・カーネギー


古典から普遍的なコミュニケーションメソッドを学びましょう。
この本に倣い、苦手な上司にあえて「小さな頼みごと」をしました。知恵を頼ったことで有用感をプレゼントできたようで、「待ってました!」とばかりに話してくれたものです。
私はただ聞いていただけなのに、なぜか「有能なヤツ」だと評価してもらえたオマケつき。
ただしこれを小手先のテクニックとして使っては意味を失います。我々は人間としての在り方を問われているのです。
社会人として身につけるべき人間関係の原則を具体的に明示して、あらゆる自己啓発本の原点となった不朽の名著。
4位『道は開ける』デール・カーネギー


カーネギーの本はいくつかオススメがありますが、本書もとてもオススメできるものです。
1つ1つが小さな短編になっており、とても読みやすく、気になるところから読むのがオススメの読み方です。
また、この本をオススメする最大の理由ですが、本書では具体例が「想像の一歩上」をいくからです。
「そんな状況に比べたら自分の状況って大したことないな」と考えられ、前向きに行動できるようになるでしょう!
悩みの正体を明らかにし、悩みを解決する原則を具体的に明示して、こころの闇に光を与える不朽の名著。
5位『自分の小さな箱から脱出する方法』
#世界150万部 #GoogleやAppleが研修に採用
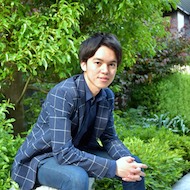
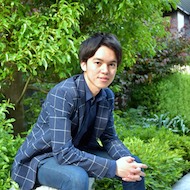
身の回りで起こる人間関係の問題は、おおよそ自分自身が引き起こしている。
そんな状態に気づかずに「箱」に閉じこもった人たちの実例が物語形式で展開される。
本著のいう「箱」とは自己欺瞞のこと。その箱から脱出し、「相手目線の行動をとる」という、一見当たり前の様なことが意外にも出来ていないという事実に、ハッとさせられるかもしれない。
身近な友人関係から組織のマネジメントまで、悩みを抱える全ての人に学びと気づきを与える1冊。
読み進めるうちに、家庭や職場での人間関係を深め、十分な成果を出す環境を作る方法を学べる。世界的ベストセラーであり、日本でも25万人が読んで大反響を巻き起こした名著。
予言の書から人類の未来を知りたい
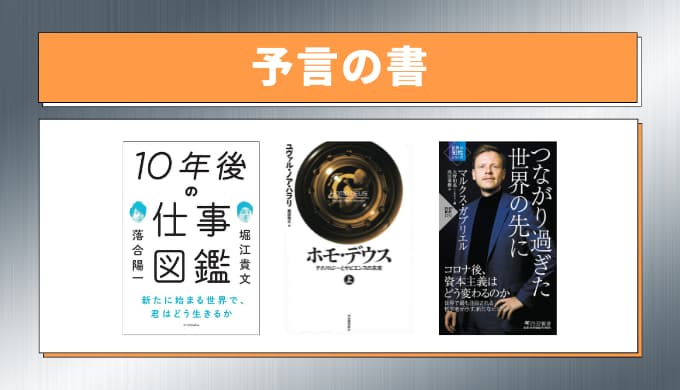
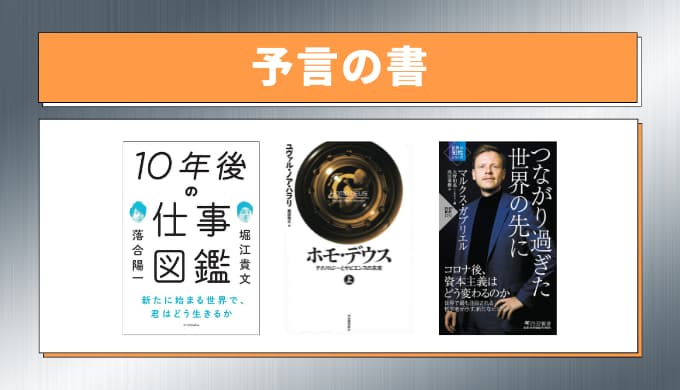
1位『10年後の仕事図鑑』堀江貴文/落合陽一


「そもそも働くって何だろう?」という根本から考えさせられる1冊。
未来のことを予想していても仕方がない。「今できることをやる」ということがどれだけ重要か学ぶことができる。
著名な2人のやりとりから、「今後の日本がどうなるか?」という予想も交えながら面白みを持って読める本だ。
AI、仮想通貨、モチベーション格差、46の仕事、働き方―。新たに始まる世界で、君はどう生きるか。
2位『ホモ・デウス』ユヴァル・ノア・ハラリ


プロに触れる、抽象化の最高峰であるこの本を読んでマクロ的な視点を入手する。
我々は不死と幸福、神性を目指し、ホモ・デウス(神のヒト)へと自らをアップグレードする。そのとき、格差は想像を絶するものとなる。『サピエンス全史』の著者が描く衝撃の未来。
3位『つながり過ぎた世界の先に』マルクス・ガブリエル


新型コロナの被害は欧米の方がはるかにシビアでしたがドイツも例外ではなく、ワクチン開発の立役者になった一方で、科学過信による対応の致命的な遅れも経験した著者。
現代の資本主義や科学中心主義を痛烈に批判してきた著者にとって、今回のパンデミックの一因は「統計的世界観の盲信」による誤りだと強く断じています。
また、一般向けの本書はタイトルの通り、インターネットやSNSで過剰につながりを持ちすぎた世界に警鐘を鳴らし、倫理と利益追求を合わせた「倫理資本主義」を提唱。
複雑な21世紀の時代に新たに求められる考え方とは何か。頭を解きほぐしてくれる一冊です!
「COVID-19の蔓延により、おそらく人類史上初めて、世界中で人間の行動の完全な同期がみられた」と哲学者マルクス・ガブリエルはいう。
日本の未来を知りたい
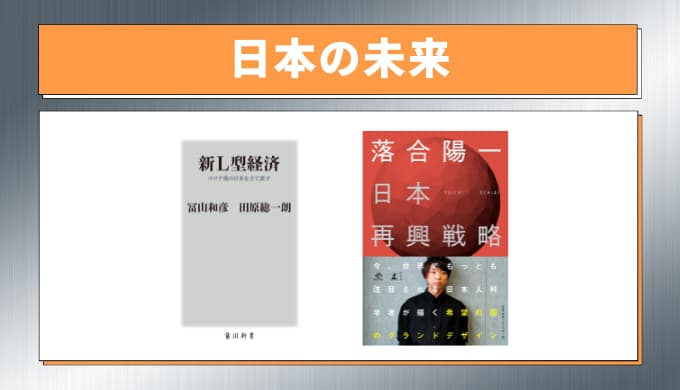
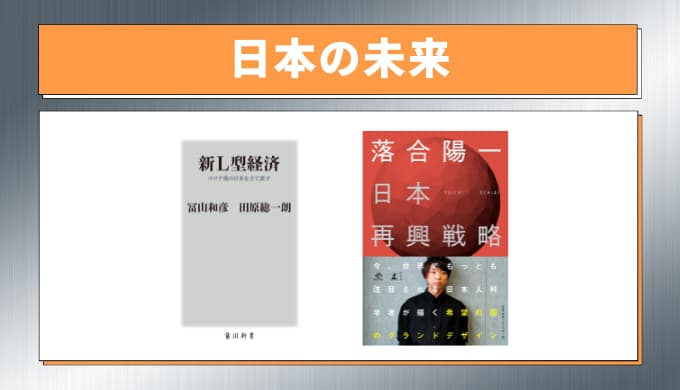
1位『新L型経済 コロナ後の日本を立て直す』冨山和彦/田原総一朗


GAFAや仮想通貨、AI、デジタル資本主義…巷間には華やかで浮ついたワードが日々飛び交っていますが、日本の現実、日本の未来はそう甘くない…。そんな本質を鋭く捉えたのがこの一冊!
本書に登場するG型、L型とは、それぞれ「グローバル型」「ローカル型」のこと。冒頭に挙げた21世紀的なキーワードは、世界に君臨する巨大経済国家のグローバル企業群のものであって、島国・日本のものではない、というのが著者の強い言い分です。
現実には、日本に生きる大半の労働者は「日本企業」という名のL型経済に属し、甘い果実のおこぼれにはありつけない。
では、どう生き抜けばよいのか?経済専門家が教えるカギは「DX」。地に足のついたタイムリーなビジネス書です!
コロナを機とし、「昭和モデル」と決別せよ! 日本社会再生へのビジョン。
2位『日本再興戦略』落合陽一


強烈にインプットできる。
大学准教授で起業家でアーティストで研究者による、今の30代が死ぬ気で構築しつつある世の中を知れる本。
今、世界でもっとも注目される日本人科学者が描く希望の国のグランドデザイン。
経済について学びたい
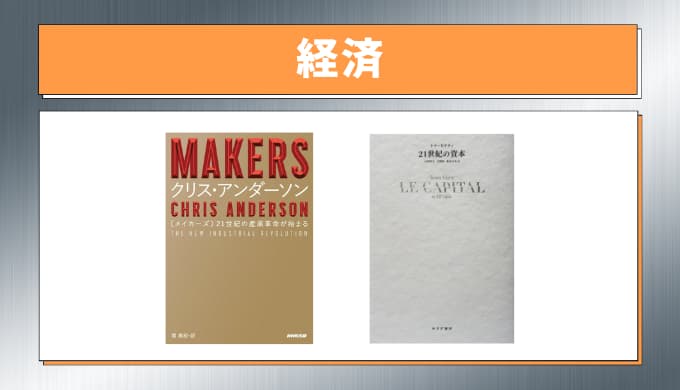
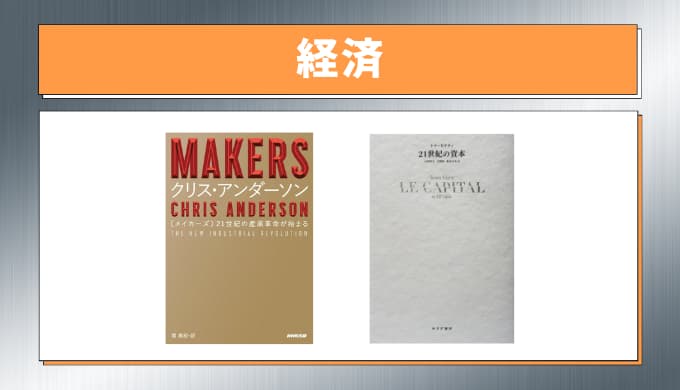
1位『MAKERS 21世紀の産業革命が始まる』クリス・アンダーソン


「日本は昔からものづくり産業の国だ」「ものづくりを大事にしよう」と言われ続けても、バリバリの工業都市や伝統工芸品の街で育ったことがない限り、いまいちピンときていない人は多いでしょう。
いっけん派手なメディア産業やIT産業に注目を奪われがちなのは、”ものづくり”という通りの悪い語感にもおそらく原因があるのでは?
だけど、「MAKER」と言い換えるとイケている感じがするから不思議なものです。
”ものづくり”を大工場から大衆の手に取り戻したスマホや3Dプリンタの登場が、私たちの暮らしを劇的に変えていることが分かる1冊。
21世紀の製造業は、アイデアとラップトップさえあれば誰もが自宅で始められる。ウェブの世界で起こったツールの民主化が、もの作りの世界でも始まったのだ。メイカーズ(モノ作る人々)の革命が、世界の産業構造を再び変える!
2位『21世紀の資本』トマ・ピケティ


現代の大きな問題といえば、格差です。「世界の全資産の90%は世界人口の1%が所有している」、ときにそう表現されます。
この本では、フランスの歴史経済学者ピケティが過去に遡って徹底的な資料調査を行い、格差社会についての歴史的事実を鮮やかに導き出しています。
その事実とは…「r>g」。このシンプルな不等式が意味するところは、人類は生まれてこの方、所有資産の方が獲得資産よりも”つねに”大きかったということ。
20世紀の世界大戦でその格差は一時的に縮まったものの、21世紀に入って再び差が開いてきたというのが著者の見方です。民主主義的価値観に反しかねないこの発見は、センセーションを巻き起こしました。
資本収益率が産出と所得の成長率を上回るとき、資本主義は自動的に、恣意的で持続不可能な格差を生み出す
自分を変えて自信をつけたい
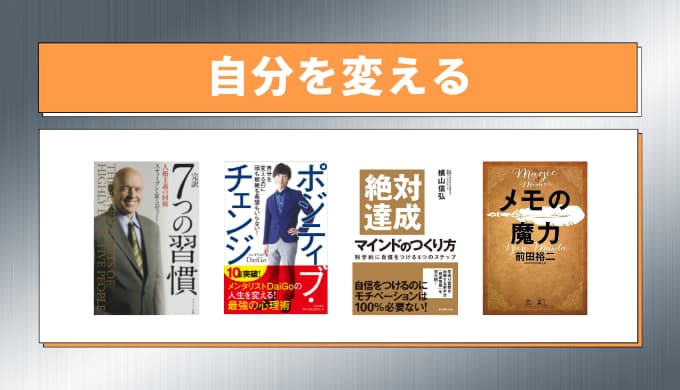
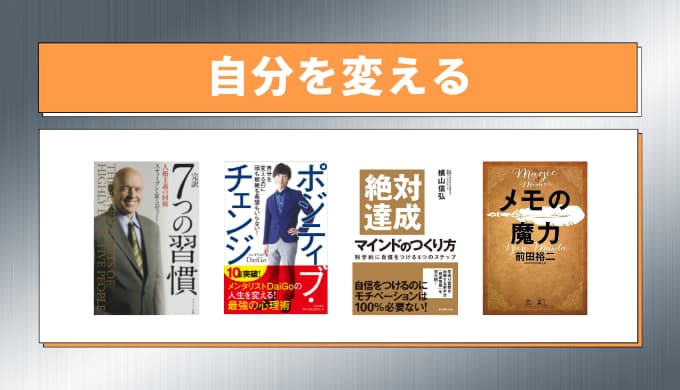
1位『7つの習慣』スティーブン・R・コヴィー


「人生を変えるのは行動であり、行動を変えるのは思考であり、思考を変えるのは習慣である」
人生を変えるには毎日の習慣から変える必要があります。
著者が提唱する習慣はつまるところ、「自分が成功するため」「まわりを成功させるため」そして「自分を磨くため」の3つに集約されます。
7つの習慣を理解し、身につける。派手なことは何も書かれていませんが、愚直にそれを実行することこそ肝心だと述べられています。全世界4000万部を達成したのも納得の一冊です。
よりわかりやすく理解しやすい完全訳の『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』。豊かな人生を望むすべての人にお届けします。
2位『ポジティブ・チェンジ』メンタリストDaiGo


「誰でもいつでも変われる」ということに気づかせてくれます。
科学的に正しい習慣を紹介しているので、良い習慣を身に付けたい人にオススメです!
たった5週間で人生を変える!最強の心理術。時間・言葉・友人・モノ・環境・外見・食事7つのスイッチで、あなたは激変する!メンタリストDaiGoが実践した超変身法を初公開!心理学と脳科学の最新研究を駆使。楽しみながら自分を変える「ポジティブ・チェンジ」で「なりたい自分」になる方法を教えます。
3位『絶対達成マインドの作り方』横山信弘


本書は目標の設定の仕方から、目標を達成するまでのシステム化、マインドセットなどを詳しく学ぶことが出来ます。
目標を設定し、達成することは自分の成果を上げる仕組みを作ることでもあるので、「成果をあげる」方法の1つとして読むことをおすすめします!
自信をつけるのにはモチベーションは100%必要ない。先送り習慣を治療する新手法「倍速管理」を初公開。
4位『メモの魔力』前田裕二


その場限りのメモ魔から卒業できる、親切丁寧な訓練本。


備忘録のためのメモではなく、前田さん式のメモを取ることで、メモをした内容から他に応用できること、自分自身の行動にまで落とし込むことができる。
そのことで、「新しいビジネスアイデアが生まれる」「プレゼン力がつく」「日々の会話に応用でき話し上手になる」「自分の人生の軸を知れる」などの利点を伸ばすことができると感じた。
僕にとってメモとは、生き方そのものです。メモによって世界を知り、アイデアが生まれる。メモによって自分を知り、人生のコンパスを持つ。メモによって夢を持ち、熱が生まれる。その熱は確実に自らを動かし、人を動かし、そして人生を、世界を大きく動かします。誰にでもできるけど、誰もまだ、その魔力に気付いていない「本当のメモの世界」へ、ようこそ。
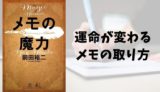
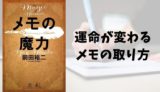
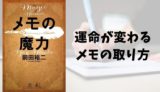
体が資本!一流の疲労回復メソッド
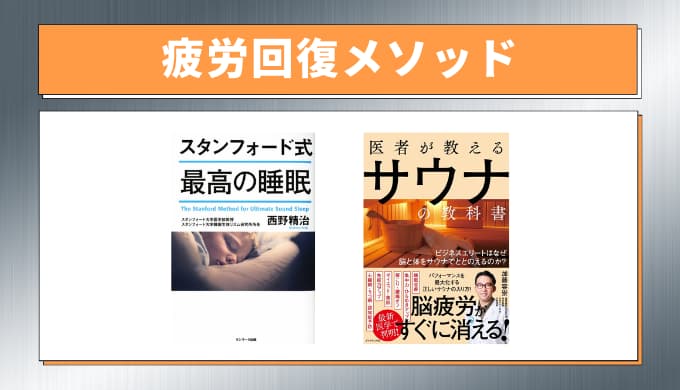
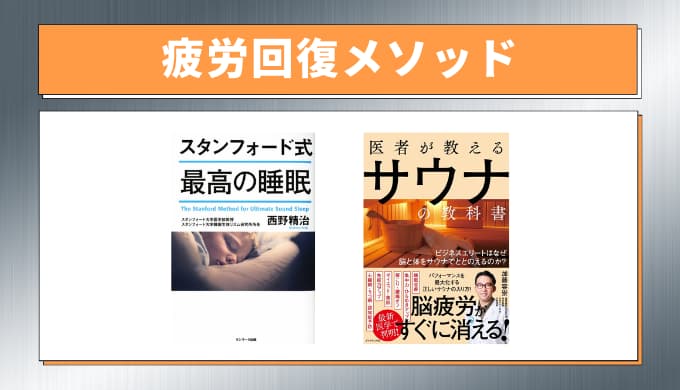
1位『スタンフォード式 最高の睡眠』西野精治


スタンフォードで研究を重ねた西野精治氏が、睡眠の質を高めるノウハウを教えてくれます。
毎日誰にでも訪れる睡眠時間。
どうせなら、良質な睡眠にしたいですよね。
本書を要約すると、「就寝の90分前に入浴する」という一言でまとめることができます。
入浴をすることで、一度急激に体の奥の温度(深部体温)が上昇します。
急激な上昇の反動として、今度は一気に深部体温を下げようとします。
深部体温が最も下がったタイミングは、副交感神経が活発になります。
副交感神経の活発化により、人間は睡眠モードに入るわけです。
この深部体温が最も低くなるのは、入浴からちょうど90分が経過したタイミングだそうです。
ぜひ入浴時間と就寝時間をコントロールしてみてください。
私は上記を実践し、眠りが非常に深くなった実感があります。
レムとノンレムは、「90分周期」じゃなかった!?最新の睡眠データ満載!科学的エビデンスに基づいた、睡眠本の超決定版!「世界最高」の呼び声高いスタンフォードの睡眠研究。そのトップを務める世界的権威が明かす、「究極の疲労回復」と「最強の覚醒」をもたらす超一流の眠り方。
2位『医者が教えるサウナの教科書』加藤容崇


「水風呂が苦手…」「サウナブームだけど実際どんな効果があるの?」という方に読んでもらいたい究極のサウナ本です!
正しいサウナの入り方とはずばり「サウナ→水風呂→外気浴」の3ステップ!サウナ室を出る目安、水風呂の重要性や理想の体勢など図解つきで解説してくれるので初心者でも分かりやすいです。
本作で紹介されている方法を実践すれば、正直いいことづくしで腰を抜かしてしまうと思います(笑)「ヤセ体質になる」「集中力が上がる」「脳や眼、肩の疲れが和らぐ」「アイデアが閃きやすくなる」など挙げるとキリがありません!
これまでただなんとなくサウナに入っていた方も、本作の内容を実践して別次元の気持ちよさを体験してください!ちなみにぼくはサウナの素晴らしさに取り憑かれ、週1でスーパー銭湯へ通うようになりました(笑)
「ととのう」のには医学的根拠がある!本書を読んでからサウナに入ると別次元の「ととのい」が待っている!



今日から実践できるノウハウを得たい
『読んだら忘れない読書術』樺沢紫苑


僕、てぃーけは大学生の途中まで一切本を読まない人間でした。暇つぶしのために入った書店で本書を立ち読みした所、どハマり!
冒頭では、読書のメリットが科学的根拠と共に語られています。これが実に痛快で、僕の読書心に火を点けました。読書習慣がない人にオススメしたい本です。
こうすれば、記憶に残すことができる!毎月30冊の読書をこなし、毎日40万人に情報発信!異色の精神科医が教える、脳科学に裏付けられた、本当に役立つ読書とは?
賢い勉強法・学習法を知りたい
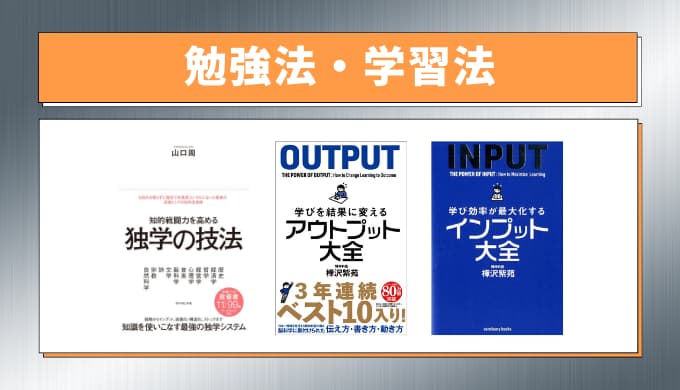
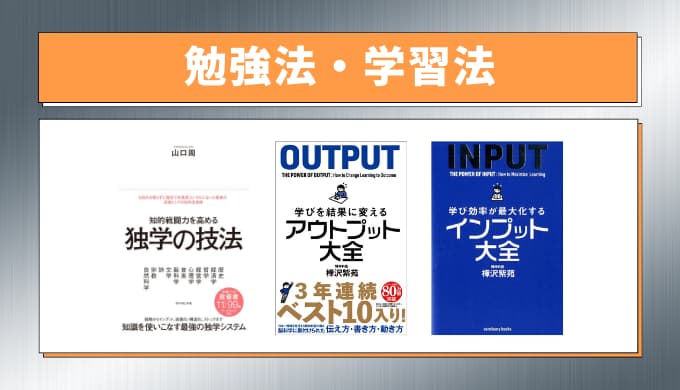
1位『知的戦闘力を高める 独学の技法』山口周


学び、経験を形にする。新たな仕事を生み出したい人におススメです。
異なる種類のインプットが、脳内で結びつき、立体的に浮かび上がる。このイメージの質と、インプットの量が、知的革命を起こします。
「インプットするだけの素人の戯言」か「結びつけ、形にする知的革命家」か、その手法を学べる本です。
MBAを取らずに独学で外資系コンサルになった著者の武器としての知的生産術。
2位『学びを結果に変えるアウトプット大全』樺沢紫苑


インプットを自己満足で終えないために。誰でも発信できる現代で、より楽しみ効率よく内面と現実を変えていくための方法論。
人間は脳が受けた最上の刺激も数秒後には忘れてしまう。脳科学の目線から見る人生の効率化を学ぶことは、よりスピード感のある成長へと繋がる。
インプット、アウトプット、フィードバックの習慣を日常に作り、脳が喜び刺激の舞い込む日々をルーティン化できたらどうだろうか。
普段何気なく使用するSNSを刺激と成長の空間に変貌させよう。
3位『学び効率が最大化する インプット大全』樺沢紫苑


高校時代の中間試験前夜。
大学の留年がかかった試験前夜。
昇格がかかった資格試験前夜。
誰もが一度は、スラムダンクの三井寿と同じことを思ったことがあると思います。
おそらく9割以上の人は、勉強が苦手。
それは記憶=インプットが下手ということとほぼ同じです。
「教科書全然覚えられない…」
「プレゼン資料に目を通しておいてと言われたけれど、全然頭に入らない…」
こんな悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
本書は、効率よくインプットをする方法が具体的に記されています。
一言でまとめるなら、「アウトプット(=誰かに説明する)前提でインプットをすると、効率が爆上がり」と書いてあります。
筆者の樺沢紫苑氏は精神科医であり、人間の記憶についても研究されている方です。
評論家に終始することなく、樺沢氏は高頻度でブログを更新しているそうです。
得た知識(=インプット)を知識のままで終わらせるのではなく、自らブログや書籍という形でアウトプットしているのです。
勉強が苦手な人にとっては、目から鱗の内容になっています!
学びが脳にとどまる人と、すぐに消えてしまう人の違いは何か?読書、勉強、記憶、情報収集etc…限られた時間で良質な学びを手に入れる、日本一アウトプットする精神科医が教える、脳科学に裏付けられた勉強法。
新しい働き方を模索したい
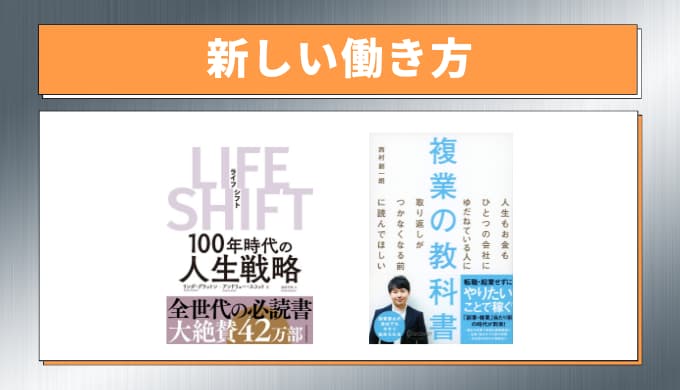
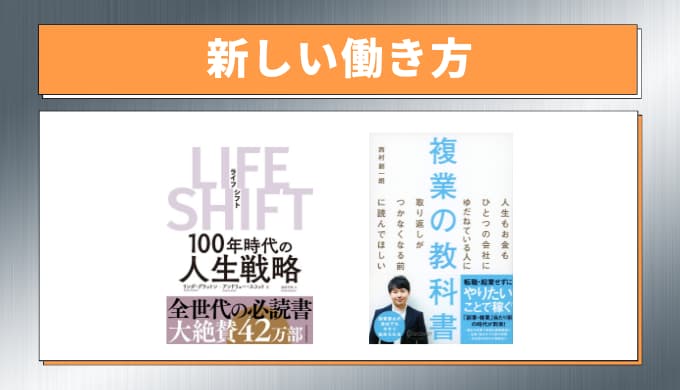
1位『LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略』


現在の健康寿命が伸びていずれは100歳まで生きる人が増えると言われていて、これまでの生き方と、これからの生き方や働き方が大きく変わってくることが予想されている中、「どのようにして、この激動の変化を乗り越える生き方をしていけば良いのか」を示してくれる本。
お金偏重の人生を、根底から変える。成長至上の次に来る、新しい生き方。
2位『複業の教科書』西村創一朗


本当に自分に合った仕事を探している人や、もう一つ自分の強みを作りたい人に強く勧めます。
お金を稼ぐのではなく、他では得ることのできない、貴重な経験を手に入れる。本業だけでは得られない、経験、信頼と出会います。
私は現代で生きていくために、後者を選びました。本業と密接に絡み合い、相乗効果が生まれています。
現代の働き方の波に乗りたい。そんな方に強くお勧めする本です。
「転職・起業のリスクを冒さずに、人生を取り戻す方法」「副業ではなく、複業だけがもっている3大メリット」「複業をはじめるための3(+1)ステップ」―今の仕事だけで、これから生きていけますか?この一冊で大丈夫!忙しい人でも1日5分からできる複業のすすめ。
仕事を楽しめるようになりたい
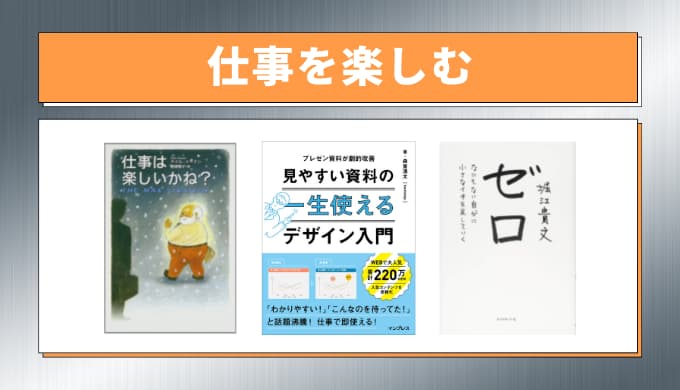
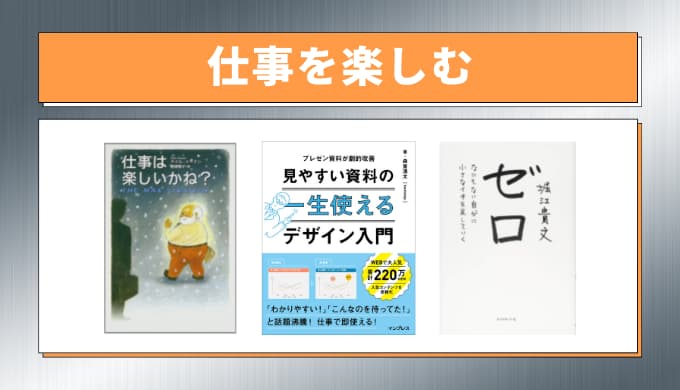
1位『仕事は楽しいかね?』デイル・ドーテン


「楽しくない」
そう答えたあなたにぴったりの物語。仕事の喜びは「試すこと」にあると教えてくれます。
「遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守る」
私もさっそく15個のアイデアを提案したところ、あえなく全て却下されましたが、面白いヤツだと注目されるようになりました。チャレンジは思わぬギフトを運んでくれるようです。
コツは目標を立てず、問題を解決しない。そんな非常識なメソットを楽しんで学べる1冊です。
大雪で閉鎖になった空港で、偶然出会った老人の問いかけに、動揺してしまった35歳の“私”。日々の仕事にゆきづまりを感じ、未来に期待感をもてない私に、老人は一晩だけの講義を開始した。



2位『一生使える 見やすい資料のデザイン入門』森重湧太


「どこかに教科書的な本はないものか…」
そんな資料作成に悩むビジネスマンたちに朗報です。
ついに!パワーポイントでの資料作成の教科書が出版されました!
「スライドのフォーマット」「各色合いの意味」「相性の良い/悪い色の組み合わせ」等、資料作成時の悩みと解決策は基本的にすべてこの本に載っています。
私は全てこの本の通りに作成するようになってから、非常に資料の評判が良くなりました。
いつの間にか「資料作成は君に頼むよ」と上司から言われるようになりました(仕事が増えました…笑)
とはいえ、資料作成スキルが本書一冊で圧倒的にアップしますので、強くおススメします!
どこに出しても恥ずかしくない資料作成スキルが手に入りますよ!
誰でも今スグ実践できる、「ほんのひと手間」で資料が変身!スライド共有サービス「SlideShare」の人気スライド「見やすいプレゼン資料の作り方」待望の書籍化!
3位『ゼロ なにもない自分に小さなイチを足していく』堀江貴文


「働くこと」とは何なのか。
仕事や趣味、恋愛など人生の様々な選択の状況には悩みがつきものであり、好き、嫌い、怖いなどの感情は全てチャンスに繋がっている。
チャンスを生かすためには「慣れないもの」に飛びつくこと。興味のアンテナを常に開けて気づいたら飛び込んでいられるように。
独房でも「自分の時間」を生きたホリエモンから仕事と人生を学ぶ1冊。
堀江貴文はなぜ、逮捕され、すべてを失っても、希望を捨てないのか?ふたたび「ゼロ」となって、なにかを演じる必要もなくなった堀江氏がはじめて素直に、ありのままの心で語る、「働くこと」の意味と、そこから生まれる「希望」について。
成功者の体験談が読みたい
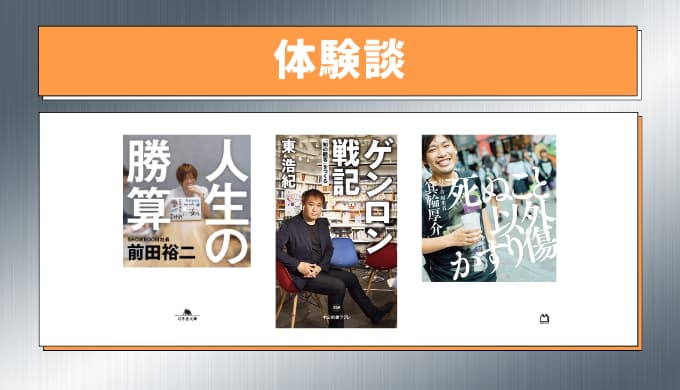
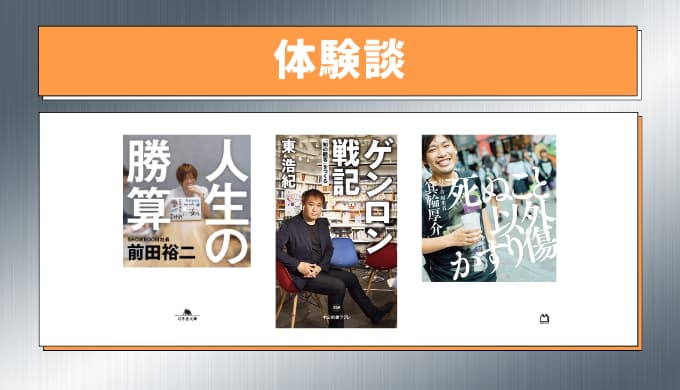
1位『人生の勝算』前田裕二


成功者と呼ばれる人たちが共通して持っているものは、自信と勇気なのではないかと思いたくなる。人生の勝ち組に憧れがあるなら是非オススメしたい。
SNS時代を生き抜く為に必要な“コミュニティ”の本質と、SNSの次の潮流であるライブ配信サービスの最前線がわかる。
2位『ゲンロン戦記』東浩紀


文筆に生きる作家・思想家が門外漢のビジネス領域に飛び込み、会社を立ち上げたらどうなるのか?というノンフィクションの体験談。
案の定、著者は想像もしなかったような苦難に巻き込まれ、良からぬ人間関係や金銭トラブルに足をすくわれることになります。
その10年間の道のりが、リアルなテイストで克明に描かれ、オフィスの棚を自作するシーンなどは涙なしでは読めません。
単なるビジネス書で終わらないのは、著者がこれまで培ってきた人生観と、向き合ってきた現実のビジネスが最終的に見事に結合する点にあります。
自らの得意領域と異なる経験を得たことで、自己の短所と向き合い、成長する過程は誰もが経験し得る普遍的プロセスなので共感できること間違いなし。
10年の遍歴をへて哲学者が到達した、「生き延び」の論理
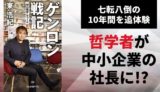
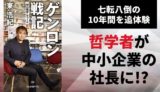
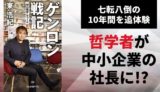
3位『死ぬこと以外かすり傷』箕輪厚介


「いやな仕事を飲み込んで、3回自分に嘘をついたら戻って来れなくなる」この言葉のように現状を見つめ直し、今何ができるのか?
行動を触発する言葉に溢れています。その中でもこの言葉が1番光っていました。
「努力は夢中に勝てない」
熱狂できる強みに出会う本です。モヤモヤを晴らし、スタートダッシュを決めたい人におススメです。


「正しいことより、楽しいことを」
「今やれよ!」
本書は、箕輪厚介の行動論であると言えます。誰よりも自分で動いて自分の足でチャンスを掴んできた人。だからこそ彼の言葉は説得力があり、素直に受け止められる。
言葉から伝わる熱量や彼のエネルギーから、どこか暖かみを感じました。今を全力で走り抜けた者にしか辿り着けない景色がきっとある。
「自分がしたいことは何か?」
「できることは何か?」
今すぐ行動したくなる、気合いが入る本です。
ベストセラー連発!わずか一年で100万部突破!天才編集者の革命的仕事術。
マーケティングを学びたい
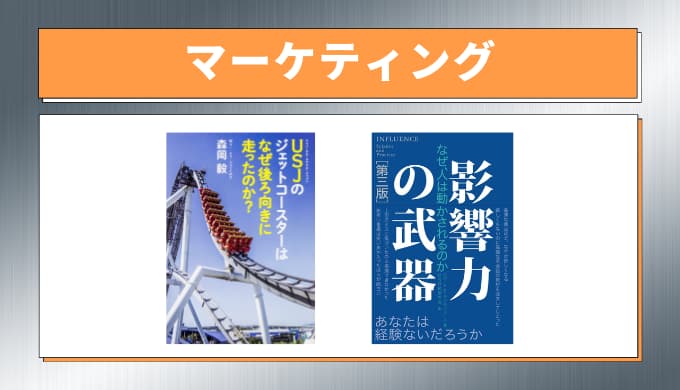
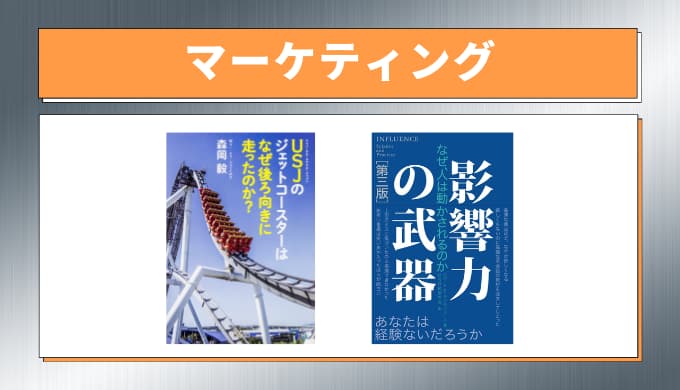
1位『USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?』森岡毅


マーケティングのお話ではなく、いかに問題解決するか。
お金もなく、でも今あるアトラクションをよりお客様に楽しんでもらい、V字回復を狙うには…と森岡さんの考え抜いた工夫がたくさん出てきます。
堅いビジネス書という内容ではないので、はじめてのビジネス書としていかがでしょうか?
ハリウッド映画のテーマパークとして2001年に大阪に誕生したユニバーサル・スタジオ・ジャパン。初年度こそ年間1100万人を集めたが、それ以降は集客が伸びず、2009年度は700万人台にまで減ってしまった。このピンチをどう乗り越えるのか?お金がないならアイデアを振り絞れ!後ろ向きコースター、ゾンビの大量放出、絶対生還できないアトラクション…斬新な企画を次々打ち出し、USJはV字回復していく。
2位『影響力の武器』ロバート・B・チャルディーニ


「最新の心理学の本やマーケティングの本はすべて本書を参考にしている」と言っても過言ではないくらいに原理原則が書かれてます。
「返報性の原理」などはビジネスをやってる人なら知っておくべき事柄ですよね。
オススメはこの本を何度も繰り返し読むこと。最新のマーケティング本を読むならこちらを熟読した方がいいです!
セールスマン、募金勧誘者、広告主など承諾誘導のプロの世界に潜入。彼らのテクニックや方略から「承諾」についての人間心理のメカニズムを解明。情報の氾濫する現代生活で、だまされない賢い消費者になると共に、プロの手口から人を説得するやり方を学ぶ。
教養を身につけたい
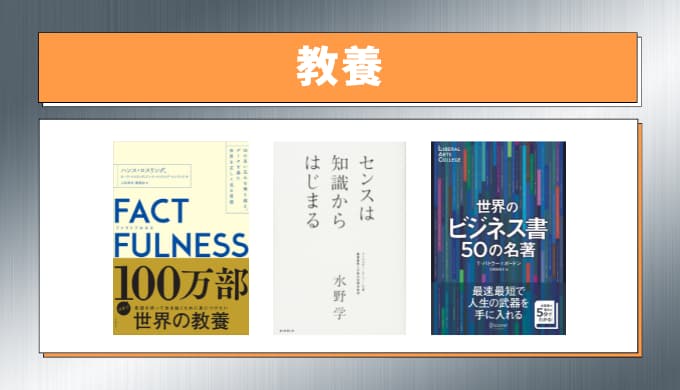
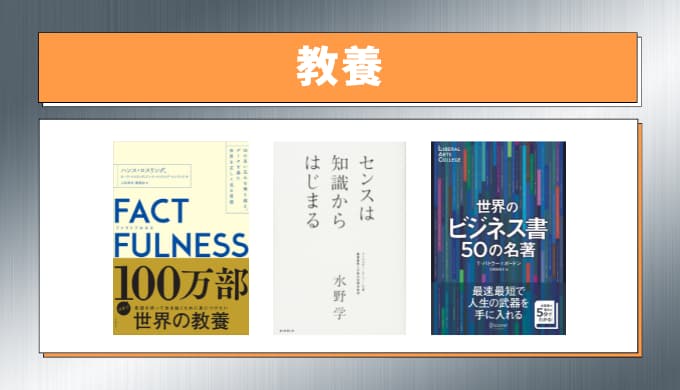
1位『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング


思い込みや先入観が、私たちの正常な認識をいかに歪めているかを教えてくれる本。
近年の時代の移り変わりはかつてなく速いため、何となく教わった知識は完全に古びており、「10の誤解」があると指摘しています。
その誤解はたとえば、「世界はより危険になり」「貧困は増え、男女格差は拡がり」「民主主義は完璧」というもの。真実は全くその逆だというのです。
普段あまり新聞やニュースに触れない人や、忙しくて世界情勢をアップデートしていない人にはおすすめの一冊!
ファクトフルネスとは――データや事実にもとづき、世界を読み解く習慣。賢い人ほどとらわれる10の思い込みから解放されれば、癒され、世界を正しく見るスキルが身につく。世界を正しく見る、誰もが身につけておくべき習慣でありスキル、「ファクトフルネス」を解説しよう。
2位『センスは知識からはじまる』水野学


センスとは知識の集合体であり、知識を持ったうえで物事を判断し、一番いい状態へ進める人が、現代における「センスのある人」です。
裏を返せば言葉で説明のできない「感覚」はあてにならない。そんなセンスの磨き方について学ぶことのできる本です。


勉強せずともどういう風にしたら、センス良く見えるか分かってる人を見ると私はセンスがないんだなぁと思ってました…この本を読むまでは!
知識の引き出しを増やすことで、センスは磨くことができる。「知識を知り、実践する、経験を積む、自信がつく」ということでセンスが磨かれる。
センスは一部の人が持っている特別なものではない。自信がなかった難しいことも知識=センスで解決できるかもしれません。
企画や制作に携わってる方にはおすすめです。
“センス”とは、特別な人に備わった才能ではない。それは、さまざまな知識を蓄積することにより「物事を最適化する能力」であり、誰もが等しく持っている。今、最も求められているスキルである“センス”を磨くために必要な手法を、話題のクリエイティブディレクターが説く!



3位『世界のビジネス書50の名著』 T・バトラー=ボードン


ビジネス書の入り口に立とうとしている人、忙しくて読書の時間が取れない人におすすめの一冊です!
出版点数が爆発的に増加している昨今、名著を挙げればキリがないし、読む時間も限られている。
時代の移り変わりによって大切なポイントがコロコロ変わるビジネス書の場合はなおさら。
現在の自分の悩みに答えを与えてくれる本や、名著中の名著とは懸命に格闘する必要がありますが、そうでもないものはひとまずサラっと知っておくだけでもよいでしょう。
ちなみに、このシリーズには心理学や哲学等もありますのであわせてチェックしてみてください。
ビジネスに必要な想像力とアイデアがつまった必読書の要点が5分でわかる!
子どもに読ませたい
『ミライの授業』瀧本哲史


「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
14歳に向けた講義を書籍化したものだけど、大人が読んでも納得の1冊。
1限目 世界を変える旅は「違和感」からはじまる。
2限目 冒険には「地図」が必要だ。
3限目 一行の「ルール」が世界を変える。
4限目 すべての冒険は「影の主役」がいる。
5限目 ミライは「逆風」の向こうにある。
わかりやすくてオススメです!
学校は、未来と希望の工場である―。きみたちは「魔法」を学んでいる。
まとめ
いかがでしたか?
「実生活や仕事で役に立ちそうだから読んでみようかな!」と思える本を1冊でも見つけていただいたら幸いです。
ビジネス書ってたくさんあって「一体どれを読んだらいいんだ?」と迷うことがよくあると思います。
そういう時には他の人のおすすめの本や、信頼できる上司などにおすすめを聞いて参考にするといいと思います。
この記事を読んだあなたが、自分の抱える悩みを解決してくれるビジネス書に出会えることを心から願っています。
最後までお読みいただきありがとうございました!!
この記事を読んだあなたにおすすめ!
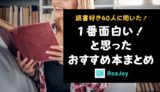
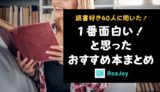
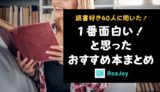



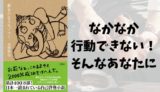
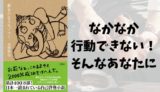
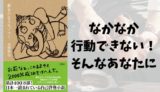

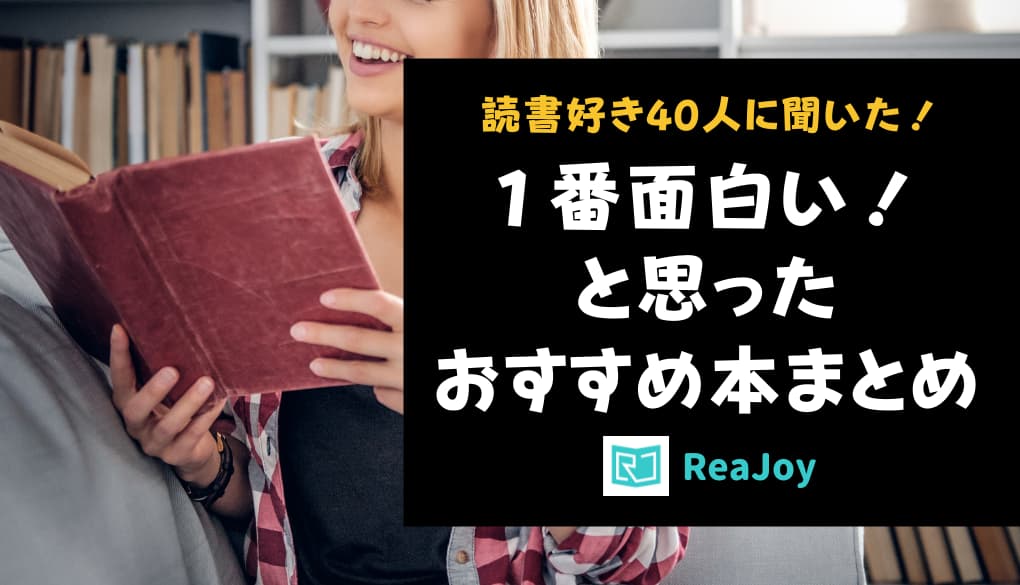


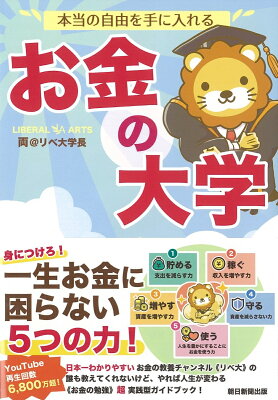

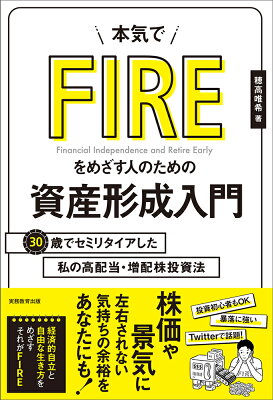

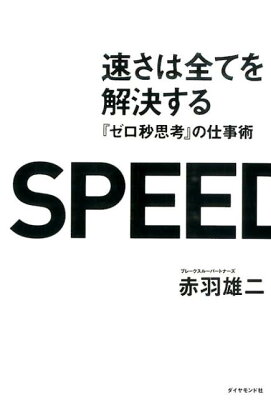
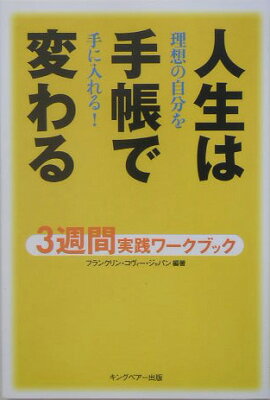
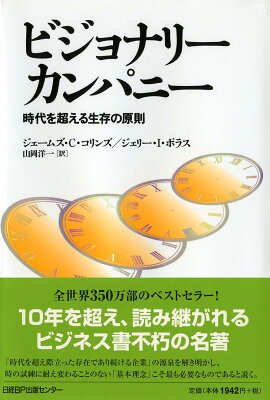
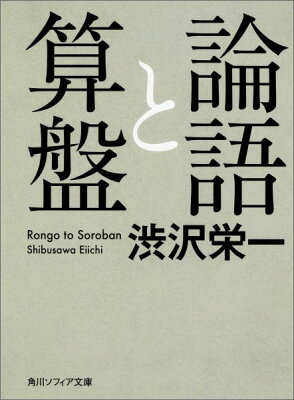
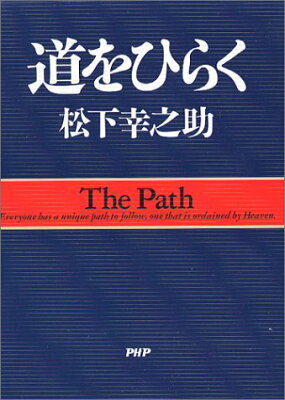
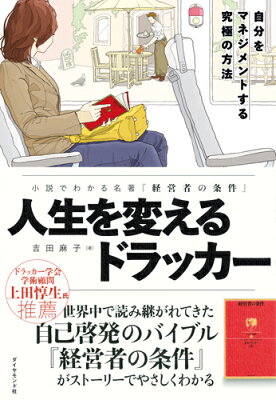
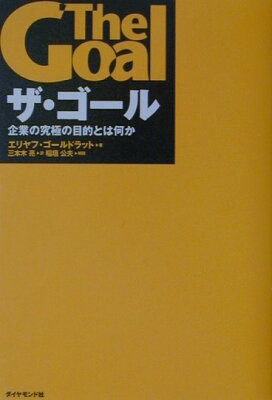
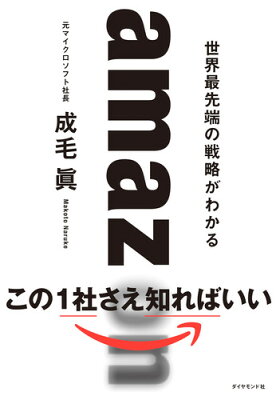
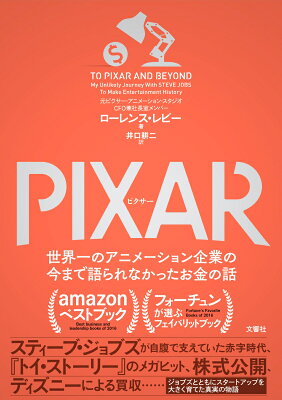
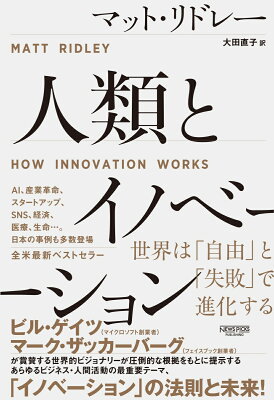


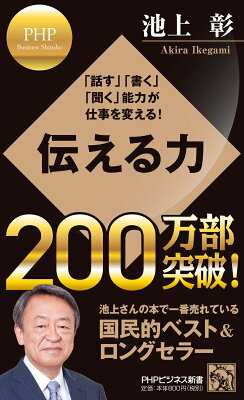

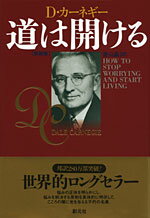
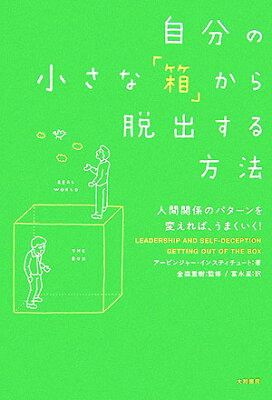
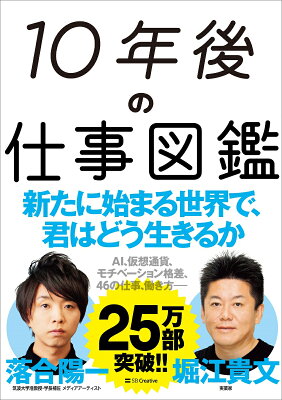
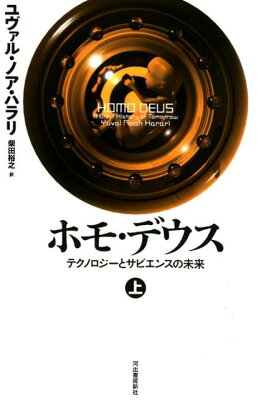
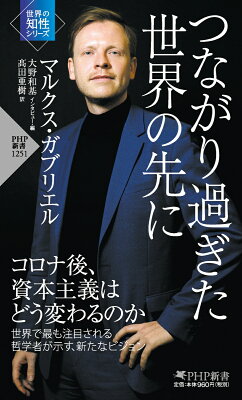
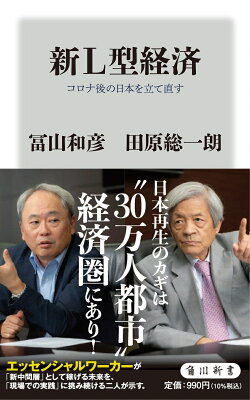
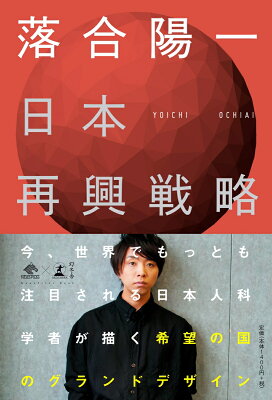
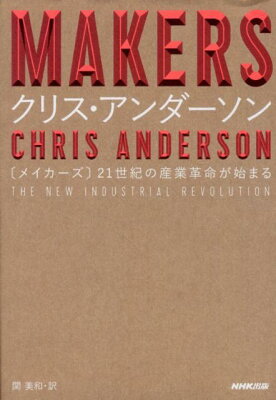
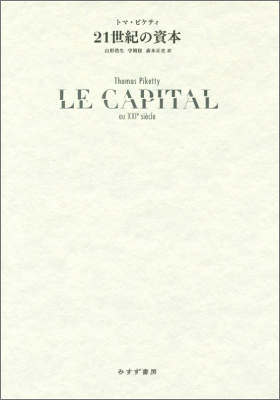
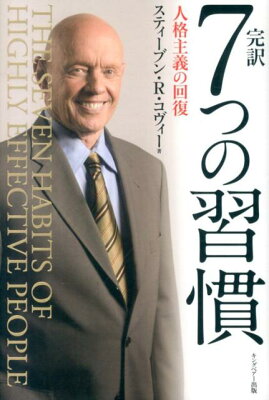
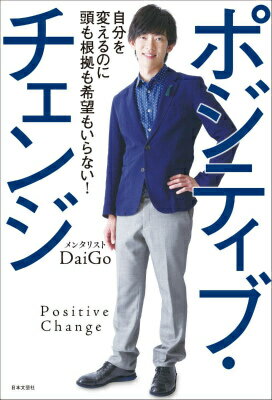

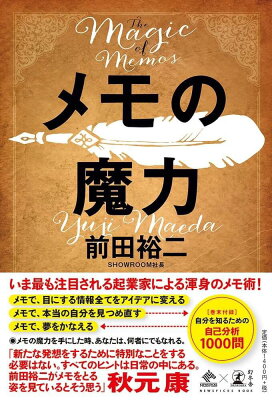

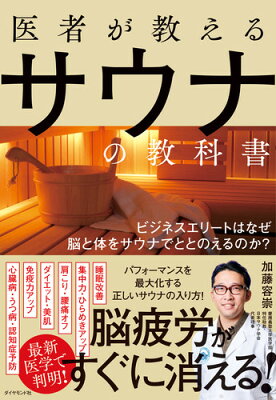

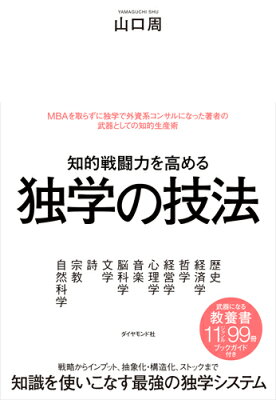
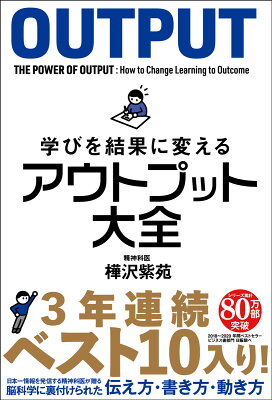

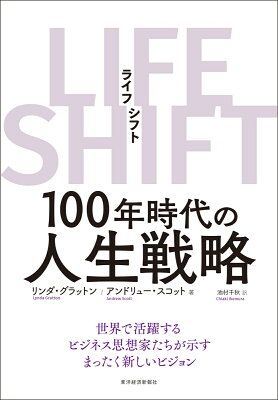

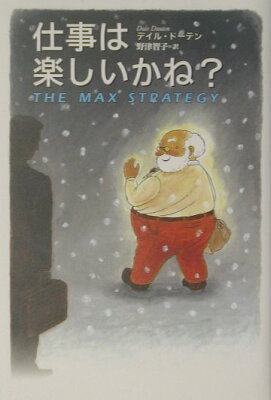
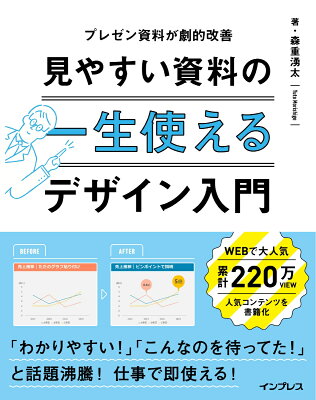

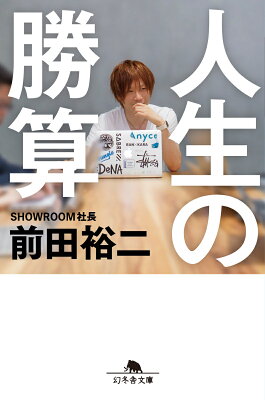

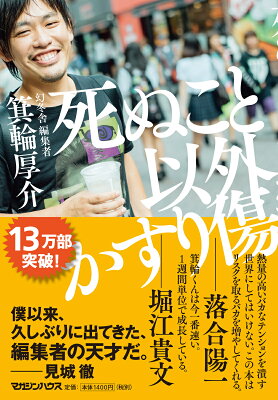
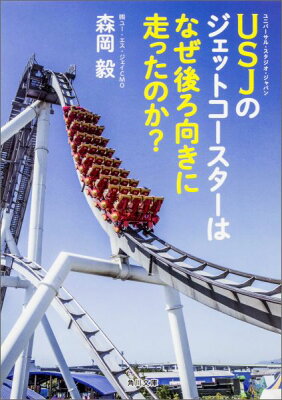

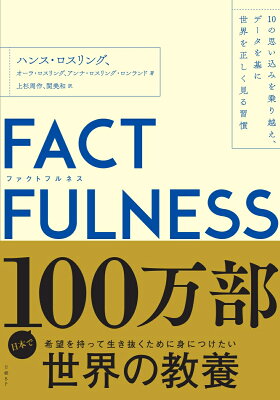

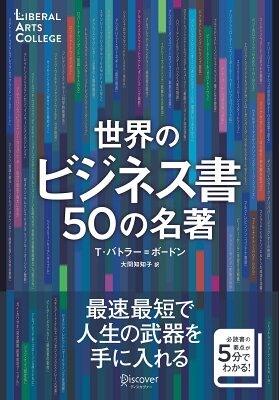
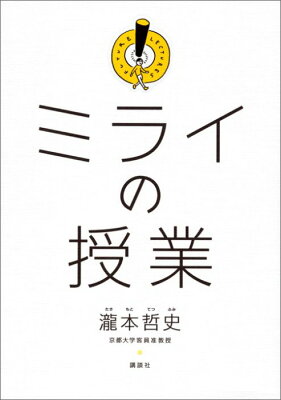

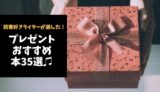
書き手にコメントを届ける