「読書ってミュージシャンにとってめちゃくちゃ大事なんですよ」
一音目がギターからはじまる曲は多い。そこで聴かれなかったらサビがどれだけ良くても意味がない。つまり、イントロを弾く人は絶対に魅力的な音を奏でなくてはいけない。今回インタビューしたのは読書家のギタリスト、坂本夏樹さん。
She Her Her Hers、チリヌルヲワカでのバンド活動を経て、現在はギタリスト、アレンジャーとして活躍中。酸欠少女さユりの『フラレガイガール』やCreepy Nutsの『ぬえの鳴く夜は』のギターサウンドを手掛けている。
She Her Her Hersで魅せたシューゲイザー、チリヌルヲワカでのカッティングに加え、フラレガイガールでの泣き声のようなサウンド、ヒップホップの楽曲で鳴らす攻撃的なギター。その音楽性の広さに読書は関連しているのだろうか。カテゴライズの枠を飛び越えることが新しい未来を切り開いていく。ミュージシャンの坂本さんが読書について語る。

読書は新しいものが生まれてくる時間
ーーよろしくお願いします。
僕は全然かしこまった感じではないのでゆるりとお願いします(笑)
ーー予め「本と音楽のぴったりな組み合わせ」を教えていただくようお願いさせていただきましたがいかがでしたか?
実は音楽と本と合わせるのすごい難しいなと思ったんです。結構、分けて考えているというか。本を読んでるときに誰かの音楽が思い浮かんでくることはあまり無くて。音楽をやってるときとは違う脳が働くので新しい曲のアイディアが浮かぶことが多くて。読書は新しいものが生まれてくる時間なんですね。
ーーそれはミュージシャンならではなのかもしれないですね。自分自身は映画のエンドロールのイメージでつけることが多いですが。
なるほど、本を読んだ余韻に合う音楽って面白いですね。
それで考えるならば「これを読んでいたらこの曲しか出てこない」というのは、西尾維新さんの『傷物語』にsupercellの『君の知らない物語』ですかね。
アニメの主題歌ですが、あんなに本の世界観と曲調と歌詞の内容とがリンクしてるのってなかなかない。
作家さんたちは柔軟に音楽と付き合ってくれているのかなと思いますね。僕は音楽一筋できてしまったので結構凝り固まった頭になってしまっていて。店で流れている音楽とかも全然楽しめない(笑)
これ面白いなと思ったらコード進行がどうなっていて、どういう楽器を使っていて、どういう展開になっているかを解析し始めてしまうので、本を読むときとかも本に集中したいので音楽を聴かなくなってしまうんですよね。別のことがどんどんと湧いてきてしまうので。
ロックをやっているんですが、普段聴いているのはヒップホップとかの方が実は多くて。
ネタを掘りに行くみたいな感じです(笑)
ーーロックはあまり聴かないのでしょうか?
そうですね。まっさらな気持ちで楽しめなくて。でも、その中でたまに「コレは!」と思ったりするものもありますけどね。
(思いついた様子で)
Billie Eilishの『bury a friend』と江戸川乱歩の『芋虫』は合うんじゃないでしょうか。戦争で四肢がなくなってしまって、目も喉も潰れてしまっている旦那さんを介護する話で。その話のエンドロールに合う気がします。ダークな曲の雰囲気があう。
虫の状態になってしまった旦那さんを隔離しているんですが、いつのまにか居なくなって。どこに行ったんだ、草むらの方からなんか音がする。それで終わるので怖いですね。
仕返しにくるのか、そのまま逃げてしまったのかっていう気持ち悪い雰囲気が今のBillie Eilishにすごい合うんじゃないですかね。世界も時系列も無視した感じで面白いなと。
ーー読後感が良い作品も読まれますか?
どちらかというと普段読んでいるのはファンタジーな作品が多いですね。気持ち悪いものとか、幽霊とか妖怪とかも好きなんです。江戸川乱歩の他には、小野不由美とか京極夏彦も。
おどろおどろしい作品が凄く好きで読んできました。ちょっと気持ち悪さがありつつ、でもなんかハッピーな感じが好きですね。
小松エメルさんは読み終わったあとに軽い気持ちになれるというか。あんまりズーンとこないのがよくて。読んだあとに優しい気持ちになれる本も結構好きですね。
(また思いついた様子で)
最近本屋大賞を受賞された瀬尾まいこさんの『幸福な食卓』に、ハンバート ハンバートの『おなじ話』。
『おなじ話』は奥さんと旦那さんの話ですし、『幸福な食卓』も奥さんと旦那さんの話でもあるので。
ーーBlueglueの渡邊さんとはお知り合いだと伺いました。
5、6年くらい前からですね。ライブハウスで演奏する仕事があるときに、一緒になることが結構あって、サポートしてるバンドの対バンで来てくれることが多かったので。めちゃくちゃ変なヤツですよね(笑)あとめちゃくちゃええ声。
僕よりも何トーンも低くて、よく響くええ声していて、気取ってんのになんか抜けている感じがします。
ーー先日インタビューさせていただいたときには、クラシカルな作品が好きとおっしゃっていました。
そうそう、あの界隈はみんな好きなんですよ。27歳くらいの下北とか新宿のライブハウスシーンでやってる子たちは三島由紀夫、村上春樹、小川洋子とかが好きな子が多いですね。
僕は新しい作家に触れるとき、まずエッセイから入るんです
村上春樹で最近読んだのは『女のいない男たち』。新刊が出るたびに盛り上がるのも分かるけども、いつ読んでも絶対面白いし、何読んでも100点超えてくるからついつい後手後手になってしまいますね。それよりも新しいやつを探しに行こうと思うことが多くて。
あと昔から体を動かすことが好きなんです。陸上部だったこともあるので、『走ることについて語るときに僕の語ること』のエッセイがすごい好きで。共感できる内容が書かれてましたね。
走ることについて語るときに僕の語ること /文藝春秋/村上春樹
ーーエッセイも読まれるんですね。
エッセイ好きですね。僕、読書の仕方が変わっていて。普通は小説家の小説が好きだからエッセイも読んでみようってなる人のが多いと思うんですよ。
ーーそうですね。その流れが多いと思います。
僕は新しい作家に触れるとき、まずエッセイから入るんです。エッセイで人となりを知った上で、その人か面白い人間がどうか、どんな人間なのかを判断してから入るんです(笑)
エッセイで好きなのは絵本作家の伊勢英子さん。大人向けの絵本を書いている人なんですが、エッセイがすごい良くて。
絵本の内容はめちゃくちゃ良い内容を書かれているのに、エッセイの内容を読むとめちゃくちゃアウトローな人生を送られている(笑)
激しい人生だからこそ静かな作品が描けるのかな。僕が一番好きなのが『ルリユールおじさん』なんですが、その本とエッセイとセットで図書館に置かれてたんですね。それだけは順当に追っていったんですが、他の本ももっと読んでみたくなりましたね。
ーーほかにはどのようなエッセイを読まれているんですか?
笑えるって意味で好きだったのは貴志祐介さんの『極悪鳥になる夢を見る 貴志祐介エッセイ集』。
どちらかというとサスペンスやミステリーを描く人なのに、めちゃくちゃユーモアに溢れていて。気持ち悪い話はブラックエンターテイメントとして笑わしにきてるんだって見方ができるようになるので、気持ち悪い話のなかに笑えるポイントを探しに行く感覚になります。
次のページ
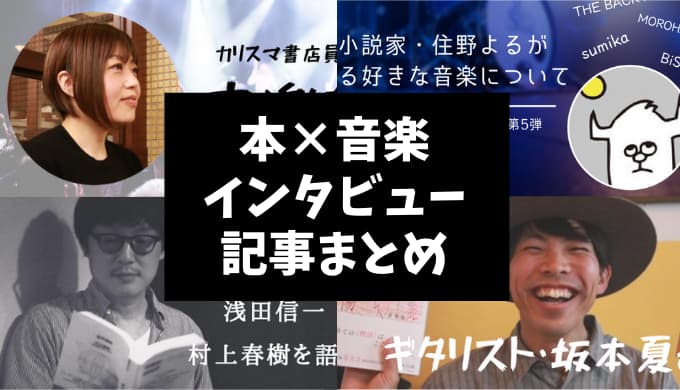
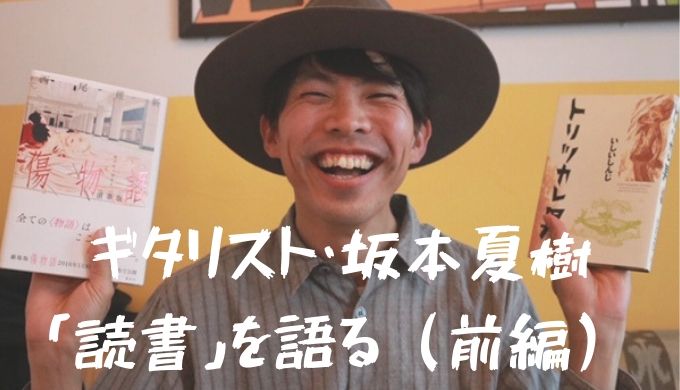







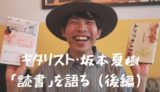
書き手にコメントを届ける