ーTrack No.2 『blue moon light』(KEYTALK)ー
KEYTALK。
彼らの音楽は、アメリカ文学に匹敵する郷愁と、狂おしいまでのメランコリーの香りがする。
『blue moon light』は、青白い月と、都会のコントラストが目に美しい一曲だ。
今回は作風、曲のコンセプトなどの視点から、少しずつ解き明かしていこうと思う。
『言葉を巧みに操る、繊細な「トリックスター」』ー小野曲の「作風」
まずはじめに、作曲者について。
KEYTALKはツインボーカルだが(ベースの首藤義勝、ギターの寺中友将)、今回はリーダーこと小野武正について話そう。
彼の曲風は、言葉遊びと繊細さを併せ持ち、非常にトリッキーである。
ASIAN KUNG-FU GENERATIONに影響を受けた結果、「言葉遊びに長け、なおかつ繊細な世界観を持ったスタイル」にたどり着いた。
また、SF風味のテーマが存在することも、彼の楽曲の大きな特徴となっている。
『blue moon light』 について
さて、本題に入ろう。
曲の主人公は、「夜の闇に溶け込みたい」という、半ば陶酔のような感情を抱いている。
『The moon, the stars, and the earth make this night?』
(月や星やそして地球で、この夜ができているのか)
『Shining in blue is the normal state of affairs?』
((それでも)青く輝くのは、正常な出来事なのか)ー(作詞:KEYTALK)
人工物である都市の光と、月や星といった自然物が共存していることに対する疑問。ここから感じ取れるのは、優しさと、柔らかな狂気だ。
都市の藍色の光と、薄い青色に染まった月の光が、重なり合う瞬間。青白く甘い闇に、全身が包まれてゆく姿。
想像してみると水彩画のようで、とても甘美である。
まとめ
甘い陶酔と、仄めかされる死の影。ネオンに照らされた青い都市と、淡い青色に染まった月。
真夜中の景色を眺めながら、じっくり聴くのにふさわしい楽曲だと言えるだろう。
ぜひアメリカ文学か、村上春樹の作品を片手に聴いてほしい。
(月のモチーフが出てくる「1Q84」、真夜中のファミレスが舞台の「アフターダーク」などが良いかもしれない。)
※なお、この記事を作成するにあたって、一部引用させてもらったことをここに記す。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14147640769
この曲に本を合わせるなら
ポール・オースターの『ムーン・パレス』だろう。
「美的次元にまで高められたニヒリズム」を体現するために人生を放棄し、皆既日食のように消滅することを望み、どんどん三日月のようにやせ細り、しだいに甘い憂鬱に陥ってゆく少年の姿は、どこか死の影を思い起こさせる。
月が太陽を覆い尽くす瞬間に、僕も消滅するだろう。-ムーン・パレス(柴田元幸訳)p36
この記事を読んだあなたにおすすめ!
『wowaka追悼 於 新木場STUDIO COAST【選書つきライブレポート】』ボーカロイドプロデューサー兼、バンド『ヒトリエ』のボーカルのwowakaさんの死から二か月後、突如開催された追悼ライブ。一人のファンが渾身の力で執筆した、追悼レビュー。
 wowaka追悼 於 新木場STUDIO COAST【選書つきライブレポート】
wowaka追悼 於 新木場STUDIO COAST【選書つきライブレポート】


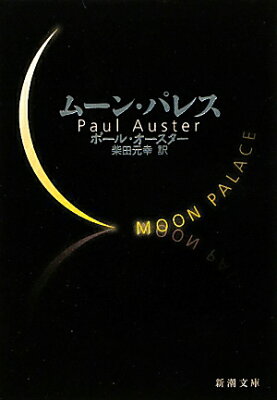
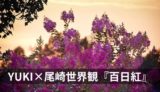
書き手にコメントを届ける