最近、何にも面白いことがない。
そもそも私が面白いと思うことってなんだっけ?
それでは、一緒に「面白い」の根本を探しに行こう!
目次
こんな人におすすめ!
- 「面白さ」を突き詰めたい人
- 「面白い」文章が書きたい人
- 自分の人生にちょっと迷子の人
あらすじ・内容紹介
よく使う言葉「面白い」。
声を出して笑うことも面白い、ミステリの事件が解決するのも面白い。
難しい問題が解けるのも面白い、スポーツ観戦も面白い。
あらゆることに対して使う「面白い」という言葉の根源に探りを入れつつ、視点を人生や日常、文章を書くことにまで言及する。
種類の多い面白さの分析から続く、著者自らが語るミステリというジャンルの壁、面白さの種類が多いことへの苦言。
著者が小説家であるが故に繰り広げられる果てのない「面白い」ことへの理論展開。
読むたびに発見があり、読むたびに自分の血肉になっていく。
森博嗣の小説のファンはもちろん、教養の1つとして、そして生きていく上で不可欠な「面白い」ことの根源を暴きだす1冊。
自分にとっての「面白さ」が迷子へのバイブルにもなるだろう。
『面白いとは何か?面白く生きるには?』の感想・特徴(ネタバレなし)
面白く生きるために自由であれ!
だれもが自由でいたいと思う。
でも「自由」っていったいなんなんだろう。
好きなときに起きて、好きなものばかり食べて、好きなことばかりする。
それが「自由」なのだろうか。
でも自由にはイコールで「責任」がつきまとう。
自由でいることはだれかに迷惑をかけていいことではないし、自由な振る舞いがなんの責任を負うわけがない。
学校でも「自由=責任」という図式は道徳や社会科でも教えられているということは、ある意味、自由とは不自由なものな気がする。
けれど私たち人間は「自由」であることにとても魅力を感じる。
たぶん、普段あまりちゃんと「自由」を感じられていないからだ。
でも日々、私たちは「自由」を享受している。
あなたが今日、朝食にごはんとみそ汁を食べたとする。
それはあなたがそれを食べると決めた、あなたの「朝食に何を食べてもいい」という自由。
昼食を抜くこともあなたの自由。
スカートを履くことも、今の職業に就いたのも、政府は、国は、「こうしなさい」と強制することもしない。
日々、私たちはごはんを選択するという小さな自由から、職業を選択するという大きな自由を享受しているのだ。
著者の森さんは「自由」を意識することで、「面白く生きられる」と言っている。
責任を伴っている自由だけど、本書のテーマである「面白く生きる」ということに自由は不可欠ということだ。
著者が考える「自由」ということはこうだ。
自由というのは、自分の思ったとおりになることです。そしてそれを実現するためには自分で「思う」ことが一番ですね。思いさえすれば、あとは実行するだけです。このように、自由は「自分」が作り出すものです。
いわゆる「自由=責任」論とはちがう「自由」に驚いた。
でも確かに、私は読書が好きで、それは「本が好き」「読書が好き」ということを「思い」、本を読むということを「実行」している。
それが「自由」だと言われたら頷くことしかできない。
著者の言う自分で作り出した「自由」というのが強いというのは、今私が読書するという「自由」を手に入れていて、「面白く」生きていると思うのだ。
「面白く生きる」=「自由」。
その自由を作り出すのは「自分」。
自分で作り出した自由だからこそ、「面白く生きる」ことができる。
本来「自由であることは面白いこと」だと気づかせてくれる。
他人に頼らない、自力で見つけた「自由」こそ、人生を面白くしてくれる最大の武器なのである。
孤独だからこそ「面白い人生」が待っているかも?
孤独は感じるときはどんなときだろう?
家にひとりぼっちのとき?
仲間はずれにされたとき?
人は仲間や家族や友達と一緒にいるときでも孤独を感じる。
それはどうしてだろう?
周りに人がいても、心はどこかひとりぼっちで、会話をしていても疎外感を感じてしまう。
なんだか孤独ってもの悲しくて、ネガティブなイメージが付きまといがちだ。
独居老人が1人で亡くなってしまうと、マスコミはこぞって「孤独死」とはやし立てる。
どうして孤独死は「悪いこと」になってしまうのだろう。
もしかしたら、1人で楽しく、今までの人生を回想しながら亡くなっていったのかもしれないのに、どうして「孤独死=悲しい死に方」と決めつけてしまうのだろう。
著者は、
一人暮らしの人が亡くなると、マスコミは「孤独死」という表現を使う。だが、その人が孤独だったかどうか、何をもって証明できるのだろう。本人は、一人でも人生を謳歌していたのかもしれない。「孤独」なんて微塵も感じてなかったかもしれないのだ。
と言っている。
それこそ「面白い人生」を送って満足して亡くなっていったかもしれないのに、1人で死ぬことを「寂しい人生を送ってきた人」みたいな報道するのはどこか不自然な気がするのだ。
著者がズバリ言っている。
「一人の面白さ」が本物
と。
孤独であることが決して「面白い人生」を送っていない証明にならない。
1人が好きな人も、1人が気楽という人も、この世にはたくさんいる。
その人たちが「つまらない」と言っていたら別だけれど、基本的には十分に1人の人生を、「面白い人生」を過ごしているように見受けられる。
著者は「読書」を例に出している。
読書は基本的に1人だし、孤独にページをめくる作業が永遠と続く。
けど、当の本人たちは楽しんで本を読んでいて、少なくとも「面白い」と思っていることをしているわけである。
それがたとえ傍からみれば孤独に見えたとしても、本人たちはちっともそんなこと思っていない。
孤独であることは、「面白くない人生を送っている」という証明にも証拠にもならないということは十分に感じることができた。
孤独であることを憂いないで。
孤独であることは悪いことではない。
孤独だからこそ「面白い人生」が待っているかもしれないのだ。
生きていれば面白い?自分の「面白い」は自分で見つけよう
「つまんない。何か面白いことはないかな」
「暇だな。何か面白いことはないかな」
暇を持て余し、気が付けば何時間もスマホを見ていたり。
私たち人間は退屈になったり、あまりにも暇を持て余し過ぎると、まるでこの世から自分に対しての「面白いこと」がなくなってしまったかのように感じる。
そもそもその人たちが求める「面白い」ことってなんなのだろう?
生きていさえすれば「面白い」ことってゴロゴロと転がっている気がする。
それを見つけるのも人生の目標になるかもしれない。
自分で「面白い」ことを見つけられないと、生きにくいと思うのだ。
人に頼って、他人任せで「面白い」ことを探そうとすると、すぐに飽きてしまったり、結局は自分に合わなかったり。
何事も面白がって生きていればいいのか?
ここでの著者の言葉がとても効く。
簡単に言えば「面白い方が生きやすい」ということだと思う。だが、もっと大事なことは、「面白いものは生きていないと分からない」という点である。
つまり、「面白くない」という思考そのものが、「面白い」生き方を否定するものだということである。
「面白い方が生きやすい」。
「つまらない」と「面白くない」という思考そのものが、私たちの人生そのものをつまらなくさせている。
生きにくい世の中になっているこのご時世、とにかく面白いことを探すことで少しでも生きやすい人生にしていかないことには、息が詰まってしまう。
ときどき息苦しくなるのはきっと、生きていることに対して面白さを見出すことができてないから。
面白いことを見つけつつ、探しつつ、「生きていれば面白い」「面白い方が生きやすい」を体現していけばいい。
それでも生きていれば悲しいことや、悔しいこと、辛いこともたくさんある。
でも、それでも、生きていなければ面白いものは見つかない。
だから今日も、生きていこう。
面白いことは、きっと見つかる。
まとめ
「面白い」と簡単に言ってしまうけど、ここまで深く掘り下げられるとだんだんと容易には口にできなくなってしまう気がする。
お笑いも面白いし、本も面白いし、YouTubeも面白い。
「面白い」ことを日常的に見つけ出し、それを楽しめば、人生もうけもんではないだろうか。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 恋愛工学の教科書を読んだ男女のぶっちゃけトーク【女性は絶対に読んではいけない!?】『ぼくは愛を証明しようと思う』藤沢 数希
恋愛工学の教科書を読んだ男女のぶっちゃけトーク【女性は絶対に読んではいけない!?】『ぼくは愛を証明しようと思う』藤沢 数希
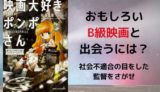
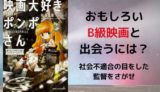
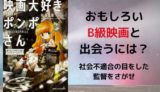



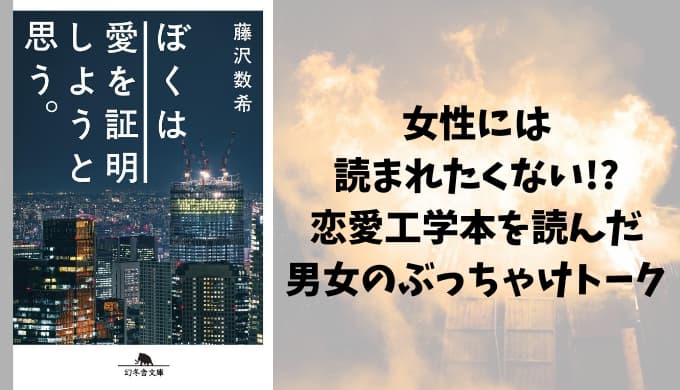
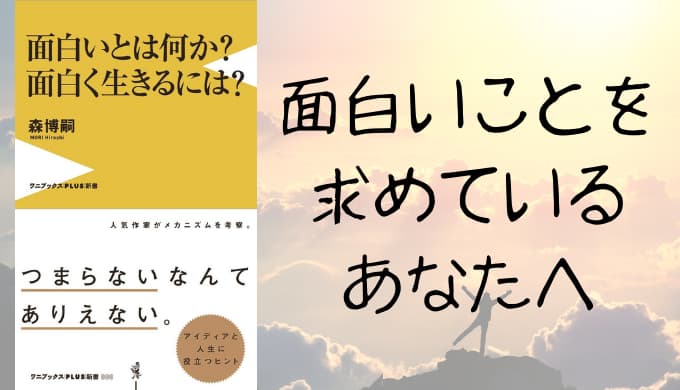

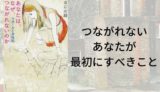
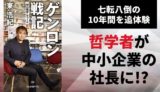
書き手にコメントを届ける