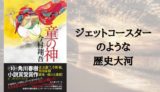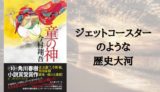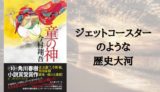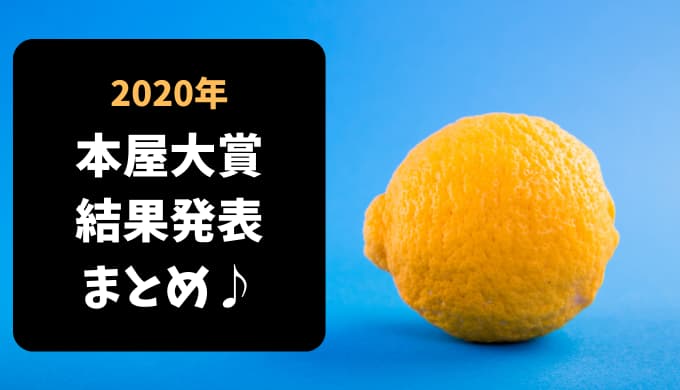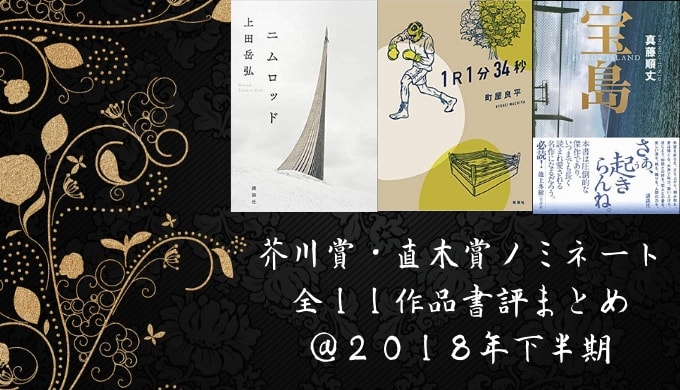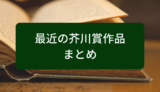2019年1月15日に同日発表された第160回芥川賞・直木賞。
ReaJoyでは受賞作品はもちろん、今回惜しくも受賞を逃したノミネート作品の書評も掲載しています!
今年は最近テレビにもよく出演されている社会学者の古市憲寿さんが芥川賞に、「夜は短し歩けよ乙女」の森見登美彦さんが直木賞にノミネートされるなど、話題性の高かった両賞!全ノミネート作品をご紹介します!
芥川賞・直木賞ってなに?
そもそも芥川賞や直木賞ってなにが違うの?という方も多いと思います。
どちらも1935年から続く非常に歴史のある日本が誇る文学賞です。
両賞の違いは、主に対象作品のジャンルにあります。
芥川賞の対象は中・短編の純文学作品。対して、直木賞の対象は中・長編のエンターテインメント小説です。
芥川賞は又吉直樹さんが「火花」という作品で受賞されて話題になりました!(本の主題歌を決める読書会@BREWBOOKSでのテーマ本にもなりました。読書会のレポートはこちら)
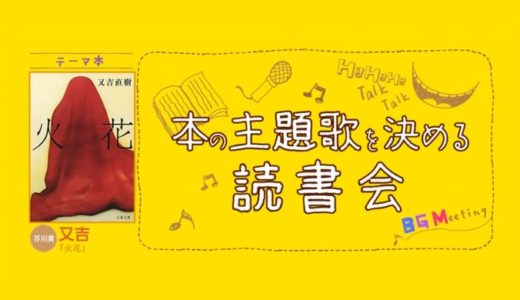 非公開: 『火花』の主題歌は、Gorillazの♫Left Hand Suzuki Methodに決定!!
非公開: 『火花』の主題歌は、Gorillazの♫Left Hand Suzuki Methodに決定!!
過去には元都知事の石原慎太郎さんが「太陽の季節」で受賞されたり、村上龍さんが「限りなく透明に近いブルー」で受賞されてセンセーショナルな内容も相まって350万部以上を売り上げるなど、毎度話題になる賞です。
一方の直木賞は、芥川賞よりも内容的には読みやすいエンターテインメントを対象としています。
過去には阿部寛さん主演でドラマ化されたことで非常に有名な池井戸潤さんの「下町ロケット」や、佐藤健さん、二階堂ふみさん、有村架純さん、岡田将生さん、菅田将暉さんら超豪華俳優陣が出演して映画化された、朝井リョウさんの「何者」などが受賞しています。
2018年度下半期の受賞作は?
2018年度下半期、芥川賞の受賞作は2作品!
上田岳弘さんの「ニムロッド」と町屋良平さんの「1R1分34秒」でした。
ニムロッド/上田岳弘の書評
「自分という人間は代わりがきかないものなのか?」と考えたことはないだろうか?
科学技術が発展し、社会の仕組みも複雑になればなるほど、そういった疑問は私たちにとって重要なテーマになるかもしれない。
そんなテーマを扱ったのが、第160回芥川賞受賞、上田岳弘さんの『ニムロッド』だ。(つづきは記事へ)



1R1分34秒/町屋良平の書評
デビュー戦を初回KOで飾った「僕」は2敗1分けと敗けが込んできていた。
次の対戦相手は「近藤青志」。
「僕」は対戦相手を調べれば調べるほど夢の中では親友のような関係になってしまう。
結局、近藤青志との試合には負けてしまうが、夢でとはいえ親友のような関係であった相手に負けた「僕」は裏切られたような気持ちになる。
勝てたかもしれない、ドローには持って行けたかもしれないなど数えきれないあったかもしれない可能性を考えながら、自分の考えすぎる癖が煩わしくなってきた。(つづきは記事へ)
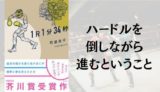
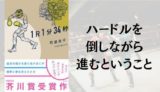
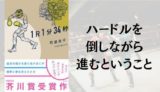
2018年度下半期の直木賞受賞作は
真藤順丈さんの「宝島」でした。
宝島/真藤順丈の書評
時は戦後。沖縄が、アメリカの統治下に置かれていた1952年です。
島一番の戦果アギヤーであった「オンちゃん」を中心に、グスク、レイ、ヤマコの三人は、深い絆で結ばれていました。
しかし、嘉手納基地の強奪未遂事件がきっかけで、オンちゃんは消息不明になってしまいます。
三人は彼の姿を探しながらも、胸に思いを秘めて、それぞれの人生を歩みます。(つづきは記事へ)
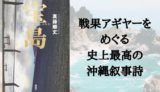
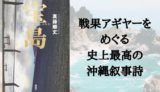
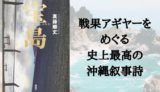
惜しくも受賞を逃した注目のノミネート作品は?
芥川賞ノミネート作品
ジャップ・ン・ロール・ヒーロー/鴻池留衣の書評
残念ながら芥川賞受賞には至りませんでしたが、だからといって決して悪い作品ということではありません。そもそも候補にあがったこと自体がこの作品のおもしろさを表しているとも言えます。
たとえ受賞しなくとも、作品そのものの魅力があります。その魅力は1ぺージ目から感じることができますので、ぜひ紹介したいと思います。
試し読みでも、本屋に行ったときにでもいいので1ページめくってみてください。この作品は他の候補作に比べて少々異色の作品になっています。
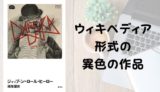
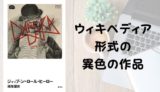
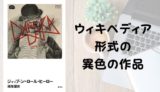
戦場のレビヤタン/砂川文次の書評
残念ながら受賞は逃してしまったが、「文學界 12月号」に掲載された芥川賞候補作、砂川文次『戦場のレビヤタン』が素晴らしかったので紹介したい。
「紛争地域」「武装警備員」などの厳つい単語の飛び交う作品を、女であり母親であるという全くかけ離れた属性の私がどう読んだか。この作品を手に取る後押しになると嬉しい。(つづきは記事へ)
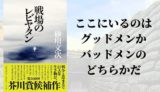
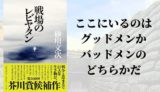
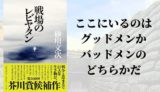
居た場所/高山羽根子の書評
「わずかずつ世界を現実からずらして、異化する技術は総じて評価が高かった」
これは選考会後の選考委員による会見でのコメントです。また委員全体から「たいへんよい雰囲気を作っている」という評価があったそうです。選考経過についての講評を聞きながら疑問が浮かびます。
「わずかずつ世界を現実からずらして、異化する技術」って何なんだ?
その技術から生まれる「たいへんよい雰囲気」とは?
これは読むしかない!
芥川賞発表の翌日には本屋で『居た場所』を手に取り、その雰囲気を堪能しました。(つづきは記事へ)
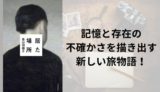
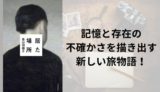
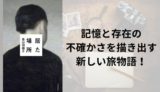
直木賞ノミネート作品
信長の原理/垣根涼介の書評
戦国小説の愛好家であればご存知のごとく、信長の人生は巨匠たちによって書きつくされている。
山岡荘八先生の『織田信長』、司馬遼太郎先生の『国盗り物語』と枚挙にいとまがない。
これらの名作によって信長像は確固たるものになっており、並の作家であれば新たに書こうという気は起きないであろう。
作者である垣根氏はこの聖域に踏み入る為、「2・6・2の蟻の法則」を手にした。(つづきは記事へ)
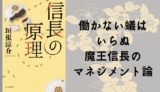
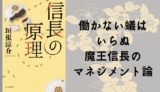
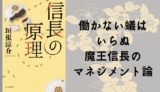
ベルリンは晴れているか/深緑野分の書評
1945年7月、ドイツが戦争に敗れ、米ソ英仏の四か国統治下に置かれたベルリンが舞台です。
ヒトラー亡き後、焦土と化したベルリンでひとりの男が死にます。その男はドイツ人少女アウグステの恩人です。
アウグステは疑いの目を向けられつつ、恩人である男の甥に訃報を告げるために旅立つことになります。
物語はアウグステが甥を探す物語と、男の死よりももっと以前、アウグステの生い立ちから恩人の不審死までを描いた幕間の章が交互に進みます。
様々なルーツや思想を持つ人々が時代にしがみつくように生きています。
そんな時代背景の中で描かれる圧倒的スケールの歴史ミステリです。(つづきは記事へ)
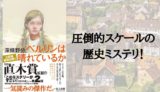
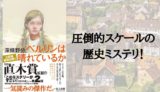
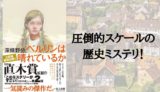
童の神/今村翔吾の書評
他人とワタシ、一体何が違うのかと考えることがある。
同じようなものを食べ、同じものを見ても、考えていることは全く違う。
この違いは、どこから来るのだろうと考える。
重要なことは、人それぞれに背景があるということ。
身分制度があった時代は、今よりも「背景」の違いが顕著だった。
今も昔も、「自分とは何か」と悩む人はいるだろう。
ただただ、流れに乗って生きている人もいるかもしれない。
むしろ、そんな人の方が多いだろう。
しかし自分の中に、ささやかでも「自分は何なのか」という疑問が生まれたとき、この「童の神」を手に取って欲しいと思う。(つづきは記事へ)