目次
祝! 芥川賞受賞
今回の芥川賞(2018年下半期160回)では町屋良平さんの『1R1分34秒』(いちらうんどいっぷんさんじゅうよんびょう)と上田岳弘さんの『ニムロッド』が二作品同時受賞しました。
二作品同時受賞は前々回の石井遊佳さんと若松千佐子さん以来になります。
『1R1分34秒』は「ボクシング」を題材にした作品、『ニムロッド』は「仮想通貨」を題材した作品になります。
この記事では町屋良平さんの『1R1分34秒』を紹介します。
町屋良平さんについて
町屋良平さんは1983年生まれ。
『青が破れる』で第53回文藝賞を受賞してデビューしました。
この作品もボクシングを題材にした作品になります。なのでデビュー作と同じ題材で、原点にかえった作品での芥川賞受賞といえます。
この『青が破れる』で三島由紀夫賞候補。
「踊ってみた」を題材にした『しき』で芥川龍之介賞候補、野間文芸新人賞候補となりました。
芥川賞候補2作品目での受賞ということで小説家としては順調といえます。
コンスタントに文芸誌にも作品を掲載していたので、多くの方が今回の町屋良平さんの受賞を予想していたのではないでしょうか。
過去の選評を読んでみると作品自体の評価だけではなく、「今後書き続けることができるか」ということも評価の対象になっていることがうかがえるので、今回の受賞も作品だけでなく質の高い作品を書き続けてきたこと自体も評価されたといってもいいのではないでしょうか。
あらすじ・内容紹介
デビュー戦を初回KOで飾った「僕」は2敗1分けと敗けが込んできていた。
次の対戦相手は「近藤青志」。
「僕」は対戦相手を調べれば調べるほど夢の中では親友のような関係になってしまう。
結局、近藤青志との試合には負けてしまうが、夢でとはいえ親友のような関係であった相手に負けた「僕」は裏切られたような気持ちになる。
勝てたかもしれない、ドローには持って行けたかもしれないなど数えきれないあったかもしれない可能性を考えながら、自分の考えすぎる癖が煩わしくなってきた。
ある時、トレーナーにも見捨てられ「ウメキチ」と呼ばれる男が「僕」の相棒になった。
「ウメキチ」に不満を感じ、反発しながら、「僕」はボクシングを続ける意味を考えていた。
1R1分34秒の感想(ネタバレ)
ボクシングを知らなくても読める
あらすじからもわかる通り、この作品はボクシングを題材にし、ボクシングを通しながら葛藤や挫折、成長を描いた小説になっています。
読者の中にはボクシングを好きな方もいれば、全く知らないという方もいると思いますが、ボクシングを好きな方はもちろん、全く知らない方も楽しめる作品になっています。
というのも、この作品は急にボクシング特有の専門用語やあるあるが出てくることがありません。
もちろん全く専門用語が出てこないなんてことはありませんが、唐突に出てくることなく文脈の上に丁寧に出てくるので十分意味の分かるようになっています。
また主人公が動きを確認しながらその用語の動作を行うので、どういう動きかがよくわかります。
ボクシングを知っている人と知らない人とで前提知識が違う中、どちらの読者も楽しめるようになっています。
なによりすごいのが、もし読んでいて用語がわからなくても楽しめるというところです。
たとえば、右ストレート・アッパー・ワンツーくらいなら多くの方がわかるでしょう。
ならインファント・ダッキングウィービングはどうでしょうか。
ボクシングを知らなければわからない、という方がほとんどなのではないでしょうか。
もちろん先ほど書いたように文脈で読み取れますが、もし読み取れなくても十分に楽しめます。
どういうことかというと、試合のシーンがものすごく想像しやすい書き方がされているんです。
スポーツやアクションものの小説で難しいのが同時進行で進んでいく事柄の描写です。
試合や戦う場面では、自分と相手、交互に動作が行われているわけではありません。
また行動の一つ一つに自分の考えや相手の作戦を反映させつつも、その動作を同時進行に行われていることを、リアルタイム性を表現しなければなりません。
この『1R1分34秒』では見事にそれを書ききっています。
単語1つ拾えばわからなかったボクシングの用語もあるかもしれません。
なので1文でとらえて読んでみてください。
流れで読めば難なく読むことができます。
その試合の雰囲気、なにより主人公の心情描写が精密に反映されています。
そして、そこに反映されている心情描写こそが私たち読者との距離をぐっと縮める部分でもあります。
ハードルを倒しながら進んでいくということ
ここに書かれている主人公は世界を目指しているわけでも、全日本の大会でチャンピオンになることでもありません。
デビュー戦を初回KOで飾ったときは優勝を目指していたものの、徐々に目標は下がっていき、ついには次の試合で勝つというところまでに下がっていってしまいます。
現実的といえば現実的かもしれません。
負け続けたとき、優勝という目標が身の丈に合わなくなったとき、ほとんどの人が目標を下げてしまうのではないでしょうか。
そして自分が目標を下げて、さらに下げて目の前のことに精一杯になっていることに気が付いたら、皆さんはどう思うでしょうか。
優勝という目標を掲げたとしても、やることは目の前の試合を一試合ずつ勝っていくことですから、本質的にはやるべきことは変わっていないといえるのではないでしょうか。
もし同じことを考えた方がいたらぜひ読んでください。
この主人公も同じことを考えています。
これはスポーツをやっている方、やっていた方ならよくわかると思います。
部活の地区大会。
目標が優勝から、現実を知りだんだんと下がっていった経験があるのではないでしょうか。
これはスポーツに限らず言えることだと思います。
入社した時に立てた目標や入学した時の目標。
また会社や大学だけでなく、私生活でも。
春になるたびに目標を立てたものの達成できずに、たとえば毎日つけると決めていた日記は三日に一回になり週一回となり、という経験は誰しもあると思います。
日記なら途中でやめても問題はありませんが、会社はどうでしょうか。
目標が下がっていてもどうすることもできず、かといってやめることもできない。
まさに主人公もこのような境地に立たされます。
最初は自分で選んだボクシングという道。
でも今は「なぜ続けているのか」という問いに答えることができません。
ただ惰性で続けている。そこへ追い打ちをかけるようにトレーナーにも見捨てられてしまいます。
この作品はスポーツものといっても、苦労の末に優勝するといった感動ものではありません。
さまざまなスポーツを題材にした作品が小説に限らずありますが、苦しいくらいに自分を反映できた作品はどれくらいあるでしょうか。
共通点があったとしても、優勝するフィクションと、優勝なんて遥か彼方の現実、そこに自分は書かれていないという方が多いのではないでしょうか。
この作品は違います。
この主人公は決して特別な存在ではありません。
ずば抜けた能力を持っているわけでもなく、才能もありません。
最初は輝かしい結果を出したものの、むしろそういう結果を出してしまったからこそ、辛く苦しい状況が続いていきます。
弱さが書かれているのです。
ここで過去の選評を紹介したいと思います。
「高いハードルをはなから見放すことと、跳んで倒しながらも前に向かうことの、どちらが小説にとって大切なのかを、もう一度考える必要があるだろう。」
山田詠美「選評」『文藝春秋』平成28年/2016年9月号
ここでどちらが小説とはいいきれませんが、私はどちらも小説になりうるし、文学にもなりうると思っています。
そしてこの作品はハードルを踏んで倒しながらも前に向かう小説であると思いました。
主人公はなぜボクシングを続けるのか明確な答えを出せないまま進んでいきます。
トレーナーに見捨てられウメキチという男と新たに練習していきますが、そこでも上手くいかず八つ当たりをしたり不満を漏らしたりします。
しかしそれでもボクシングを止めることはありません。
自分にはボクシングしかないと、どこかでわかっているのでしょう。
その選択肢がたとえ他に選びようがないからだとしても、それを受け入れ進んでいく姿に胸を打たれると思います。
勇気付けられもすると思います。
ハードルをはなから無理だと諦めることをせず、倒しながらも進んでいく。
まさにそういう作品ではないかと思います。
無駄のない登場人物
この作品で出てくる主な登場人物に、映画を撮っている友人やトレーナー、その代わりとなったウメキチ、ジムに来た女の子などが出てきます。
それぞれ主人公と関わってくるのですが、ただ話を広げるだけでなく、主人公の心情を上手く引き出しています。
たとえば友人。映画を撮っている友人ですが、主人公にもカメラを向けます。
そこで自由に話してくれ、と言われ主人公は思ったことを話します。
思ったことをそのまま話すわけですから、一人称の地の文のようなまとまった綺麗なものではありません。
とりとめもなく溢れ出す感情。
語るという不慣れな行為から出てくる言葉がリアルな心情を引き出しています。
上手く言葉にできないままそのまま思ったことを言うことによって一人称語りが単調にならないようになっています。
また友人がコンテストで優勝したと言われたときの憎むような嫉妬が描かれていたり、美術館に連れていかれたとき、芸術と触れた時の心情など、多面的に描かれています。
またシャドーやってと言われるシーンでは、見せるようのシャドーを、行います。
そこでも単にサービス精神でやって終わる、ではなく、主人公の心情が反映されています。
見せるシャドーボクシングは、綺麗なもの。
ただ、それではいけないことを自覚していて、綺麗なボクシングか、勝つためのボクシングか。
ウメキチに言われた台詞を反芻し、考えるきっかけにもなっています。
また女の子との関わりでは、弱い自分を慰めて欲しいという弱さを出しつつも、最終的にその女の子とどうなるか(ネタバラシになってしまうので書けませんが)ということによって主人公が選んだ決断もわかるようになっています。
このように単に話を広げるためや、あるエピソードを通じて主人公を描くための存在、なんて使い捨てのような存在にならずに、人間関係を描き、主人公をあらゆる角度から書いています。
ボクシングという相手との戦いが中心となるスポーツですが、まるでマラソンのように自分自身の戦いに昇華しています。
試合に比べたら練習のシーンはおもしろみがないのが一般的だと思います。
しかし緻密に書かれる練習風景が読者を飽きさせません。
技術的に成長するだけでなく、精神的にも成長していくからではないかと思います。
そしてこれは身体性というものにも繋がってくるように思います。
文学と身体性
動作に連動するように言葉が発せられ、感情が動く。言葉と身体の親和性が非常に高い小説だと思います。
考えるより先に体が動いたり、逆に考えているように体が動かなかったり、とそのずれさえも描きこの作品をただのスポーツ小説、青春小説に留めません。
試合中の描写は勝敗が気になるだけでなく、試合を通した主人公の心情の揺れ動きが必見です。
上手くいなかければ今までの練習に疑問を抱いたり、後悔をしたりします。
思い通りに動かないもどかしさと苛立ち。
体と結びついて湧き上がってくる感情だからこそ読者が感じるものがあります。
また動作からくるものだけでなく、試合中、練習中、普段の生活と、それぞれの状況に置かれたことによる変化というのもまた身体性といえるのかもしれません。
またそれは誰といるかによっても変わります。
「ウメキチ」といるときは反抗的な態度をとっていても、友人といるときは弱音を吐くなどと、自分がいま誰と接しているか、どのような状況に置かれているかによって自分自身に変化が起こります。
このように心情⇔身体と互いに作用する様子が描かれています。
まとめ
紹介したように主人公っぽくない人物がこの作品の主人公です。
主人公っぽくない人が圧倒的多数の現実において、まるで自分たちと同じような立場の人物が主人公の小説は、たくさんの人の共感を得られるのではないかと思います。
またバーチャルが流行り、なんでもスマホで済んでしまい、身体性の欠如が指摘されています。
これは決して悪いことではないですが、この急激な変化が起こっているときに身体性が感じられる小説は、あえて手間のかかるアナログのものを使うような心地よさが感じられるのではないかと思います。
純文学ということやスポーツものということを気にせず、ぜひお手に取ってみてください。
主題歌:YUI/again
YUIの『again』を選んでみました。
なんのために生きているのか、という問いかけは「僕」がなぜボクシングを続け生きているのかという疑問にシンクロすると思います。
他にも「もう引き返せない」や「無難になんてやってられないから」は今更ボクシングを辞められないとも感じ、綺麗なボクシングか勝つためのボクシングをするのか選択する状況にもぴったしです。
ぜひこの曲と一緒に本を開いてみてください。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 『しき』あらすじと感想【芥川賞受賞作家が投じる痛みとずれを伴う青春小説】
『しき』あらすじと感想【芥川賞受賞作家が投じる痛みとずれを伴う青春小説】




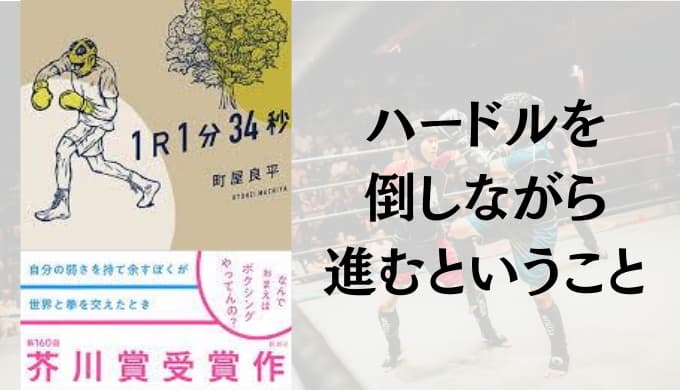

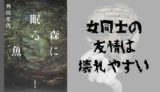
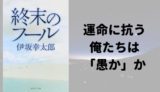
大学に入学した事実はありません。御本人は2016年12月の対談で『僕は高校を出てから、大学へは行かずにフリーターになって小説を書いていて、』と明言されております。証拠→[http://web.kawade.co.jp/bungei/909/ 【町田康×町屋良平 特別対談】] ウィキペディア上に記載された経緯ですが、該当の某大学を宣伝したいがために虚偽の記載をしたことが判明しております。
ご指摘ありがとうございます。失礼しました。
訂正しました。