「自分という人間は代わりがきかないものなのか?」と考えたことはないだろうか?
科学技術が発展し、社会の仕組みも複雑になればなるほど、そういった疑問は私たちにとって重要なテーマになるかもしれない。
そんなテーマを扱ったのが、第160回芥川賞受賞、上田岳弘さんの『ニムロッド』だ。
登場人物
サーバーを管理する会社に勤めていたが、社長の気まぐれで、仮想通貨の発掘を担当させられることになる。
ときどき悲しいわけでも、感動しているわけでもないのに左目から涙が流れてくるという症状をもつ。
前夫とは子どもの染色体異常が見つかり、堕胎させたことをきっかけに離婚。
このことによって傷を抱えて、睡眠薬を使用している。
あだ名はニムロッド。中本の元同僚。
書いた小説が3回新人賞の最終選考で落選している。
うつ病になったことをきっかけに、名古屋の実家に移り住む。
東京を離れた後も、中本に対して、「駄目な飛行機コレクション」や「僕はニムロッド、人間の王」と始まる奇妙な小説を送りつける。
あらすじ・内容紹介
この作品ではビットコインを代表とする仮想通貨がキーになっている。
「仮想通貨はソースコードと哲学でできている。」
このセリフは荷室が中本に対して放ったセリフである。
仮想通貨の価値が担保されるためには、世界中の人々が仮想通貨を採掘するために、コンピューターを動かし続けなくてはならない。
すなわち、人々が仮想通貨を欲望し続けなければ、価値そのものがなくなってしまうということだ。
これは私たちもそうだろう。
私たちのほとんどが自給自足で生きていくことができず、誰かから欲望されなければ、存在が揺らいでしまうし、生活することもできない。
自給自足を行っていた社会から、科学技術の進歩や経済の高度化によって、私たちの存在は常に揺らいでいる。
誰かから必要とされなければ、存在自体無くなってしまう。
仮想通貨という現代の象徴のようなものを使って、この私たちが抱える不安を巧みに表現している。
ニムロッドの感想(ネタバレ)
人間は交換可能だ
この作品では、人間の交換可能性が大きなテーマとして扱われている。
荷室が中本にメールで送る小説は、すべての人間がAIに結びつき、一つに溶け合って、すべてのことを知り尽くしてしまったという内容だった。
それに対して、中本はこう思うのだ。
できることがどんどん増えていって、やがてやるべきこともなくなって、僕たちは全能になって世界に溶ける。「すべては取替え可能である」という回答を残して。
実際に、ほとんどの知識がインターネットを使えば、手に入る。
そのため、昔だったら重宝されたであろう知識を豊富に持っている人までも、交換可能になってしまった。
将棋で人工知能がプロ棋士に勝っているのをみても、それは明らかだ。
人工知能を使えば、素人でもプロ棋士に勝ててしまうかもしれないのだ。
実際に中本も世の中には手に余るほどの情報があふれていることを悟り、それならば、知らなくてもいいという態度をとっている。
感情も交換可能に?
田久保と荷室は過去に傷を抱えているのにもかかわらず、作中では涙を見せない。
しかし、その一方、中本は感情のない涙を流す。
これを読んで、感情までもいつか交換可能になってしまうのでは?という漠然とした不安が私の頭の中に浮かんだ。
科学技術が進歩すれば、感情さえ、交換できるようになってしまうかもしれない。
もしそうなれば、自分が自分でいなければならない理由は果たして何なのだろうか?
まとめ
主人公である中本は未来の人間を象徴しているのでは?と読み終えてから思った。
彼は、情報が多すぎて、人間には把握しきれないことを悟り、あえて無知でいる。
さらに、何の感情もないのに涙を流している。
全能になり、あらゆるものが交換可能になった未来の人間として、中本を描かれているのではないだろうか?
これは私の勝手な解釈である。
しかし、このように自分の解釈を重ねながら、読むことができるのもこの作品の魅力なのだと思う。
主題歌:Radiohead/Kid A
作中で、Radioheadのボーカル、トム・ヨークについて言及される場面があり、念仏みたいな歌ばっかり作っていると紹介されている(笑)
この小説を読んだ人がRadioheadを食わず嫌いしてしまうのは、ファンとして心苦しいので、Radioheadの代表曲「Kid A」を主題歌として、選曲した。
この曲の歌詞は不気味で、シンセサイザーの音が私たちの不安を煽ってくる。
この小説のように。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
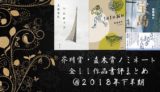 芥川賞・直木賞(2018年度下半期)ノミネート作品書評まとめ
芥川賞・直木賞(2018年度下半期)ノミネート作品書評まとめ






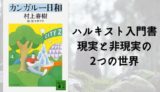
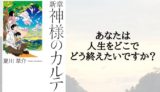
書き手にコメントを届ける