挑戦的な本のタイトルですが、生きる上でとても参考になる心理学の本です。
特に世間一般の価値観や、周りの目線を気にして自分らしく生きることができていないかもしれないと思われている方にぜひ読んでほしい。
心の底から豊かだと思える幸せを見つけられるかもしれません。
目次
あらすじ・内容紹介
著者は筑波大学卒の心理研究家。
自己啓発書の元祖ジェームス・アレン『「原因」と「結果」の法則(原題:AS A MAN THINKETH)』を基礎にしたと思われるものでありながらも、学者向けではなく、我々一般人が日常的に経験することについてケースメソッドのような形式で、どのように心理学という学問を生活に活かすかを説いた1冊です。
ともすれば、「心理学」と聞くと、自分優位に事を運ぶために人を欺くためのものと思ってしまいますが、この1冊は違います。
学問によって人が救われること。
学ぶことによってあなただけではなく、周りの方々も幸せに過ごせますように。
という想いが込められています。
『ジーパンをはく中年は幸せになれない』の感想
周りの目に惑わされず、自分の価値観に従えばいい
自分の望むままに行動しても、道徳の規範から外れることはない
孔子の言葉です。
ジーパンを履いて若作りするような、若いだけが取り柄の価値観は危ないということ。
年齢を重ねると、上記の心境にならないことには、挙句のはてに自分を追い込んでしまうこともあるので、モラルを高めましょう、ということです。
コールバーグの「モラルの発達段階説」
レベル1 自分の損得で判断します
レベル2 社会のルールや世間の目に基づいて判断します。
レベル3 自分の良心に従って判断します
私のような俗世間で給料が上がらないことに腹を立てている人間には関係ないと思ってしまいますが、諦めるにはまだ早いようです。
5人に1人、つまり20%くらいの人はここまで到達できるそうです。
なんだか希望が湧いてきます。
成功したのに満たされないのはなぜ?
某銀行の情報誌が経営者や重役など、成功者にアンケート調査を行った。
それによると「なぜか心が満たされない」ことに悩んでいる人が多いことがわかった。
なぜ成功したのに心が満たされないのか?
何が欠けていたのか?
幸福には3種類ある
【パワー動機】と【達成動機】と【親和動機】です。
簡単にまとめると、
【パワー動機】は「勝ち組になりたい」
【達成動機】は「夢をかなえたい」
【親和動機】は「人と心のつながりを持ちたい」
わかりやすい例が掲載されておりました。
あるバンドがレコード会社の目に留まったのだが、デビューの条件として異なる音楽性を求められる。
その場合、デビューするために音楽性を変えようとするのが【パワー動機】タイプ。
自分たちのやりたいことが出来ないのなら意味がないと断るのが【達成動機】タイプ。
デビューしなくてもいいから仲良くやっていこうよ、と仲裁するのが【親和動機】タイプ。
自分がどのタイプか見極めて選択しないと、もし成功したとしても心が満たされない結果になるそうです。
裏を返せば、世の中の成功本に踊らされることなく、特に成功しなくても、自分にふさわしい幸福を目指すことで、後悔のない人生を送ることが出来るのではないでしょうか。
「こうゆう女はダメだ」と言いながら、そういう女と浮気する
これは【二分割】といって、多くの男性に見られる心理です。(中略)もともと無理に分割したものなので、両方とつきあってはじめて、精神的に安定するのです。
男性心理について学術的に分析をされていて、なんだか笑えてきます。
【二分割】の傾向があるかどうかの見分け方まで解説されており、婚活中の女性にもこの本はおすすめ。
ビジネス書と思っていましたが、実用書なのかもしれません。
不幸がうつるのはなぜか?
じつは、不幸は実際にうつることがあるのです。といっても、悪い運勢がうつるとか、悪い気がとか、そういうオカルト的なことではありません。うつるのは、考え方のクセです。
失敗や成功の原因を「何」だと思うか。
まったく同じ状況でも、人によって、以下の4種のどれかを特に選びやすいという傾向があるそうです。
これを【原因帰属】といいます。
この4種の【原因帰属】は、次のように分類できます。
・自分自身の問題《能力》《努力》
・自分の外部の問題《運》《課題の難易度》
知り合いの精神科医に、「何か上手くいかない事があった時は自分のせいにしますか?他人のせいにしますか?」と尋ねてみたところ、
「自分のせいにすると落ち込むし、他人のせいにすると腹がたちますよね。」
とお答えいただき、やり過ごすしかないのかと思っていたのですが、ここに答えがありました。
《努力》に【原因帰属】すれば、失敗したときにも、成功したときにも、つねに前向きな気持ちを失わずにすむのです。
まとめ
この記事を読んだあなたにおすすめ!
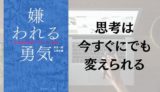 『嫌われる勇気』あらすじと感想【今なお売れ続けるのはそこに救いがあるから】
『嫌われる勇気』あらすじと感想【今なお売れ続けるのはそこに救いがあるから】




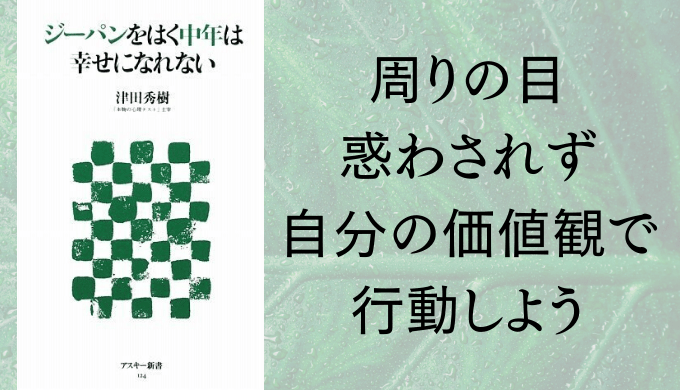

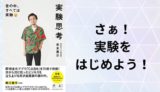
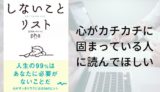
書き手にコメントを届ける