ちょっと雑談がてら私の読書スタイルについてお話すると、読むジャンルは小説とビジネス書、それから仕事関係の専門書が中心です。
漫画はもう何年も読んでいません。
嫌いってわけじゃないけど、読むのが遅いんです。
例えば、「ザワザワ」「はっ!」という様な擬音もきちんと読みます。
漫画1冊読むのに40分くらいかかります。
だったら、アニメでいいよねというスタンスです。
余談はこのくらいにして・・・
今回紹介する本は、ビジネス書です。
この本を読んでいなかったら、ReaJoyのライターとしての私は存在していなかっただろう。という1冊です。
これを機にちょこちょこビジネス書の記事も書いていければ良いなと思っています。
普段は本を見返しながら記事を書くのですが、今回は私の記憶上で書いています。
この本を読んだきっかけ
日頃、「研修」や「セミナー」などに参加する機会がよくあります。
その場でふむふむとメモを取り、わかった気になっている自分。
専門知識を得るため、様々な本を読んでいるだけの自分。
得た知識を活かさなければ!
と思うものの、それが中々出来ず悩んでいました。
そんなときに出会ったのが、『学びを結果に変えるアウトプット大全 』です。
(以後、アウトプット大全と呼ばせてください。)
黄金比は3:7
これは理想のインプットとアウトプットの黄金比率。
インプットが3でアウトプットが7だ。
心に手を当てて考えてみてほしい。
果たして自分はこの割合でアウトプットが出来ているだろうか?
みんな圧倒的にインプットばかりしているよね。
10冊より3冊
趣味が読書の人には少し耳が痛い話かもしれない。
 Aさん
Aさん
 樺沢先生
樺沢先生
 Aさん
Aさん
 樺沢先生
樺沢先生
3
アウトプットっすることが大切だって言われても…
どんなことをすればいいか分からない。
恐らくこういう思考に陥ってしまう人は、完璧主義なのかもしれない。
「3」がひとつのキーワード
- まずは30点
最初から完璧を目指さない。100点を目指して考え込むより、まずは30点を目指し、そこから修正を重ねて100点に近づければ良い - 本を読んだら、その本の中から学んだことを3つ書き出す
- 自分が読んだ本について2週間で3回話す
他にも色々とアウトプットの方法が書かれているが、実際に読んで自分に合う方法を見つけてほしい。
この本から得たこと
早速、この本から学んだことを3つ書いてみる!
- 雑談するのもアウトプットの1つ
内容よりも1度に沢山話すよりも、ちょこちょこ話す方が良い。
「ザイオンス効果」と言って、接触回数が増えると好感度が上がる。 - パワポは構成が固まってから
いきなりスライドを作ろうとしても中々出来ず。そこで止まってしまう。
じっくりアイデアや構成を書き出し、纏まってきたらスライドを作ろう。 - フィートバックをもらうこと
アウトプットしたら終わりじゃない。
失敗した原因や成功した理由を考える事が大切。
パワポはいつも、よーし作るぞ!と意気込むものの、白紙のスライドのままただ時間だけが過ぎたりしてた。
そしてアウトプットだけじゃなく、フィードバックを受けて次に繋げることも忘れてはいけないのだ。
感想
中身がカラーで、基本的に見開き1ページで1つのテーマが終わるので、「ビジネス書って難しそう」「なんだか取っつきにくそう」と思っている人でも読みやすい1冊です。
今すぐ実践できそうなアウトプット方法も紹介されているので、みなさんも自分にできそうなことから挑戦されてみては??
私のアウトプット
私がこの本を読んで、先ず自分が出来そうなアウトプット方法が読書感想を書いたり話したりすることでした。
手軽な方法として、読書会に参加するようになりました。
読書会では、ReaJoyで記事にしていない本を紹介したりしています。
それからすぐにReaJoyのライターをはじめました。
ライターは未経験なので、書きたいことがあってもそれを表現するのに悪戦苦闘する毎日です。
アドバイスをもらいながら記事を仕上げてなんとか形にしています。
ReaJoyのメンバーと情報交換も出来たり、読書会で本が好きな方たちとお話できるのがとても楽しいです。
主題歌:RAM WIRE/歩み
RAM WIRE「歩み」
グループ名のRAM WIREは「羊たちの絆」という意味の造語。
「自分たちは迷える子羊であり、同じように迷っている人たちとの絆を築きたい」という思いがこめられています。
この本を手に取った多くの人も、悩んだり迷っているのでは?
『アウトプット大全』で簡単なアウトプット方法を紹介してもらい、この曲でさらに背中を押してもらえると思います。
上手く歩かなくていいから 一歩ずつ君らしくあれ
完璧じゃなくて良いから、まずは一歩を踏み出す(アウトプット)ことが大切。
そんなことを言っている本であり、そんな曲だと思います。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
アウトプットの手助けとなるメモについて学んでみませんか?
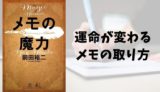 『メモの魔力』あらすじと感想【運命が変わるメモのとり方とは?】
『メモの魔力』あらすじと感想【運命が変わるメモのとり方とは?】




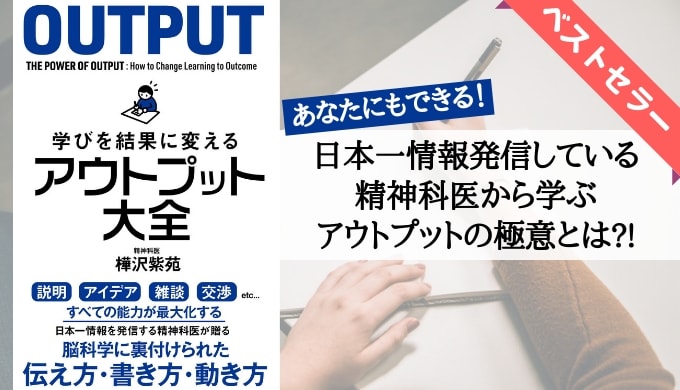
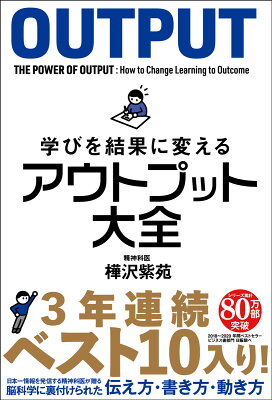

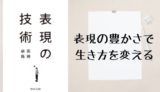
書き手にコメントを届ける