2016年、2017年の「東大生協文庫売上1位」となった『思考の整理学』。
1986年に初版が発行されてから異例のロングセラーを続けており、大学自体に生協で見かけた人も多いはず。
一見、難しそうに見える本書だが、一度紐解けば中身はシンプルでわかりやすい。
この記事では要約を踏まえながら、その面白さをご紹介する。
目次
こんな人におすすめ!
- 創造的な仕事をするためのコツを探している人
- 大学の生協や本屋でこの本を見かけたことがある人
- 以前読んで「難しい」「つまらない」と読むのをやめた人
あらすじ・内容紹介
2016年、2017年の「東大生協文庫売上1位」となった『思考の整理学』。
作者は受験現代文で頻出の外山滋比古氏だ。
実際に読んでみると本書が、1986年初版だとは思えないほど、現代でも役立つ情報が満載であり、心に残る名言の数々も多くあった。
しかし、ネットで検索をかけてみると、「難しい」「つまらない」と感じた読者の意見も少なからずある。
そこで本記事では、『思考の整理学』の全6章を3つのパートにわけ、要約も交えながら、わかりやすくその内容を伝えていきたい。
『思考の整理学』の感想・特徴
「飛行機人間」は思考を溜め、発酵させる(第1章、2章)
大学のレポートなどでも出題されることの多い、第1章は「①グライダー②不幸な逆説③朝飯前」の3本立てである。
第1章で外山氏はこれからの人間は「グライダー兼飛行機人間」になるべきだと訴える。
人間には、グライダー能力と飛行機能力とがある。受動的に知識を得るのが前者、自分で物事を発明、発見するのが後者である。両者はひとりの人間の中に同居している。(……)現代は情報の社会である。グライダー人間をすっかりやめてしまうわけにも行かない。それなら、グライダーにエンジンを搭載するにはどうしたらいいのか。学校も社会もそれを考える必要がある。この本では、グライダー兼飛行機のような人間となるには、どういうことを心掛ければよいのかを考えたい
つまり、知識をただため込むだけなら、グライダー能力に長けたコンピューターで事足りる。
だからこそ、これからの時代は従来のグライター能力に加え、自らが考え、発見する飛行機能力も兼ね備えた人間になる必要があるのだ。
「不幸な逆説」では、知識を与えることに指導者が有能であればあるほど、学習者は受け身となり、本当の教育にはならない、と書かれている。
ではどうすればいいのか。
重要なことは学習者が自発的に興味を持つことである。
かつての日本では、漢文をひたすら暗唱させることで学習者に「一体ここには何が書かれとるんや」と興味をもたせる式の教育がされていたらしい。個人的にはそれもどうかと思うけど。
その上で第2章で外山氏は、優れた思考とは「カクテル」のようなものだといっている。
発見したアイデアにはすぐ飛びつかず、アイデアを複数案だしてからしばらく放置し、考えが煮詰まったのちに調和させよというのである。
また、その際の思考はすべて自分の独創性に満ちている必要はない。
第1章で述べた、情報をインプットする力、つまり「グライダー能力」を活かして収集した情報を「飛行機能力」をもって調和させればいいのだ。
新しいことを考えるのに、すべて自分の頭から絞り出せると思ってはならない。無から有を生ずるような思考などめったにおこるものではない。すでに存在するものを結びつけることによって、新しいものが生まれる
いかかだろうか。
一見すると難しそうな同氏の主張もざっくりと説明してしまえば、そんなに難しい内容ではない気がするだろう。
次のセクションでは情報をどのように整理するのか、外山氏オススメの方法をご紹介していきたい。
溜めた情報は上手に整理し、活用させよ(第3章、4章)
これまで最初に思いついたアイデアは寝かせるべきだという話をしてきたが、外山氏はこれを「メタ思考」と呼んでいる(ちなみに「メタ」とは「高次の」という意味のギリシア語の接頭辞で、ある学問や視点の外側にたって見る事を指す)。
つまり、寝かせた情報は強度のより高い思考となり、そうして得た情報は抽象化される傾向にあるのだという(粗末な例で恐縮だが、①柴犬②秋田犬③コーギーという複数の情報から、「犬」という一段抽象化された思考を導くことができる)。
「メタ思考」を発明するためには、その具体例となる個々の情報をいかに取集し、整理するかが重要となってくる。
そこで外山氏が第3章でおすすめするのが「①スクラップ、②カード(単語帳)、③ノート」に自分の思考を分類して溜めていくことである。
個々の方法についてはご紹介しないが、気になった新聞や雑誌のスクラップを分類ごとに封筒に集め、それらから共通する項目を見出すというお手軽なものから、執筆当時53冊もあったという外山氏直伝の思考ノートの書き方というハードなものまで紹介されている。
現代では、PCやスマホがすでに幅をきかせているので、メモ帳アプリやクラウド上に自分のアイデアをメモしている人も多そうだが、外山氏のアナログな方法も、わりと簡単にできるので一度やってみる価値はありそうだ。
そして第4章では思考をいったんノートに預けたら、1度忘れて、記憶のろ過装置にかけよと述べている。
そうすることで、不要なものは取り除かれ、純化された思考だけが残るのだ。
忘れ上手になって、どんどん忘れる。自然忘却の何倍ものテンポで忘れることができれば、歴史が三十年、五十年かかる古典化という整理を五年か十年でできるようになる。時間を強化して、忘れる。それが、個人の頭の中に古典をつくりあげる方法である。そうして古典になった興味、着想ならば、簡単に消えたりするはずがばい。思考の整理とは、いかにうまく忘れるか、である。
集めた情報が意外な化学反応を起こす場合もある(第5章、6章)
最後に『思考の整理学』の第5章、6章について。
あくまで自分の感想だが、本書の中で一番文章が読みにくく、難しいのがこれらのセクションだと思う。
これまで集めて整理した情報の最終調理段階は「化合させること」。
「化合」は、
①他分野の友人と語らうこと
②整理した解釈を超えた先に独創性を見出すこと
で生まれる。
外山氏は「拡散と収斂」のなかで、集めた情報を整理する思考を「収斂」、それらの情報をこれまで誰も考えもしなかったような方法で結び付ける思考の力を「拡散」と呼んでいる。
拡散作用によって生まれたものは、散発的である。線のようにはまとまらないで、点のように散っている。点と点は一見、相互に関係がないように思われる。本書ですでに用いた比喩を採用するならば、飛行機型の思考である
これまでの学校教育は、主として収斂性による知識の訓練を行ってきた。(……)そういう頭で、満点の答のない問題に立ち向かうと、手も足も出なくなってしまう。自分の頭で考えを打ち出すことはできないが、教えてもらった知識を、必要に応じて整理するのは巧みであるという学習者が優等生として尊重される。グライダー人間である
けれど、第1章で外山氏が述べていたように、これからの人間はグライダー思考と飛行機思考の両方を併せ持つ人間――「グライダー兼飛行機人間」になる必要があるのだ。
「もし、拡散するのみあって収斂することを知らないようなことばがあれば、それは消滅する」と外山氏は締めている。
まとめ
いかがだっただろうか。
本記事によってすこしでも『思考の整理学』の内容がわかりやすく伝わったのならば、嬉しい。
また駆け足でご紹介してきたため、本書のおすすめポイントをあまり多くご紹介できなかったが、思考の整理方法などに興味があれば、また改めてじっくりと読んでみて欲しい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
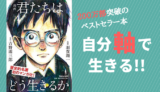 『漫画 君たちはどう生きるか』あらすじと感想【現代の私たちに求められる生き方とは?】
『漫画 君たちはどう生きるか』あらすじと感想【現代の私たちに求められる生き方とは?】



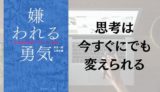
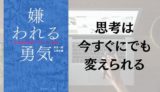
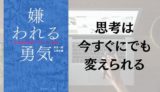

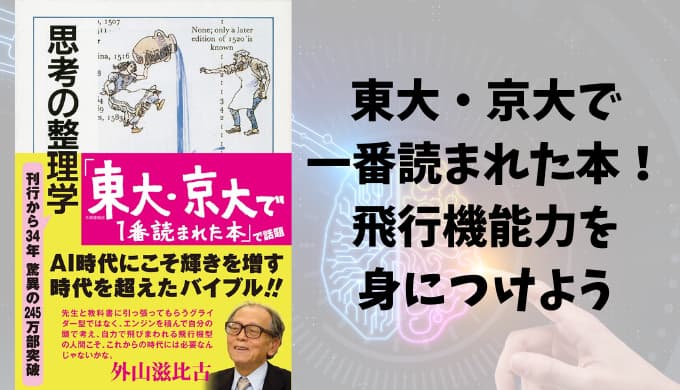

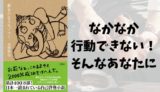

書き手にコメントを届ける