「自分にはセンスが無い」と諦めて日々を過ごしていないだろうか。
本書は、センスの磨き方から活かし方、センスとは何なのか、センスとはどこから生まれるのかを全業種、職種の方に向けて分かりやすく説明している。
“現代社会においてセンスとはマナー”とまでなってきている時代の背景に何があるのか知ることで、読み終わる頃には今自分が何をすべきか見えてくるだろう。
目次
こんな人におすすめ!
- センスを磨きたい人
- センスとは何か知りたい人
- 売れるものを作り出したい人
- クリエイティブな仕事をしている人
あらすじ・内容紹介
著者の水野学はグッドデザインカンパニー代表であり、慶応義塾大学教授も務めているので、センスについての授業を受けたかのように非常に分かりやすく面白い内容となっている。
まず、センスとは何なのかから始まり、時代と共にセンスがどのように必要とされてきたか、そしてセンスとはどこから来るものなのかが詳しく書かれている。
実際にセンスを仕事で活かすにはどうしたらいいのか、最終的に仕事力を向上させるための実践方法など普段の生活から仕事まで役に立つ知識が詰め込まれている。
知識をたくさん得る為にはどのようにしたらいいのかを普段の生活の中から考え方含めて紹介されており、誰でもすぐにセンスを磨けるのだと知ることができる。
著者がどのようにしてヒット商品に携わってきたのかも書かれており、その裏側についても触れられている。
『センスは知識からはじまる』の感想・特徴
普通を知ることが、センスを向上させる第一歩
私はセンスとは感覚のように捉えていたが、本書を読み進めていくとどうやら違うようだった!
センスとは、良いと思うものを感覚で捉えているつもりでも、そこにはなんらかの理由があるはずで、それを言語化するのが難しいと良いと思う理由を感覚と捉えてしまうということだった。
では、そのセンスとは一体どういうものなのかというと、大切になってくるのが「知識」である。
まずは知るということが重要になってくるとあったが、その中でも普通を知ることが最優先される。
普通を知るために知識が必要となってくるのだ。
普通を知ることで可能性がひろがる
つまり、真ん中を知ると全体が見えてくるのだ。
しかしこれには弊害もあるようで、普通を知ると優劣が付けられてしまう。
商品開発などのため、大人になってからその業界で自分の仕事においての普通を知ることと、子供が音楽の授業などで普通を知ることの違いが書かれている。
子供の頃の優劣が芸術との決別になっているともあり、もし子供にセンスを学ばせるとしたら今の日本の授業では難しく、普通を知ったあとにどのように選択していくかの考え方を教えなければいけないのだなと感じた。
それと同時に、上手い下手だけでなく歴史を学んだり、例えば音楽であればその曲の背景を知ることで歌い方も変わるかもしれない。
普通を知り、背景や歴史の知識を得ることがセンスに繋がっていくのだなと納得した。
最初の章では、美術の授業についての問題点も書かれており、芸術の授業をそのような視点で考えたことがなかったのでとても新鮮に思えた。
なるほどと頷ける点が多いので是非読んでもらいたい。
まずは普通を知ることがセンスを向上させる第一歩である。
技術からセンスへ。クリエイティブディレクターの役割とは?
なぜ今センスが必要とされる時代になってきているのか、本当にセンスって必要なのだろかと思うかもしれないが、それにはちゃんとした理由が書かれていた。
企業の美意識やセンスが、企業価値になる。これが今の時代の特徴です。
高度経済成長時代には真面目で熱心に働くことが一番求められていた。
もちろんそれは今も大切だ。
しかし、今はどうやらそれだけでは足りなくなってきているようだ。
ものを作ることに力を入れてきた日本が、次のステージに行くにはスティーブジョブズのように、そのものにセンスという美しさ、つまり人が触ったり見たりして心地よいと感じるものがなければ売れなくなってきている。
確かに私も同じようなものがあるならオシャレな方を選ぶだろう。
技術が発展し、ある程度のところまでくると次に売れるものはそこにセンスがあるかどうかになるのは当然とも言える。
クリエイティブディレクターを改めて定義すれば、企業価値をセンスによって高めていく仕事。センスの力は、商品開発はもちろんのこと、名刺、社屋の内装、制服があるのであれば社員やスタッフの制服におよびます。社長のネクタイの色までを徹頭徹尾考え、実践していくのがクリエイティブディレクターの役割です。
まさに、今必要なのはクリエイティブディレクターのような仕事であるのかもしれない。
技術がある程度発展してきた今こそ、センスがある人が必要になってきているのだと改めて考えさせられた。
どんなにいい仕事をしていても、どんなに便利なものを生み出していたとしても、見え方のコントロールができていなければ、その商品はまったく人の心に響きません。
今まであった技術を最大限に活かし、便利なものに美意識や心地よさのセンスを加えれば、より魅力的なものに生まれ変わるのだろう。
ではセンスを磨くためには知識だけ増やせばいいのかと言われると、そうではないようだ。
あらゆることに気が付く几帳面さ、人が見ていないところに気がつけるような観察力も必要で、さらにそれを維持すること、向上することも加えて必要となってくる。
そこを意識することで磨かれていくのだろう。
知識の増やし方のコツ。まずは王道を知ろう
センスを磨く前にまず知識を増やそうとするにしても、どこから手をつけたらいいのか途方に暮れるかもしれない。
本書では、知識の増やし方も細かく書かれているのでかなり参考になる。
効率よく知識を増やす三つのコツが書かれており、私は一つ目の“王道から解いていく”というところが勉強になった。
王道が何か見定めるのは意外と難しいだろうなと感じたが、そこを知ることができれば王道という安心感に新しい何かを加えたものを創り出すことが出来るのだろう。
何かを選択する時に、これはどうだろうと調べていく癖があればそれは自然と知識を増やしていくことに繋がっている。
著者がお勧めしていたのが、自分と全く違う職業の人と話すことだ。
自分とは違う世界を知ることが出来るし、知識も広がっていく。
いつもと違うものを食べ、いつもと違う道を歩く、いつもと違うことをするのは旅だと著者は例えているが、本当にそうだなと共感した。
旅は感じる力を育てるそうだ。
実際に旅に出るのではなく、いつもと違うことをするだけで知識を増やし感じる力を育てることができる。
他二つの知識の増やし方も非常に勉強になるので、ぜひ本書を実際に読んでみてほしい。
まとめ
著者は本屋さんをぐるっと回ってみることをお勧めしていた。
本の楽しみ方や楽しさについても触れてあるので、本が好きな方はぜひ最後まで読んでもらいたい。
そしてファッションについても、センスを取り入れると自分に似合うものがどのように導き出されるのか書かれている。
かなり広い分野でセンスを発揮しているが、狭い分野で豊富な知識を持っている特異なセンスの持ち主についてもそれを活用する技術が書かれている。
さまざまな職種、年齢、知的好奇心が広範囲な方、狭い方、どんな方でもセンスを向上させ活用できるということが分かる一冊となっている。
私は著者のように、広範囲に知的好奇心を持ち続け、そして本書に書かれているように自分というガラパゴスから飛び出して、広い世界の知識を得て、著者の言う、センスを磨く冒険の旅に今すぐ出てみようと思った。
あなたも是非、この一冊をきっかけに新しい世界を知ることでセンスを広げてみてはいかがだろうか。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 ビジネス書おすすめランキング52選!20代・30代・40代の社会人必読
ビジネス書おすすめランキング52選!20代・30代・40代の社会人必読
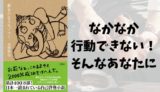
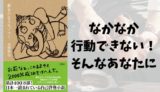
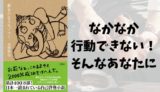
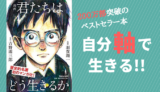
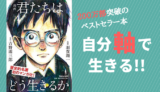
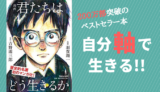

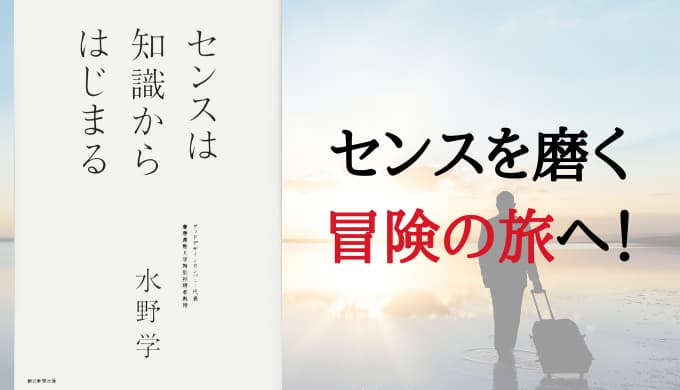

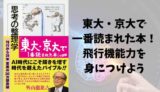
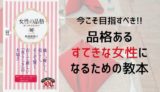
書き手にコメントを届ける