読書好きには音楽の、音楽好きには読書の魅力を伝えるクロスカルチャー・インタビュー企画第9弾。
今回のゲストは、オカルトパンク探偵冒険活劇小説『空想東京百景』シリーズの著者、ゆずはらとしゆき。
ご自身の作品紹介、執筆で意識していることなども含め、「好きな音楽」について存分に語ってもらった。

ゆずはらとしゆき
東京都出身。小池一夫氏に師事し、漫画原作者、ゲームシナリオライターなどを経て、小説へ活躍の場を移す。作家以外にも、出版企画者として活動中。主な著作に『空想東京百景』シリーズ、『咎人の星』、『雲形の三角定規』がある。
呪われた王子様とろくでなしの魔女のオカルトパンク探偵冒険活劇
ーー最新作『メトロポリス探偵社 空想東京百景〈令〉』はどのような作品か教えてください。
2002年から『ファウスト』(講談社)などで書いてきた「オカルトパンク伝奇探偵活劇」のシリーズで、今回はLINE文庫(LINE)からの刊行になりました。
表のコンセプトは第二次世界大戦末期に「3発目の新型爆弾」投下で壊滅し、似て非なる歴史を辿った〈東京〉で、魔女や怪異と戦う探偵たちを描く冒険奇譚です。
裏のコンセプトはとびっきりの美少女だけども、胸いっぱいの愛と悪意で運命を捻じ曲げる「ろくでなしの魔女」九葉祀と「呪われた王子様」矢ノ浦光鶴のラブコメディです。
「オカルトパンク」と称しているので、歴史改変SFや塩辛、ジャムやセミの抜け殻も入っていますけど。
なので、ジャンルはライトノベルやライト文芸になりますが、やってることは荒唐無稽でごった煮なスリップストリームですね。
ジャンルとしてのSFやミステリがあんまり好きじゃないので、ライトノベルに居候している、という感じです。
「ライトノベルへの愛はあるけど、たぶん場違いなんだろうな」とか思いつつ。
執筆が煮詰まるとムーンライダーズばかり聴いています
ーー普段聴いている音楽、好きなアーティストやジャンルなどを教えてください。
世代的には80年代のバンドブーム直撃世代で、TVKの『ミュートマJAPAN』を観て、ムーンライダーズ、PSY・S、BARBEE BOYS、ニューエスト・モデル、電気グルーヴなどを聴いていた小生意気なガキで、洋楽もNew Order、XTC、The B-52’sとかを聴いていました。
2000年代以降はくるり、キリンジ、フジファブリック、9mm Parabellum Bullet、凛として時雨などを聴いていましたが、最近はスカート、amazarashi、ドレスコーズ、ヒトリエ、フレデリックあたりを聴いていますね。
歳を取ってライブへ行くペースが落ちて、嗜好も保守的になりかけたところでサブスクリプションが出てきたので、また広がったな、という感じです。
ーーよく聴くアーティストはどなたでしょうか?
生来の雑食性なので、普段はSpotifyとかで無節操に聴いていますが、執筆が煮詰まってくるとムーンライダーズばかり聴いていますね。
原点回帰というか、70~80年代のニューウェーブが本質的な好みのようです。
ーーアーティストや曲の好きな所、エピソード等について教えてください。
『咎人の星』(早川書房)という小説を書いていたときは、ムーンライダーズの『バック・シート』という曲をエンドレスループで流していたんですが、これはネガティブで厭世的な投身自殺の歌で、それでいてモダンな名画からの引用が歌詞の端々に透けて見える重層性が心地よい曲です。
重層性は複雑化する弊害もあるんですが、どちらか一方の要素だけでは面白くならないんですよね。
互いが互いを相対化するというか、この曲だと主観に引用を幾重も貼り合わせていくことで、ようやく聴き手が入り込める隙というか、客観性が生まれてくる。
ぼくは東京出身なんですが、ムーンライダーズは都市生活者の寂寥感といけ好かなさが入り混じったところが肌に合うんですよ。
小説で言えば小林信彦さん、音楽だとムーンライダーズがそうなんですが、どちらもメインストリームにはならなかったし、なれるわけがない。
似たような立ち位置でも、YMOだとワールドワイドに理解されてしまうというか、田舎のヤンキーやオタクでも楽しめるんですが、ムーンライダーズは都市出身者にしか理解できないひねくれた叙情性というか、偏屈な古くささが足枷になっていて、上京者が都市生活者を擬態するために作ったサブカルの領域でもわりと嫌われています。
都市に過剰適応したがっているトンガリキッズにとって、故郷に捨ててきたはずの古くささが都市にも存在しているなんて、悪夢でしかないですから。
都市出身者はつい「気楽に過去を捨ててきた田舎の坊ちゃん嬢ちゃんがイキってるねえ」と鼻で笑ってしまうんですが、全国津々浦々に売らなくてはならない商業作家としては、そういう偏屈さが思想の根幹にあることは大きなハンデでして、地方出身者の担当編集さんにはよく怒られました。
「X JAPANを聴け!」とか。
それはそれで好きなんですけど、思想的にはどうしても合致できないんですね。
音楽も小説も、引用とそれを繋ぐ技術で成り立っている
ーー音楽によるご執筆への影響やエピソード等について教えてください。
実は、社会人になるまで小説を書いたことがなかったんです。
学生時代からライターの仕事はしていたんですが、小説を書こうとはまったく思わなかった。
書き方も分からないし。
ところが、ライター業の延長で小説の依頼が来て、どうやって書くか悩んだ末に、普段読んだり聴いたりしていた作品を分析してみたんです。
たとえば、ムーンライダーズのアルバムでは『カメラ=万年筆』を1番よく聴いているんですが、客観的に見るとフレンチ・ポップやフォーク・ロックや歌謡曲をXTCの『White Music』やDEVOの『頽廃的美学論』で繋ぎ合わせたフランケンシュタインの怪物で、すごく食い合わせが悪いんですよ。
このアルバムが発表された1980年はwebなんてなかったので、海外の流行情報も断片的で、足りない空白は手持ちの古いカードで適当に埋めるしかなかったんですけど、「架空の映画のサウンドトラック」というコンセプトと技術で一貫性を与えています。
ニューウェーブの時代だから許された、というのもあるんでしょうけど、「コンセプトさえ決めておけば、わりと何とでもなるんだな」「音楽も小説も、引用の妙とそれを繋ぐ技術で成り立っているんだな」と思い至って、ようやく小説を書き始めた、という感じですね。
小説だと、こういう手法はスリップストリームという言葉で括られていて、日本では舞城王太郎さんが第一人者なんですが、一般的には「わけの分からん電波ゆんゆん小説を書くひと」だと思われているようです。
なので、ぼくの小説も既存ジャンルの信仰者にはよく嫌われていますね。
ジャイアンシチューに見えるらしくて。
重層性とコンセプトを徹底的に突き詰めるよう心がけています
ーー普段のご執筆で意識していることを教えてください
前述の通り、ぼくの小説は引用の寄木細工で作り上げていく伽藍ですが、重層性とコンセプトがないと「仏作って魂入れず」になってしまうので、その2つは徹底的に突き詰めるよう心がけています。
鈴木慶一さんはかつて「ムーンライダーズの作品は暗号だ」と言ってましたが、簡単に解読されても困るし、かと言って、誰も解けない暗号では意味がないですから、重層性のさじ加減は毎回、試行錯誤していますね。
あと、コンセプトにまつわる部分ですが、登場人物のキャラクターたちはどんなに荒唐無稽な存在でも、その物語に至るまでの人生や思想を考えます。
ようは「ひとりの人間として扱う」ということですね。
使い捨てのフラットキャラクターだと思っていても、展開の都合でラウンドキャラクターへ転じることがありますから、用心に越したことはないです。
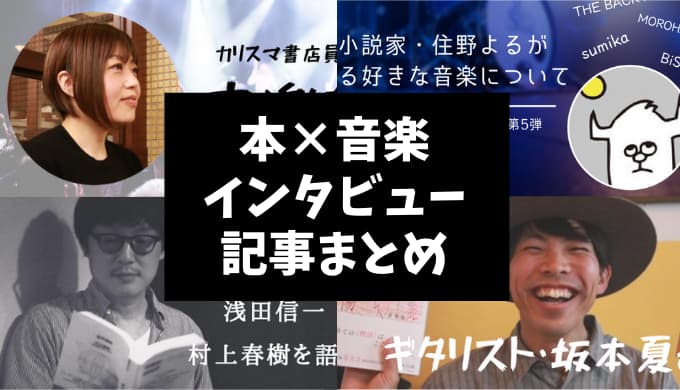
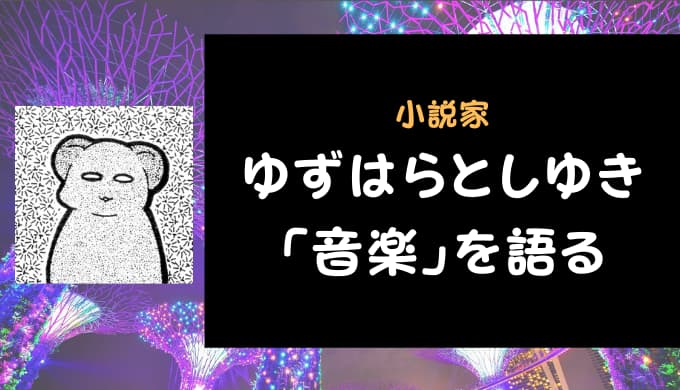


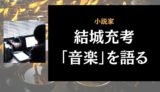
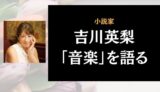
書き手にコメントを届ける