かつて浅草が「文化の中心」と言われた時代がありました。
歌劇やストリップ、お笑いコントは隆盛を極め、「夢」「エロ」「笑い」が混在する黄金のような賑わいを見せていました。
しかし昭和30年代後半に新たな娯楽「テレビ」に観客を奪われ、陰りを見せ始めます。
芸人たちが浅草を出て行きテレビへ活躍の場を移す中、「テレビでは本物の芸は出来ない」と頑なに劇場一筋を貫く男がいました。
彼の名は「深見千三郎」。伝説の浅草芸人と呼ばれる男です。
そして、深見を慕う1人のみすぼらしい青年が劇場にやってきます。
彼こそが「北野武」であり、後に「ビートたけし」として日本の笑いを席捲し、「世界のKITANO」と呼ばれる男の若き日の姿でした。
あらすじ・内容紹介
昭和47年(1972年)、学生運動は終わりを告げ、行き場を失くした若者たちが「哲学」「芸術」を語り、あてもなく街を徘徊していた。
大学を中退した26歳の「たけし」は、自称芸術家の生ぬるい彼らとは合わず、ひたすらに乾いた心を満たす何かを求めていた。
そんなある日、たけしは突如「芸人になる」と決意し、「浅草フランス座」の門を叩く。
当時、「浅草フランス座」はストリップ劇場と同時に演芸場も兼ねており、「いのうえひさし」「渥美清」「萩本欽一」を輩出した名門劇場でもあった。
「ここしかない」と決めたたけしは何とかエレベーターボーイとして雇ってもらい、日々、掃除とエレベーター案内に勤しむ中、尊敬する芸人 深見千三郎に出会う。
直ちに弟子入り祈願をするたけしであったが、深見は「やめとけ」と門前払い。
しかし、そんな事で諦める彼ではない。何度も何度も懇願し、根負けした深見から「ならこれを覚えろ」とタップダンスを教えてもらう。
たけしは黙々と練習を続け、1週間もしないうちにマスターし、彼の才能を見抜いた深見は黙って次のステップを教える。
深見が弟子入りを認めた瞬間であった。こうして、たけしは芸人としての一歩を踏み出したのであった。
『浅草キッド』の感想(ネタバレ)
たけし、芸人になるため浅草へ
2019年、年末の紅白歌合戦。「ビートたけし」の独特で味のある歌声がお茶の間に響き渡りましたが、あの歌の題名は「浅草キッド」です。
今回紹介する本『浅草キッド』と同名であり、この歌を元に書かれた自伝的青春小説です。
昭和47年、大学を中退したたけしは、母に「芸人なんかにするために勉強させたわけじゃない」と泣かれたものの、決められたレールを走れる性分ではありませんでした。
行き場の無いたけしは、ある日、芸人になる事を決意し、若者たちに取り残された街「浅草」にやってきます。
はじめはたけしも「浅草は終わった街」だと思っていました。
しかし、彼が浅草で出会った人々は、気取らず、懸命で、等身大で、それでいてカッコよく、若いたけしの心を躍らせました。
「浅草こそオイラの居場所」と気づいたたけしは大物芸人、深見千三郎に弟子入りし、彼の下で成長していきます。
芸人、深見千三郎の魅力
作品の冒頭「亡き深見千三郎に捧ぐ」とあるように、小説では深見に対するたけしの強い思いが余すところなく書かれています。
「いいかタケ、人を笑わせんのに、顔とか、姿とか、そんな見てくれのことで笑わすんじゃねえんだよ。芸人は芸でで笑わすんだよ、芸で。客に笑われるな、笑わせろ」
初舞台に立つ時、たけしは客にウケるだろうと滑稽で面白おかしい化粧をしました。その時に深見が放った言葉です。
見た目だけで笑いを取ろうとする弟子への戒めでした。
また、この時代のたけしは売れてないので、毎日が素寒貧(すかんぴん)。劇場で貰う日給は、朝のモーニングセット・昼の蕎麦・たばこ・夜のチューハイ2杯で消えていました。
そんなある日、みかねた深見が寿司を奢ってくれることになります。
遠慮するたけしに、
お前がみすぼらしいと師匠の俺がみっともなく見られる。いいから来い
と寿司屋へ。
それでも遠慮してしまうたけしはタコとイカを注文します。
「バカヤロー、そんなもの食うんじゃないんだよ。芸人はもっといいものを食うんだよ。もっといいものにしな」
深見は「俺と同じものを食え」と、トロ、イクラにアワビと高いネタを腹いっぱい食べさせてくれました。
口が悪く「バカヤロー」「コノヤロー」が口癖の深見ですが、その実、繊細で寂しがり屋で人一倍気を使うのをたけしは見抜いていました。
彼は「芸人」として「人間」として、深見を心から慕っていきます。
たけしが関わった人々。踊り子、いのうえ、マーキー
ここで、たけしが浅草で出会った深見以外の人たちも紹介します。
・踊り子たち
ストリップ劇場で働く女性の多くは、地方の貧しい出身。文字通り裸で稼いでいますが、その実とてもたくましい人たちでした。
それでいて自分より弱い人には、親切にする優しさも持っています。
幸か不幸か、踊り子さんたちに「飢えたかわいそうな若者」と見られたたけしは、まるで犬猫にエサをあげるかの如くご飯をご馳走になり、おかげで飢えることは無かったと語ります。
・いのうえ
ある時、作家志望の「いのうえ」という若者がやってきます。
男同士ということで、たけしはいのうえと仲良くなるのですが、色白でインテリのいのうえは踊り子たちからモテる。
彼女らの人気を持っていかれ、内心「チクショー」とたけしは悔しがりました。
・マーキー
待ちに待った「芸人志望」の後輩がやってきます。通称「マーキー」、20歳を過ぎたばかりの青年でした。
ひょうきんなマーキーでしたが、たけしは彼の奥底にある繊細さを気に入ります。
マーキーもたけしを慕い、コンビとしてやっていこうと2人で頑張りますが、マーキーは線が細く、酒に逃げる事が多かったのです。
結果、彼は倒れてしまいました。
マーキーの復帰を待っていたたけしでしたが、治る見込みはなく、コンビは諦めるしかありませんでした。
歌「浅草キッド」の「おまえとあった仲見世の」の「おまえ」とはマーキーのことだと言われています。
芸人として大ブレイク!浅草や深見との別れ
様々な苦難の中で、たけしは深見の下で学んでいき、笑いの力をつけていきます。
「ツービート」を結成したたけしは、劇場でも爆笑をかっさらうようになりますが、一方で悶々とした日々を過ごすことになります。
「俺はこのまま浅草の芸人で終わるのか?もっと大きい舞台に羽ばたきたい」
浅草を出て、もっと大きな場所へ行く。それは同時に浅草、つまりは深見との別れを意味していました。
散々悩んだ末、たけしはついに深見に思いを伝えます。
「師匠、一度外に出て勝負してみたいんですけど」
深見は沈黙の後に一言。
「ふん、バカタレどもが」
その顔は「お前らなんかの腕じゃ通用しない」と語っていましたが、その実、自分のもとを去っていくたけしと別れることへの寂しさに溢れていました。
しかし、浅草から飛び立ったたけしは、破壊的な漫才でお笑い界を爆走。世間には「マンザイブーム」が到来し、ビッグウェーブに乗った「ツービート」は一躍有名になります。
深見はたけしが売れたことを心から喜んでくれましたが、一方で最後まで「漫才なんか、あんなもの芸じゃねえよ」と認めてはくれませんでした。
かつて浅草から人気を奪った「テレビ」の世界に羽ばたいていったたけし。彼が浅草の舞台に帰ることはありませんでした。
それからおよそ10年が経った昭和58年2月、「オレたちひょうきん族」の録画中、楽屋にいたたけしに知らせが入ります。
「浅草軽演劇35年 深見千三郎さん アパートで焼死」
寝たばこが原因と言われ、渥美清、長門勇、東八郎らと共に浅草を盛り上げた伝説の芸人の最期でした。
まとめ
ラストにたけしはつづります。
師匠もフランス座の劇場を退(や)めてしまって、きっとたまらなく寂しかったのに違いない。
亡くなる2年前に浅草の舞台を降りていた深見。
その後は、弟子の伝手で化粧品会社で働いてましたが、元踊り子の妻(たけしにご飯を沢山食べさせてくれた方)を病気で亡くし、酒が度を越えたりと、他人には分からない寂しさを抱えていたのです。
しかし、あの火事は本当に偶然の事故だったんだろうか
芸人を辞めた寂しさ、愛する人を失った悲しさ、それらが生きる力を奪ってしまったのかもしれません。
たけしは師匠の死に疑問を投げかけたあと、このように述べています。
オイラは芸人としてなんとか売れ有名になったが、気がついたらかけがえのない人たちが次々といなくなっていたのだ。そして有名になることでは師匠に勝てたものの、しかし最後まで芸人としての深見千三郎を超えられなかったことを、オイラはいまも自覚している
大スターとなったたけしによる深見への尊敬と追慕で幕を閉じます。
1人の天才芸人の終幕と、もう1人の天才芸人の開幕を描いた作品でした。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
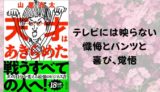 『天才はあきらめた』あらすじと感想【みみっちいのはそれだけ真剣だから】
『天才はあきらめた』あらすじと感想【みみっちいのはそれだけ真剣だから】







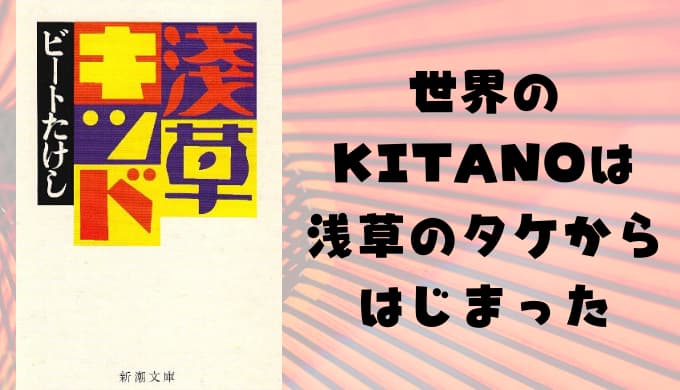

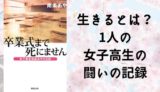
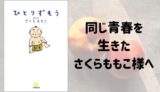
書き手にコメントを届ける