あらすじ・内容紹介
ある男の殺人事件の捜査線上に桐田麻衣子という女が浮上する。
被害者は吉川一成という緊縛師で、事件現場で見つかった名詞から麻衣子の関与が疑われる。
だが、偶然にも事件を担当する刑事、富樫は麻衣子と男女の関係にあり、咄嗟に彼女の犯行を隠蔽する。
しかし、同僚の葉山は、富樫の不正行為に気付き密かに彼の行動を監視して徐々に追い詰めていく。
一方、調査の過程で、伊藤亜美という、もう一人の女が浮かび上がり、富樫は伊藤亜美に麻衣子の罪を着せ真犯人にでっち上げようと画策するが、事件の深い闇に飲み込まれて自分を見失っていく。
事件は迷宮入りするかと思われたが、やがて、葉山が事件の背後に見え隠れする黒幕の存在を突き止め、事件は誰も予想しなかった驚くべき真相を迎えることになる。
その先の道に消えるの感想(ネタバレ)
いまにも火が消え入りそうなひとたち
「さすがですよ、噂通りだ。こうして対峙していると気味が悪い! でも、でもですよ、あなたが僕に勝てないものが一つある。」僕は叫ぶように言っている。僕は狂ったのか? 僕が何かから遊離していく。「闇です! 不安定な闇! ハハハ! あなたはこれから、弱く不安定に揺らぐ闇というのがどういう行動に出るか見ることになる」
物語を四分割したときに、第一幕の山場となるプロットポイント1に当たる場所が恐らくこの引用箇所である。
実際に、ここで富樫は麻衣子の犯行を隠蔽したことを同僚の葉山に見破られるわけであり、物語中で最もダイナミックな見せ場の一つと言える。
第一幕では、まるでラスコーリニコフとペトロヴィッチの心理戦を見ているような緊張感のあるシーンが展開される。
しかも、追われる立場のラスコーリニコフも追う側のペトロヴィッチと同じ刑事であるという倒錯した構図が我々読者の興味を一層かき立てる。
そして、ここで最も注目すべきは、第二幕に移行する前に作品のテーマが明確に表出している点だ。
中村文則氏は、これまでにも常に人間の抱える闇の部分を扱ってきた。
それも常人には計り知れない、アウトサイダーの烈しい孤独がもたらす底なしの暗闇だ。
この作品では富樫は自らの暗い生い立ちから不安定な精神状態にある人物として描かれており、事件をきっかけに闇の深淵に完全に飲み込まれていく。
だが、富樫はまるで闇そのものが彼自身であるかのようにして、闇と同化することを望む。
この作品では富樫だけでなく、桐田麻衣子や伊藤亜美をはじめとして他の主要な登場人物たちはみな、このように、やむに已まれず闇と同化し、ギリギリのところで生きている。
じつは、富樫を追う葉山もまた、同じように負けず劣らず闇の中で、ほとんど生きる意味を見失いかけている。
生きることへの希求心が燃え尽きて、いまにも灯が消え入りそうな人たち。
それが、この作品に登場する人たちに共通する大きな特徴だといえる。
なかでも殺人事件の被害者である緊縛師の男、吉川一成は作品中で最も深い闇を抱えている人物の一人だ。
彼は性のアウトサイダーとして描かれており、人生を底なしの虚無感のなかで彷徨っていた。
「第二部」から、物語は一気に加速する
思えば自分は生来、性的な人間でした。人生というものは味気なく、嘘くさく、くだらないものであるとしか、感じることができずに生きてきました。当然のことながら、この世界に非があるのではなく、自分に問題があったのです。自分を夢中にさせるものが、ほとんど性しかないという人生。自分が過ごした人生は、そういったものでした。
第二幕、この小説では「第二部」から、物語は一気に加速する。
登場人物たちは次々と暗闇の向こう側に吸い込まれていく。
引用箇所は吉川一成の手記の冒頭だが、これを読んだ時、ふと、三島由紀夫の『金閣寺』を思い出した。
金閣寺の放火犯である主人公の青年は、破滅に向かっていくしかない定めを予め負っていた。
吉川一成もまた同じような定めのもとに生まれ、徐々に破滅へと導かれていく。
暗い絶望の果てに待っているのは死だ。
この作品では登場人物の誰もが、死の世界へ誘われており、あと一歩というところで、こちら側に踏み留まっているのだが、吉川一成は、まるで望んでいるかのようにして絶望の闇に飲み込まれ、あちら側へと落ちていく。
その意味では皮肉にも刑事の富樫と殺人事件の被害者の吉川はどこか似ている。
そして、この作品のもう一つの特徴は、この登場人物同士に見られる鏡のような相似関係にある。
事件の鍵になる伊藤亜美と山本真里は外見上、瓜二つである。
また、桐田麻衣子と伊藤亜美は、吉川との関係性において相互交換的な役割を果たしている点で似ている。
さらに、これらの女たちは麻縄で縛られることで、生きることの無力感から逃れることを望んでいるという共通点でつながっている。
「縛られると、人間性を、剝奪されたような気持ちになる」(略)「もう動けないから、自由意志を奪われた私は……、もう何もする必要がない。自由意志には責任が付きまとう。自分で選択することの、責任からの解放……。奴隷になることの、喜び。社会から、人生から、過去から、私から、その時だけ私が解放されていく」
伊藤亜美のこの言葉は非常に印象深い。
作品のテーマの一つである緊縛とは、自由を完全に奪われることで自由になるという倒錯的な欲望である。
自由意志の放棄によってのみ生きる実感を得られる人生とは一体どんなものだろうか。
恐らく、それは想像を絶する地獄のような空虚感に苛まれながら人生を送ることだ。
それは、最早、生きていることを意味しない。
このような倒錯的な快楽に溺れることは狂気であり、狂気は必然的に破滅へと続いている。
だが、狂気に蝕まれているのは縛られる女だけではない。
縛る側の男は自らの嗜虐性を縛られる女に投影している。
言い換えれば、サディストはマゾヒストを介して本来の内に秘めた欲望を疑似的に味わっているのだ。
それが故に縛る男は反転して縛られる側に身を転じた時点で、存在意義を失う。
そして麻衣子様は、こちらを縛ったのです。(略)腕を後ろに回され、麻縄で縛られた瞬間、涙が出ていました。麻衣子様は基本的にМの属性ですが、時々発作的にSの属性になるようでした。SとМを両方嗜好する者達は少なくない。(略)自由。無力にそう思っていました。自分の人生から、罪から、悩みから、自由になっている。奴隷の自分はもう、選択する必要がない。支配する側に従順に、刃向かわず、選択の全てを預ける。これは快楽です。「可哀想に」麻衣子様が汚れた顔を優しく抱えてくれます。自分は不幸で幸福でした。
役割の交代によって、吉川はこの時点で本物の狂気に陥っていく。
この引用は吉川の台詞だが、先述した伊藤亜美の言葉と驚くほどに似ている。
絶対的な存在との一体感。
これは『金閣寺』の放火犯の青年が陥った諧謔的な認知と非常に似通っている。
しかし、絶対的な存在は傅く者を簡単に抹消することのできるだけの力がなければならない。
この作品で忘れてならないのは、事件の背後で、絶対的な存在として、登場人物たち全てを飲み込むブラックホールのような男、Yの存在だ。
彼は中村文則氏の作品において初期の『王国』から最近の『教団X』へと引き継がれる絶対的な悪の系譜を体現する人物として登場する。
では、絶対的な悪とは、どのような人物なのだろうか。
「……私は、全てをやったよ。自分の人生において、文字通り、全てだ。……そしたら」ソファに深く背を預けている。「こうなった」だらけた身体、整っていただろう顔にも、今は力が入っていない。(略)「現実が、ただの映像にしか、見えなくなった。……興味の喪失だ。そこに人間がいても、それが人間に思えない。ただの絵だよ。さわれる絵。(略)気が付いたら、こうなっていたのだよ。
絶対的な悪を顕在化する男の正体は、葉山に向けられた上記の引用箇所で語られるYの言葉から、うかがい知ることができる。
高度資本主義下の倦怠という名の絶望の果てに、ぽっかりと心に穴を穿たれた空っぽの人間。
それがYという男だ。
興味深いのは、Yは対峙する葉山も自分と同じであることを見抜いている点だ。
作品を貫く相似関係の仕掛けは、ここにも表れている。
ふたりはとてもよく似ているのだ。
「お前は、こっち側の人間だ。そうだろう?」Yが言う。Yの声も乾いている。「人生に喜びを覚えるのは、勝手だよ。他人を押しのけ、幸福をむさぼり、それを他者にアピールし続ければいい。でも時々、こんな風に、バグを起こす奴もいる。人間がこんなにいるんだ。そうなる奴もいるだろう?(略)唯一私を震わせたのは性だ。だが、それもやがて飽きがくる。射精した後の気分は最悪だろう?射精する前からな、もうその快楽の程度とその後の倦怠を想像してしまうの私のような人間は、射精するのもだるくなるんだよ。人間はどんなことにも慣れていく。どんな異常な性にもやがて倦怠が来る。想像力と慣れが加速して混ざり合うと人間はこうなる。(略)何にも執着がないだろう?私と同じだよ。お前はこの世界に合わないのに、存在してしまったバグだ」
Yの独白には、行きつくところまで行きついてしまった、まさに絶望の果てがある。
この究極のニヒリズムは、ミシェル・ウェルベックが描く圧倒的な虚無感に覆われた砂漠のような世界に通じるものがある。
空洞の闇。
登場人物たちはYの蟻地獄に似た絶望の奥底へと引きずり込まれていく。
Yの言うバグという言葉は、まさに、この作品の核心をついている。
そこに救いはない。
なぜなら、バグは徹底的に排除されるべき存在だからだ。
社会のバグとなった人間の世界には何の意味もない。
だが、本当にそうだろうか?
確かに私たちの生きている現実社会においては、その通りだろう。
しかし、文学においては違う。
文学はどんな悪を描いてもいい。
むしろ、システムに不具合を発生させるバグの存在に、何らかの意味を付与することこそ、文学の重要な役割なのではないだろうか。
たとえば、先述した、三島由紀夫やミシェル・ウェルベックに至るまで、文学作品は、これまでにもシステムエラーを起こす無数のバグの存在を扱ってきた。
文学において、バグという逸脱は、読者の気付きを促し、同時に、社会規範や価値観について別の角度から検討する機会を提供する。
文学作品を読む価値はそこにあるのではないか。
私たちは、文学を通じて、普通や当たり前として、まかり通っている社会通念や常識を常に疑ってかかるべきなのだ。
逆説的な言い方だが、かつてウイルスが生物を進化させてきたように、バグもシステムを進歩させる。
まとめ
中村文則氏は、デビュー作から一貫して人間の暗い部分に光を当ててきた。
この最新作でも一切の妥協を許さず、常に読者の期待の水平線を裏切り、絶望の果てにいかに生き延びるのか、という難しい命題を読者に突きつける。
この作品を読み終えて、ふと、三島由紀夫の『金閣寺』で、主人公が作中で放った、それにしても、悪は可能であろうか、という言葉が私の頭をよぎった。
恐らく、ミシマの投げかけた、この問いかけに答えることのできるのは、現代において中村文則氏をおいて他にいない。
主題歌:Nine Inch Nails/Hurt
Nine Inch Nailsの “Hurt“。
トレント・レズナーが命を削って歌い上げる絶望の旋律と、この小説のヒリヒリするような皮膚感覚が完璧にマッチすること間違いなし!
ぜひ、いっしょに聴いてみてください。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 『カリギュラ』あらすじと感想【不幸な真理を砕け!】
『カリギュラ』あらすじと感想【不幸な真理を砕け!】
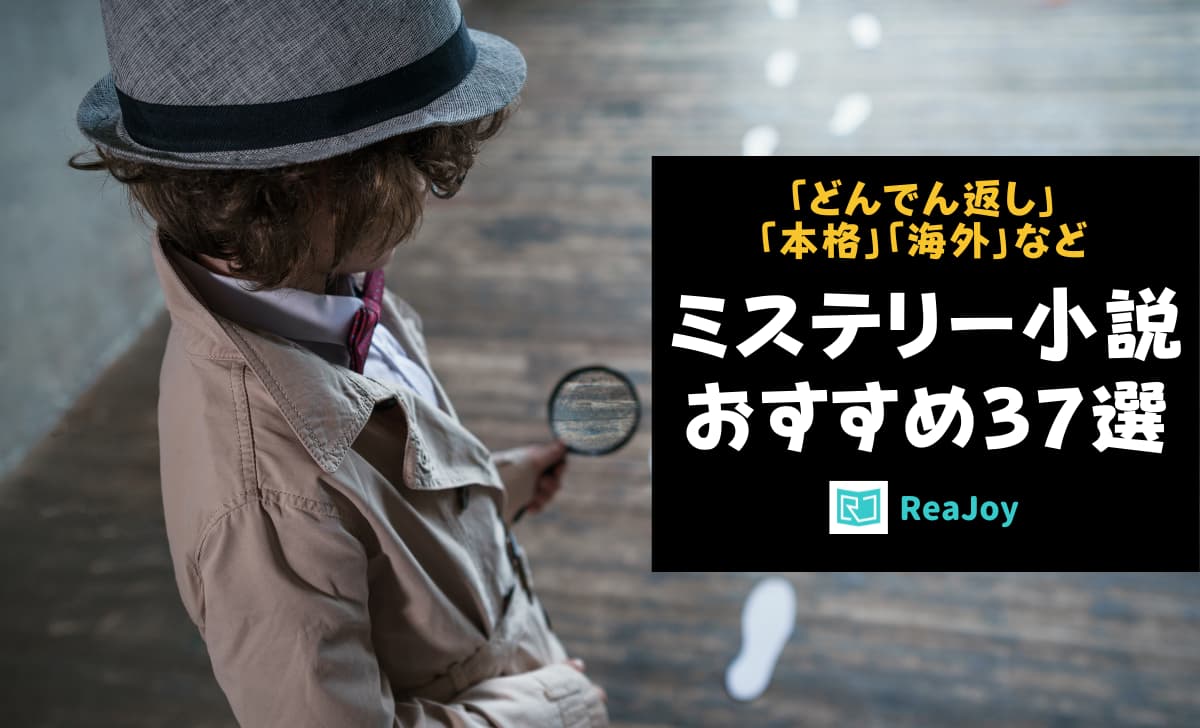
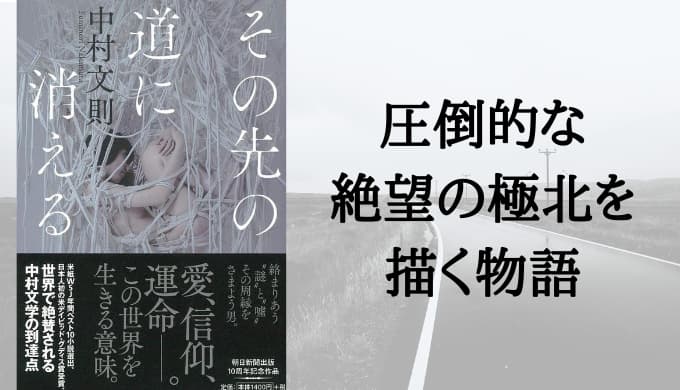


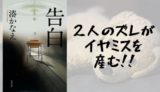
書き手にコメントを届ける