米澤穂信さんの『本と鍵の季節』をご紹介します。
書店で平積みになっている落ち着いた装丁のこの本を見つけて手に取ってぱらぱら捲ってみます。
短編集ということが分かって1編目のタイトルを見ていると、「913」!
語呂合わせ?「くいさ」、「きゅういみ」、いやちょっとかわいく読んで「くいみー」?
いずれにしても意味分かりません。
本の帯などから情報収集してみると図書室に持ち込まれる謎に挑む短編集らしい。
図書室も図書館も大好きだったし、ゆっくり読んでみようとレジに向かいました。
あらすじ・内容紹介
図書館を中心に展開されるミステリです。
高校2年生で図書委員の僕(堀川次郎)と松倉詩門の元に持ち込まれた頼まれ事の謎に挑みます。
全6編の短編集の形式です。
それぞれの短編で提示される謎は短編毎に解決されながらも、少しずつ堀川次郎と松倉詩門の関係が変化していくので「次の短編では2人はどうなるのだろう」と一続きの物語のように引き込まれます。
堀川次郎と松倉詩門、2人の人間模様こそが「爽やか」で「ほんのりビター」に揺れ動き、ついつい気になってしまうのです。
謎解きだけでなく、高校2年生という時間を過ごす堀川と松倉の関係の変化や抱えている事情が浮かび上がっていく推理と友情の物語です。
本と鍵の季節の感想(ネタバレ)
堀川次郎と松倉詩門、2人のコンビについて
それぞれの短編は堀川次郎の元に届いた頼まれごとに松倉詩門と二人で挑んでいく物語です。
堀川次郎の一人称「僕」の視点で綴られています。
週に一度、利用者のほとんどいない放課後の図書室で堀川次郎と松倉詩門は当番を務めています。
利用者はほとんどいませんから暇を持て余して、たわいもない会話をしたり、言葉遊びをしたりして二人は過ごしています。
二人共、物事の裏側にある事柄によく気づきます。
ただ性格は違って、堀川次郎は他人が話すことに共感から入れるタイプで、それに対して松倉詩門は共感の前に疑いから入るタイプです。
ただ謎に対するアプローチが違う分、松倉詩門に気づけないことに堀川次郎は気づくこともあり、お互いに認めて合っています。
表向きは皮肉っぽく感じてしまう松倉詩門の言い分の裏にある気持ちを堀川次郎は理解していて、お互いに「いいやつ」と評しあえる仲なので、いい友情関係ができています。
私は読んでいてまるで兄弟のような二人だと思いました。
二人の会話は時々知的で、時々馬鹿っぽさも感じる愉快さがあります。
謎解き要素について
短編それぞれには謎解きの面白さがあります。
その種はどこか洒落ていてオシャレです。
上記した興味を持った短編のタイトル「913」。
まさか「913」が図書館の書籍を分類するラベル番号とは思いませんでした。
私自身、大学時代に図書館のボランティアで返却図書を棚に戻す時に注目していた馴染みのある番号だったのに、と悔しい気持ちと親しみある事柄からくる面白さが湧いてきました。
これだけではなくてそれぞれの短編の謎の種や張られる伏線が気になると、どうしても短編の途中で本を読み終えることができず、ついついすっきりするまで読んでしまいます。
寝不足なんてお構いなしに次の日の仕事に響くなんて分かっていたとしても……。
そして次の日しんどくて後悔してしまって。
これってあるあるじゃないでしょうか(笑)
それに謎の種だけではなくて、解き明かしていく二人の様子が心地いいんですよね。
一人称(僕)だからかもしれませんが、本気で松倉詩門の頭の冴えに感激し、頼りになるなぁと感じて、そして「僕」がいい仕事をすれば嬉しくなります。
松倉詩門を「僕」が唸らせることができたらもう天まで昇ってしまうような勢いです。
後半、よく松倉が堀川を褒めるのでいい気になるような心地でした。
こうやってがっちり感情移入できることは小説を読むことの醍醐味なのかも。
そしてコンビで謎を解き明かすという物語の構造はよく刑事ものや探偵もので見られますが、この高校生の図書委員のコンビは新鮮で、学生だからこその爽やかな雰囲気の居心地がいいです。
小さな伏線と大きな伏線
この言い回しが正しいのかは分かりませんがそれぞれの短編の謎解きに関する伏線が面白くて、上記したように読むことを止めることができずに謎が解き明かさられるまでついつい読んでしまいます。
でも段々とそれだけではなくて、物語の裏にある松倉詩門の背景やそれに気づく堀川次郎の心情が気になり始めます。
3編目「金曜に彼は何をしていたのか」の終わり、
「立ち去る松倉の背中は、知らない男のそれのように見えていた。」
ちらっと胸の中に不穏の影が現れ、4編目「ない本」の終わりの松倉のセリフ、
「どうも俺は人を信じるのが苦手だ。心からの言葉でも、狙いはなんだと疑っちまう。その点、お前は偉い。先輩の話をまともに聞いたんだな。尊敬する……これは、言葉通りに受け取ってくれ」
を読んで、あんなにクールで皮肉屋で大人びた松倉詩門の表には見せない内面が見えて、これは一つ一つの読み切り短編でもあるけども、一つの大きな堀川次郎と松倉詩門の二人の物語なんだと気づきました。
そして一番長い短編の5編目「昔話を聞かせてくれよ」でいよいよ松倉詩門自身の話になると、今までの短編での松倉詩門の態度を始めとする事柄が伏線として主張し始めます。
こういうことだったんだ、という驚きを感じてぱらぱら戻り始めてた時にはもうこの本にどっぷり浸かってます。
終わりまで一気読みでした。
寝不足の仕事も恐れず……。
そして最後には謎解きの心地よさに加えて、二人の心情の変化に感じ入ってしまいました。
まとめ
松倉詩門がディープな自分の気持ちや背景が分かると、元のただの図書委員だった関係とは変化していることに気づきます。
堀川次郎が図書室で松倉がいつものように来てくれることを願って仕事をする姿は感慨深くなります。
松倉は来るのだろうか。
それとも来ないのだろうか。
物語はここで終わっているので分かりません。
腹を立てながら松倉詩門を待つ堀川次郎の姿には込み上げるものが……。
友達関係って離れようと思えば離れられるし、そこに理由なんていらない。
何も言わずに一生会わないことだってできる。
そう考えると脆いですが、だからといって家族や恋人と比べて軽いわけじゃない。
なかなか訪れない松倉詩門の姿に堀川と同じように腹立つし、加えて、悲しくもなる。
そして少しどんな気持ちだ、大丈夫かって心配してしまう気持ちにもなりました。
謎は全てすっきりしたのにもどかしい。
深くて心に残る小説でした。
面白かった。
主題歌:YUKI/さよならバイスタンダー
YUKI『さよならバイスタンダー』
バイスタンダーとは「傍観者」という意味です。
歌詞の中の「さよなら バイスタンダー」というフレーズが様々な出来事の中で、人間関係が色濃くなっていくこの小説に合っていると思い選びました。
曲調についてもアップテンポの曲で学生時代の力強さと勢いが高校生活にぴったりです。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
伊坂幸太郎『砂漠』。爽やかでほんのり不思議な大学生の物語を堪能できます。伏線の切れ味も最高です!
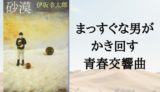 伊坂幸太郎『砂漠』あらすじと感想【僕らの青春は終わらない】
伊坂幸太郎『砂漠』あらすじと感想【僕らの青春は終わらない】






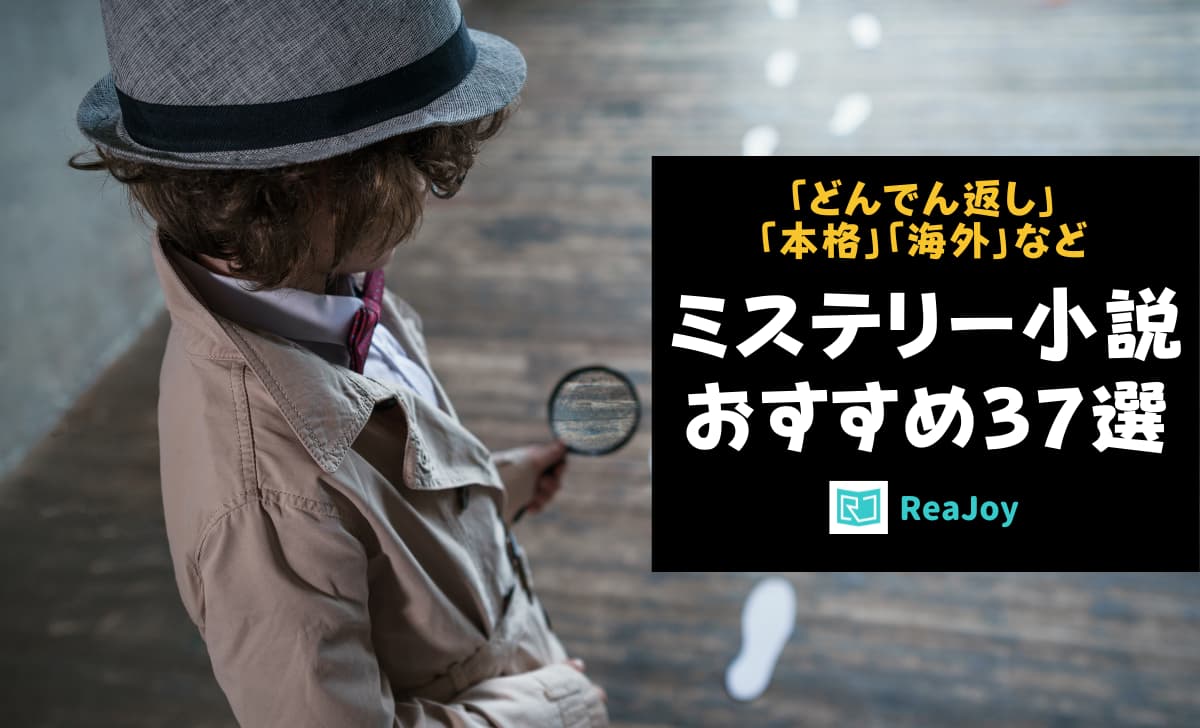
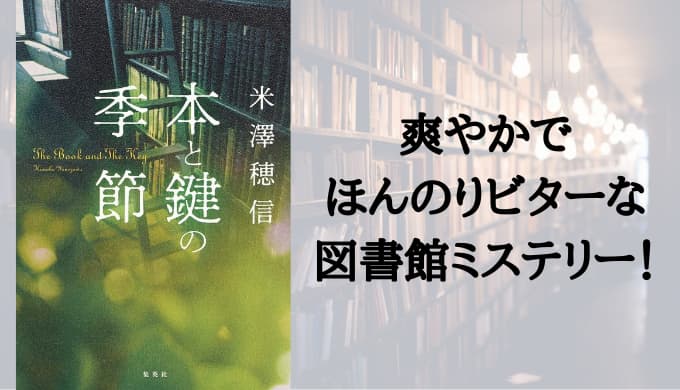

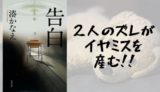
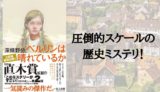
書き手にコメントを届ける