あらすじ・内容紹介
プロダクト・デザイナー相良郁哉は、ある雨の日に、職場の近くで起こった交通事故に巻き込まれ瀕死の状態にあった女優の叶世久美子を助ける。
久美子は事故で片足を切断する大怪我を負う。
久美子は偶然にも相良が過去に仕事でデザインを手がけた病院に入院し、相良のよき理解者でもある病院経営者の原田紫づ香から、久美子のために従来の概念を覆すような美しい特別な義足をデザインしてほしいという依頼を受ける。
相良は事故のショックで落ち込んでいる久美子と期せずして再会し、義足の制作に向けて出会いを重ねるうちに徐々に久美子と信頼関係を築いていく。
心の通った二人は次第に恋愛感情を抱くようになる。
だが、久美子は会社社長の元愛人の三笠竜司から執拗につきまとわれ、相良も嫌がらせ行為を受けるようになる。
一方で相良は幼少期に家族を捨てて出て行ったきり音信不通だった母親の死を急に知らされ、母親と自分をめぐる暗い過去と向き合うことになる。
相良は久美子との恋愛関係に思い悩みながらも、彼女を献身的に支え再帰復活を願って最高の義足を作るために奮闘する。
かたちだけの愛の感想(ネタバレ)
社会的に成功して、他人から見れば十分に地位も名声もある一組の男女が偶然に出会う。
平野啓一郎さんの『かたちだけの愛』に登場するのは、そんな成熟した大人の男女だ。
言い換えれば、この小説は、まず前提として中年期の恋愛心理を描いていることが大きな特色のひとつだと思う。
経済的にも余裕があり、自分の仕事にも充足感を得ることができるのは、若者ではなく目標を達成するために努力を重ねてきた大人だ。
10代や20代の若者たちの恋愛心理は純粋で美しいが、裏を返せばピュアであるということは社会的な役割がなく、まだ何者でもない状態に置かれていることを意味する。
未熟であるということは若者の特権であり、人生における選択肢が限られていることに無自覚でいられるが故に彼らの恋愛は成立する。
けれども、30代も半ばを過ぎればダンテの言うように、人生の道半ばで道を踏み迷い、はたと気づくと漆黒の森の中だった、という迷いが生じ、40代にもなれば、ユングの人生の正午に見られるように、残りの人生の選択に迫られる。
中年期の恋愛は、決して不倫云々といった安っぽい社会通念に基づく表層的な意味においてではなく、自らの人生で根源的なリスクを取ることを理解した上で選択するものだ。
一般的にリスクは日本語では危険と訳されるが、本来は不確実性を意味する。
リスクにはチャンスも含まれる。
作中に、こんな印象的な場面がある。
相良が久美子と病院で再会する時に交わされる会話で、相良がデザインした一風変わった時計の話だ。
…針は通常とは違って十二時間で半周、二十四時間で一周するようになっている。工夫はその数字盤で、内側と外側とに二重に記されていて、内側は当然、0から始まり、1,2、…と増えていくのだが、外側は逆に、24から始まって、23, 22, 21…と一時間ずつ減っていく。(略)時間が減っていく、という意味で発想としては砂時計のようなものである。相良はいつも、一日を、一時間経ち、二時間経ちと加算的に数えて過ごすのではなく、大体、あと何時間、あと何分と考えながらしている(略)人間の年齢も、八十歳くらいを基準にして、毎年一歳ずつ減らして数えていけば、日々の生活の中で、何をまず優先すべきかを、もっと真剣に考えるようになるだろう(略)
相良と久美子も砂時計のような人生の中で最優先事項について真剣に考える。
そして、この作品では、彼らのような成熟した大人があえて恋愛をするリスクを取ることを選ぶ。
相良は母親との確執や妻との離婚を経験しており、久美子も暴力団まがいの男との体だけの関係を持ち、性的に奔放な遍歴がある。
そうした彼らの過去や三笠という久美子の愛人の存在は、当然恋愛小説におけるプロットの展開に重要な装置として機能している。
だが、じつはこの作品の特色はそこにはない。
片足を失った久美子と、相良が制作する義足による見えない二人三脚という逆説的な軌跡の果てに、ふたりがお互いに愛とは何かという問題を共に解き明かしていくことに、この作品の小説としての肝がある。
成熟した大人が、引き算の人生において後戻りできないリスクを取り、愛という不確実性について真剣に考えるプロセスに通常の恋愛心理とは違った深い味わいがある。
では主人公の相良が導き出した愛の定義とは一体どのようなものなのだろうか。
相良が愛について久美子に次のように述べるくだりがある。
…愛って、もっと偶然的で、選ばれる人間に優劣があるわけでもなければ、選ぶ人間が賢かったり、愚かだったりするわけでもない。ただたまたま、誰かと誰かが出会って、うまくいったり、いかなかったりするだけだってね。
ここでは愛の不確実性が述べられている。
そして、相良が作る義足は物語において不確実な愛にかたちを与えるメタファーとして見事に機能している。
義足が完成する過程で、相良は久美子という存在が自己肯定感をもたらすことに気づく。
同時に久美子も相良との関係において徐々に自分を肯定していく。
この作品では、愛は思いやりや理解といった安易な相互補完的な関係としてではなく、久美子という鏡に映った相良の自分自身への新たな存在の気づきとして描かれている。
自分自身の姿形は自分では見ることができない。
ラカンになぞらえれば、だから人は幼児期に鏡を見て自我を形成する。
そして、この作品における優先事項である愛の議論に対する核心は恐らくここにある。
つまり『かたちだけの愛』とは、幼児期にラカンの鏡像段階によって形成されたはずの自我を人生の道半ばあるいは人生の正午を迎え、ただたまたま出会った中年期の男女が、相手という鏡の反射を通じて再び自我の再構築を行うことだ。
だが、一度出来上がった自我を、再構築するには、それまでのセルフイメージを見直す必要がある。
中年期を迎えた人間にとって、それは決して簡単なことではない。
したがって、必然的に自分を反射する鏡として恋愛というリスクを取らざるを得ない。
平野啓一郎さんの『かたちだけの愛』は、成熟した大人が恋愛というリスクを取ることで分人として別の顔を見出すという独自の視点を提示する新たな恋愛小説だ。
主題歌:Ravel/ピアノ協奏曲ト長調:第2楽章
ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調:第2楽章
相良が入院中の久美子に自選のiPodをプレゼントした中に入っていた曲。
相良が、まるで何かの映画のエンドロールを思い起こさせる、と言ったこの曲を久美子も気に入って何度も聞くシーンが印象的。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
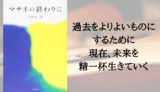 非公開: 『マチネの終わりに』原作小説あらすじと感想【福山雅治×石田ゆり子で映画化!】
非公開: 『マチネの終わりに』原作小説あらすじと感想【福山雅治×石田ゆり子で映画化!】




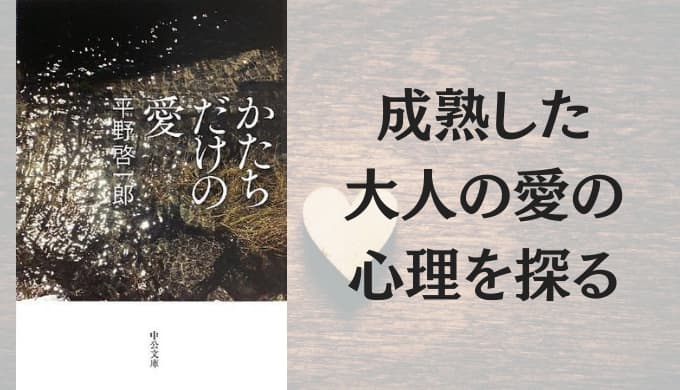
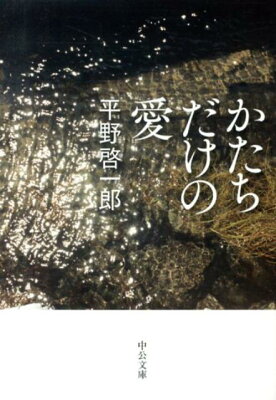

書き手にコメントを届ける