若者のための「ユートピア」。
三秋縋の描く世界は、私にはそんなふうに見える。
作家は人生のなかで本質的に一貫して同じテーマを求め続けると言われている。
では、一体彼は何を探しているのだろう。
なぜいつも彼の本を読み終えたとき、見知った町で迷子になって途方に暮れた子どもの頃を思い出すのだろう。
理由を知りたくて、懲りずにまた読み続ける。
どうせ「ハッピーエンド」にはなれないと、わかっているくせに。
こんな人におすすめ!
- 「リア充」に憤りを感じる人
- 恋愛小説の中でも悲恋に共感する人
- 自分は世の中に馴染めていないと感じている人
あらすじ・内容紹介
あいつらが三億円なら、と俺は考える。俺は三十億くらいあってもおかしくないな
主人公は二十歳の貧乏学生であるクスノキである。
彼は容姿に恵まれる一方、性格は斜に構えており、心のどこかで自分は「特別な人間」だと期待する気持ちを捨てきれずにいる。
小学生の頃に幼馴染の女の子と交わした「二十歳になってもお互いに恋人がいなかったら一緒になる」という約束を覚えており、今年の夏が約束の年だということを意識している。
ある日、金に困っていたクスノキは古本屋の店主から「寿命が売れる」という話を聞く。
半信半疑で教えられた場所に向かうと確かに店があった。
その店で残りの人生の査定価格を聞いた彼は、三ヶ月を残して寿命をすべて売り払ってしまう。
翌日、クスノキの家に女の子が訪ねてくる。
彼女はミヤギという監視員で、最期の三日間までクスノキを監視することが仕事だという。
その日からクスノキとミヤギの奇妙な共同生活がはじまってゆく……。
『三日間の幸福』の感想・特徴(ネタバレなし)
ボーイ ミーツ 100% ガール
容姿に限った話をすれば、彼女は俺の好みそのものだ。涼し気な目、憂鬱そうな眉、きつく結ばれた口元、綺麗な形の頭、柔らかそうな髪、神経質そうな指、ほっそりとした白い太腿――挙げ始めたらきりがない
三秋作品の特筆すべき特徴、それはヒロインが尋常ではなく可愛いということ。
この法則は、本書におけるヒメノやミヤギにも当てはまる。
「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」は、言わずと知れた村上春樹の有名な短編だが、おそらくこれを意識している三秋作品におけるヒロインもまた、ほぼ高確率で100%の女の子である。
可憐で儚げな見た目に加え、内面も健気で淑やか、主人公の青年の傍若無人さを理解し、無言で抱きしめてくれる、もはや世の男性諸君の理想像のような女性であることが多い(男性にガチギレして鉄アレイを振り回す私のような狂暴な女の居場所は三秋作品にはないのだ)。
また、主人公とヒロインは何らかの運命的な絆で結ばれており、奇妙な出来事をきっかけに、過去に失った自身の一部に偶然巡り合うかのようにして、二人は恋に落ちる。
しかし彼らの物語は「幸福」の一歩手前で幕を閉じる。
結末は世間的な意味での「ハッピーエンド」にはならない、というのも三秋作品のお約束である。
運命的な出会いや悲恋、そういうものに魅力を感じる人とこの作品は相性がいいと思う。
しかし、ここまで考えた私はふと考えをめぐらせ、確信する。
それは、平均的日本女子代表として「こんな女性は現実には絶対いない」という確信。
けれど、そんなことはおそらく著者もわかっている。
それでも、美しく非現実的なヒロインとの恋愛を彼が描き続ける理由は何だろう。
「ヒロイン」と「ユートピア」の共通点
今から、衝撃の一言を放つ。
おそらく、三秋作品における「ヒロイン」とは、生物学的に「女」と分類される実態をもった生き物ではない。
もっと別の、切実で観念的な「まぼろし」のような存在なのだと思う。
現実を離れたまぼろしは、美しければ美しいほど良い。
主人公の心の欠落にそっと寄り添い、ひと時の癒しを与える幻影。
「ヒロイン」とは、主人公が遠い昔に失くした「魂の片割れ」であり、あらゆる幸福の原風景なのだ。
こう考えると、あらゆる反発がしぼんで、作品の美しさがすとん、と胸に落ちてくる気がする。
たとえば、誰かにとっては「家族の食卓」が幸福の原風景であるように、きっと三秋さんにとっては「ヒロイン」と過ごす日々が重要な意味をもつのだろう。
それはどこか、「ユートピア」を思わせる。
ユートピアとは、古今東西の人々が、つらい現実から目を背けるために絵画や文学、あらゆる芸術や宗教の中に創造した、未知なる場所。
どこにあるかはわからないけれど、どこかにあると信じたい、幸福の国。
太宰治は『女生徒』のなかで
明日もまた、同じ日が来るだろう。幸福は一生来ないのだ。それはわかっている。けれども、きっと来る、あすは来る、と信じて寝るのがいいのでしょう
と書いている。
だから、きっと著者も自分の欠落を補う何かがどこかあり、それが「幸福」の手がかりなのだと、読者に信じさせたいのかもしれない。
たとえ、結果的に現実の世界で手に入れた何かが、当初想像していたものとは少しだけ姿を変えていたとしても。
そういうわけで、私にとって、本書を含む三秋作品は、「ユートピア」についての話のようにも見えるのだ。
雨の音が子守歌になった。俺はいつものように、眠りにつく前の習慣を始めた。瞼の裏に、いちばんいい景色を映す。俺が本来住みたかった世界について、一から考える。ありもしない思い出を、いったこともない「どこか」を、過去かも未来かもしれない「いつか」を、自由に思い描く(中略)しかし、こうすることでしか、俺が世界に折りあいを付けられなかったのも確かだ
このシーンのあとで、クスノキがみたものは、夢か、現か。
自らの寿命が尽きるとき、クスノキが手にするものは何か。
それは皆さんが自分の目で確かめてほしい。
音楽や文学に対する知識量の多さ
「好きなことをすればいいんです。あなたにも趣味くらいあるでしょう?」
「ああ。音楽鑑賞と、読書がそれだった。……しかし、今考えると、この二つは俺にとって、『生きて行くため』の手段だったんだ。どうしようもない人生と折り合いを付けるために、音楽と本を用いていたんだよ。無理に生きていく必要がなくなった今、その二つは俺にとって、以前ほど重要ではなくなってきてる」
ここまでの文章で、言いたいことはすべて伝えてしまった気がするけれど、最後のパートではネタバレにならない範囲で、「他作品へのオマージュ」について言及したい。
本書は特に他の文学作品への言及が多いように思う。
たとえば、クスノキが図書館で選んだのは、ポール・オースター、宮沢賢治、オー・ヘンリー、ヘミングウェイだ。
クスノキは上記の作品たちを「いかにも面白味のない選択」だというが、中盤のとあるブツをばらまく場面は、オースター作品によく出てくるし、ノートに記録を残すことも、思い出の場所を徘徊することも、クスノキが彼の作品に十分影響を受けているからだと解釈することもできるだろう(ちなみに私のオススメ作品は『ムーン・パレス』と『ティンブクトゥ』)。
そしてユダヤ系アメリカ人であるポール・オースター自身もまた「ユートピア」という概念を作品の中で模索する作家のひとりである。
この『三日間の幸福』自体が、クスノキによるひとつの記録なのだとしたら、最終章のタイトルはエピソードを含めて、ひどく効果的に響くし、書くことについて書くというメタフィクション的な意味においてもある意味では成功している。
また、作中では文学作品だけではなく、音楽に対する言及もかなり多い。
きっと著者は相当に守備範囲が広い方なのだろう。
作家の知識量はすごいなと敬服すると同時に、読むたびに新しい知見が広がってゆくのも、三秋作品の魅力のひとつである。
まとめ
わたしたちを取り巻く現実は、時にどうしようもなく、淋しく、厳しい。
けれど、本を読み、心を震わせることで、私たちは命を感じることができる。
本を読み、美しさに浸ることで、現実が途方もなく脆いことも思い出す。
それでも、今もまだこの世界で生きているのは、「いつかいいことがあるかもしれない」という期待を手放せずにいるからだ。
そして、そのような生き方しかできない人間にとって、幸福と絶望の狭間で微妙なバランスを保つ三秋縋の作品は、ある種の延命措置的な「ユートピア」になりうるのだと思う。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
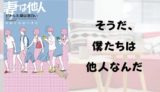
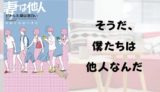
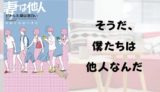
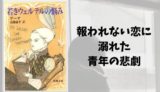
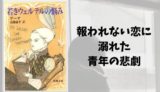
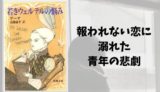



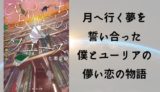
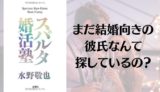
書き手にコメントを届ける