「残業したくない、でも残業するな!も困る。」
という本の帯に惹かれて購入。
残業がつらいのは、自由な時間がなくなることだけではない。
残業が続くと、まず、体力が持たない。
さらに、「残業しても仕事が終わらない」と、自分の能力や努力が足りないのでは?と思ってしまうため、精神衛生上もよろしくない。
とはいえ、「残業を減らせ」と言われても、仕事は減らない。
と、悩んでいる方に、お勧めしたい本だ。
今回紹介する本により、「残業がなくならないのは、あなたの努力不足だけではない」と伝わればいいなと思う。
こんな人におすすめ!
- 残業続きで疲弊している人
- 労働問題に興味を持つ学生
- 残業時間が規制されても、全く楽にならない人
- 残業なんて、仕事ができない人がすることだと思っている人
あらすじ・内容紹介
タイトルの通り、「なぜ残業がなくならないのか?」を、著者の実体験も交えつつ、統計や調査をもとに考察する本。
残業が発生するには、それなりに理由があるはずだと、残業の「合理性」や、残業しなければならない制度設計など、あえて残業の「メリット」について書かれている。
また、問題設定そのものが本当に正しいのかについても言及されている。
たとえば、「日本は諸外国と比べて生産性が低い(だから生産性をあげるべき)」と使い古された言い回しだが、そもそも「生産性」とはなにか?
「生産性が高い」国に共通する特徴とは?
さらに、「働き方改革」や、労働時間を減らす「解決策」についても、画期的なようで実は古いし、当然万能ではないと指摘。
「テレワーク」を始めとした「働き方改革」は、本当に労働時間を削る飛躍的な解決方法か?
本当に労働者のための働き方改革になっているのだろうか…働き方に対して「当たり前」「思い込み」に疑問をつきつけてくれる1冊。
著者は、大手企業で営業から管理業務まで携わり、ベンチャー企業、フリーランスと様々な「働き方」を経験しており、様々な体験談についても「あぁこうやってヒトは残業をしていくのか。」と、イメージがしやすい。
著者の体験談のみに終始せず、統計や根拠もきちんと示して、読み終えたあとは何かしら新たな発見があるはず。
そのうえで、著者独自の労働時間を減らすための10の方法に注目だ!
『なぜ、残業はなくならないのか』の感想・特徴
なぜ残業が発生するのか
厚生労働省が企業に調査を行った「残業が発生する要因」については以下のとおりとのこと。
「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」が最も多く
「業務量が多いため」
「仕事の繁閑の差が大きいため」
「人員が不足しているため」
あれ、どこにも「従業員の能力が低い」「仕事の効率が悪いため」と書いていないぞ。
企業側の回答であるにもかかわらず、個々人の能力・資質に起因する回答が少ないのも、特徴である。
と、言われてみれば思い当たるケースは多い。
まず「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」深夜まで仕事をしている官僚が思い浮かんだ。
朱野帰子『わたし定時で帰ります。』の主人公も、勤務先はソフトウェア会社で、顧客の要望に応えるため社員が残業せざるを得ないという小説だったように思う。
著者個人のリクルートの営業企画時代の体験談とも結びつくが、顧客とは社内の人間も含む。
業務量もさることながら、打ち合わせの回数、さらには企画書を書くための時間が原因だった。打ち合わせを商談に置き換えると、営業時代とまったく変わらない
営業担当と打ち合わせをする機会が多いのだが、彼らは昼間営業に出ているので、午後6時以降の会議がマストとなった
そう、企画職や事務職なども、外勤こそないとしても、社内の顧客(社員)の都合で残業が増えるんだよなぁ。
残業が減らない理由1位は、個人の努力以外の要因だった。
別に新しくもないし、万能でもない「働き方改革」
印象深かったのは、「業務量が多い」「人が少ない」という問題について、単純作業を切り離してアウトソーシングするという手法について、
ルーチンとなっている部分を派遣社員に任せる、外部にアウトソースするなどである。AI(人工知能)に置き換えるという議論すらありうるだろう。ただ、皮肉なことにこのやり方は、ますます正社員の業務の属人化を誘発する可能性を秘めている。
というデメリット。
こんな弊害があるのか!と目からウロコ…の、ようでいて、思い当たることがあるような気もする。
確かに、「単純作業はどんどん他の人に振って」と言われるが、単純作業そのものより、作業を振るほうが頭と神経を使う。
何をどこまでどうやればいいかわからない状態から、道筋をつけて、人に説明するまでが、脳のメモリを消費する感覚といえばいいのか。
AIに仕事を奪われるというが、AIすら引き取らない仕事のほうが、難易度が高いうえ、「ワークシェアリング」しづらいという問題点がありそうだ。
また、テレワークについても、期待しすぎるのもどうだろうか、とは個人的に常々感じていた。
正直、新型コロナウイルス感染防止のために、在宅勤務が推奨された中で、「在宅勤務の弊害も知られるといいさ」とひっそり感じていたくらいだ。
テレワークに対する期待が集まっているが、時間や場所の自由を手に入れて働くことで劇的に変わるのは、移動時間が減ることだ。
そう、確かに、移動時間が節約できるのは大きいだろうなとは思う。
しかし、「家で」仕事をするとなると、オンとオフの境目がつかなくなりそうだ。
原稿に集中しようと思ったら打ち合わせの電話が入り、30分から1時間潰れることもしょっちゅうだ。宅急便の配達、家事などもあり、業務は常に止まる。
あぁ、やっぱり。在宅ワークは未経験だけど、個人的に懸念しているのはこれ。
自己管理能力に長けていて、意志が強くないと、在宅勤務はかえって効率が悪くなりそうと感じてしまう。
込み入った話だと、電話でのやりとりは対面のやりとりより、伝達に時間がかかりそうだし。
と、当然不便な面もあるテレワーク。
むしろテレワークから、オフィスに出社してのワークを推進する方向に舵を切った企業もある。世界のIT企業が都市部にオフィスを構え、対面でのコミュニケーションを重視する方向にシフトしていることなどが良い例だと言えよう。
あら、テレワークって、もはや時代遅れ?
コロナ禍のメリットって、テレワークのメリット・デメリットが可視化されたことかなぁと感じた。
当たり前だけど、良さそうに見える取り組みにも、当然デメリットや、カバーしきれない領域ってあるよね。
「目新し」く思える解決策にも、期待しすぎてはいけない。
「誰得」の「働き方改革」?
庶民の視点から言うならば、個人の働き方を国が考えてくれそうでいて、単に介入しているように見えてしまう。
確かに。
誰のための働き方改革か。
特に、利益誘導についての指摘が興味深かった。
働き方改革に取り組んでいる企業には、IT企業や人材ビジネスが目立つ。実際、「働き方改革」はこれらの業界に「特需」をもたらす。かなり意地悪な見方だとは思うが、自社を事例にして営業をかけようという思惑すら見え隠れする。
「働き方改革は利権だ」と極端なことを言うつもりはないけれど、確かに「働き方改革」は、特定の企業にとってはビジネスチャンスでもある。
「働き方改革」需要により、仕事量が増えて社員が疲弊する、という皮肉な企業もありそうだ、と想像してしまった。
で、誰のための働き方改革か?と考える中で、1番すきなフレーズがこちら。
「働き方改革」は所詮、「働かせ方改革」である。
「いかに働かないか」「いかに一生懸命働かないことを許容するか」という発想がない限りは、画餅に帰してしまうのである。
いい!いい!「いかに一生懸命働かない」。
「働かない」というと聞こえが悪いなら、取捨選択とでもいおうか。
「顧客を選ぶ、絞る、仕事の絶対量を減らす、仕事の受注ルールを明確にするというのも、一つの選択選択肢なのだ」
あれ、これって「エッセンシャル思考」の考え方じゃないか。
 『エッセンシャル思考』あらすじと感想【全現代人の課題図書】
『エッセンシャル思考』あらすじと感想【全現代人の課題図書】
まとめ
どのみち「残業ありき」で制度設計されている社会だ。
「私が頑張らなきゃ」で思考停止していたんだな…と気づいた。
これからは、取捨選択・効率化という美しい響きのもとに、全力で楽をする方向に頭を使いたい。
「働き方改革」は「働かせ改革」でもあると割り切り、自分を「働かせない改革」を、こっそり推奨していこう。
この記事を読んだあなたにおすすめ!






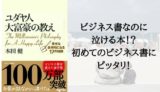
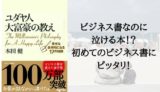
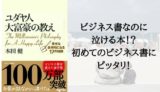

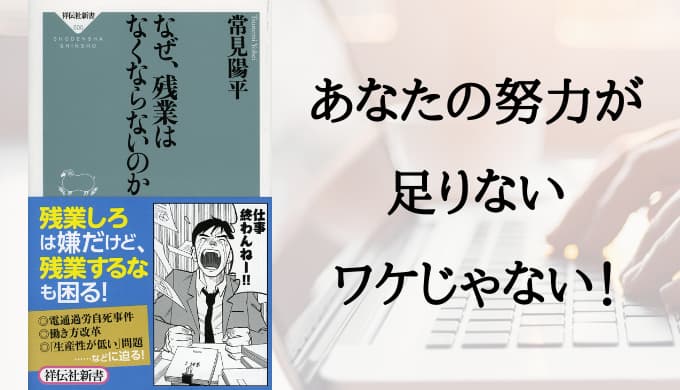

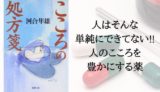
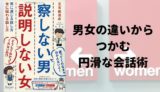
書き手にコメントを届ける