バブル真っ只中の東京港区を謳歌(?)する日々を綴った、エネルギー溢れるエッセイ。
都会に染まりきれない田舎者、プライドの高い女性、必読です。
あらすじ・内容紹介
ファッション、芸能界、スキャンダル、オトコ――〝発展途上有名人〟であった著者がそれぞれの世界の裏表を旺盛な好奇心で覗き見、探求して、発見した意外な〝真実〟――繊細な感性と匂いたつ筆さばきで描く「週刊文春」連載の好評エッセイ集の第一弾。
今夜も思い出し笑いの感想(ネタバレあり)
鋭すぎる観察力
「完璧なマニキュアをする美人」
「私ってイイ女よ。いつもみんなに見られているわ。だからおテテも綺麗にしとかなければ……」という義務感なしでは、とうていやりおおせるものではない。
非の打ちどころがないマニキュアをしている女とは、まず初対面でダメだ。絶対に友達になれそうもない。
あまりに的確な指摘に、ひっくり返りました。
超わかる。
そういう女いる。
装具の一種としてのネイルであれば全く問題ないのですが、女としての感情が伴った段階で、虫唾が走るのです。
何だか鼻につく人って、思えばこんなこと考えてそうかも。
彼女の鋭すぎる程の観察力と巧妙な描写は、痒いところを一緒に掻き毟ってくれるような〝痛〟気持ちよさがあります。
容赦ない斬り捨て
「オトコが鏡に向かう時」
男が鏡に向かう時間は、最小限、かつ義務的であってほしいと思う。
「ちょっと気になる男」
「女」と「相談」、この二つの単語がドッキングすると、私は異常といっていいほどイライラするのである。
わかる~~~~~~~。
超わかる。
彼女が牙を剝く対象は、美人だけではありません。
自分の容姿に、近寄ってくる女の存在に、浮足立つ男性を容赦なく批判します。
その小気味よさと言ったら!
もはや偏見だろうというご意見もあることと思いますが、ご本人も自覚の上。
さらには、見栄っ張りで、田舎者が抜けず、ずぼらで気分屋な自分自身への皮肉も忘れません。
このユーモアが、彼女をただの毒吐きではなくどこか憎めない存在に映す理由だと思います。
港区民になっても
「本のなかのウソ」
けれども、「本」という名称でよばれるものに、白い紙の上に、嘘をつくことは絶対に許せない。
本に対する信頼や尊敬は人一倍だと、彼女は言います。
ファッションだオトコだ、と奔放に書き綴る中でも、やはり本の話は避けられないのだな…本好きであればあるほど頷けるのではないでしょうか。
華々しく、移ろいの激しい世界に生きていても揺らがない、幼い頃から構築された文学少女気質。
これも彼女をチャーミングに見せる理由のひとつです。
主題歌:PUFFY/アジアの純真
PUFFY「アジアの純真」
ぶっ飛んでいるけれど、それがクセになる。
年代や歌詞の内容が本作と重なるわけではありませんが、読みながら頭を巡るのはこの曲でした。
追記
最後に、この本と出会った古本屋さん、尾道にある「弐拾dB」を紹介します。
(記事の公開にあたり「すごく古い本ですね!」「本のチョイスが面白いです」とのお言葉を頂きました。とても嬉しかったので、その出会いを書きたくなったのです)
寝静まった商店街を黙々と歩き、看板の灯りを目印に店内へ。
年季の入った本棚の間を行ったり来たり、立ったり座ったり。
カバーをかけて頂いた数冊をポケットに入れて、夜のキンと冷えた空気の中、来た道を戻る。
すぐ傍のコンビニでお菓子も買ったし、これから夜更かしだなあとわくわくしながら。
深夜の外出は、何歳になっても胸躍るものですね。内心大はしゃぎでした。



営業時間は23時から。
医院を改装したという面白い内装、ブックカバーも薬袋のデザインそのままです。
お話上手な店主さんは、とても素敵な人です。(選んだ本を見られるのちょっと緊張しました)
尾道を訪れた際はぜひ。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
「言いすぎる女」「めんどうな女」という言葉がどうにも本作の作者を彷彿させます…
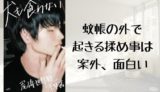 『犬も食わない』あらすじと感想 【蚊帳の外で起きる揉め事は案外、面白い】
『犬も食わない』あらすじと感想 【蚊帳の外で起きる揉め事は案外、面白い】




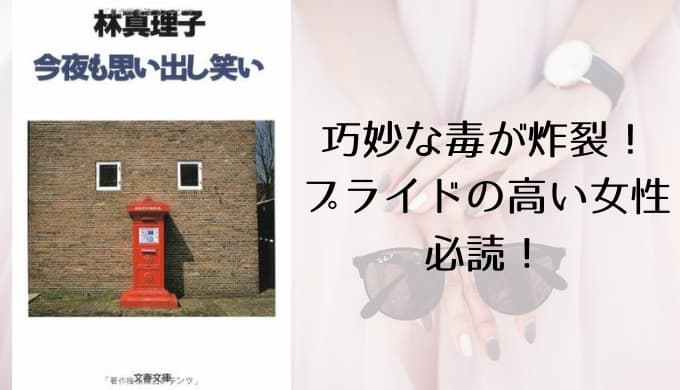

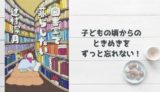
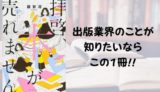
書き手にコメントを届ける