2007年公開の同名映画のノベライズである本書は、日本映画としては非常に特異と言える構図で物語が進展していく。
登場人物たちは所謂「オフ会」の会場である一室、ただ其処のみにおいてストーリーを展開する。
閉鎖的な舞台、ともすれば単調にもなりかねないその一室で繰り広げられる推理劇は、当初至って平穏な空気で幕を開ける。
しかし読み進めるにつれその一室に漂う雰囲気は多彩に変貌を遂げて行く。
時に陰鬱なほどシリアスに、時に思わず声を上げて笑える程愉快なコメディに。
そして最後には荒れ狂う悪天がやがて爽やかな快晴に移ろう様に穏やかに、読む者の心にも日が差したかのような得も言われぬ温かさに包まれる。
今回は、そんな本書に秘められた魅力をお伝えしていきたい。
こんな人におすすめ!
- 冴えたツッコミで笑うのが好きな人
- 原作映画を鑑賞し、その魅力に当てられた人
- 与えられた情報の断片から推理するのが好きな人
あらすじ・内容紹介
―― 一周忌に、みんなで集まりませんか。
“遅れてきた清純派アイドル”「如月ミキ」(きさらぎ みき)。
焼身自殺によって亡くなった彼女を今でも心から愛してやまないファンの1人、ハンドルネーム「家元」(いえもと)が開設した掲示板にそんな1文が書き込まれる。
その提案を受け、家元の主催で開催されることになった追悼式には他に4人の男が集まった。
追悼会発案者の「オダ・ユージ」、福島で農業を営む肥満男子「安男」(やすお)、雑貨屋店員で垢抜けたルックスの「スネーク」、そしておよそハンドルネームから来る印象とは似ても似つかない中年男性「いちご娘。」(いちごむすめ)。
自己紹介もそこそこに互いのコレクション披露や思い出話に華を咲かせる面々。
しかしただ1人オダ・ユージだけは心ここに在らず、発せられる言葉の端々に家元は違和感を禁じ得ない。
そしてオダ・ユージの意図によるものか否か、話題はいつしか如月ミキの命を奪った凄惨な事件についてへと移って行く。
『キサラギ』の感想・特徴(ネタバレなし)
映画では語られなかった「家元」の胸中
本書と原作映画における最大の相違点は、「物語を俯瞰する三人称視点から当事者による一人称視点への変化」である。
原作映画は、ある種舞台劇にも近い三人称の視点でストーリーが進行しており、登場人物1人1人の心情は本来劇中で発せられる言葉から読み取るしかなかった。
しかし本書は家元の一人称視点で物語が展開されており、彼の言動の裏に隠された心情を主観的に体感できる構成となっている。
他のメンバーへの印象、如月ミキへの愛情、そして家元自身が抱える悩みや葛藤。
劇中では語られることの無かったそれらの思いは、繰り返し映画を見た人にとっても確実に新鮮に映るだろう。
逆に原作を未鑑賞の方は是非読了後に映画の視聴をお奨めしたい。
家元の胸中を同じ視点で体験した後ならば、彼の浮かべる表情、発せられる言動、その1つ1つに秘められた思いを噛み締めながら鑑賞を楽しめるはずだ。
徐々に明かされるメンバーの秘密
如月ミキの死の真相に迫るにつれ、話の流れで追悼会に参加したメンバーの正体が徐々に明らかになっていく。これは本書の見所の1つと言えるだろう。
そして彼らの正体が暴露されることこそが、場の雰囲気の転調に一役買っている点にも注目したい。
読み進めるにつれ、何れの人物もが事件の核心に迫る重要な役割を担っていることが判明してゆく。
それは時に思わず生唾を飲むような緊張をもたらし、時に思わず「マジで!?」と叫びたくなるような衝撃と爆笑を誘う。
徐々に明かされる真実が緻密に噛み合う濃厚な密室推理サスペンスでありながら、タイミングと言い回しが練り上げられた秀逸なコメディでもある。
本来両立しえないそれらが混在するため、「早く続きを!」と読み進める手を逸らせながら、しかし一言一句たりとも読み飛ばすことができない。
非常に読み応えが有る、より正確に言うならば「読む手応えが確かに得られる」作品であると言える。
「現実」と「真実」
それぞれの抱える秘密が明らかになるにつれて、如月ミキの自殺は新たな側面を見せ始める。
バラバラだった状況証拠が彼らの裏付けによって1つ1つ音を合わせる様に組み合わさる終盤は、読み進める毎に奇妙な快感を呼び起こしてくる。
「あぁ、あの話がここに来てこんな展開に!!」
巧妙に仕組まれた伏線の数々が新たな真実を生む度に、そんな興奮が読者の胸中を占め、まるで自身もその場に在って彼らと共に新たな真実の誕生を祝福し合っているかのような感覚に陥らせてくれる。
しかし、如何に辻褄が合っていたとしても、それはあくまでも状況証拠の寄り合せに過ぎないのもまた事実なのである。
「あまりに都合のいい仮説だ」
作り上げられた真実に納得が行かないオダ・ユージに対して家元が返した言葉は、「現実」と「真実」という似て非なる2つの言葉について読む者の価値観に大きな波紋を起こすだろう。
「都合のいい仮説で何が悪いんですか。みんながいちばん納得できる仮説です。あなたも罪の意識から解放される。実際に何が起きたかなんて、いまとなっては誰にもわからないですよ。でも、だからこそ考えるわけでしょう。そして、真実は考えることができた者の心の中にしかないんじゃないですか。この説をみんなで信じる事にしませんか」
どんなに些細な事であったとしても、物事の「真実」を明らかにすることはまずもって困難だ。
主観的にしか観測しえない其れを断定することは、およそ不可能と言っても過言ではない。
だからこそ、「現実」とは違い「真実」は関わった全ての人の数だけ存在するとも言い換えられる。
ならば、その中から自分にとって最も納得のいく都合の良い真実を選ぶことこそが、相手に対する最大の信頼と愛情の現れと言ってよいのではないだろうか。
まとめ
一般に「密室推理」と銘打たれる作品は、最終的に揺るぎ無い「真実」に辿り着くことを至上の命題としている。
「真実は闇の中」などとのたまって全てを明らかにしないまま完結する推理サスペンスが有ったとしたら、恐らく読者の反感を買うことは間違いないだろう。
本書はその点を逆手に取り、明かされない「真実」によって全員が精神的に救われる形で幕を閉じている。
本当は如月ミキの身に何が起こったのか、彼女は何を思いどのように行動したのか。
それを捉えられないからこそ彼女は虚像、真の偶像(アイドル)であると納得する。
それは一見して現実逃避なのではないのか、そんな疑問を差し挟みたくなるかも知れない。
それもまた人の情、否定できるものでないのも確かである。
しかし生きて行く上で受け止め難い現実を自身に都合の良い形に変換して解釈することは、ある種健全な精神活動であるとも言える。
終盤にかけて多用される「真実」と言う1つの言葉は本書における最大のテーマでもある。
誰もが求め、しかし常に疑わずにはいられないその言葉を誰もが納得できる形に収めている。
それこそが、私自身この作品に取りつかれて止まない最大の理由なのかもしれない。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
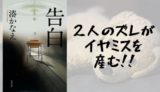 湊かなえ『告白』 あらすじと感想【良かれと思ったことが面白いほどにズレていく】
湊かなえ『告白』 あらすじと感想【良かれと思ったことが面白いほどにズレていく】
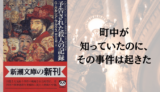
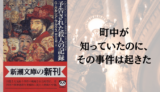
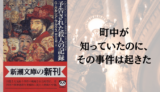



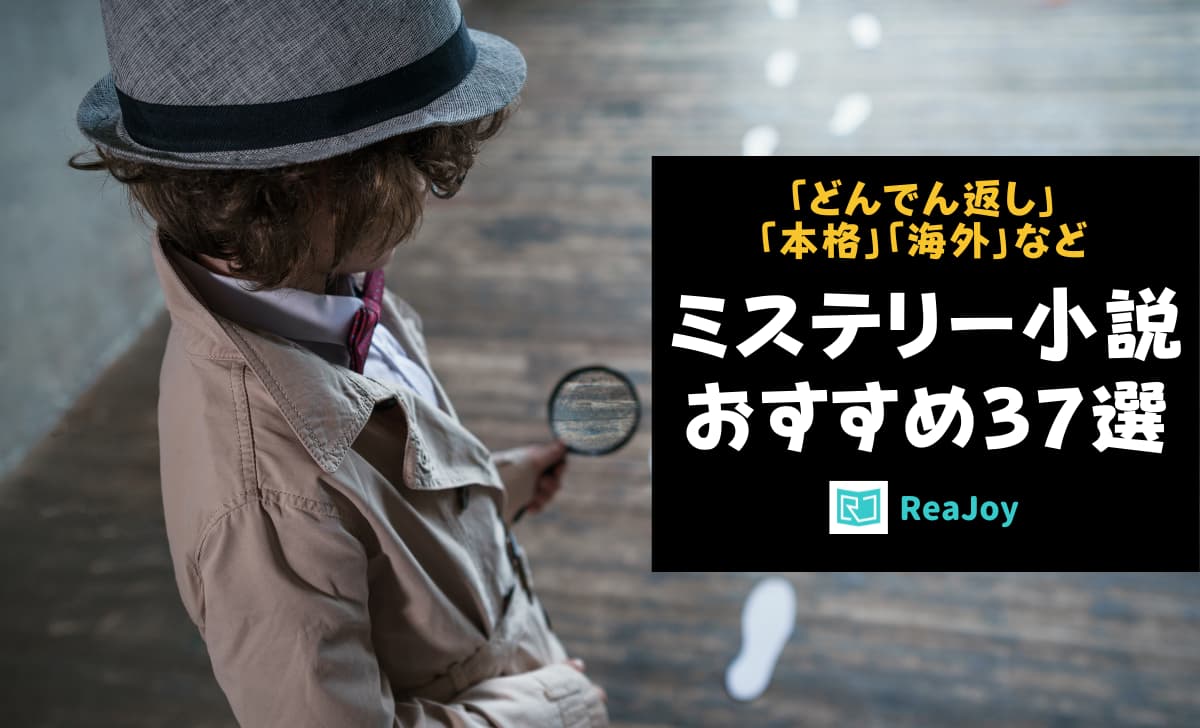
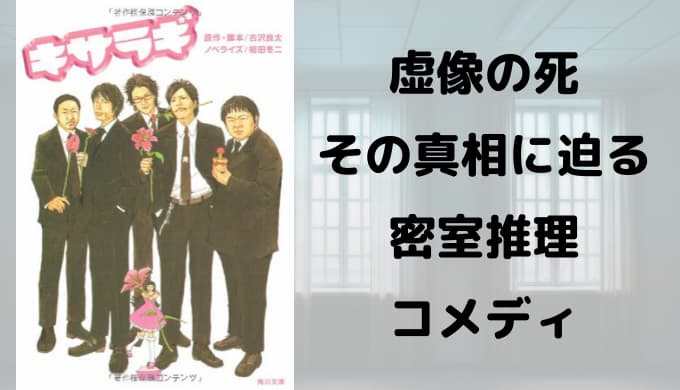

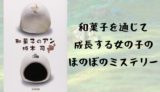
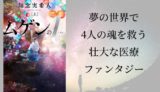
書き手にコメントを届ける