全3回にわたって落合陽一の魅力を伝えるこの特集。
前回の記事はこちらを参照していただきたい。
 【現代の魔法使い!落合陽一特集】第1回: 落合陽一とは一体何者なのか?
【現代の魔法使い!落合陽一特集】第1回: 落合陽一とは一体何者なのか?
第2回の今回は落合氏の著書全作品(2019 2月時点)の書評を公開したいと思う。
なかなか他のサイトでもすべての作品を比較することはまずないと思うので、最後までぜひ見てほしい。
なお、私の独断と偏見で本の難易度を★で5段階評価したので、購入の際の参考にしていただければ幸いである。
また、年代順に作品を並べてある。
目次
静かなる革命へのブループリント: この国の未来をつくる7つの対話
落合陽一にいまいちなじめない人に!
難易度:★★
落合氏自身が書いた最初の著書、というわけではないが7つの対談の一つとして落合氏の話が載せられている。
この本が出版されたのが2014年でおよそ5年前なので、現在の落合氏とはやや異なる(本質的には同じ)ように感じるので注意したい。
落合氏のページはそれほど多くはないので、今まであまり興味はなかったけどちょっと知りたいかな?という人におすすめである。
内容が少ない分エッセンスが詰まっているので落合氏が好きな人も、嫌いな人も読んでいただきたい。
魔法の世紀
まず初めに読むべき本!
難易度:★★★★
この本で落合氏が一躍有名になったと言っても過言ではない、落合氏の代表作である。
本書を読んだ人はまずかなりの衝撃を受けたことだろう。
まず驚くのが中身の濃さ。
注釈や参考文献などがあげられているが、それを見ながらでないとすべてを理解するのは難しそうだ。
ざっくり言ってしまうとこの本では
「充分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない」
というテーマが中心となっている。
なかなか抽象度が高いので理解しにくいかもしれない。
(※抽象度が高いものを具体化している練習の一つとしてSHOWROOMの社長である前田裕二氏が書いた「メモの魔力」という本でメモの技術を磨くのがよいだろう。参考までにこちらの記事を参照していただきたい。)
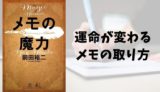
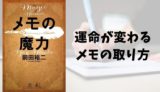
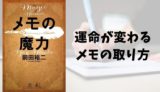
ただ、何回も読み進めることでなんとなく落合氏の世界観がわかってくる感じがする。
まぁ、所詮凡人の私には100年かかっても理解できないのだが。
これからの世界をつくる仲間たちへ
これからの世界、どう生き抜いていくのか?
難易度:★★★
コンピュータと人間の関係性について述べつつ、どのような人がこれからの世界を創造していくことができるか?といったことが本書での鍵となる。
224ページあるのだが、比較的読みやすい文章が並んでおり数時間あれば読み切れると思う。
ちなみに私は通学途中で本屋で購入、その日のうちに一気読みした!
一番印象に残っているのがこの文章である。
コンピュータに負けないために持つべきなのは、根性やガッツではありません。コンピュータになくて人間にあるのは、「モチベーション」です。
たしかに、この発言は的を得ているように思う。
どれだけコンピューターやAIが発達しても、企業家のような熱いモチベーションを持つことはない。
そういった点において、これからの時代も人間の優位性が維持されるのではないだろうか?
また、自分の専門性を高めるために、以下の5つの文言を提示している。
・それによって誰が幸せになるのか。
・なぜいま、その問題なのか。なぜ先人たちはそれができなかったのか。
・過去の何を受け継いでそのアイディアに到達したのか。
・どこに行けばそれができるのか。
・実現のためのスキルはほかの人が到達しにくいものか。
なかなか心に刺さる言葉である。
一種の自己啓発本的な役割も果たしつつ、現代の課題や解決策も提示している、他の著者の本とは一線を画す良書である。
超AI時代の生存戦略― シンギュラリティに備える34のリスト
AI全盛期時代に向けた、人間が取るべきアクションとは?
難易度:★★
本屋を見渡せばAI関連の本が多数並べられており、著者によって意見がばらばらなので私自身どれが正しいのかわからない。
特にシンギュラリティ(端的に言えば人工知能が人間の知能を超える点)が訪れるのか否か、を問う問題が非常に物議を醸しており、専門家によって真っ二つに意見が分かれている。
そんな中で、落合氏はシンギュラリティが訪れるとの意見も持っているので、読む際にはこの点を注意していただきたい。
大きなテーマとなっているのが、先ほどの本でも述べられているのだが「人間らしさとは何か?」ということである。
そこで落合氏は働くという概念を根本から見直す必要がある、と主張している。
今の社会において、雇用され、労働し、対価をもらうというスタイルから、好きなことで価値を生み出すスタイルに転換することのほうが重要だ。
先述のとおりAI関連本は多数存在するので、落合氏の主張を鵜呑みにするのではなく、ほかの著者の本も参考にするとよいだろう。
日本再興戦略
ポジションをとれ。
難易度:★★★
題名から保守的な本かと予想していたが、全くそうではなかったので安心してほしい。
そろそろ書評も飽きてきたと思うので、ここでは気になった項目を一つだけ取り上げる。
それは百姓的な生き方である。
これからの時代、一つの仕事をずっとするのではなく、より多くの仕事を掛け持ちし百の生業を目指す、というものである。
こうすることで機械に置き換わられなくて済む、と主張する。
しかし、ここで注意していただきたいのは前提条件としてまず一つの分野でずば抜けた実力が必要だということである。
私は幻冬舎の箕輪厚介氏やSHOWROOMの前田裕二氏の講演会に参加したことがあるのだが、この二人も同じことを言っていた。
色々やって全部中途半端で終わるのではなく、まずは誰にも負けない分野を一つ作っておき、そこから横や縦に展開していく、という意味で受け取っていただきたい。
本書の最後にTwitterでつぶやかれた名言が掲載されている。
ポジションを取れ.批評家になるな.フェアに向き合え.手を動かせ.金を稼げ.画一的な基準を持つな.複雑なものや時間をかけないと成し得ないことに自分なりの価値を見出して愛でろ.あらゆることにトキメキながら,あらゆるものに絶望して期待せずに生きろ.明日と明後日で考える基準を変え続けろ.
かっこいい。
肝に銘じたい……
10年後の仕事図鑑
落合陽一とホリエモン、夢のコラボ!
難易度:★★★
この本は落合陽一氏と堀江貴文氏の共著である。
落合氏の他の著書とは異なり、この本では特にこれからの仕事にまつわる環境やトレンドについて焦点を当てている。
例えば、本書の第2章では機械化、AIの台頭で無くなる仕事、変わる仕事について具体例を交えて説明されているので非常にわかりやすい内容となっている。
AIによってこれまで管理職がおこなっていたほとんどの管理に関する仕事は取って代わられる可能性が高いし、介護職などは機械と人間が共同で行うことで人間の負担が軽減される
と落合氏は語っている。
また、そのような脱近代において私たちはAIに取って代わられない領域で生き残る必要があると警鐘を鳴らしている。
そして、以前は大企業に就職すれば一生安泰というイメージがあったが、現代ではほとんどの企業は人間の寿命より短く(医療の発展で人間の寿命が延びた)なることで、一生にいくつかの仕事を経験する人の方が標準的になると語っている。
こんな世の中で、私たちは一体どう生きるべきなのか、本書にはそのヒントが隠されているように思う。
ホリエモンこと堀江貴文氏は、私が思うに落合氏とはややタイプが異なる人間で、自分が好きなことをただひたすらやる、というのをモットーとしている。
大学教員(だけではないということは本特集の第1回を見ていただいた方ならご存知だが)という立場の落合氏と、カリスマ実業家のホリエモンとの共著はある意味でそれぞれの良さが引き立ったミックスジュースのような感じを呈している。
ビジネス書として売られているが、これから就活を控えている大学生や、未来のことに関心がある高校生など、若い世代の人にも読んでいただいたいと思う本である。
次のページ

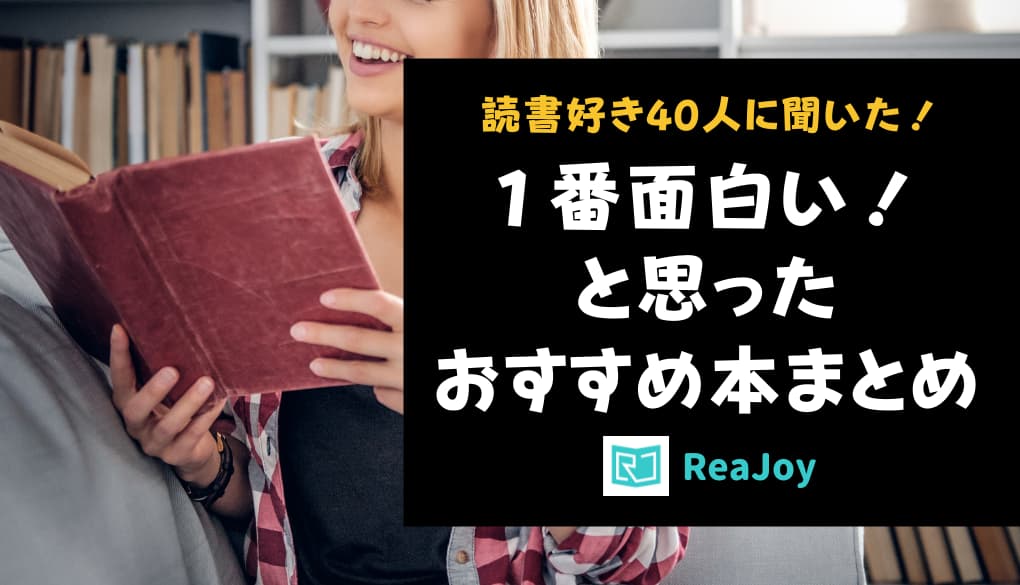
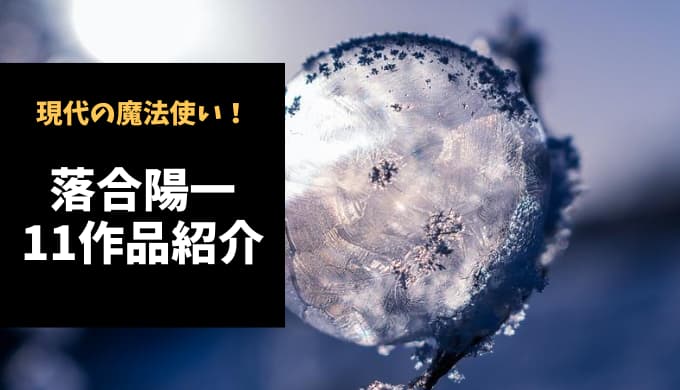




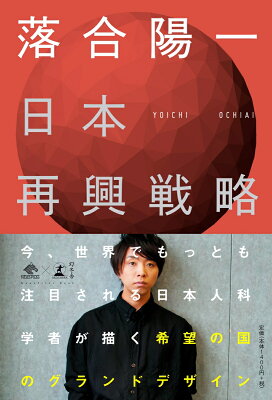
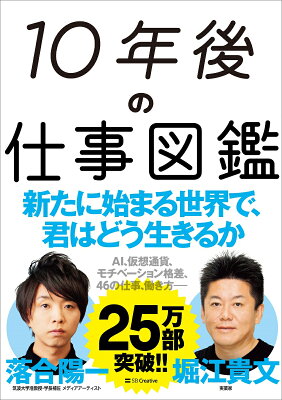
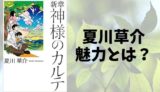

書き手にコメントを届ける