あなたは海外小説に親しみがあるだろうか。海外小説は翻訳されているため読みづらく、登場人物までもが難解で読むのに抵抗がある方も多いことだろう。
でも大丈夫。今回はそんなあなたのために、面白い!と断言できる海外小説を12作品ご紹介する。
確かに時間はかかるかもしれないが、時間をかけてでも読む価値のあるもので、読まなければ損をしてしまうほどの作品たちだ。少しでも海外小説に興味を持っていただければ幸いである。
目次
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ
「プラハの春」の激闘下に書かれた、チェコ出身のミラン・クンデラによる名作。
プラハの優秀な外科医であるトマーシュと、その恋人・テレザを中心に描かれた激闘下での愛の物語。
トマーシュの愛人であるサビナや、サビナの愛人・フランツの登場で物語は思いがけない方向へと突き進む。全世界の存在は必ず二分され、肯定的なものと否定的なものに分けられるというペルメニデースの哲学。では、「重い」と「軽い」では、どちらが肯定的で、どちらが否定的なのか。もし「軽い」が肯定的だとしたら、なぜ私たちは恋愛において、「重い」行為を求めてしまうのだろう。
たった一度しかない人生で、「愛」という存在の軽さは果たして本当に耐えがたいものなのだろうか。「愛」というテーマに真っ向から立ち向かった、20世紀恋愛小説の最高傑作だ。
『神秘大通り』ジョン・アーヴィング
小説は長ければ長いほどいいと評した、ジョン・アーヴィングが手掛ける長編超大作。
フワン・ディエゴは人の心が読めるが兄にしか分からない言葉を話す妹と共に、ゴミ捨て場で育った。ゴミ捨て場に捨てられた本を読み漁り、膨大な知識を身につけたフワンは、ある日父親とも呼べる存在が運転するトラックに轢かれて足が動かなくなる。
母親は教会の掃除婦であり、妹はサーカスに入団。その2人の存在をのちに亡くすことになるフワンは、古い友人との約束を守るために遥々マニラへと舞い降りた。彼がとある親子と出会い、その親子と性交渉を繰り返す中で、亡き友人、亡き妹、亡き母親への感傷旅行(センチメンタルジャーニー)は、一体どこへ向かっていくのだろうか。
アーヴィングが25年間温めてきた長編大作を、ぜひ堪能あれ。
『地下室の手記』ドストエフスキー
この作品はジッドによって、「ドストエフスキーの全作品を解く鍵」とも評されたものであり、それほどドストエフスキーの思想が全面的に溢れている。
極度の自意識過剰のせいで社会と断絶し、地下に閉じこもった主人公。人間は結局、目的を達成することに楽しみを見出すのではなく、その過程を好んでいるだけなのではないか。自然とは一体何か。神は最強というのならば、自然よりも強いということになる。
しかし2+2=4、という自然の法則は変わらない。では、自然の摂理を変えられない神は最強とはいえないのではないか。
なぜ彼は地下室に閉じこもるようになってしまったのだろうか。その全貌が、彼が地下室で書きなぐった手記によって明らかになる。第一部では彼の思想。第二部では彼が地下室に閉じこもった経緯が書かれる。人間の本性とは一体何なのだろうか。究極のテーマに向かい合ったドストエフスキーの大作である。
ページ数も少ないため、ドストエフスキーをこれから読んでみたいと思う方におすすめの作品だ。
『イワン・イリイチの死』トルストイ
物語は1人の判事、イワン・イリイチが死ぬところから始まる。
彼は昔から、「こうすれば幸せになるんだ」という思いが強く、必死に勉強して良い仕事に就き、立派な家庭を持った。それこそが幸せなのだと感じていた彼に、不治の病が襲い掛かる。周囲の者たちは、「病気は治る」と、ありもしないことをイワン・イリイチに日々訴えるが、彼はその嘘を見抜く。
しかし「嘘」とは、イワン・イリイチが自分自身に対してついてきたものだった。自分のやってきたことは果たして正しかったのだろうか。自分の内側に秘めた嘘が彼を苦しめ、精神的にも肉体的にも彼は追い込まれていく。
人は死を目の前にしたとき、どのような思考になり、どのような態度をとるのか。そのあまりにもリアルな描写から、目が離せない。
『灯台守の話』ジャネット・ウィンターソン
著者は孤児として育ち、過去に壮大な苦労をしたことで知られる。
そんな彼女の分身のような、少女シルバーを中心に物語が展開されていく。シルバーは灯台守である老人のピューに引き取られることになるのだが、そこで彼女はピューから、約100年前に壮絶な人生を歩んだ牧師のダークの話を聞くことになる。
その話から彼女は困難に立ち向かっていく術を学び、苦しい人生を乗り越えていく。シルバーはピューにハッピーエンドの物語を要求するが、老人はいつも物語に「エンド」なんてないのだと訴えかける。
人は「物語」を聞くこと、そして話すことによって、他人の人生に干渉でき、救われるのだ。そんな彼らの心温まるストーリーに、あなたはきっと胸を打たれることだろう。
『三人姉妹』チェーホフ
チェーホフはロシアの戯曲家として知られるが、「戯曲」に対して抵抗を持つ方は多いだろう。物語のテーマを見つけるのに苦戦するため、それは当然だといえる。しかしその中でもチェーホフの『三人姉妹』はぜひ読んでいただきたい作品だ。
旅立ちをすることに対して抵抗がある人物が数多く登場する。登場人物のそれぞれが、「過去」に執拗にしがみつき、「未来」へと向かっていく勇気を持っていないのだ。
私たち人間が過去に見た「夢」の中の自分と、今の現実の自分を重ねたときに、明らかに異なっていることは多々あるだろう。だからといって、かつて見た「夢」の自分を執拗に追いかけるのではなく、たとえその繰り返しになったとしても、自分たちの子孫のため、未来の世代のために、未来を繋ぐものとして生きていかねばならない。
私たちはなぜ、今を生きているのか。戯曲に込められたその奥深さを堪能していただきたい。
新潮文庫版には、太宰治が愛し、彼の作品『斜陽』のモチーフにもなった『桜の園』も収録されているので、あわせて読んでみることをおすすめする。
『異邦人』カミュ
新型コロナウイルスが蔓延したこのご時世で、『ペスト』という彼の作品を本屋で見たことがある方も多いのではないだろうか。
そんな彼の一番の代表作は『異邦人』。主人公ムルソーは、一般人とはかけ離れた思考回路で物事を判断し、異常な行動をとる人物。彼は母親が死亡した時でさえ、冷淡な態度をとり、その彼の異常な精神が母親を殺したと言われるほど、異常な人物だ。
友情など様々なものを捨てて彼が求めたのは、「性」への莫大な欲望だった。人間というものが持つ矛盾とは一体何なのだろうか。理性とは何か、欲望とは何か。本作を読むとその核心に迫っていくことができるだろう。
ノーベル賞作家の傑作・『異邦人』と『ペスト』は、何度も繰り返し読むことが求められるため、苦戦する可能性がある。それでもその奥深さに気付いたとき、あなたは驚愕するはずだ。
『車輪の下』ヘルマン・ヘッセ
ヘルマン・ヘッセは数多くのドイツ文学を手掛けた。そんな彼の代表作は多くあるが、その中の一つがこの『車輪の下』である。
たくさん勉強することによって、難関の進学校に合格した少年・ハンスは新たな生活に心を弾ませ、期待に胸を膨らませていたが、待っていた現実はそれとはかけ離れた過酷なものだった。教師には理不尽すぎることを突きつけられ、模範生だったはずのハンスはその状況に絶望し、学校を挫折してしまう…。
タイトルにある、車輪の下とはまさに、車輪の下に押しつぶされそうなほど苦しい彼の精神そのものであった。そんな悲劇に救いの一手はあるのだろうか。
『青い眼がほしい』トニ・モリスン
美や人間の価値は白人の世界にのみ見出され、そこに属さない黒人には、存在意義すら認められない世界の不条理の中、一人の黒人少女・ピコーラは誰よりも青い眼がほしいと祈るのであった。
しかし、彼女の祈りは誰にも届かず、誰もが彼女に無関心だ。白人によって奴隷にされた黒人は、人権を得るために抗わなければいけない。そんな現実が目の前にあるにもかかわらず、その残酷な現実に立ち向かい、本当の問題の解決のために抗うことができる人は、果たしてどれだけいるのだろうか。
差別、貧困、そういった概念は誰の手によって生まれ、誰によって深刻になっていくのか。ノーベル賞作家が届けたかったメッセージとはいかに!?
『グレート・ギャツビー』フィッツジェラルド
ある男の視点から描かれる主人公のギャツビーはいつも偉大であった。
大豪邸に住み、何百人もの人たちを招き、連日のようにパーティーを開く。そんなギャツビーはかつて、一人の女性を心から愛し、その思いはずっと続いているのであった。彼の愛した女性は既婚だが、それでも彼の思いはとどまらない。一途に愛した女性を追い求めるあまり、彼は最後、悲惨な運命に直面することになる…。
あの村上春樹が「人生において最も大切な本」というほどの小説。村上春樹や野崎孝など、様々な人が翻訳しているので、その違いに触れてみるのも面白いだろう。
また、レオナルドディカプリオ主演で実写映画化もされているので、小説に抵抗がある方にはそちらを観ていただきたい。アメリカ黄金期を象徴する名作をぜひご堪能あれ。
『三体』リウ・ツーシン
#2015年ヒューゴー賞長編小説部門
ある日を境に、科学者たちが次々に命を落としていく。
それは絶対に間違いがないと証明された科学に歪みが生まれたからであった。それには巷で話題になった「三体」と呼ばれるゲームと、その作成に携わる団体が深く関連していた。
「三体」のゲームの世界では太陽が3つ存在し、次々に人が死んでいく。そんなゲームの中での世界が現実に存在することが判明した。三体世界との戦争に備えるために、科学者たちは結束し立ち向かっていく。
スティーヴン・スピルバーグが手掛けた『レディープレイヤー1』のような世界観で、SF好きに限らず、誰もがページをめくる手が止まらなくなる長編大作。
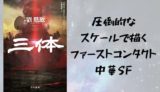 『三体』あらすじと感想【圧倒的なスケールで描くファーストコンタクト中華SF】
『三体』あらすじと感想【圧倒的なスケールで描くファーストコンタクト中華SF】
『アーモンド』ソン・ウォンピョン
アーモンドと呼ばれる「扁桃体」が人より小さく、喜怒哀楽の感情を表現したり、感じたりできない高校生のユンジェ。
感情のない彼は、目の前で通り魔が自分の祖母や母を襲っているのを見ても、何の感情も出さず、ただ黙ってみているだけだった。
彼の母は彼に、「こういう場面ではこういう感情を表現するのだ」ということを一覧で丸暗記させるも、中々うまくはいかない。しかし事故によって感情を教えてくれた母が植物状態に。彼はみんなから「怪物」と呼ばれていたが、ある日もう一人の怪物・ゴニが現れる。ゴニはユンジェとは違い、激しい感情を持つ。ゴニの登場によって物語の展開は加速していき…。
2020年本屋大賞翻訳部門で1位を獲得した作品をお手に取ってみてはいかがだろうか。
おわりに
以上、海外小説のおすすめ12作品を紹介した。
もちろん、すべてがすべて簡単に読み進められる代物ではない。しかし、何度も何度も読んでいくことで、日本の作品より魅力に感じる部分も見つかることだろう。
私たちの発想にもない世界、自分が普段関わることのない世界に、足を踏み入れたことによる優越感は尋常ではない。
この記事を読んだあなたにおすすめ!



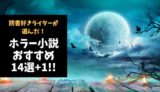
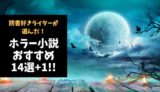
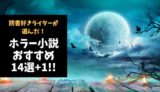




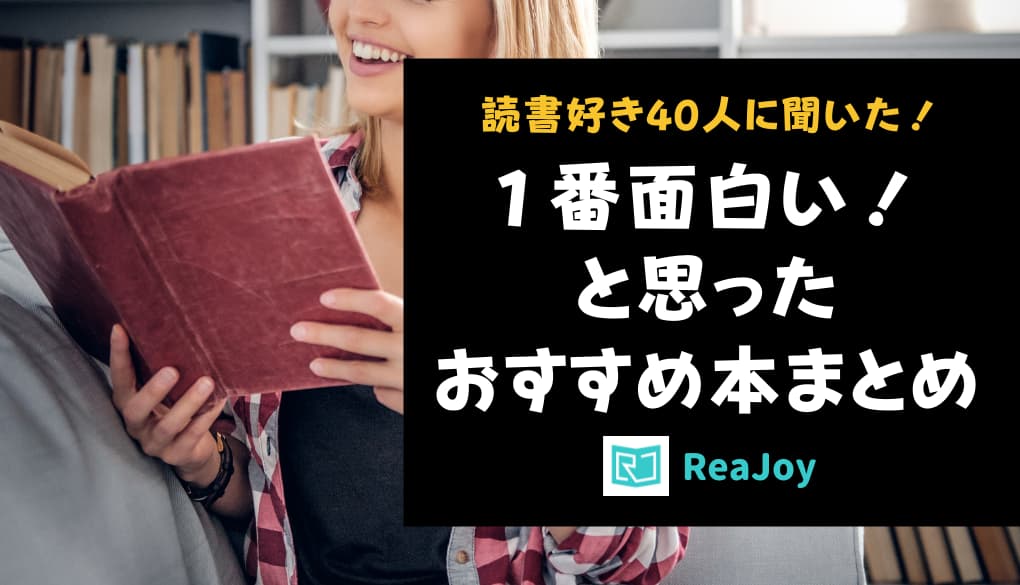
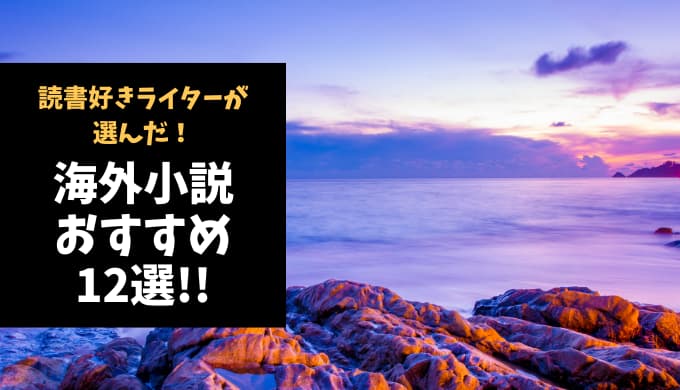
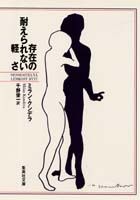
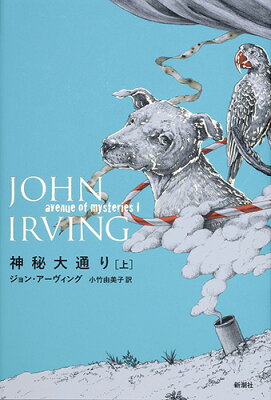


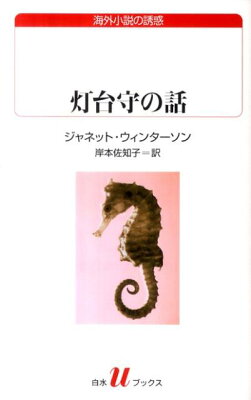

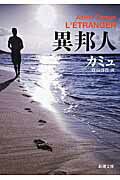
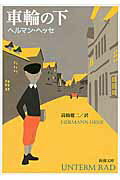
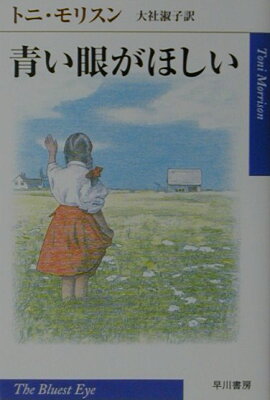
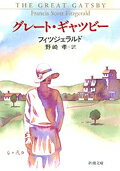


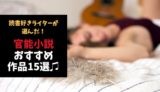
書き手にコメントを届ける