日本人なら誰もが知っている『ゲゲゲの鬼太郎』の作者・水木しげるが妖怪と出会ったのは、近所のお婆さん「のんのんばあ」がきっかけだった。
本書は水木しげるの少年期エッセイであると同時に昭和初期の貴重な記録でもある。
こんな人におすすめ!
- 「のんのんばあ」の妖怪談義を受けたい人
- 昭和初期がどんな時代だったかを知りたい人
- 漫画家そして人間・水木しげるの魅力を知りたい人
あらすじ・内容紹介
『ゲゲゲの鬼太郎』『悪魔くん』『河童の三平』などの作者・水木しげる。
彼が日本の漫画に与えた影響は計り知れない。
漫画を通して妖怪の存在を大衆化したのは、ほとんど水木の功績といっても過言ではなかろう。
日本全国に伝わる妖怪、昔ばなし、伝承。
砂かけばばあ、ダイダラボッチ、牛鬼、あずきあらい、など例を挙げればキリがないが、彼らを可視化させ、名前を聞いただけで「ああ、あの妖怪ね」と分かるのは、水木が作品を通してイメージを作ってくれたからに他ならない。
その水木に妖怪の世界を教えてくれたのが、近所に住む「のんのんばあ」という拝み屋のお婆さんだったのだ。
また彼が過ごした少年時代は、日本が戦争に突入していく昭和初期。
軍人の勇ましさが讃えられ、挙国一致体制が築かれようとしている時代でもあった。
その様な時代、一少年として水木が「どんな少年であり、どんなことを経験してきたか」。
本書はそれらが余すところなく書かれている。
『のんのんばあとオレ』の感想・特徴(ネタバレなし)
のんのんばあと妖怪との出会い
水木しげる、本名、武良茂は、鳥取県境港市に当時としては珍しい大学卒のインテリ文化人の父と、武家の名家育ちの母の間に男兄弟3人の真ん中に生まれた。
幼い頃に自分のことを「しげる」と言っていたものの、周りからは「げげる」にしか聞こえず、いつしか友達から「ゲゲ」と呼ばれるようになった。
そして比較的裕福な「ゲゲ」の家には「のんのんばあ」というお婆さんが時々お手伝いに来ていた。
「のんのん」とは山陰地方の方言で神仏に使える人のこと。
「のんのん」のお婆さんだから「のんのんばあ」である。
彼女が、まだ幼児のゲゲに数多くの日本の妖怪・昔話・伝承をおとぎ話として聞かせてくれたのだ。
晴れた日に雨が降るときには狐の嫁入りが行われている。
お風呂を不潔にしていると妖怪・あかなめがやってきてあかを舐める。
年をとったサザエはサザエオニになる。
誰も居ない寺で鐘が鳴るのは妖怪・野寺坊が鐘を鳴らすから。
廃屋には古いぞうきんのお化け白うねりがいて首に巻き付いてくるから注意すること。
寒くないのに寒気がするときは妖怪・ぶるぶるに取りつかれている。
などなど。
これら魅力的な妖怪話が、ゲゲの心を鷲摑みにし、ここではないどこか不思議な世界へ誘い、漫画家になった時の作品作りに貢献したのは想像に難くないだろう。
水木妖怪の原点ともなる出会いであった。
ガキ大将
この時代は、スマホ、パソコンはもちろんテレビすらない時代。
子ども達は3歳~13歳くらいの近所同士が集まって遊ぶのが普通であった。
特に何もない田舎なら尚更のこと。
そしてその子ども達の間で絶対的な権力を持つのがガキ大将であった。
ガキ大将が気に食わない子供に「相手無し」と宣告すれば、誰も話してはいけないという絶対無二のルールが存在しており、ゲゲも一度ガキ大将の機嫌を損ね「相手無し」をくらい兄からも無視されることがあった。
ただ「権力あるものは義務も果たさなければならない」という暗黙のルールもあり、ガキ大将はいかにグループの皆を楽しく遊ばせるのかという力量も求められていたのだ。
でないと、子どもたちからの支持を失い、その地位から下ろされることもある。
まるで武士や騎士達が幅を利かせた中世社会のようである。
またグループ同士の抗争も、武士や騎士に負けず劣らず凄まじかった。
ゲゲの町は、ゲゲの所属する正やん組、西の忠助組、南のタケヤス組、東の花町組に分かれ、群雄が割拠するまさに戦国時代。
平穏な時は一緒に遊ぶこともあるが、ひとたび戦争となれば大変である。
集団でどつきあう、石を投げ合う、相手を罠で仕留める、捕まった相手に鼻くそとカエルを食わせる等と、ジュネーヴ捕虜条約もビックリのワイルドな遊びに興じていたのである。
今なら日本全国大炎上になりかねない危険な遊びである。
時代は下るが、1980年代にツッパリと呼ばれた中学生や高校生がバイクで走り回りグループごとでケンカしていたのは、この頃の少年たちの遊びと非常に似ている。
ゲゲの世代は、小学生の時にこうした経験を通じて大人になっていったのだ。
落ちこぼれの青年期
「楽しみが多すぎて勉強する時間など無い」と語るゲゲは、ネボスケで遅刻の常習犯。
勉強はしないで遊びまくりだから当然、成績はみるみる下降。
算数は常に0点であったという。
兄と弟は中学へ進学出来たのにゲゲは学力不足で進学できなかったのだ。
ちなみにこの時代は現在のように中学は義務教育ではなく、貧しい家の子どもは小学校卒業と同時に働かされるのもザラであった。
ただ、ゲゲの武良家は比較的裕福で、両親がゲゲに中学進学を望んだにも関わらず、学力不足で進学出来なかったのだ。
にもかかわらず当のゲゲ本人はのんびり屋で「なんとかなるだろ」と朝は寝床でグーグーグーを地でいくタイプ。
卒業後、心配した両親に大阪で仕事を紹介してもらうことになるが、ここからの落ちこぼれぶりも半端ではない。
印刷原版屋に勤めた時は、新聞を読んでる社長の頭をうっかり踏んでクビ。
版画屋では、届け先の住所が分からず配達物をそこらに置いて帰りクビ。
しばらく大阪の父親の下で居候(ニート)。
その後、図案学校へいくが退屈し2年で中退。
その次に50人募集の園芸学校を受験し51人の受験者の中のただ1人の不合格者になる。
今度は美術学校への転入を目論見、工業学校採鉱科へ入学するものの寝てばかり。
と読んでいて、見事なほどに「ダメ人間」のゲゲ。
だがそんな彼にはずば抜けた才能があった。
絵画である。
まだゲゲが高等小学校1年の頃。
父親に買ってもらった油絵道具で油絵を描き続けていたゲゲは、ひょんなことから教頭先生にその絵を絶賛される。
そして「個展を開こう」ということになり、個展を開催。
小さいながらも毎日新聞に「天才少年画家あらわる」の記事が載るほどであった。
ゲゲが大成するのはその何十年も後のことになるが、やはり才能というものは隠せないのであろう。
大器の片鱗を見せていたのだ。
またこの頃、ゲゲは新聞記事で「施設で暮らす絵が上手い知的障害の少年」のことを知る。
しかも年齢はゲゲと同い年。
ゲゲはこの無名の少年に何やら親近感が湧いていたとのことであったが、その少年こそ、放浪の天才画家「山下清」の若き姿であった。
型にはまらない天才は天才を知ると言ったところだろうか。
昭和初期の隠れエピソードである。
その後のゲゲ
水木しげるは妖怪漫画以外にも回顧録や歴史人物の漫画などを数多く描いており、どれも非常に面白い。
特に本書には収録されていなかったが、ゲゲがこの後にたどる運命である「戦争」。
その「戦争の記録」は我々現代人の想像を遥かに超えている。
ゲゲは、太平洋戦争の中でも激戦中の激戦地、生きて帰れないと言われたニューギニアに送られ、戦友たちが米軍の圧倒的な火力の前に容赦なく殺されていくのを目の当たりにする。
まさに地獄であった。
ゲゲが、ガキ大将時代に夢見た勇ましい軍人の姿などはどこにも無かったのである。
本書を含めそういった戦記物も、昭和を語る上で水木しげるが後世に遺してくれた大いなる遺産である。
また一方で「なまけものになりなさい」や「なんとかなる」精神も激動の時代を生き抜いてきた人間ならではの説得力ある言葉だ。
せこせこと目の前の小事に追われ一喜一憂している我々が学べることは数多くあるであろう。
まとめ
漫画家としてレジェンドとなった水木だが、彼が成功するには苦難の連続があり、安定するのは40過ぎという当時としてはずいぶん歳をとってからだった。
そんな苦労を経験してきた水木だからこそ、作品もエッセイも非常に深みのあるものとなっている。
落第生でも生きる道はあるし、気楽にいこう。
戦争に比べれば大したことない。
本書を含め、水木しげる作品は本当に深いので、ぜひ、一読してもらいたい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
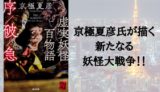 『虚実妖怪百物語 序破急』あらすじと感想【京極夏彦氏が描く、新たなる妖怪大戦争!】
『虚実妖怪百物語 序破急』あらすじと感想【京極夏彦氏が描く、新たなる妖怪大戦争!】



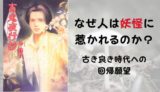
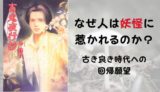
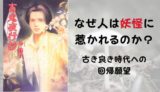

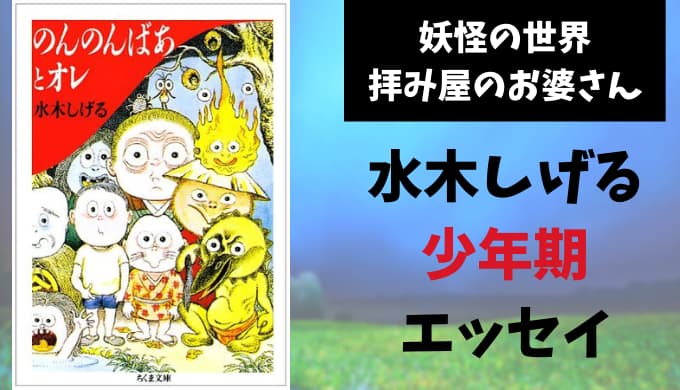

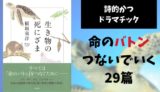

書き手にコメントを届ける