「本格ミステリ」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。
孤島?密室?嵐の山荘?あるいは、颯爽と現れる名探偵?
本格ミステリのギミックをこれでもかと詰め込んだ本書は、まるでミステリの宝石箱だ。
ミステリを愛するがゆえにほとばしる知念実希人の筆の暴れっぷりと、大いなる「本格への挑戦」が楽しめる作品になっている。
目次
こんな人におすすめ!
- 気持ちよく騙されたい人
- 大どんでん返しが好きな人
- 本格ミステリの知識をつけたい人
あらすじ・内容紹介
生命科学の分野で財を成し、ノーベル賞受賞も近いと言われている神津島太郎(こうづしまたろう)。彼から「硝子の塔」へ招待された医師、刑事、霊能力者、小説家、編集者、名探偵の6人は、和気あいあいと会話をしながら神津島の発表を今か今かと待っていたが、神津島は密室で何者かに殺害されてしまう。
刑事の加々見(かがみ)がその場を取り仕切ろうとするが、名探偵・碧月夜(あおいつきよ)が嬉々として捜査に乗り出した。医師・一条遊馬(いちじょうゆうま)をワトソン役とし、月夜は密室の謎を解こうとするところで第2の密室殺人が発生。月夜は遺憾なく名探偵としての能力を発揮していくが、その努力もむなしくまたも密室殺人が起きてしまう。
果たして3つの密室殺人の犯人と巧妙に仕組まれた驚きのトリックとは?知念実希人が描く大胆な本格ミステリ!
『硝子の塔の殺人』の感想・特徴(ネタバレなし)
名探偵という存在は必要か?矛盾を抱える名探偵・碧月夜の苦悩
私たちの住む世界に「名探偵」という人物は存在しない。殺人事件が起きれば解決するのは警察で、探偵自体が事件に介入することはないのだ。
しかし、名探偵コナンやシャーロック・ホームズなど、この世には創作物の中でたくさんの名探偵で溢れかえっている。
彼らは殺人事件や誘拐事件などが起きれば速やかに事件を解決へと導いてくれる、スーパーヒーローのような存在だ。そんな名探偵たちに、苦悩はないのだろうか?
本書で事件解決にあたる名探偵・碧月夜は、最初こそ嬉々として事件の捜査を始め、人が不愉快な気持ちになるのも止めずに聞き込みなどをしまくる。医師・一条遊馬をワトソン役とし、心から楽しそうに。
しかし、刑事である加々見はそれを許さない。なぜなら、殺人事件は現実に起こっているものであり、解決するのは加々見のような警察だからだ。「事件を解決するのは警察である」という、読者と同じ世界の法則にのっとり物語は進んでいく。
それでも月夜は「名探偵」の存在の大切さや重要性を頑なに主張するが、ある瞬間から、自らが課せられている「名探偵」の存在について苦悩するようになる。
「犯行を止めることができず、いたずらに被害者を増やした挙句、犯行がすべて終わったあと、多くの人を集めて得意げに犯人を糾弾する。果たしてそれでいいのだろうか。(…)けれど、前者の方が『名探偵』として認められるんだ。それこそが、私をずっと悩ませていた矛盾だよ」
月夜の苦悩は、名探偵の存在そのものを揺るがすものだ。だいたいの名探偵は事件が起きたあとに登場するし、未然の事件の発生を防ぐよりは起きた事件の解決を依頼されることが多いように感じる。そこに矛盾を感じてしまった月夜は、現在起きている事件の捜査への気力を失ってしまうのだ。
しかし、名探偵には相棒がつきもの。ワトソン役を勤める遊馬は、月夜にこんな言葉を投げかける。
「俺の知っている名探偵たちは、どんな苦境に陥っても、絶対に捜査を放棄することなく犯人を追い詰め続け、そして最後には事件の真相を暴いてきた。(…)君がやるべきことをしよう。本当の姿を取り戻そう」
名探偵の相棒は、その存在を影で支える人物である。遊馬が月夜と出会い、相棒になったのはたまたまだろう。しかし、苦悩を抱えた名探偵をそばで見ているからこそ、遊馬は月夜を奮い立たせられる言葉をかけることができた。
「名探偵」という存在の矛盾は、名探偵自身にもどうすることもできない。だからこそ、名探偵には相棒が必要なのである。そして、その存在の矛盾と戦いながら、事件を解決し続けるのだ。
散りばめられた本格ミステリのうんちく、そして愛
『硝子の塔の殺人』は知念実希人が書いた初の本格ミステリである。島田荘司から始まった新本格ミステリは、綾辻行人を輩出したことにより大いに盛り上がりを見せ、現在でも栄華を極めている。本格ミステリを書きたくて作家になる人も多いのではないだろうか。
本書は本格ミステリの愛があふれんばかりに書かれている。例えば、館の主である神津島太郎が密室で殺害されたことについて、月夜はカーの『密室の講義』というものを引き合いに出して推理する。
「数々の密室ミステリを生み出し、『密室の王者』とさえ呼ばれたジョン・ディクスン・カーが一九三五年に発表した『三つの棺』の第十七章、『密室の講義』は、密室トリックを分類したエッセイとして有名で、その後、様々なミステリで引用されてきています。」
ジョン・ディクスン・カーとは、アガサ・クリスティとともに本格ミステリの黄金期を築いた人物である。密室ものを得意とし、著書『火刑法廷』はミステリ史にさんぜんと輝く作品である。
このように本格ミステリのうんちくがちょこちょこと挟まれており、まったく本格ミステリに触れてこなかった人でも楽しめるようになっている。
筆者が最も感動したうんちくは、「後期クイーン問題」を一文で書ききってしまっている部分だ。「後期クイーン問題」は本格ミステリを好きな人や、実際に本格ミステリを書いている作家が目の当たりにする課題である。
幾人もの人がこの問題を解説してくれているのだが、私はイマイチ理解することができなかった。知らなくても本格ミステリを読むことはできるし、楽しむことはできる。しかし、例えばミステリの評論集や書評集などを読むようになると見かけるのが「後期クイーン問題」という言葉なのだ。
『硝子の塔の殺人』はその問題をたった一文で説明してくれる。
「ミステリ小説において『作中で探偵が最終的に提示した解決が、本当に真の解決であるかどうか、作中では証明できないこと』という問題だよ」
確かに、探偵が「犯人はこの人で、証拠はこれです」と言われてもその証拠が本物かどうか、そしてその証拠をもとに示された真相が本物かどうか、読者には確認しようがない。
ここまで明快に「後期クイーン問題」を解説してくれたミステリを初めて読み、私は心の底から感動してしまった。
本格ミステリそのものを楽しみつつも、ミステリの知識が一緒につく1冊でもあるのだ。
殺人は芸術か?憧れは狂気か?「ミステリ」の存在に狂わされてしまった人々
「それらも一緒です。概要だけ聞くとどれも魅力的な謎に見えますが、解決してみれば二流の犯罪者が起こしたつまらない犯行でしかありませんでした。名探偵としての能力を十分に生かせるような、残酷でありつつ、美しく芸術的な犯罪には、なかなか会えないんです」
名探偵を名乗る月夜は、事件をまるで芸術作品のように扱う。凄惨な殺人事件も、狡猾な誘拐事件も、世間を騒がせた大事件も、月夜にとっては己が名探偵であるための欲を満たすための一つの道具に過ぎない。彼女の言う「二流の犯罪」とは何だろう?何が彼女にとって一流の犯罪なのだろう?
「名探偵が扱うのは複雑で不可思議な事件だけです。警察でも解けないようなミステリアスな難事件」
月夜は難事件を求めている。それはまるで飢えた狼のようだ。そして、何よりも自らが名探偵としてその難事件を解決することに酔っている。
ゆえに、月夜は硝子の塔で起きた事件も嬉々として解決しようと動く。そして、ミステリの知識がない人には解説をまくし立てる。それはまるでミステリというものに狂わされてしまったかのように。
もう一人、ミステリに狂わされてしまった人間がいる。この「硝子の塔」の主人・神津島太郎だ。彼は財力にものを言わして、日本中、世界中のミステリに関わる品々を収集している。そんな彼はこんなことを言っている。
「生命科学での名声など、私にはまったく意味のないものだったんだ。ノーベル賞にも興味ない。ワトソンやクリックではなく、私は綾辻行人になりたかったんだ」
彼はミステリを愛するがあまり、新本格ミステリの旗手とも言っていい実在の人物である、綾辻行人になりたいと言った。
月夜も神津島もある意味ではミステリという存在に狂わされた人なのだ。その狂気が、硝子の塔で爆発してしまったのだろう。
まとめ
著者が愛する本格ミステリがここにあり、読者はそれを心から楽しむことができる。
すべてを読了したとき、ぜひともプロローグに戻ってほしい。
そこに驚きの仕掛けがほどこされているからだ。
知念実希人は最初も最後も手を抜いてないこと分かり、感動を覚えるだろう。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 知念実希人おすすめ小説ランキング15選【読書好き23人に聞いた!】
知念実希人おすすめ小説ランキング15選【読書好き23人に聞いた!】






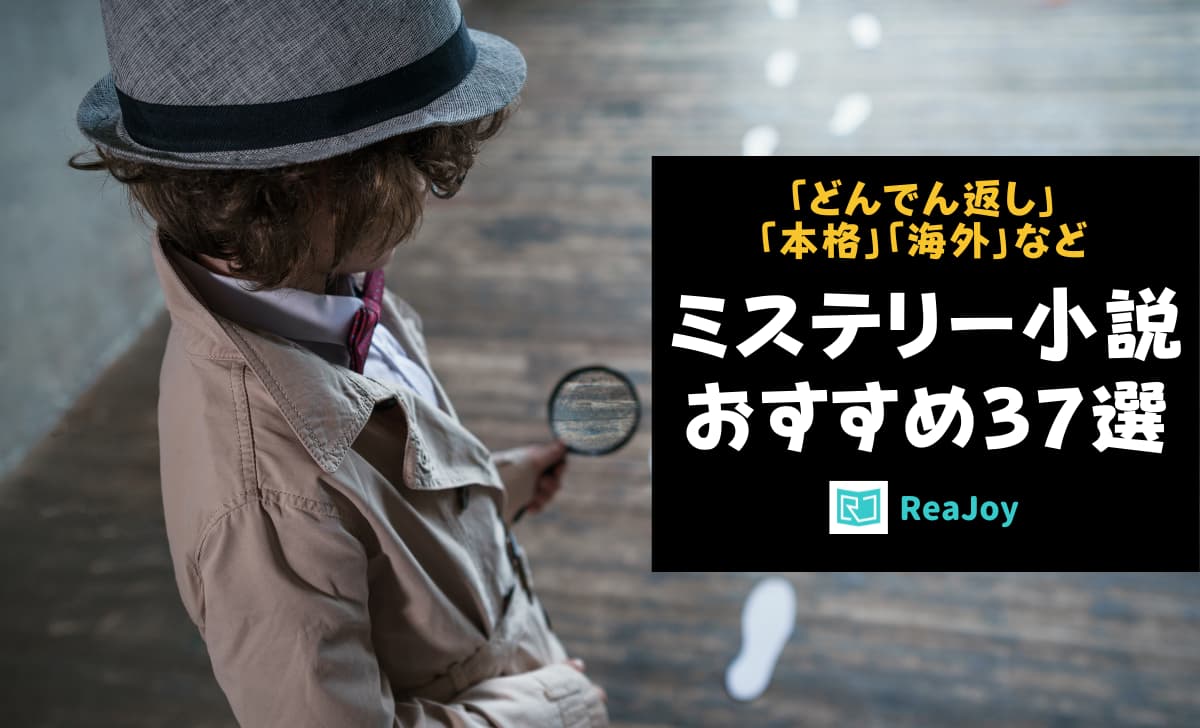


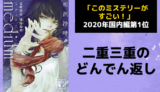
書き手にコメントを届ける