孤独に酔う行為は、無意味なことですか。
陶酔ごと受け入れ、愛してしまえばいいのではないですか。
私は濁った感情に苦しめられながら生きている人を甘えだと、むやみやたらに切り捨てられません。
無力で才能がなく、魅力もない。
そう言って自らを罵っていませんか。
誰のことも信じられなくなる日があっても一向に構わないのです。
弱くてどうしようもない自分ごと、もう一度愛してみませんか。
こんな人におすすめ!
- 本を読む気力がない人
- 気取った言葉が苦手な人
- 何かを失った経験がある人
- 適度な距離感の本が読みたい人
あらすじ・内容紹介
意味の為だけに存在する言葉は、ときどき暴力的に私達を意味付けする。
身勝手に意味付けされた言葉に疑問を抱き、本質を鋭利に言い当て、むきだしの感情を届けることを生業にする現代詩人、最果タヒ。
多種多様な媒体を駆使して伝えられる彼女の言葉は、詩の概念を越え、現代的な芸術作品としても高く評価されている。
今回は死をテーマに、既存の向き合い方とは異なるやり方で切り込む。
すべての「死んでしまいたい」人へ向ける詩集。
『死んでしまう系のぼくらに』の感想・特徴(ネタバレなし)
44編の「死」
本書で扱われている作品は、すべて「死」をモチーフにしたものです。
いうなれば、無数の言葉の骸です。
度重なる失望や、残酷な現実に圧迫されて身動きが取れなくなった悲しみたちです。
死者は星になる。だから君が死んだ時ほど、夜空は美しいのだろうし、僕はそれを少しだけ期待している君が好きです。
死ぬこともあるのだという、その事実がとても好きです。
いつかただの白い骨に。いつかただの白い白い星に。
僕のことをどうか、恨んでください。望遠鏡の詩
誰かの喪失によっていやでも世界が美しく見えるという経験はありませんか?
心に穴が開いて、世界が輝いて見える時はありませんか?
そういう時、私は不意に静かな場所で空を見上げたくなります。
自分以外の誰かが存在しない世界にひとり取り残されたような気分になるのです。
ちょうど、宮沢賢治のよだかの星のよだかが、自己犠牲で青白い星になって夜空を照らすように、『君』は星になることを望んでいます。
人はいつか必ず死ぬ。普遍的な価値観に変わりありません。どの先、ゆく道はみんな一緒です。
どのような人間も分け隔てなく、等しく死んでゆくのです。
そう考えると、孤独に意味があるような気がしてきませんか。
最も、簡単に割りきれないことも、人間が人間でいるために残された感情ですが。
安易に感傷的な気分に浸らせない
才能は死の前では無力なの。
いくら才能に溢れた人であれ、死んでしまえば、その優れた能力が戻ることは二度とありません。
功績を残した偉人であれ、一般の方であれ、例外なく等しい状況に置かれているのです。
死の概念は死神と呼ばれ、諸外国で擬人化されるように、広義的な意味では神と等しい存在です。
日本では閻魔大王やイザナミが近しいものと言えます。
また、生命の尊さや愛情の尊さによって迫害される個人を描いています。
愛する人がいる状況をひっくり返せば、その人以外誰も必要としないことが成り立ちます。
愛する人の前では他者は無力です。
「なんとなく」であれ、きっかけがない限り、見ず知らずの人を愛する気持ちにはならないからです。
代わりがある世界であることを信じていながら、愛を望むのは狡猾なことなのでしょうか。
さみしさの色
かなしくはないけれどさみしい、という感情が、ひとの感情の中で一番透明に近い色をしているということを、知っているのは機械だけで、私は名前を入力しながらなんども肯定の言葉を抽出した
夢の中で死んだ人が生きていることや、愛が存在していること、都合のいい世界は破綻していつだって壊れていくことを音楽みたいに聞いている。きえて
寂しさや悲しみは、人間の感情の中で一番純粋なものです。
心が満たされない状態を示す「寂しい」と、心がしくしく痛みだす「悲しい」気持ちとは、厳密には異なります。
孤独とは、そのような感情を極限まで洗練してゆく過程なのです。
拒絶された世界の中でひとり生きる人に、私たちは生々しい美を感じます。
人間には感情というフィルター(色眼鏡)がありますが、何も通さずにありのままの世界をレンズで視認できる機械なら、感情をより鮮明に認識するのかもしれません。
仮にもし、悲しみに打ちひしがれたまま息絶えたとしても、植物が土に還るのと同じです。
あるべき場所に帰還するのと変わりません。
意識無意識を問わず行われる、原始的な帰巣本能とでも言えば良いのでしょうか。
かつて神道を信仰していた日本では、遺体を土に埋める土葬が一般的でした。
神様や仏様が辿り着いた先と、一生を終えた人が行きつく場所は同じなのかどうかはわかりません。
世界は融通が効かないものであり、いとも簡単に破壊される脆い構築物であることを、私たちは物語を摂取することで把握しています。
わたしをすきなひとが、
わたしに関係のないところで、わたしのことをすきなまんまで、わたし以外のだれかにしあわせにしてもらえたらいいに。わたしのことをすきなまんまで。
遅くでいいから、愛してほしかった。わたしがしんでも、わたしが目の前に永遠にあらわれなくても、愛してほしかった。
夢やうつつ
愛はいらない。寂しくないと拒絶しつつ、一方で愛を求めます。
相反する気持ちを同時に受け入れ、矛盾を表現できるのは人だけです。
自分の死後、誰かに愛してほしい気持ちはまだわかります。
自分がいない世界で、自分を好きな人が、自分を好きだという気持ちを保ったまま、ほかの誰かに幸福にされている姿を見て幸せに繋がるのでしょうか。
一時だけは慰められますが、自分の未練をさらに強めるのではないのでしょうか。
いない自分の代替品として利用される「わたし以外の誰か」にも申し訳ない気がします。
もしそれが望みならば、やや傲慢に受け取られてしまうでしょう。
救済されない自分を永遠に待つことでもあります。
寂しさのなかに自分を埋めて待ち続けるのです。
そうすれば、悲しみは少しずつですが安らいでゆきます。
まとめ
私たちは些細なことですぐに傷つき、自分を責め立ててしまいます。
他人の理不尽な優しさが無価値に思え、訳もわからず涙を流したり、自分以外に誰も助けてくれないと思い込み、話すことをためらい、誰の話にも耳を塞ぎたくなる日もあります。
他人には自分の気持ちはわからないと全てを拒絶して、ひとりきりになりたい日も。
そんな日に手に取りたいですね。
真夜中の冷え切った空気に浸されながら、静かに読むのが良い詩集です。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 『現代詩人探偵』あらすじと感想【詩をめぐる鬱くしいミステリー小説】
『現代詩人探偵』あらすじと感想【詩をめぐる鬱くしいミステリー小説】
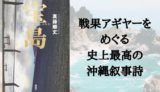
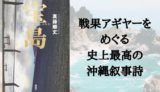
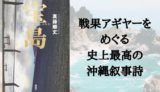
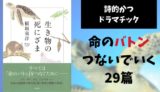
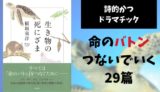
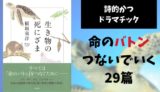
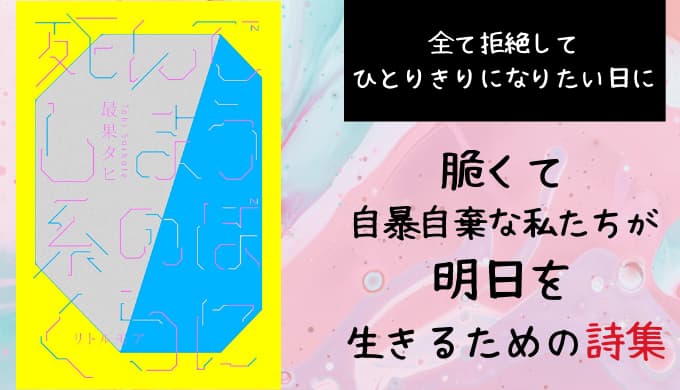

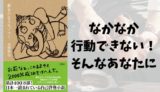
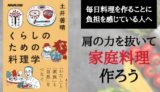
書き手にコメントを届ける