料理とは何か?
この問について改めて考えると難しい。
本書は、料理研究家の土井善晴さんが料理学のさまざまな視点から、料理とはどのような営為なのかについて教えてくれる1冊となっている。
普段料理する人もしない人も、作る・食べるということについて改めて考えることで、料理をより深く知ることが出来るだろう。
こんな人におすすめ!
- 料理が好きな人
- 料理で暮らしを豊かにしたい人
- 毎日料理を作ることに負担を感じている人
あらすじ・内容紹介
「料理」の言葉の意味から始まり、どのように食文化が変化し、現在はどのような家庭料理が日本で必要なのか、その在り方について考えていく。
歴史や倫理観、西洋との違いを知ることで調理法や食べるものの違いを理解し、料理とはただ作るものでも食べるものでもなく、もっと深い、生きることそのものであると知ることが出来る。
そして、昔に比べて忙しい現代人の心に余裕を作るのは一汁一菜であり、一汁一菜こそが家族だけでなく地球や社会に優しいものであると著者は述べる。
本来の家庭料理とは何なのか、今一度考え直す一助となるだろう。
『くらしのための料理学』の感想・特徴(ネタバレなし)
西洋料理は「進化」し、和食は「深化」した
料理の進化について、最初にフランス料理の歴史から詳しく説明されている。
贅沢で濃厚な美味しさを好む美食文化は、経済的な発展とともに人々のライフスタイルが変わることで、軽やかで胃にもたれない料理が考案され進化していった。
その後は「科学的」な加工技術にも目が向けられていく。
ここで私が気になったのが、「進化し続けていくと伝統的なものは消えてしまうのか」ということだ。
料理界の進化は、経済とともにあって実現できるものです。だからこそ、芸術的な料理の世界は、伝統を否定してでも、進化し続けることを使命とするのです
進化し続けていくこともまた大切であるが、土井先生はこうも述べている。
本来、伝統と新しさは別々に評価すべきものです。たとえば音楽においては、クラシック音楽とポップ音楽、電子音楽など、新古に敬意を払い、さまざまなジャンルを立てて区別しています。料理も同様に、クラシックなフランス料理とポップアートのような芸術的な料理は区別しなければならないのです。
フランスには、街のビストロや地方の小さなレストランで昔ながらの伝統的な料理が提供されているそうだ。
芸術的な料理と暮らしの料理の2つの世界観を持っているのがフランス料理であり、西洋の料理界は、より科学的に芸術的に進化しているのである。
それに対し、本書では日本の料理について「深化」したと表現している。
和食とは自然観から生まれる食文化であり何もしないことを最善とするため、和食においての創造性は精神性を深めるところにあると述べられている。
西洋の食文化の豊かさと和食の奥深さの両方に気づかされた
「ケ・ハレ」を意識して肩の力を抜いて家庭料理を作ろう
第二章では、日本における料理観について触れられている。
料理には「日常」と「非日常」があるが、西洋では両者が地続きだそうだ。
例えば、特別な日に食べたローストビーフの残りを普通の日にも食べたりする。
だが、和食では日常と非日常がまったく異なった意味を持っている。
それが、日本人独自が持つ「ケ・ハレ」という概念だ。
「ケ・ハレ」は、一般的に、「ケ(日常)」と「ハレ(非日常)」とを区別するものとして、対立するもののように言われます。しかし、「ケ」は日常というよりも「弔い」を意味するものであって、日常とは「ケ」と「ハレ」の間にあるものです。
ハレの料理で分かりやすいのがお正月に食べるお雑煮だ。
確かに、お正月以外にお雑煮を食べる機会はあまり無い。
これが和食における「日常」と「非日常」の区別であり、日本では縁起やお供えなど「ハレ」の日の料理は綺麗にした特別なものを作る。
そして「ケ」の日の料理だが、日常での一汁三菜の考え方は世界共通であるが、日本にもそれが根付いているために料理が大変、と思う人が多いのだそうだ。
和食には、豆腐などの大豆製品というたんぱく質があるため、メインのお魚やお肉を最初に考えず、まず季節の食材を考え、一汁一菜で十分であると著者は言う。
毎日料理を作る人からすると、これは肩の荷が下りるようなホッとする提案なのではないだろうか。
「ケ・ハレ」を意識して、メリハリのある力を抜いた家庭料理をつくることが大切なのだろう。
料理に含まれる人間の情緒と無限の変化
「利他」という言葉について考えていきたいと思います。利他とは利己の対義語ですね。利他とは、無意識に他人の幸福を願うこと、無意識のうちに自分を犠牲にして他人に利益を与えることです。私は、料理には、利他性がそもそも備わっているのだと考えています。
食べることと生きることは直結しているため、料理には利他性が備わっている。
そのため、料理の中には作る人と食べる人、両者の関わりによってもたらされる人間の情緒のやりとりなどが含まれるのだろう。
和食では、特にそれが重要なようだ。
野菜や果物などのすべてが均質化されてきている世の中では、選ぶ楽しみや選び抜く力、違いを感じ取る力を失う恐れがある。
和食はシンプルであるが故、小さな違いに気づき、一汁一菜というシンプルな家庭料理にすることで、毎日のお味噌汁でも少しずつの違いに無限の変化がある。
家庭料理は私たちに、普段から様々なことを教えてくれているのだ。
まとめ
全てのページに付箋紙を貼りたくなるような素晴らしい視点と考え方に、料理からこんなにも世界が広がるのかと衝撃を受けた。
料理をすることの楽しさやメリハリのつけ方、家庭では料理をする人をリーダーとすること、という考え方も新しく、目からうろこである。
忙しい現代人にとっては、料理の大切さや食べる側の心の重ね方などを教えてくれる教科書になるだろう。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
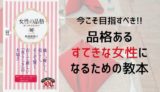 『女性の品格』あらすじと感想【今こそ目指すべき!品格あるすてきな女性になるための教本】
『女性の品格』あらすじと感想【今こそ目指すべき!品格あるすてきな女性になるための教本】






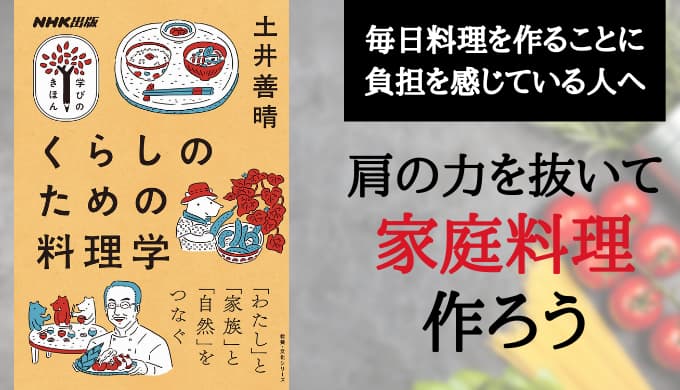

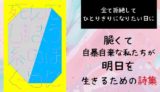
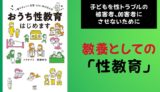
書き手にコメントを届ける