大概の大人はきちんと性教育を受けずに育っている。
そもそも、カリキュラムとしてしっかり学ぶ時間がなかったのだから仕方ないのかもしれない。
けれど、子どもには性教育を教えたい。
『おうち性教育はじめます 一番やさしい!防犯・SEX・命の伝え方』は、様々な性の悩みに答えてくれ、性教育の入り口として、非常に読みやすいマンガである。
子どもに興味がない大人にも、知識教養としてぜひ読んで欲しい一冊だ。
こんな人におすすめ!
- 教育に携わっている人
- 性教育を今一度学び直したい人
- 近くに3歳~10歳の子どもを持つ人
あらすじ・内容紹介
本書は「赤ちゃんはどこから来るの?」といった子どもからの定番の質問から、いつまで一緒にお風呂に入っても大丈夫なのか、子どもが「うんち」や「ちんちん」と公共の場で連呼してしまうなど、様々な悩みに答えてくれるガイドブックである。
最愛の子どもが性的なトラブルの被害者にならぬよう、そして加害者にならないようにするにはどうすべきかも学ぶことができる。
漫画形式で執筆されており、分かりやすく読みやすい。
著者はフクチ マミと村瀬幸浩。
村瀬氏は東京教育大学(現筑波大)を卒業し、私立和光高等学校保健体育科教諭として25年間勤務していた経験を持つ。
その後は一橋大学や津田塾大学等で25年間セクソロジーの講義を担当した実績がある。
村瀬氏の教えを、誰にでも分かりやすくイラスト化しているのがマンガイラストレーターのフクチ マミ氏だ。
難しいことをわかりやすく伝えるコミックエッセイを多数刊行しており、『マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK』などがある。
『おうち性教育はじめます』の感想・特徴(ネタバレなし)
子どもを守るためにまず知って欲しい、教養としての「性教育」
”性教育”と言われると構えてしまう人が多いだろう。
伝えにくいから学校で教えて欲しい、と思う人や、自然な流れで知るだろうからそっとしておこうとする人もいるだろう。
「セックス」は性教育にあるたくさんのテーマのうちの一つであり、ポルノと性教育は全く別のものである。では、本当の性教育とはなんなのか。
本書では、これからの世の中を生きていく人格を育てるのに必須の「教養・知性」だと定義されている。
性教育を教えるのは思春期からだと漠然と思われているが、実は1 歳前後から就学前までの 5~6 歳頃の幼児期がベストとされているそうだ。
思春期の子どもにある日突然性の話をすること自体、かなりハードルが高い。
そのハードルを下げるため、性を身近に感じられるように早めのスタートが良いと本書では綴られている。
しかしながら、筆者を含め、これを読んでいる方の多くは子どもの頃に性を教わっていない。
それは親のせいではなく、日本という国の空気感がそうさせているのだと思う。
教わっていないことを、子どもに教えることはほぼ不可能。そのために改めて学ぶ必要があるのだ。
子どもが3歳~10歳と仮定した時、まず学ぶべきことは「プライベートパーツ」について。
プライベートパーツとは、他人に勝手に触ったり触らせたりしてはいけない場所のことで、「口、胸、性器、尻」がそれに当たる。いずれも命に直接関わる場所だ。
世話や介護で触らなければいけない場合は除いて、親子間でのコミュニケーションとしてお尻を触ったりすることも避け、いわゆる”お尻ペンペン”も避けることが望ましい。
親がプライベートパーツを意識し、線引きをしないと、子どもはプライベートパーツに触ることが「愛情表現」だと勘違いしてしまう可能性もある。
その勘違いは、やがて好きな女子にスカートめくりをしてしまう男子を生み出し、被害者を作ってしまう。
実はズボン下ろし、お医者さんごっこ、カンチョーなども性暴力に分類される。
大人たちは知らず知らずに経験しているため、子どもに対して強く注意しない場合もある。かなり根の深い問題なのだ。
そういった性トラブルに子どもが巻き込まれないためには、「NO、GO、TELL」を日常的に伝えることが重要だと本書では書かれている。
はっきり拒否し(NO)、できるだけ人が多いところに逃げ(GO)、「秘密だよ」と言われても信頼できる大人に話すこと(TELL)だ。
悪意なく触ってくる近所のおばさん、不意に距離感が近くなる先生、いつも公園にいる知ってる人など、本当は嫌だけど我慢してしまう距離感の人にこそ、「NO、GO、TELL」が必要。
空気を読んで、つい我慢しているうちに自分を守るセンサーは少し鈍くなっていってしまう。
男の子に対する性教育の方法。精通があったらどうする?
男の子の体の構造や、射精の仕組みについての解説を挟み、議題は「もし子どもに精通があったら」に移る。
大人は経験の刷り込みで、性器や性を不潔視してしまう人が多い。
その理由には”快楽の後ろめたさ”が根っこに存在している。
そのため子どもを注意する際に「おまた触るとばっちいよ」や「おちんちん触った手は汚いから洗って」と言ってしまうのだ。
この発言が子どもの肯定感を傷つける要因にもなるし、「性器は汚いもの」という意識の押し付けに繋がってしまう。やがて訪れるであろう精通に対し、罪悪感や否定の気持ちを生み出すことにもなる。
大人が子どもの精通に気がついた際は、淡々と事実のみを聞き、淡々と処理法のみを伝えることが求められる。
過剰な肯定や、否定は子どもの感情をかき乱してしまうためだ。
精通が起こるとホルモンの分泌が変化することも頭に入れておきたい。
本書ではその一例としてイライラしたり、人のことが気になったり、疲れやすくなることが挙げられていた。
ここからは子どもとの付き合い方も変わり、多めに見ることや、少し遠くから見守ることが大事になってくる。
”異性とお風呂にいつまで入れるのか問題”にも的確な回答が出されているので紹介したい。
単刀直入に言えば、「年齢に関わらず、体つきに変化が出てきたら」が良いとされている。
性毛が生える、声がわり、胸が膨らみ始めたなどが挙げられる。
体の変化には個人差があるため小1でも小4でもあり得る。
お風呂だけに限らず寝室も別にするべきだそうだ。
この理由について、本書では
体つきが変わってくると子どもではなく、異性として捉えてしまうことがあるからなんだ
これは個人の人格の問題ではなく、「生物的なしくみ」としてそう言えるんだよ
と記されており、衝撃的な見解だった。
子どもは親からの性的な視線を感じると、嫌な気持ちになる。
そして親は他意はなくとも生物的なしくみで異性として認識してしまうことで、親子の信頼に大きく影響を及ぼす可能性がある。
子どもが一緒にお風呂に入りたがっても、親の方から線引きすることで、信頼の崩壊を回避することができるのだ。
一方で、子どもの方も思春期に入れば異性は異性として見えるようになってしまう。
そのため成長によって生まれてしまった距離は健全なものと言える。
それが例え「パパは汚いから一緒に洗濯回さないで」といった悲哀に満ちたものでも、実は成長している証なのだ。
父親必見!女の子に対する性教育の方法
女の子編では月経についての話がメインになる。
体から血が出ることを初めて経験する子どもの戸惑いや恐怖が緩和できるように、本書では”生理が来た時”の対応が父親でも分かりやすいように書かれている。
ナプキン、タンポンの特徴に始まり、捨て方や交換のタイミングなど男性が詳しく知る機会の少ないポイントがまとめられている点は助かる。
例えば以下のものが参考になった。
”経血がついたものは”
お湯で固まる性質があるため水かぬるま湯でつまみ洗いし、その後は普通に洗濯
また時間が経つと取れにくくなってしまうため気づいたら早めに洗うことが重要である。
”お風呂について”
生理中は体が冷えやすいのでシャワーだけで済ますのではなく、湯ぶねでしっかり温まると良い。基本的にはお湯の中では経血は出ないので安心して。
昔は生理中は最後にお風呂に入るようにと言われていたが、デリケートな時期だから最初のお湯に入った方が良いとされている。
そういった具合に生理のアレコレが端的にまとめられている。
プールや体育の時の対応が載っているのも嬉しいポイントだ。
婦人科や産婦人科は何才でも受診できるので、生理で困った時には受診して痛み止めなどを処方してもらうのも一つの手段だということも忘れずにいたい。
また精通、生理、どちらにも言えるが、性別特有の話は同性から伝えた方が、子どもの抵抗は少ない。
そっと席を外すなどして触れてほしくないところにはなるべく触れない。
例え片親の場合でも、信頼できる家族や本、保健室の先生などに頼って欲しいと本書には書かれている。
子どもの有無に関わらず知っておきたい!性を形成する4つの要素とは?
5章には大人が知っておきたい知識として、多様で豊かな性のあり方について述べられている。
基本的な性の考え方として、4つのものが性を形成している。
それが体の性、心の性、性的指向、性(別)役割だ。
まず体の性。
性器は胎児である12~16週頃に男女に分化する。
この時、男性器と女性器がハッキリ分かれず中間の形になることもあるそうだ。
一方で脳は妊娠後半から男脳、女脳に分かれていく。
そのタイミングが異なっているために性器の性と、脳の性にズレが生じる可能性があるのだ。
心の性は自分で認識する性別のことである。
性別は本来、パキッと分かれるものではなく、グラデーションのようになっている。
人によっては、その日その時によって男性だったり女性だったり、どちらとも言えなかったりすることもあるそうだ。
この感覚を知っていると性的マイノリティに対する考え方も変わってくる。
グラデーションのようにバラバラになっているならば、誰もがマイノリティ(少数派)だし、各々の塩梅は簡単に計れないため、という括り方自体が違うのかもしれない。
さらには恋愛感情や性的欲求を感じる相手がどの性別かも人によって異なり、恋愛感情や性的欲求を抱かない(無性愛)もある。
古代ギリシャでは男女とも同性愛が当然視されており、江戸時代にも、同性愛の風習は残っていたという。
そこに性(別)役割が入る。
性(別)役割とは、生まれつき決まっているものでなく、社会や文化を学習し、身につけていくもので、ジェンダーとも言われている。
男らしさ、女らしさの一般的なイメージが、本来グラデーションである性を2極に分断してしまう要因になっている。
日本では物心つく前から「らしさ」を求められてしまう傾向が強い。
そして、気がついた時には「らしくあらねば」と思って苦しんでしまう人も少なくない。
体の形だけではなく、体の性、心の性、性的指向、後天的に身に着ける性の役割が、その人独自の性のあり方を形作っている。
子どもの未来のためにも、偏見や誤解を解消するために勉強していく必要がある。
親は伝えたい意見が、子どもに先入観を植え付ける結果にならないか、今一度考えて欲しい。
まとめ
子どもが性的なトラブルの被害者にならぬよう、そして加害者にならないように大人は最新の知識をインプットし、子どもに伝えなければならない。
各家庭で、学校で性教育がきちんと教えられるようになれば、どんな人も生きやすくなる社会に少しずつだが、変わっていくはずだ。
本書はそのきっかけを与えてくれる大事な本である。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
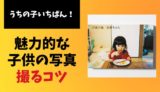 うちの子いちばん!最高に魅力的な子供の写真を撮るコツは?
うちの子いちばん!最高に魅力的な子供の写真を撮るコツは?
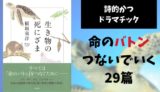
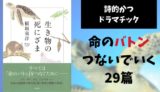
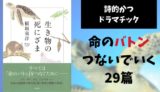
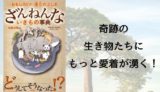
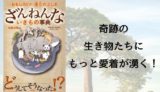
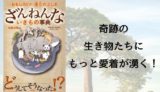
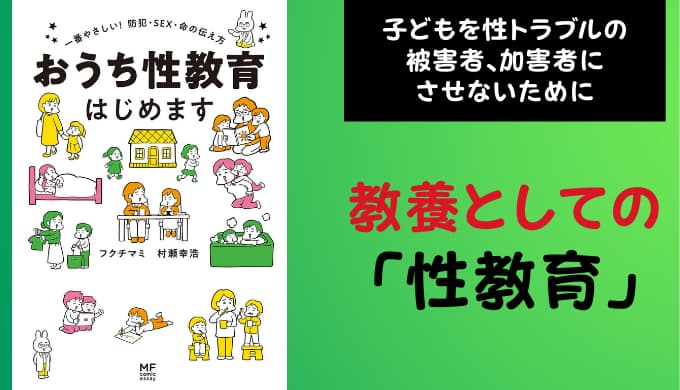

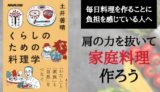
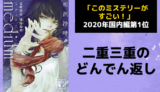
書き手にコメントを届ける