この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。
「何故生きねばならないのだろう。」名だたる偉人たちが一生をかけて答えを探し求め、それでさえただ一つの絶対的な真理は発見されることのないこの問いに、私のような小娘が答えなど出せずに当然なのだと何とかケリをつけてなお、「どう生きるべきなのか」という問いからは依然としてその答えを迫られ続けている。
十年先に何をやっているかを今すぐに決めろというのはずいぶん理不尽な要求だと思って、ぼくは何も決めなかった。社会は早く決めた奴の方を優先するらしかったが、それはしかたのないことだ。ぼくは、とりあえず、迷っている方を選んだ。
主人公「ぼく」のいる状況もさほど変わりはしないだろう。
ただ、「ぼく」の淡々とした語り口からは現状に対する焦りや不安は感じられない。
前途未定である自分自身をおとなしく受け入れている。
人生においてある決断を迫られたとき、それを下すのが人より遅れれば遅れるほどと逃げや甘えという言葉を与えられそうになるものだが、自分という一つの世界をみつめる彼にその言葉はあまり似つかわしくはないように思われる。
これは少し、私自身への弁護も含むかもしれない。
染色工場でアルバイトをする彼は、何かするに値すること、長い生涯を投入すべき対象を探している。
そして、その染色工場で佐々井と出会う。
彼もまたアルバイトを転々とする身であり、見かけは「ぼく」と同じようだ。
しかし「ぼく」には、自分が探しているものを「彼はもう見つけてしまった」という印象を受ける。
少なくとも、彼はぼくと違って、ちゃんと世界の全体を見ているように思われた。大事なのは全体についての真理だ。部分的な真理ならいつでも手に入る。
人が人に出会う。
自分に何かいいものを与えてくれるだろうという期待を抱えて誰かと繋がりを持つことはあるだろうし、それは決して悪いことではない。
しかし、こちらからは特段の意図もなく、不意に誰かと深く接することになったときの心地よさ、高揚感は言葉に尽くせないものだ。
佐々井は「人の手が届かない部分がある」と話すが、人の出会いもそれに違いないだろう。
佐々井からある計画を持ち掛けられた「ぼく」は、「妙な話をすべて歓迎する心境」からそれに協力することになる。
「ぼく」は自分の世界に拘る一方で、外の世界からの何らかの作用が自分の世界を変えてくれるはずだという期待をも持っていたのだろう。
そしてその計画の遂行により、佐々井のおそろしく現実的かつ実務的な顔が現れる。
興味深いのは、「ぼく」が佐々井の「遠方を見る精神」に一種の共感を覚えたのであり、「彼の現実的な面を信頼するのは話が別」とあくまでも冷静に彼を見つめるところだ。
多くの場合、人のある面に好感を抱くとそれがその相手のただ一つの真実のように見える。
それに反する面が覗くと「そんなはずではない。こんな人ではない。」とそれを否定し、自分の信じたい像を押し付けてしまう。
付き合いを続ける上で人は多面的なものだという割り切った前提の認識を持つべきであり、その全ての面を慕うことはあまり重要ではないのかもしれない。
もしかすれば、違うようにみえる二つの顔の奥から何か一つの連続性が伺えることもあるだろうが。
どんなことになってもぼくを巡る世界はぼくを傷つけることができない。そういう自信があった。
話は終始「ぼく」の視点で進む。佐々井のことは「ぼく」が聴いて感じたことからしか分からない。
佐々井は「ぼく」にある効果を与える物語上の一役割を担っているにすぎず、佐々井の視点を考えるのは無意味な気もする。
だが私はふと佐々井の側に立ってみたくなった。
佐々井はなぜ「ぼく」を誘ったのだろう。
「ぼく」が定職に就いていないからだとか、人とのつながりが希薄そうだからだとかそのような穿った推察は的外れに思われる。
二人は自ら自分のことを語りだすまでは互いを深く追求したりはしない。
佐々井にとっても「ぼく」のとる距離感が心地よかったのではないか。
人と人が適度な距離感を保ちながら、じんわりと影響を与え合うことはなんて尊いのだろうと思う。
自分という世界に膜を張ることは、自分を保ち、守るという面で何かと都合がいい。
だがその一方で知らず知らずのうちにその膜の厚みは増し、外の世界の感触に鈍くなることもある。
膜が鎧であるうちはいいが、檻になれば反って我が身を苦しめてしまう。
人は一人では生きていけないなどという啓蒙じみたことを言いたいわけではないが、共感できる他者に求められ、その人生に一瞬でも深く触れることができるというその責任の重みは少し心を柔く温かくする。
到底世間には大っぴらにできないある秘密を打ち明けられても、それは変わらない。
それはやはり自分の世界があってこそなのだけれども。
大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡をつけること、一歩の距離をおいて並び立つ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。たとえば、星をみるとかして。
全てが終ったあと、佐々井は「ぼく」の前から去っていく。
じきに「ぼく」はまた以前の日常に戻っていくだろう。
そして「するに値する何か」を再び探し出すに違いない。
佐々井は、何かを約束したわけでもなければ、全体の真理を教えてくれたわけでもない。
しかし彼は、それらを探し歩き続ける「ぼく」を包む空気を澄んだものに変える術、そのための世界・景色の観方を示していった。
世界は時折、人々が同じ速度で生きることを望むようだ。
その速度についていけないものは群衆が過ぎゆくその背中を眺めることを強いられる。
自分の速度で歩くことを自ら決めてさえも、とうに踏み荒らされ見えない道に傷つけられることもあるだろう。
それでも、空気の澄ませ方を知っていれば呼吸はずっと楽になる。
忘れていけないのは、この世界とは別に、自分という一つの世界がすでにあるということ。
場合によっては、自分という世界は、身近な、けれど遠くにあるものの力を借りて、外の世界よりはるかに大きなものになるということ。
外の世界に飲み込まれることも、押しつぶされことも必要ないのだ。
最後に
ガラスを通して情景を知覚するような文章が静かにつづられ、透き通った言葉がゆっくりと沈み込んでくる。
佐々井も「ぼく」もともに達観しているせいか、読んでいて苦しくなることはない。
気を張ることなく心を委ねて、自分自身に溜まった泥塊を浄化できる。
読了後、あまり知らぬ誰かとできるだけ遠くの話がしてみたくなった。
たとえば、星をみるとかして。
この小説に私が選んだ主題歌
Far Away – Libera ~ 彼方の光 ~
Where-ever I go
Far away and anywhere
Time after time, you always shine
Through dark of night, calling after me私がどこへ行くとしても
遠くどこまでも行くとしても
どんなときも あなたは輝いている
暗い闇夜を抜け 私に呼びかけてくるように
この記事を読んだあなたにおすすめ!
川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』美しい言葉で綴られる心模様。友情、恋愛、人との関わりで揺れ動く姿を描き出す。
 『すべて真夜中の恋人たち』あらすじと感想【こんなにも美しく綺麗な文章に出逢えてよかった】
『すべて真夜中の恋人たち』あらすじと感想【こんなにも美しく綺麗な文章に出逢えてよかった】

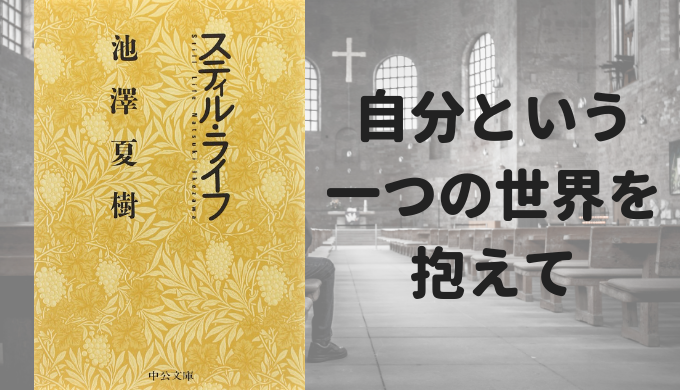

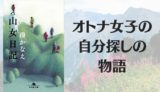

「佐々井」は「ぼく」のもう一つの人格であって、彼等の会話は全て「ぼく」の頭の中の出来事。
私にはそのように思えました。