泣きたくなるほどにあたたかな物語を生み出す、村山早紀さんの作品を読んだことがあるだろうか。
もしまだ手にしたことがないという読者がいたなら、どうかお名前を覚えておいてほしい。
たとえば、眠れない夜や心が傷ついたとき。
優しくてあたたかくて、何か信じられるものに「ふれたい」と願ったときに、きっとあなたをあたためてくれるはずだ。
あらすじ・内容紹介
老舗百貨店にある銀河堂書店で文庫の担当をしている月原一整は、万引きをしようとした少年を追いかけたことをきっかけに、ある不幸な出来事に巻き込まれてしまう。
そんなとき、 小さな町で書店を営んでいる老人に会いにいくことを決意するが、店主から思いがけない申し出を受ける。
やがてある1冊の本をきっかけに、その本を「届けよう」と、さまざまな人がそれぞれの居場所で力を尽くし、応援の輪が広がっていく。
本屋にできることは何なのか、「思いをつなげる」というのはどういうことなのか。
本と本屋への思いがつまった、奇跡のような物語。
『桜風堂ものがたり』の感想(ネタバレ)
銀河堂書店との別れ
一整が長年勤めた銀河堂書店を離れることになってしまった理由は、ある悲しい出来事が原因だった。
万引きの中学生の少年を追いかけた際に、その少年が交通事故に遭い、やがて彼が「いじめが原因で、万引きをさせられていた」という事実が明らかになる。
幸いにも少年は致命的な傷は負わず、彼の両親が書店に丁寧に詫びたこともあって、少年を責める人は少なかった。
かわりにその刃は、銀河堂書店や一整へと向けられたのだ。
「万引きは悪いことだったかもしれない。でも、中学生を、車道に飛び出したくなるほどに追いかけなくてもよかったんじゃないか」
つぶやくひとびとの数が増えていった。
つぶやきはやがて叫びになり、怒号になった。
インターネットを経由して、事故の目撃情報がまとめられ、いろいろな人びとの声が広がっていった。
銀河堂書店に、クレームの電話がかかるようになった。万引きをした子どもを追いかけた店員を責め、入院しているその子に詫びたのかと詰問し、両親が払った本代は返すべきだと罵り、すぐに切るのだった。
店あての電話は、誰がとるかはわからない。みんな受話器をとるのを怖がるようになった。特にアルバイトの学生たちの腰が引けるのがわかるので、電話はそのうち、古株の社員や、店長、副店長がとるようになった。
銀河堂書店にとってはまさに受難の日々であり、「善意の第三者」によって、書店で働くスタッフたちは苦しめられた。
書店へのクレームの電話は鳴り止まず、やがて百貨店の電話も鳴りつづけることになり、一整は自分から店を離れることを決意する。
桜風堂書店との出会い
仕事を辞めたあと体調を崩していた一整は、ある日、不思議な夢を見る。
かつて同じアパートの隣に住んでいた船乗りの老人が「どうした、兄ちゃん。風邪でも引いたか?」と、寝込んでいた際に夢に現れるのだ。
そこまで踏み込んだ話をしてきたことはなかったが、そのときの一整は問われるままに、店を辞めたことと、仕事が見つからないかもしないという不安を打ち明けていた。
すると、老人はこう微笑むのだ。
生きることをあきらめるな。幸せになることを。前に進むことをあきらめたら、人間その場で腐っていくだけだ
やがて、老人はこう続ける。
「なあ、この俺があんたのことを気に入ってたんだからさ、兄ちゃんは幸せになっていいんだよ。あんたを待ってる幸せが、この世のどこかに、お宝みたいに埋まってる。
あんたは優しいいい奴だから、きっと神様がそうしてくれている。そいつを探しに行くんだよ」そいつを探しに行くんだよ。──もう一度、老人は繰り返した。
夢から覚めた一整は不思議と体が軽くなっており、そのとき老人から預かっていたオウムが、こう歌うように鳴いた。
『──サガシニ、イクンダヨ』
そのとき、一整のなかにある思いつきが浮かんだ。
「桜野町に行ってみようかな」
1度も会ったことのないネットでの付き合いのみだった、年長の友人である、桜風堂書店を経営している店主の元へと向かうことになる。
そして訪れた先で、店主から「店が休業していることと、今は病院にいること」を告げられ、丘の上にある病院へ向かうと、桜風堂の店主から、ある話を持ちかけられるのだ。
「ここでひとつ、きみに提案があるのですが」
「はい?」
「うちの店を預かってはくれませんか?」
まぎれもなくありがたい話であるその提案に、また書店で働けるという喜びを感じる一方で迷いもあり、一整は「考えるための時間がほしい」と店主に頼み込む。
すると店主に、「よかったら、今夜はうちに泊まっていきませんか?」と声をかけられ、一整はその夜、桜風堂を訪れることになるのだ。
ここでいよいよ一整が桜風堂書店を訪れることになるのだが、この場面がまた素晴らしいのだ。
店主の老人には透という孫がいて、この孫が出迎えてくれるのだが、桜風堂書店が近づいてくるにつれ、私自身の胸も高まった。
本の匂いがした。
ガラス戸から差し込む光を受けて、星くずのように空気が光って見えるのは、カーテンや床から舞い上がった、ただの埃だ。
閉ざされたままだった書店には、うっすらと埃が積もっていたのに違いない。それを知っていながらも、一整には妖精の羽から散る光の粉を見るような思いで、店を飾る、その小さな光にしばし見とれた。
(ああ、本の匂いだ──)
鼻の奥に染み透るような、針葉樹に似た匂い。かすかに冷たさを感じる、けぶるような静かな匂い。果てしなく懐かしい、その匂い。
この匂いをよく知っている、そう思った。
その紙の匂いが、ページのこちら側にいる私の周りにも広がっていったような気がした。
きっと、この匂いを知っている読者は多いはずだ。
本の森のような、その場所で。
やがてある出来事がきっかけで、一整は桜風堂書店で働く決意を固めることになる。
「誰かの大切な居場所は、守らなきゃいけないんだ」
『四月の魚』
『桜風堂ものがたり』を支える大事な柱となるのが、『四月の魚』という作品の存在だ。
かつて、高視聴率を挙げたドラマのシナリオを何作も手がけ、けれどいまは忘れられた存在になりつつある、ひとりのシナリオライターが書いた、初めての小説。
病を得て、死期を宣告されたひとりの母親と、その家族の、悲しいけれどどこまでも明るいコメディ。軽快なテンポの中で、次々と起こる事件に読者もともに翻弄される物語。
そして、気がつくと、リカコも家族たちも、そして読者も、生きること死ぬことについて、考えさせられている、そんな物語だった。
埋もれていた名作を見つけ出して光を当てることの多い一整は、銀河堂書店の店長から、「宝探しの月原」と呼ばれるほどに信頼されており、この『四月の魚』は一整によって見出だされていた。
だが一整が銀河堂書店を去る決意をしたことで、その意志を引き継ぎ、この作品を「売ろう」と、さまざまな人物が思いを強くする。
かつて勤めていた銀河堂書店の店長をはじめ、同僚であった仲間たちや、一整を見守る人びと。
さらに一整の知らないところでも、手を差し出してくれた人たちがいた。
『四月の魚』という希望にみちた物語をまだ見ぬ読者に届けるために、続々と応援の輪が広がり、それぞれが力を尽くしていく場面で、きっと胸が熱くなるだろう。
桜風堂書店でも『四月の魚』を無事仕掛けられることになるのだが、ここでもまた奇跡のような出来事が起きるのだ。
それがどんな奇跡かは、どうかその目で確かめてほしい。
この『四月の魚』を読んでみたいと願う読者は多いだろうが、かくいう私もその1人だ。
まとめ
『桜風堂ものがたり』という作品は、田舎の小さな本屋と、街の老舗百貨店にある書店、そしてそこで働く書店員と、ある小さな奇跡の物語だ。
少し不思議なエピソードこそあるものの、現実で働く書店員たちの苦悩や現実がそこに描かれている。
ファンタジックでありながら、現実に生きる人びとの思いをそこに乗せ、人の思いがつないだ奇跡の欠片が、いくつも散りばめられている。
たやすく奇跡だなんて言葉で言ってしまいたくない、けれど奇跡としか言いようのない出来事が、そこに描かれているのだ。
それは魔法や不思議な力ではなく、私たちの中にもある奇跡を呼び込む思いの力なのだと信じてやまない。
小さな町の本屋を舞台にしたこの作品は、2017 年、書店員によって選ばれる本屋大賞にノミネートされた。
書店の世界を描いたこの作品が、現場で働く書店員たちにどれだけ「愛されたか」ということが、伝わってくる。
この作品を届けるにあたって、外せないのが空犬太郎さんによる解説である。
何度もくり返し読み返した1文を、どうか紹介させてほしい。
本は言ってしまえば紙を束ねたものでしかないが、書き手や作り手の思いを凝縮することにきわめて長けた容れ物でもある。
この1文に出会った瞬間、心が震えた。
心の底から紙の本を愛し、本屋という場所を愛している人間でなければ、こんな言葉は生まれてこないだろう。
登場人物たちのその後が気になる方は、どうか続編の『星をつなぐ手』を手に取ってみてほしい。
銀河堂書店のある星野百貨店が登場する、『百貨の魔法』に手を伸ばすのもいいだろう。
ページを閉じたそのあとも、登場人物たちの人生に幸せが降り注ぐことを祈りたくなる。
人の思いが起こす奇跡を、信じてみたくなる。
読んだ人間同士で、思いを共有したくなる。
これは、そんな物語だ。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
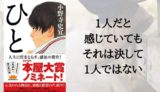 『ひと』小野寺史宜 あらすじと感想【2019本屋大賞ノミネート!今、自分1人きりだと感じているあなたへ】
『ひと』小野寺史宜 あらすじと感想【2019本屋大賞ノミネート!今、自分1人きりだと感じているあなたへ】




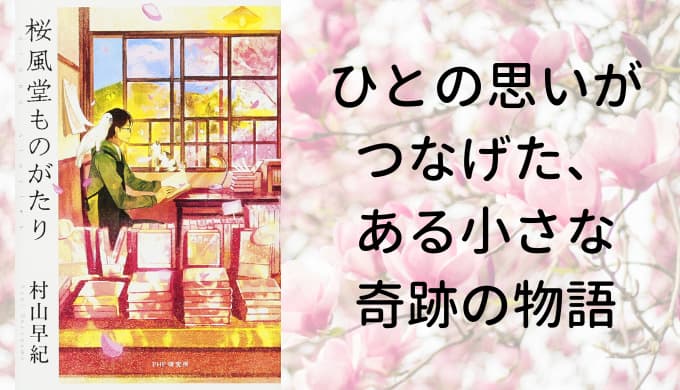


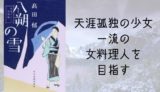
書き手にコメントを届ける