「嘘をつくことはよくない」と、子どもの頃大人に言われた人は多いだろう。
けれど「嘘も方便」という言葉もあるくらいで、誰しも人生において、大なり小なり嘘を口にしてきたのではないだろうか。
真実を伝えることが必ずしもいい結果をもたらさず誰かを傷つけてしまいそうなとき、優しい嘘で誰かを守る人もいるだろう。
これは、「嘘」についての話だ。
嘘が守った、ある家族の物語。
こんな人におすすめ!
- 自分の殻に閉じこもりがち
- 人には言えない苦しみを抱えている
- 家族について、周囲に理解されにくい
あらすじ・内容紹介
「僕」こと羽猫山吹には、おかしな家族がいる。
祖父母に両親、そして2つ年上の姉。
変なのは名字だけではなく、それぞれがちょっと変わった嘘をつくのだ。
山吹には亡くなった青磁という弟がいるのだが、母親は青磁が「この世にいない」という事実を受け止められず心を病んでしまう。
山吹は弟のフリをして母親に手紙を出し続けるのだが、姉はそれを好まずやがて家族から遠ざかっていく。
祖父は思いつきで行動しては失敗し、祖母は嘘を織りまぜて商売をし、父親は家の外に愛人を作り、妻と向き合うのを避けている。
物語は山吹の小学生時代から始まり、家族それぞれの視点で語られていく。
やがて山吹が大人になり、みんなの「嘘」が解かれたとき、本当の家族の姿が見えてくる。
『架空の犬と嘘をつく猫』の感想・特徴(ネタバレなし)
この家にはまともな大人がひとりもいない
この家にはまともな大人がひとりもいない、というのが姉の言いぶんで、山吹もなかばそれに同意する。
まともな大人はいないけれども山吹はまだ八歳だから、その大人たちに頼るしかない。「あの人たちはあてにならん、わたしたちがしっかりせんと」と主張する姉の紅とて、先月十一歳になったばかりなのだ。
羽猫家の家族構成は、祖父母に両親、姉と山吹の6人家族だ。
父親は工務店を経営しており、祖父の代から勤めている腕利きの職人のおかげで何とか存続できている。
祖父の正吾は悪い人間ではないのだが、商才もないのにむやみに新しい商売を始めたがるという厄介な人物だ。
父親の淳吾は女癖が悪く、スナックのような店を営む女のもとに通っている。
母親の雪乃は青磁を失ったことを認められず、自分の世界にこもり現実を見ようとしない。
祖母は商店街の真ん中で小物などを取り扱う店を営んでおり、家族のなかでは比較的まともなのだが、嘘を織り交ぜては商品を売りつけていた。
このように羽猫家の大人はまともとは言えないのだが、そもそも「まともである」ということは、どういうことなのだろう。
どの家庭にも、多かれ少なかれ歪みのようなものは存在する。
「普通」な家族というものが、いったいどのくらい存在するのだろうか。
羽猫家の大人たちは、自らのずるさや弱さや脆さを包み隠さない。
子どもの前で、立派な大人を演じようとはしない。
現実から目をそらし、自分の殻に閉じこもる。
「弱さ」や「ずるさ」をあっさり認めてさらけ出してしまえるのは、「大人であるフリ」をしようとしていないということでもある。
大人としての責任を果たさないと言ってしまえばそうかもしれないが、むしろ「取り繕わない」潔さを感じるのだ。
もちろん子どもに不安を与えている時点で、紅や山吹に負担を背負わせてしまってはいるのだがどうにも憎めない。
羽猫家の面々は、互いに向き合うことから逃げて目を反らしている。
憎しみあったり罵りあったりするのではなく、静かにそっと目を反らす。
互いを見ない代わりに、自分の世界だけを見つめているのだ。
しかし、自分の中にあるのが強固なものかといえばそんなことはなく、否定されればあっさり崩れてしまうような代物だ。
弱いのではなくずるく、そして逃げている。
この怠惰さが、どうにも人間くさくて憎めない。
いずれ逃げられない時が来る
「逃げたいだけ逃げたらいい。いずれ逃げられん時が来る。その時まで力をたくわえとったらいい」
ある意味、「逃げてはいけない」と言われるよりおそろしい気がする。
要するに、逃げた後のおとしまえは自分でつけろよ、ということだと思った。
羽猫家の人間は、紅と祖母以外はほぼ何かと向き合うことから逃げている。
けれど、そんな人は多いのではないだろうか。
たとえば、ダイエットや勉強を「明日からやろう」と棚上げしてみたり。
人間関係においても、家族や友人とすっきりしないとき、きちんと相手とのコミュニケーションを取ろうと向き合える人はどれぐらいいるだろう。
ほんの少しだけ自分自身をごまかすことができてしまえば、その瞬間だけ目を背けてしまえば、人間はいともあっさりずるずるとないがしろにできてしまう。
けれどその目を背ける瞬間、ある種の息苦しさを感じるのではないだろうか。
時間が経てば経つほどに、いつかそのツケを払う日の負担がぐんと増すことを知っているからだ。
何かから「逃げている」という実感があるからこそ、この物語にいい意味で打ちのめされるだろう。
自分自身が目を反らしていた方角の先にあるものを、嫌というほどに突き付けられる。
だが、この作品が「逃げること」を必ずしも否定しているかといえば、決してそんなことはないのだ。
正しくなくてもいい
高校を卒業した山吹はデザイン系の専門学校に入り、家賃や食費を稼ぐためにアルバイトを始める。
そんなときにバイト先のビヤガーデンで出会ったのが、佐藤頼(さとう・より)という同い年の大学生だ。
人見知りをしがちな山吹にとって、他人の悪口を言わない彼女と話す時間は心地よく、それ以降長く関わっていくことになる。
社会人となったあともその関係は続くのだが、ある時、頼に声をかけられ、絵本の読み聞かせのボランティアに付き合うことになる。
そのボランティアに訪れた先で1人の少年がいなくなるという出来事が起きるのだが、そこで山吹がある言葉を少年にかけるのだ。
この言葉は是非本書を読んで確かめてみてほしいが、それを目にした瞬間、「正しくなくてもいいのだ」と許された気がした。
誰もが現実と正しく向き合えるわけではなく、「逃げている」という負い目があればこそ、さらに自分自身を責めてしまう。
そんな人は、多いのではないだろうか。
逃げることや目を反らすことを手放しで賛成するわけでは決してなく、それでいて「逃げざるを得なかった人々」にも追い込むのではなく、自らスッと立たせてくれる。
寺地はるなさんの書くものには、凛とした何かがあるのだ。
心の弱さや脆さやずるさを否定せず、「そこにあるもの」として受けとめ前へと進ませてくれる。
まとめ
誰もがごく当たり前な家庭に育つわけではない。
そもそも「普通の家族」なんてものは存在しない。
家そのものが「帰りたい場所」ではない読者もいるだろう。
「家族なんだから」という言葉は、ときに呪縛となる。
けれどこの物語は、「まともではない家族」そのものを、あるがままに受けとめてくれるのだ。
現実が辛いものでしかなかったときに、そこから目を反らし、自らの殻にこもることを許容してくれる器とともに、ふたたび現実へと立ち向かわせてくれるしなやかさがある。
真面目な人であるほど、現実逃避している自分自身を許せず、責めてしまいがちだ。
そんな人にこそ、この『架空の犬と嘘をつく猫』という作品を手に取ってほしい。
世の中に立ち向かう手段は人それぞれで、そこに優劣も善悪もないのだと信じたい。
どうかこの1冊が、誰かにとって呼吸がしやすい日々への道筋となることを願ってやまない。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
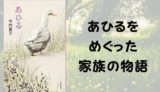
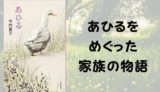
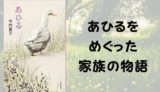
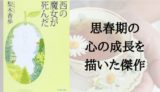
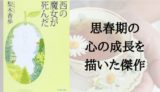
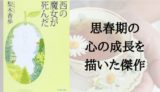

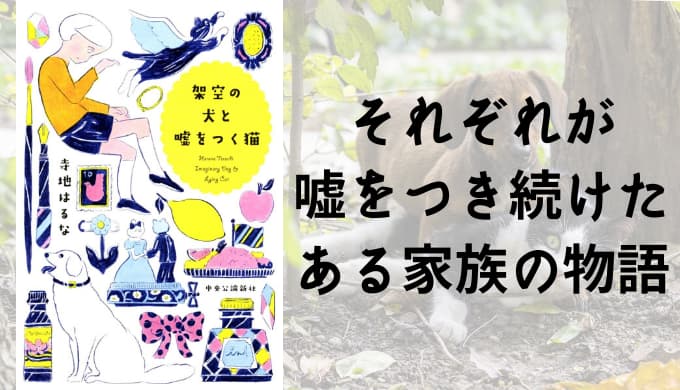


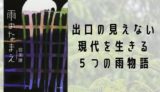
書き手にコメントを届ける