コロナ禍の世界を生きる術はどこにあるのか?
この本に答えはないかもしれない。
でも、きっとあなたの知りたいことが書いてある。
こんな人におすすめ!
- コロナ禍を生き抜きたい人
- 今、読むべき本が読みたい人
- 人々の心の機微が読みたい人
あらすじ・内容紹介
舞台はアルジェリアのオラン市。
医師のリウーは病気の妻を遠地へと送る準備をしていた。
彼は、自身の住むアパートの階段でネズミが死んでいるのを見つける。
管理人に報告するも、管理人のミッシェル氏は「自分が管理するアパートでネズミが出るなんてありえない!」と憤慨するも、死骸を片付けてくれた。
しかし、ネズミの死骸は日々増える一方で、その死骸はリウーのアパートだけではなく、街中で見つかるようになる。
そしてついに、アパートで増え続けるネズミの死骸の処理をしていた管理人のミッシェル氏がリンパ腺腫を発症する。
リウーはその症状と、ネズミの死骸を関連付け、感染症「ペスト」を疑う。
なかなかペストを認めない知事やほかの医師。
しかし、病魔は確実に街へと、人々へと迫っていた……。
『ペスト』の感想・特徴(ネタバレなし)
迫る恐怖にだれも気づかない
「ペスト」とはペスト菌がもたらす病気である。
ペスト菌を持つネズミやノミに噛まれたり、空気中に漂うペスト菌を吸い込んだりしても感染する。
世界では実際に3回にわたって大流行しており(エジプト、ヨーロッパ、インド・中国)、この小説のようにアルジェリアで流行した記録はないので、これは架空のペストの流行物語と言っていいだろう。
ペストについての基礎知識をもう少し話すと、ペストには腺ペスト、肺ペスト、敗血症の3種類の形態がある。
この物語の初期は腺ペストが主である。
腺ペストの症状が門番に最初に現れるのだけれど、かなり辛そうな描写が続く。
病人は半ば寝台に外に乗り出して、片手を腹に、もう一方の手を首のまわりに当ててひどくしゃくり上げながら、薔薇色がかかった液汁を汚物溜めの中に吐いていた。しばらく苦しみ続けたあげく、あえぎあえぎ、門番は床についた。熱は三十九度五分で、頸部のリンパ腺と四肢が腫脹し、脇腹に黒っぽい斑点が二つ広がりかけていた。彼は今では内部の痛みを訴えていた
腺ペストはリンパ節にペスト菌が入ったために起こる。
この描写を読めば簡単にペストが恐ろしい病気だと分かるのだけれど、ペストの流行とはまだ気づかない。
まず、知事は「流行がたしかなものか?」を医師たちに問うのだ。
専門家に教えを乞うというのは今も変わらない風景である。
さらに今も変わらないのは、なかなか「流行している」と決定づけられないことである。
ネズミの死骸が街中からあふれたときに、まずどう行動すればよかったのか。
実は、ここオラン市でペストが流行し始めると、ヨーロッパでのペスト大流行の話題がリウーと別の医師の間で上がるのだ。
なぜそこで「ペスト流行の兆し」と気を付け始めなかったのか。
その理由がもう少し先に書いてある。
ペストの流行が決定づけられると、人々はこう思うのだ。
天災は人間の尺度と一致しない。したがって天災は非現実的なもの、やがて過ぎ去る悪夢だと考えられる
地震も、台風も、山火事も、そして疫病も。
すべては天災である。
いつ起きるか分からない天災に、多くの人が起きてしまったときに右往左往する。
日本は地震、台風大国なので、ある程度備えている人もいるとは思うけれど、だれもが思うのは上記のとおり「やがて過ぎ去る悪夢」ということだ。
やがて過ぎ去る悪夢ということは、再び来るかもしれないということだ。
だれかがペストに罹患しても、それは一時の悪夢であって、まさか自分たちの生活を脅かすものだとだれが考えようか。
ペストがやがて街のロックダウンをもたらし、大切な人との面会も叶わなくなり、手紙さえも出せず、家族の死に立ち会えないなんて、だれが考えようか。
自覚を持つ大切さ
二つの分館病棟から大急ぎでほかの患者たちを移転させ、その窓を密閉し、その周囲に伝染病隔離の遮断線を設けたものである。流行病のほうで自然に終息するようなことがないかぎり、施政当局が考えているぐらいの措置では、とうていそれにうちに勝つことはできないであろう
新型コロナウイルスの大流行でも初期対応の遅さが鮮明に現れたが、当時は今の日本のように医学も政治も発達していないのでなおさらのことである。
病気は勝手に「終息」も「収束」しないのである。
今も「終息」と「収束」をもちろん願ってやまないけれど、そのためには、やはり政府の的確の判断と指示、そして人々の協力が不可欠なのである。
どんなに政府が後れを取り戻そうとも、オラン市の政府が病人を隔離し、社会と病魔を離そうとしても、市民が協力しなければ何にもならないのである。
「自覚」というものがどんなに大切なことか……。
「今は疫病と闘っている」という自覚も持つことが、おそらく早く病気を終息に向かわせることなのではないかと私は思う。
オラン市の人々はロックダウンの中でも出歩き、酒を飲み交わし、大いに街の中に残った市民と交流し続けた。
これが緊急事態宣言中の日本だったら?と想像すると恐ろしい。
ペストが大流行したオラン市も、そして世界中で大流行しているコロナも。
人々の「闘う自覚」で、さらに良くなっていくのではないかと私は希望を持っている。
決して「絶望」に慣れてはいけない
人は簡単に絶望する。
例えばメールの返事がなかなか来なかったり、何かに裏切られたような気分になったり。
どんなときでも、人は簡単に「もうダメだ」と絶望する。
けれど、カミュは言うのだ。
絶望に慣れることは絶望そのものよりもさらに悪いのである
たとえ何かに絶望しても、立ち直ることができればそれはそれでいい。
でも絶望することに慣れてしまったら?
「今日も上司に叱られた」
「今日も恋人からメールが来なかった」
「また人に裏切られた」
毎日の中で絶望することに慣れてしまうと、次に見えてくるはずの希望を感じることができない。
コロナは明日に終息するかもしれないという希望を、「今日も何十人と感染した」という絶望で決して消さないで。
絶望に慣れてはいけない。
オラン市に人々が捨てなかった希望を、我々も持とうではないか。
まとめ
本書をコロナ禍の最中に読むのは正直、間違いだと思うのだ。
3度も大流行し、たくさんの死者を出したペストを疫病が流行する前から「教訓」として読まれるべきなのだ。
それでもなお、パンデミックが起きている最中に読む意味があるとすれば何だろうか?
「次」を失くすためだと思う。
何度も流行させないため、次の死者を出さないため、そして「次の流行はいつ?」と人々に思わせないためだ。
今も闘っている医療関係者がたくさんいる。
ペストが流行してしまったオラン市でも医師リウーを始め、たくさんの人が自分の大切な人と会えなかったり、家族を亡くしたり、友人を失った。
それは現代でも同じ状況なのである。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 『カリギュラ』あらすじと感想【不幸な真理を砕け!】
『カリギュラ』あらすじと感想【不幸な真理を砕け!】
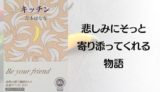
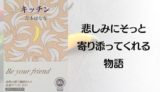
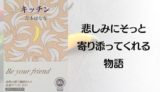
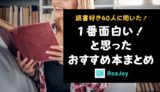
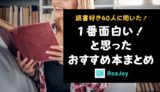
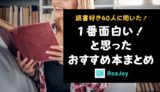

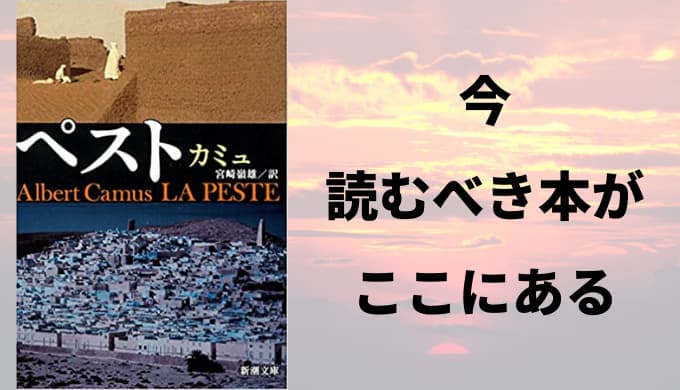
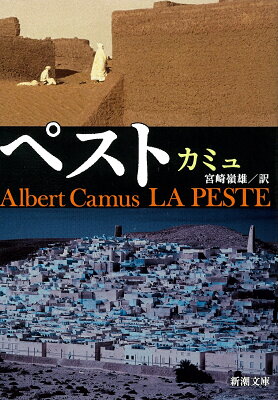
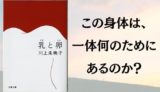
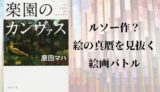
書き手にコメントを届ける