みなさん、こんにちは。
今日は「洗脳」の授業をしていきたいと思います。
「この人を洗脳できたらなあ」と思うことはあっても、いざやろうと思うと中々難しいですよね。
でも大丈夫、ゆっくり学んでいきましょう。
SF名作『一九八四年』から洗脳のポイントを学ぼう!
教科書を開いてください。
『一九八四年』は、ジョージ・オーウェルさんが書いたSFの名作です。
舞台は、「オセアニア」というイギリスが主体となってできた「イギリス社会主義党」(通称イングソック)が支配する独裁国家。
みなが国家への忠誠を尽くさざるをえない環境の中、役人ウィンストン・スミスが密かに革命を起こそうと画策する夢と希望に溢れたお話です。
ポイント1:愛すべき象徴を作り上げよう!
イングソック党のトップは、「ビッグブラザー」という口髭をはやしたイカツイ見た目のおじさんです。
その顔はポスターに描かれ「ビッグブラザーはあなたを見ている」というキャッチフレーズと共に国中に貼られています。
ここでのポイントは、国や党といった「組織を象徴する人物」を用意するということです。
オンラインサロンや宗教、ゆるキャラを押し出す企業サービス。
漠然としたものより、人やキャラクターの方が愛着を抱きやすいですよね?
もしあなたの運営するサークルや会社、国家に対して愛情を抱かせたいと思うなら、まずは1人のカリスマを全面に押し出しましょう!
ポイント2:自分自身を騙すように仕向けよう!
教科書の最重要キーワードとも言えるのが、相反する2つのことを同時に信じる離れ技「二重思考」です。
「教祖様は完全無欠なお人だ!間違えるはずがない」と信じつつ、「人は誰しも過ちを犯します」という教祖の優しい言葉を信じること。
「このゆるキャラ、ピュアで可愛い!」と、その魅力を信じつつ、「企業による顧客獲得のための営業マン」という客観的側面も忘れないでいること。
それが「二重思考」です。
打ち消し合う二つの意見を同時に奉じ、その二つが矛盾することを知りながら、両方とも正しいと信ずること
ここ、テストに出ます。
オセアニアでも、
民主主義は存在し得ないと信じつつ、党は民主主義の守護者であると信ずること
などの多くの「二重思考」が要求されます。
では「二重思考」に陥らせるために必要なものはなんでしょう?
それは「徹底的な監視」です。
ポイント3:間違いはすぐに見つけて正してあげよう!
間違った考え方をしている人がいても、放っておけばすぐに洗脳は溶けてしまいます。
教祖について「あの人、間違いだらけだよね」などと教団内で口走ろうものなら、すぐに居場所はなくなるでしょう。
そんな人がいないか普段からしっかり聞き耳を立てて、見つけたら優しくしつこく諭してあげましょう。
オセアニアの場合、街中に「テレスクリーン」という監視用液晶パネルが設置されており、党に対する否定的な言動が見られたら「思考警察」が飛んできて世界から消されてしまいます。
この徹底的な監視があるからこそ、歪んだ現実を信じざるを得なくなり二重思考に慣れてくるのです。
ポイント4:無知のままでいてもらおう!
洗脳にかかりやすくしたり解けないよう維持するために必要なのが、賢くさせないこと。
そもそも「労働組合」とか「転職」とか「人権」などという概念を知っているから、洗脳が解けやすくなってしまうんです。
そういった考えを学ばないよう、なるべく意識が低いままでいてもらいましょう。
企業であれば、社員による上層部の預かりしれないワークショップや勉強会を禁止するのがよいでしょう。
なおオセアニアの場合、「ニュースピーク」という新しい言語すら作ろうとしています。
「自由」「正義」「道徳」「国際協調主義」などの語彙は削られ、文法も単純化し、言葉の元々の意味がわかりにくいよう略称が多用されました。
「国家社会主義ドイツ労働者党」も「ナチ」と略され、掲げられた理念が意識されにくい状態になっていますよね?
ポイント5:憎き敵を仕立てあげよう!
敵の敵は味方。
内政が上手くいかないとき、敵国に国民の意識を向けて不満を逸らすのは、古今東西使われてきた政治の常套手段です。
イングソック党も他国との戦争が起きているように見せかけて、国民の怒りをそちらに向け続けます。
これにより「国は私達のために頑張って戦ってくれているんだ!生活が貧しくても我慢しよう」と不遇も受け入れてくれるようになります。
また、お役所では、役人たちが敵国の軍隊映像を映す巨大なスクリーンにひたすら罵詈雑言を浴びせまくる「二分間憎悪」という狂気のイベントすらあります。
これぐらいやれば、効果はてきめんでしょう。
まとめ:勇気を出してやってみよう
今日の授業はここまでとなります。
どうでしたか?
なんだかやれそうな気がしませんか?
きっとみなさんの中にも素敵な素質が眠っています。
はじめるなら今ですよ。
Let’s 洗脳!
この記事を読んだあなたにおすすめ!
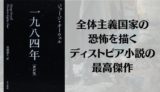 『一九八四年』あらすじと感想【全体主義国家の恐怖を描くディストピア小説の最高傑作】
『一九八四年』あらすじと感想【全体主義国家の恐怖を描くディストピア小説の最高傑作】
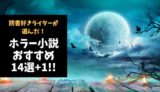
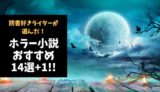
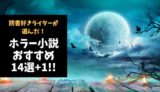



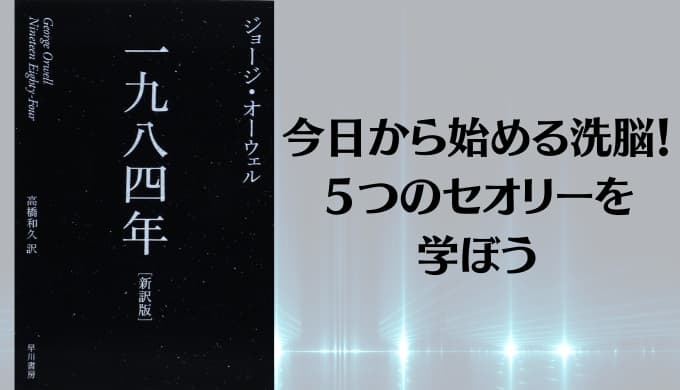

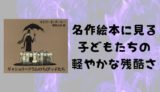

書き手にコメントを届ける