『母影』と書いて「おもかげ」と読ませることからも分かるように、この小説は非常にトリッキーである。
読む人を選ぶ内容だし、ひらがなばかりで読み難いという人もいるだろう。
そういう点においては、かなり挑戦的とも言える。
子どもの視点から見た母との関係が唯一無二というありきたりな表現しか出来なくなってしまうほど、独特な角度で切り取られている尾崎世界観初の純文学作品。
目次
こんな人におすすめ!
- 現実主義者な人
- 言葉遊びが好きな人
- クリープハイプに興味がない人
あらすじ・内容紹介
主人公の少女は小学校でも友だちをつくれず、上手く馴染めずにいた。
学校に居場所のない少女は母親の勤めるマッサージ店の片隅に身を寄せていた。
母にマッサージしてもらいに来る客は何故か「ある?」と尋ね、いつも何かを探している。
それが見つかると嫌な音がして客の苦しそうな声が聞こえてくる。
まだ習ってなくて書けないけど読むことは出来る漢字みたいに、カーテンを1枚隔てた向こう側で母が何をやっているのか、書けないけど読めた。
そんな母と至って平穏な日常を重ねていくなかで、お金持ちの女子や同じクラスの男子と関わり合うことで、少しずつ母親以外の人間とも混ざりあっていく。
ある日、学校で家族のことを作文に書く宿題が出される。
くっついたり離れたりして少しずつ母を知っていく少女が作文に書くこととは?
『母影』の感想・特徴(ネタバレなし)
『母影』誕生秘話〜バンド結成10周年と新型コロナウイルスの流行〜
エッセイやインタビュー集など、これまでコンスタントに作品を出してきた尾崎世界観。
本作はデビュー作『祐介』以来、4年半ぶりの小説にして、初の純文学作品になっている。
今回は『新潮』に載せてもらうという明確な目標の元で執筆されたが、結果的にその目標を超えて、第164回(2021年下半期)芥川龍之介賞の候補作に選書され、大きく注目を集めた。
バンド・クリープハイプのフロントマンとして音楽活動も行っているが、昨年は新型コロナの影響で活動がストップ。
バンド結成10周年を記念して幕張メッセでのワンマンライブを含むアニバーサリーツアーが予定されていたが、ほぼ全公演で中止を余儀なくされた。
この悔しさを音楽で晴らそうとすると、つくる曲自体がコロナに感染するような気がして、ひたすら小説を書いていました。(尾崎世界観インタビューより抜粋)
という思いを背負って誕生したのが『母影』だ。
惹き込まれる表現技法
この小説に強く惹かれる理由の1つに、その表現方法にある。
子ども目線で描かれているため、習っていない難しい漢字は全てひらがなに開かれているのが視覚的にも返って新鮮だ。
不思議、独特、奇妙、どんな言葉で例えるのが適切か形容し難いが、どうしたらこんな表現が思いつくのかと、ただただ圧倒される。
それが上っ面だけの言い換えだけでなく、ダブルミーニングになっていたり、ブラックジョークを混じえていたりと、言葉の軸が太く、読んでいてゾクゾクする。
‘ガソリンスタンドのお兄さんは、いつも大きな声を出しておこってる。でも、まじめな顔で車のためを思っておこってるのがちゃんとわかるから好きだ。お兄さんに怒られると、くるまはいつもスピードを落としてゆっくりになった。だから、はんせいしてるのがじゅうぶん伝わってきた。
お母さんに向かってあなたはおくれてるっていった。そんなに早口でしゃべったら、だれだってついていけないのに。(中略)
家に帰るまでのお母さんは速くて、私はついていくのが大変だった。さっき先生におくれてるって言われたのを気にしているのかもしれない。
言葉通りに受けとってしまう子どもの無邪気さが見事に描かれている。
大人と子ども、視点の違いによって生じたズレがアンプのような役割を果たしてコミカルなものはよりコミカルに、グロテスクなものはよりグロテスクに増幅されて伝わってくる。
1つになれない者たち
少女は非常に不器用な性格な上に、人生経験の乏しい子どもだ。
大したことない小石でもちゃんと躓き、些細な出来事は予想以上に大きな話になってしまう。
大人であれば、人と関わる時には本音と建前を使い分けるものだが、少女は純粋故にそれがない。
素直さが裏目に出てしまっている。
ビー玉を水槽のなかに入れて傾けると低い方へと転がっていく。
やがては壁に当たり、重力に従ってさらに低い場所に滑っていく。
出口のないところでビー玉はゴツゴツと壁にぶつかる。
少女のどこにも居場所がない窮屈さ、息苦しさからはそんな景色が脳裏に浮かぶ。
少女から見た母は絶対的な存在として描かれているが、世間から見た母は”足りない”、あるいは異物として認識されてしまっている。
娘と世間の温度差にうら寂しさのようなものを感じさせられた。
それを知らずに頼る子ども、そうだと分かっていて利用する教育者。
弱者と強者の間にある壁を感じ、しかもそれが壊せないという現実にやるせなくなる。
かなり乱暴で極端な言い方をすれば、発達が遅れているから稼げない、稼げないから人に言えないことをしなければいけない、言えないことをしているからビクビクしながら生活することになり、最終的に娘も巻き込まれる。
弱者は連鎖的にどんどん弱くなっていく一方で、そこから這い上がるのはあまりにも難しい。
また『母影』からは、弱者と強者の壁だけでなく、大人と子どもの間にある大きな溝の存在も伝わってきた。
大人は子どもの延長線だが、成長の過程で忘れた感情や捨てた価値観が浮き彫りになっている。
ガチャガチャを前にして少女が空のカプセルが欲しいと言ったことだって、少女は本心で言ったのに、大人からするとそれは遠慮で、むしろ可愛げの無い行為になってしまう。
男子の手遊びも、大人の視点で見れば育ちの悪さを感じさせてしまう悪癖だが、子どもたちからしれてみれば、限られた範囲のなかで生まれたエンターテインメントだ。
双方の考え方によって生まれる差違が、子どもを理解してあげられない大人、大人の考えが分からない子どもの分断をより強固なものにする。
書かれてないけど読める”大人の事情”
同じクラスのお金持ち女子は、グループで主人公の少女を目の敵にしていたが、授業参観では恥ずかしい思いをしてしまう。
親近感のようなものを感じた少女は接点を持とうとする。
冒頭にある“書けないけど読める”が『母影』を象徴づけるキャッチコピーのようになっている。
明確には書かれていないが、金持ちの女子と主人公の少女にはある共通点があることが読んでいて何となく分かる。
2人はお互いに何の共通点があるのか知らないのであろう。
主人公、クラスの子ども達は知らない、読者だけが大人の事情で隠された“本当“に気付く。
そして、辟易する。
隔たりが繋げた母と娘の絆
不格好で不器用な展開が続くなかで、母と娘が織りなす、常夜灯のようなほんのりとした光を感じる不思議な光景に安らぐ。
彼女とその母が親子としての思いが通じ合える空間にはカーテンが一枚隔てられている。
そのため表情や動作を直接読み取ることはできない。
それでも通じる彼女たちに心を動かされた。
他の人と違っても、歪でも、そしてシルエットでしかお互いが良く見えなくても、少女にとって、この隔たりも含めて、母との繋がりであり、ひとつの家族の形として刻まれていく。
カーテン越しで母は言えなかった(正確には出せなかった)感情を吐露し、母親像が砕け散った母を、娘が優しく受け止める。
まるで子どもと母親の役割が入れ替わったようなユーモアを感じさせつつ、和やかな柔らかさがあった。
娘は母の優しさをダイレクトに触れ、それにようやく気付くことで強張りが解けていき、子どもらしい子どもに戻っていく。
隔たりを介して、お互いの心が裸の状態で繋がる。
一度失った感情を取り戻すことは、元々なかったものを手に入れるよりも難しい。
他者と交わり、ぶつかっていきながら、あるべきところに戻ってくる少女の姿に、喜びのようなものが込み上げてくる。
まとめ
子ども目線で書かれた表現が秀逸と書いたが、無修正で生々しい、エゲつない現実を“こども目線”というある意味シュールなフィルターでモザイク処理を施し、見てはいけない部分をぼかした演出に思えてくる。
生々しさを軽減させると同時に、そのモザイクの存在感が異様な雰囲気を醸し出している。
普段見ているものが全く違う見え方をしている子ども目線の表現が堪らない名文の向こう側では無修正の現実が怪物のようにガバッと口を開けてこちらを覗く。
グロテスクな現実が垣間見えるからこそ、少女と母のちょっとした重なりに温かさや希望を感じた。
全体的に不気味な雰囲気が漂っているが、足元に花が咲いているのを見つけたような小さな喜びも共存している、この世界をデフォルメ化したような小説だった。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
【2023年】最高に面白いおすすめ小説ランキング80選!ジャンル別で紹介
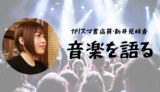
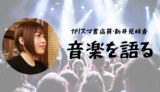
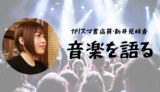
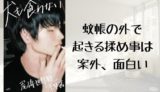
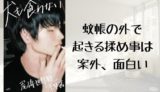
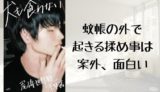

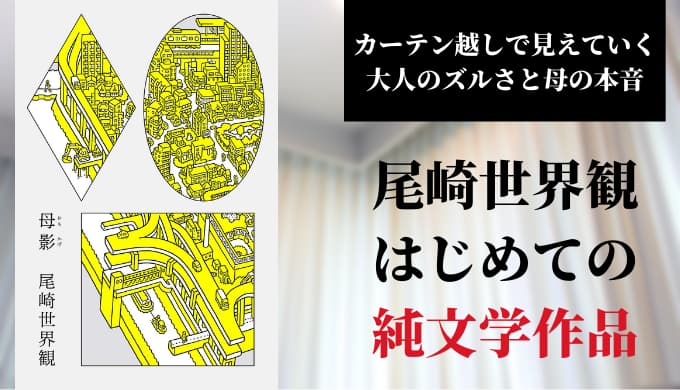



書き手にコメントを届ける