子どもの頃、大人は絶対に偉い存在なのだと思っていた。
それが、「大人も間違えるのだ」ということを知ったのは、いったいいつからだろう。
この物語には、「大人である」というだけで子どもを追い込む、ある教師が登場する。
だがそれを、子ども達がある言葉を唱えながら自らの力で乗り越えるのだ。
それが、どんな言葉なのか。
ぜひ、この『逆ソクラテス』の中で出会ってみてほしい。
目次
こんな人におすすめ!
- 爽快感のある物語が読みたい
- 小中学生の子どもたちや学生たち
- 初めて伊坂幸太郎の作品を読む人
あらすじ・内容紹介
登場人物達の多くは、まだ小学生の子ども達。
一番手の『逆ソクラテス』は、先入観のある教師・久留米の価値観を打ちのめそうと、転校生の安斎が中心になり、主人公達と教師に立ち向かう痛快な物語だ。
続いて、『スロウではない』。
運動ができることが何よりも最優先である小学生時代に、あまり運動が得意ではない少年達と、彼らの前に現れた転校生の少女を描いた瑞々しい作品である。
授業の妨害をする少年のいるクラスの生徒と、それを受け持つ教師の物語の『非オプティマス』。
高校時代に、忘れがたいバスケットボールの試合の思い出がある青年達のその後を描いた『アンスポーツマンライク』。
学校を休んだクラスメイトが、血の繋がっていない父親に虐待されているのではないかと疑い、事実を探ろうとする少年達の『逆ワシントン』。
表題作である『逆ソクラテス』をはじめ、どの作品にも学校や教室や部活動の中を通して出会うリアルに、少年少女が果敢に立ち向かっていく痛快かつ爽快感あふれる短編集である。
伊坂幸太郎『逆ソクラテス』の感想・特徴(ネタバレなし)
先入観に立ち向かう少年少女達の清々しさ
『逆ソクラテス』の主人公の加賀は、小学六年生の男子生徒だ。
ある日、転校生としてやってきた安斎にある作戦を持ちかけられる。
それは、担任の久留米の「先入観を崩してやろうよ」というものだった。
担任の久留米は体格も良く顔立ちは俳優のように整っており、どこか独特の威厳があった。
だが彼が不用意な発言をしたことで、望まないあだ名をつけられた草壁という男子生徒がいた。
草壁は「クサ子ちゃん」とからかわれるようになり、それを安斎がとがめ、それに対してからかった生徒の土田が反論する場面がある。
「だいたい、最初に先生が言ったんだよ。三年の時に久留米先生が」土田が口を尖らせる。
その時のことは僕も覚えていた。久留米は上級生の担任だったのだけれど、たまたま全校の集まりがあった時に、薄いピンクのセーターを着ていた草壁に向かって、「おまえは女子みたいな服を着ているな」と言ったのだ。からかうのではなく、教科書を読むような言い方で、周りの同級生たちはいっせいに笑った。
久留米という教師が、どんな人物かが伺えるエピソードだ。
だがその話を聞いた安斎はこう返すのだ。
「ああ」安斎はそこで事情を察したかのような声を出した。「久留米先生は、そういうところがあるよね」
「そういうところって何だよ」土田は興奮した。
「いろんなことを決めつける」
さらに安斎は、「ピンクの服を着たからって、女だとは思わないよ」と続けるのだ。
久留米は何かと草壁を見下した態度を取ることが多く、それを覆そうと安斎は作戦を練っていく。
転校生の安斎に加賀に草壁、それにさらに佐久間という成績優秀な女生徒が加わり、担任の教師の先入観を叩きのめすのだ。
この『逆ソクラテス』という短編の中で最も読者の印象に残るのは、安斎の「僕は、そうは、思わない」というセリフだろう。
誰かに何かを否定された時、大切なものを見下された時、おそらく大多数の人間が頭に血が上るか逆に真っ白になってしまい、気の利いたことを言い返すのは厳しいだろう。
だが、この魔法のような言葉を、どうか覚えておいてほしいのだ。
「僕は、そうは、思わない」
たったこれだけの言葉が、きっとあなたを守ってくれるはずだ。
理不尽さにどう立ち向かうか。担任久保のスピーチ
授業中にわざと缶ペンケースを落とし授業を妨害する騎士人(ないと)。
それをまともに注意もしない担任の久保。
それを苦々しく思う主人公の将太。
転校生で痩せており、いつも同じ服を着ているため騎士人にからかわれている保井福生(やすい ふくお)。
これが、『非オプティマス』の主な登場人物達だ。
騎士人の父親は有名な企業に勤めており、騎士人は何人も取り巻きを従えて好き放題にしていた。
授業の妨害ばかりする騎士人に対して、福生は「ちょっと、騎士人を痛い目に遭わせよう」と持ちかける。
とはいっても暴力を振るうわけではなく、夜に駅前のゲームセンターで遊んでいる騎士人達をビデオで撮影し弱味を握ろうとするというもの。
だが、いざ撮影しようとなって、「子どもだけで学区外に行ってはいけない」「決められた時間の後に、外で遊んではいけない」という決まりを破っているのは、自分達もなのだと気づいてしまう。
そこへ警察官が現れ、「あわや」という時に助けてくれたのは、担任の久保だった。
久保と別れた後、将太たちの前にある若い女性が現れる。
どうやら先ほどのやり取りを目にしていたらしく、「君たち、久保君の教え子?」と訊ねてきた。
そして、将太たちは久保の知らなかった姿を目にする。
授業参観日の日、ふたたび騎士人たちは缶ペンケースを落として授業の妨害をする。
だが、久保はこう言うのだ。
「音が鳴ると、授業ができなくなるだろ。缶ペンケースは落ちにくいところに置き直しておくんだ」
それまでと違いはっきりとした注意の仕方だったが、ふたたび別の机から缶ペンケースの落ちた音がした。
授業参観に来ている親たちはざわつき、「もっと厳しく指導してもいいんじゃないか」と口を募らせる。
それに対して、久保は授業を中断してある話をするのだ。
ここから続くスピーチを、生徒だけではなく親の立場にいる人はもちろんのこと、ありとあらゆる世代の人間に目にしてほしい。
人によって態度を変えたり誰かを馬鹿にするということが、どれだけ愚かなことかが身に沁みるだろう。
そして、周囲にそんな理不尽な人間がいる読者にとって、この上なく胸のすく最高の瞬間が待っているだろう。
いじめにあった時にどうするか?絶対に忘れるな、反撃の日は必ずやって来る
この短編集のトリを飾るのが、『逆ワシントン』という作品だ。
主人公の少年・謙介は、学校を休んだクラスメイトの靖にプリントを渡すために家を訪れる。
すると、平日にも関わらず出てきたのは髪の毛を少し茶色くした若い男だった。
靖の両親は離婚しており、二年前に靖の母親は再婚したらしいのだが、靖の父親はどうしてか謙介達と靖を会わせようとしない。
やがて、靖に大きな痣が出来ていたことがわかり、「新たな父親に、靖が虐待されているのではないか」という疑いが持ち上がるという、ちょっとしたミステリー要素のある作品だ。
物語は意外な結末を見せ、その顛末は清々しいものなのだが、この短編の中でもっとも読者の心に残るのは、主人公の謙介の母親が、かつていじめについて語ったあるエピソードだろう。
謙介の姉が、小学五年生の時のことだ。
書写の手伝いのために学校にいた母親は、偶然ある女生徒がいじめを受けていることに気づく。
そして、「いじめられています、って人はいる?」と声を張り上げるのだ。
加害者、つまりいじめている側とおぼしき女子が、「突然、何を変なこと言ってるんですか?」と茶化すように声を上げるのだが、母親は尚も話をつづける。
その中で、こんな例え話を持ち出すのだ。
もしかしたら、大人になって大怪我して、担ぎ込まれた救急病院の担当医が、昔、自分がいじめていた相手だったら、どうする?
謙介の母親は、そう話すことでクラスの子ども達に意識づけを行った。
いじめをしている奴がいたらそいつのことを覚えておけ。今はつらくても、いつか反撃できるはず、と。
そして仮に、自分が誰かをいじめたら、ほかのみんなが覚えているぞ。
将来、自分が成功や幸せをつかむ時に、過去の振る舞いが襲いかかってくるかもしれない。
いや、きっとそうなる、と植え付けたかったのだろう。
「いじめはよくない」と、大人は口にする。
だが、大人の世界にもいじめは存在する。
通りいっぺんの綺麗事よりも、なんて心に響くのだろう。
想像力や、心の中で何をどう思い、考える力だけは誰にも奪えない。
どうかこの言葉を、小中学生や高校生達に届けたいと願ってしまうのだ。
まとめ
小学生の頃に出会いたかった。
『逆ソクラテス』を読んで真っ先にそう思った。
小学生や中学生、あるいは高校生。
学校という理不尽な枠組みの中で息苦しい思いをしている全ての子どもたちに、痛快かつ爽快な気持ちを呼び起こしてくれるだろう。
あるいは、日々の中で鬱屈を抱えている全ての世代に清涼な風を届けてくれるだろう。
現実に、理不尽なことはいくらでもある。
誤解されたり先入観を持たれたり、「そうではない」と心の中で歯噛みする日々を送っている人は多いだろう。
固定観念を覆し先入観を打ち砕くこの物語は、その中でもがき苦しむさまざまな人の現実にカウンターパンチをくらわせてくれるだろう。
「僕は、そうは、思わない」
この言葉を、繰り返しお守りのようにして人生に向かっていきたい。
そう、多くの読者に思わせてくれるだろう。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
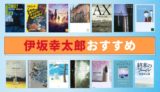 【2023年】伊坂幸太郎おすすめ小説ランキング28選【読書好きが選んだ!】
【2023年】伊坂幸太郎おすすめ小説ランキング28選【読書好きが選んだ!】







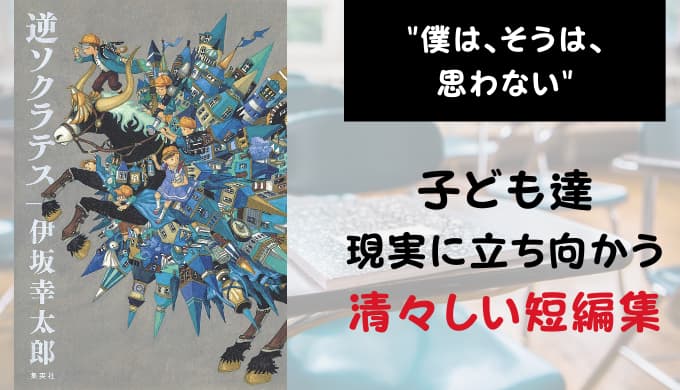
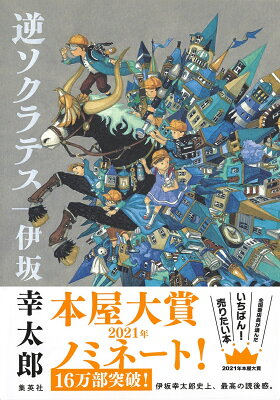
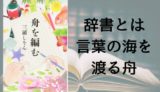
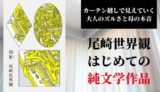
書き手にコメントを届ける