ただ旅をする。歩みを進める。
一歩ずつ、一歩ずつ。ただひたすらに。
止まることは許されないのだ。
そして、きっとこの旅には終わりはないのだ。
目次
こんな人におすすめ!
- 普通のSFに飽きてしまった人
- SF色が強くないSFが読みたい人
- 「真面目な」筒井康隆が読みたい人
あらすじ・内容紹介
北から南へ、南へ旅するラゴス。
ムルダムの一族に加えてもらい、初めてスカシウマやミドリウシと寝起きし、その一族の忘れられない女性と出会う。
自分の理想と顔を描いてくれる男、壁を抜けられる男、巨大な卵を産む鳥が存在するたまごの町、銀鉱の奴隷になりながらも、古代の宇宙船の残骸が残る街へとたどり着く。
二度も奴隷として身を落としつつも、ひたすらにラゴスは旅を続ける。
彼の旅の目的はいったいなんなのか?
彼がこの旅に求めるものはいったいなんなのだろうか。
一旦は本懐を遂げつつも、ラゴスは再び旅に出ることを決意する。
日本のSFの御三家の1人が描くこの世界は、人類の過去なのか、未来なのか。
現代を生きる私たちが失ったものを取り戻す旅を、さあ始めよう。
『旅のラゴス』の感想・特徴(ネタバレなし)
親切設計一切なし。急に世界へ放り出される読者
小説というのは、ある程度舞台設定や、世界観の説明があったりする。
例えば「魔法が今も息づく……国では、」と言われれば「あぁ、この世界は魔法が存在していて、ということ魔法使いや魔女がいるんだな」と、たった数行の文章で読む本の世界を把握し、そこから派生して想像を巡らすことができる。
がしかし、この筒井作品にはそんな親切設計が一切ない。
冒頭で説明がないのはまだ理解できるが、いくらページをめくっても主人公・ラゴスの旅をする世界の説明がないのだ。
ひとまず、ここは現代の世界ではないんだなと認識して読み進める。
しかし、この一文で世界観が一気に崩れる。
食後のマテ茶を飲みがてら食事中からずっと続けていた旅の話のついでにおれがウンバロの噂をすると、トリド家の人びとの顔色がたちまち暗くなった。
何が世界観を崩したかというと、「マテ茶」だ。
「マテ茶」をご存じだろうか。
現実にも存在する、南米のお茶である。
つまりここは、ラゴスが旅する世界は、私たちが住む世界と同じということだ。
思えば、読み始めから読者はラゴスが旅する世界へ放り出されてしまうのだ。
もちろん、なんの装備も持たされずにだ。
まるで身一つでモンスターと戦え!と言われてるようなものだ。
正直、不安しかない。
道行く人に説明を求めようにも、てんで言葉が通じない。
しかし、ラゴスはどんどん旅を続けていくので、頑張ってついていくしかない。
そして途中で気づくのだ。
放り出された世界でも、なんとか生きていけることに。
筒井康隆はあえてなんの説明も加えてないことで、読者にもラゴスが経験する同様のサバイバルを味わわせようとしているのだ。
どこからか御年80を超えた日本のSFの大家の高笑いが聞こえてきそうである。
「どうだ?ラゴスと旅するこの世界は?」と。
発展か、衰退か
文明の利器は獲得しつつあるそれら得難い形質の消失につながるのではないだろうか
電気の実験を中断したラゴスが思ったことである。
現代は文明の利器にあふれ返っている。
テレビ、スマホ、エアコン、洗濯機、新幹線、飛行機。
ありとあらゆる文明の利器は、それだけ私たち人間が発展した証である。
けれど、ラゴスは人々に電気を与えることをためらい、やめてしまった。
それがまさに上記の理由からだ。
ガラケーからスマホへと移行したとき、確かに便利になった。
ナビの代わりもしてくれるし、もっと手軽にコミュニケーションを取れるようになった。
私自身もご多分に洩れず、その恩恵を受けている人間の1人だ。
けれどその分、スマホ自体の寿命はがくんと短くなった。
たくさんのことができるようになったぶん、バッテリーの消耗が激しいためだ。
「人とどこにいても連絡が取れる」という便利さだけで開発された文明の利器が、スマホになり「得難い形質の消失」につながってしまったのである。
ラゴスは人々に電気を与えてしまった、そのあとのこと、その先のことを予想していた。
人々がなまける原因になってしまうかもしれない、漏電が原因で火事になってしまうかもしれない。
あらゆる文明の利器は、その後のことを考えて作られていない。
過不足なく人々に幸せをもたらすものと考えられている。
だいたいのものが、きっと人間を幸せにする。それは間違いない。
でも筒井康隆が言わせたラゴスの言葉は、あまりにも文明の利器に頼り過ぎている私たちへの警告にも取れる。
「得難い形質の消失につながるのではないだろうか」とラゴスが言った時点で、私たちは気づかないといけないのだ。
たくさんのものが形を変えて、たくさんのものを私たちにもたらしてくれた。
でもそれと同時に、失っているものも多い(精神的余裕とか)。
ラゴスの言葉を読んで、「あれ?」と思ったときには実はもう、遅いかもしれない。
やりたいことがある人へ。「やりたい」ではなく「やろう」へ
あなたには現在、やりたいことがあるだろうか?
そして、やりたいことがある人は、それをやれているだろうか?
在宅勤務など、仕事の仕方が変わり、ある程度時間に余裕が生まれてきた人もいるであろうこのご時世。
新しくいろんなことにチャレンジしている人もいるかもしれない。
やりたいことがあって、やりたいことがやれている人は幸せだ。
ラゴスは南へ、南へ旅をしている。
その目的はなかなか明かされない。
けれど、ラゴスにはやりたいことがあることが明白なのだ。
きれいな女性に出会っても、奴隷として身を落としても、ある程度幸福な生活を手に入れても、ラゴスは旅をずっと続けている。
やりたいことをこんなにも目的意識を持って進める人は、なかなかいない。
やりたいことがあっても、例えばその規模に尻込みしてしまったり、経済的な理由だったり、弊害になるものはたくさんある。
そう、私たちの前には、現代を生きる人たちの前には、壁がいくつもある。
だれかが背中を押してくれたら。
だれかが一言「やってみたら」と言ってくれたら。
そんなあなたに、このラゴスの言葉を贈ろう。
人間にはただその一生のうち、自分に最も適していて最もやりたいことに可能限りの時間を充てさえすればそれでいい筈だ。
人生は長いようで、短い。
これがやりたい、あれがやりたいと思っているうちに、あっという間に年老いてしまう。
「やりたい」ではなくて「やろう」でありたい。
ラゴスの言葉のように、私たちは可能な限り、やりたいことに時間を使うべきなのだ。
たとえそれが難しいことだとしても、ただ「生きている」のではなく、目的意識を持って、ラゴスの旅のように続けていきたい。
気づいたら、やりたいことをやり続けて歳を取っていきたい。
自分の人生をやりたいことをやり続けていくことで、満たしていきたい。
人生のすべてを、ラゴスが続けていった旅のように、最後まで命をまっとうする人生を送っていきたい。
まとめ
ファンタジー小説だと冒険のようなものが割とある。
ただ、普通の冒険のようにハラハラすることもドキドキすることもあまりない。
平坦に感じる物語でもあるのかもしれない。
けれど、あぁ、そうか、と思い直す。
これは本当はSF小説なんだ。
宇宙人も出てこない、光線銃も出てこない、宇宙の「う」の字すら登場しないけれど、不思議で、ちょっと切ない、それでいて壮大な旅するSF小説だった。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
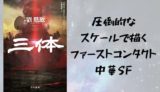 『三体』あらすじと感想【圧倒的なスケールで描くファーストコンタクト中華SF】
『三体』あらすじと感想【圧倒的なスケールで描くファーストコンタクト中華SF】
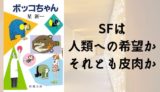
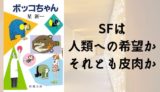
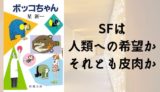



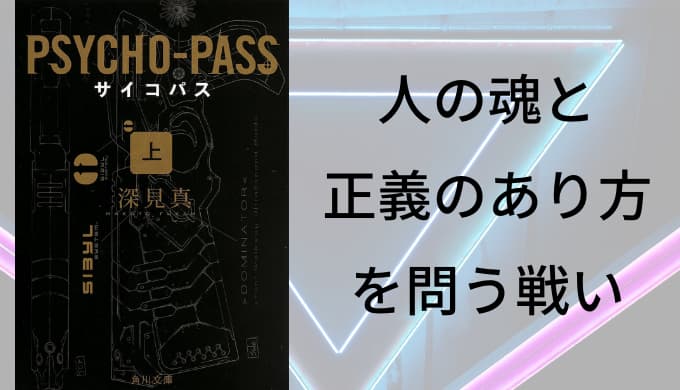
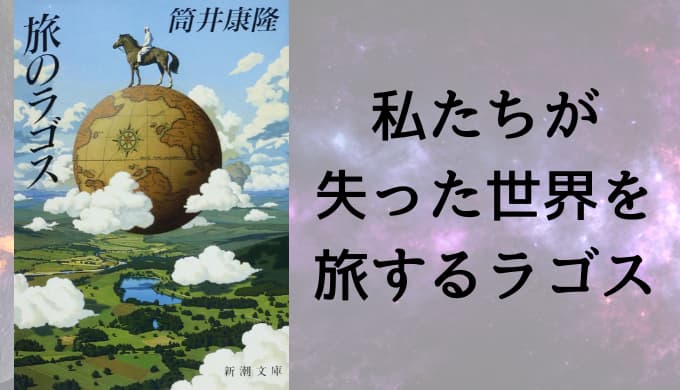


書き手にコメントを届ける