科学の進歩により「火星のテラフォーミング」が近い将来、実現可能とささやかれるようになった現在。
もし火星に先住の「火星人」がいたらどのような物語が紡がれるのだろうか?
これはSF作家レイ・ブラッドベリによる、美しく儚い火星と地球の未来の物語。
こんな人におすすめ!
- 歴史とSFの親和性を感じたい方
- 詩・文学的要素のあるSFを読みたい方
- ブラッドベリ作品をおさえておきたい方
あらすじ・内容紹介
1999年1月、人類初の火星調査隊が地球より出発した。
だが火星には火星人が文明を築いており、数千年以上平和に暮らしていたのだ。
地球からの調査隊をテレパシーによりキャッチした火星人たちは、自分達の滅びの運命を知ってしまい、さらにその原因が「地球人」にあることも知ってしまう。
地球人を憎悪する火星人たちは、繰り返しやってくる地球人を撃退していく。
一方の地球側は、これまでの第一次、第二次、第三次調査隊が火星人により全滅させられたことを知り、武装した第四次調査隊を編成。
火星に乗り込む。
だが火星に着いた彼ら調査隊が見たものは、誰も居なくなった火星人の廃墟であった。
そう、火星人は先遣の地球人が持ち込んだ「水疱瘡」で絶滅していたのだ。
その後、主のいなくなった火星に地球人が続々と入植してく。
入植地球人は、先住者であった火星人の精神と道徳には興味を示さず、地球、とアメリカの生活を火星に持ち込み、廃墟の上に地球様式の都市を建設していった。
まるで火星人の存在など無かったように、子ども達は、火星人の骨を木琴代わりに遊びながら・・・。
一方、故郷地球では「大規模核戦争」のカウントダウンが始まろうとしていた…
『火星年代記』の感想・特徴(ネタバレなし)
26の短編からなる謎解き構成
本書は、時系列で進む26の短編から成り立っており、それぞれ違う主人公で物語が進んでいく。
一つの話は短いもので1ページ、長い話でも30ページほどでまさに短編集ともいえる構成。
各話の主人公に直接的な繋がりは無く、それぞれ独立した物語になっており、一話だけでは全体像はつかめない。
だが、それら短編を読み進むにつれて、火星、地球、火星人、地球人に何が起きたのかが分かっていくという、謎解きの要素もある非常に面白い構成となっているのだ。
例えば、第2話「イラ」は2030年2月の火星で暮らす火星人夫婦の話である。
これから起こる破滅を予知してしまい涙が止まらなくなってしまう火星人の女性イラと、イラの夫が慰める台詞‘あしたになればよくなる’が何ともせつない。
第6話「第三探検隊」は2031年4月の火星を調査する16人の探検隊の話である。
探検隊員達は火星に降り立ったものの、そこは1930年代のイリノイ州の田舎町そっくりであった。
驚きを隠せない隊員たち。
さらに驚くことに彼らは既に亡くなった父母や家族と再会し、喜びに打ち震える。
しかし、それは・・・
第13話「火の玉」は、2033年、11月の地球からはじまる。
ペレグリン神父は、続々と火星に移住をはじめる地球人達を見て、
われらは、われら自身の罪を、この地上で解決すべきではないのか。古い罪はここに残して、火星で新しい罪をみつけるのか?
とつぶやき、自身も火星に行き自らの信仰の道を歩んでいく。
第22話「地球を見守るひとたち」は2036年11月の火星。
人々は火星の空に浮かぶ地球を眺めながら、通信を受ける。
原爆の爆発によりオーストラリアは粉砕され、ロサンゼルス、ロンドンは爆撃され戦争が勃発した
舞台は火星でありながら、登場人物はどこにでもいそうな普通の人たちである。
だからこそ読み進めていくうちに、彼らの運命が分かっていき悲しさが増していくのだ。
SF小説というより、SF純文学かもしれない
1950年に出版された本書は、1920年生まれの作家レイ・ブラッドベリによって書かれた。
他のブラッドベリ作品で有名なのは、「本の所持」が一切許されない偽ユートピアを描いた『華氏451度』が挙げられるであろう。
『華氏451度』はSFの定番「管理された社会に反旗を翻す主人公」の物語であり、主人公が一人であるから感情移入もし易い。
一方の『火星年代記』は特定の主人公がおらず、断片的な物語であるため、感情移入はしずらいかもしれない。
しかし、一つ一つの話がそれぞれ個性的であるため、深夜に観るショートムービーのような心地よい酔いに誘ってくれるだろう。
SF小説だが、「詩」のような短編も多いため、海外純文学を読んでいる感覚にもなれる。
日常、文明、精神、信仰、破滅と数多くのテーマがところどころにちりばめられているのもまた魅力の一つである。
本書はSF小説というより、SF純文学かもしれない。
小見出し
また、この『火星年代記』。
アメリカの歴史と比較して読んでみると、「アメリカ人作家ブラッドベリによる歴史への懺悔と警鐘」ともとれるようなストーリーになっているのだ。
さて話は逸れるが、ここでアメリカの歴史をおさらいしてみよう。
1492年、クリストファーコロンブスによりアメリカ大陸は「発見」され、その後、多くの人々が「信仰の自由」「富」「飢えからの逃避」を求めヨーロッパからアメリカへやってくることとなった。
その後、アメリカは拡張時代へと入り領土を西へ西へと広げていったが、そこで問題になったのが、数千年間変わらない狩猟生活をしていた「ネイティブアメリカン(インディアン)」であった。
土地所有の概念が無く昔ながらの狩猟を続ける「ネイティブアメリカン」達と、産業、工業、農業を発展させようと土地に定住するアメリカ白人達。
価値観が異なる人種間の接触。
それは時に、衝突と悲劇を生む。
拡大を続ける白人の前に、多くのネイティブアメリカンは争いを好まず、土地や資源を明け渡していった。
中には立ち上がるネイティブアメリカンもいたものの白人は彼らを武力で弾圧。
最後の抵抗者であるアパッチ族の勇者ジェロニモが敗れた後、白人が持ち込んだ疫病と殺戮により激減していたネイティブアメリカンは、狭い居留地で少数派として生きる権利を許されるのみとなってしまったのだ。
現在のアメリカの繁栄はこうした悲しき歴史の上に成り立っている。
ここで話を『火星年代記』に戻そう。
伝染病で滅んだ火星人と、その廃墟に地球流の都市を建設していく地球人。
似ていないだろうか?
火星人は、アメリカ白人に土地を奪われ追いやられたネイティブアメリカンに。
そして地球人は、ネイティブアメリカンが居なくなった土地に、ヨーロッパ流の産業革命を持ち込み、強大な国家を築いていったアメリカ人に。
ブラッドベリはアメリカ白人である。
彼は、この贖罪意識を訴えるために本書を書いたのではなかろうか?
特にラストは、ブラッドベリによる母国アメリカや人類への警告そのもののようにも思われる。
まとめ
本書は、全体が400ページもあって非常にボリュームある作品となっている。
流れとしては、火星に到達した地球人、火星人たちの生活、滅びゆく火星人、火星に入植する地球人達、発展する火星、大戦争が起こる地球、その後の火星となっており、まさに地球人と接触した火星の年代記そのものである。
その架空の「火星」の歴史を描くことでブラッドベリは自分達が犯してきた歴史上の過ちを描いたのであろう。
マヤ、インカ、そしてネイティブアメリカン達と一度滅ぼされた文明は永遠に戻ってはこないのだ。
二度と犯してはならない過ちとして、ブラッドベリが現代に伝えてくれることは多い。
歴史とは何か、SFとは何か?
本書を読むと幾分、理解が進むかもしれない。
ぜひ一読してもらいたい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
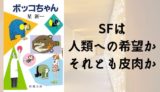 『ボッコちゃん』あらすじと感想【SFは人類への希望か、それとも皮肉か】
『ボッコちゃん』あらすじと感想【SFは人類への希望か、それとも皮肉か】



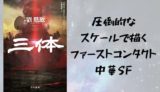
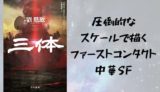
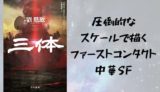
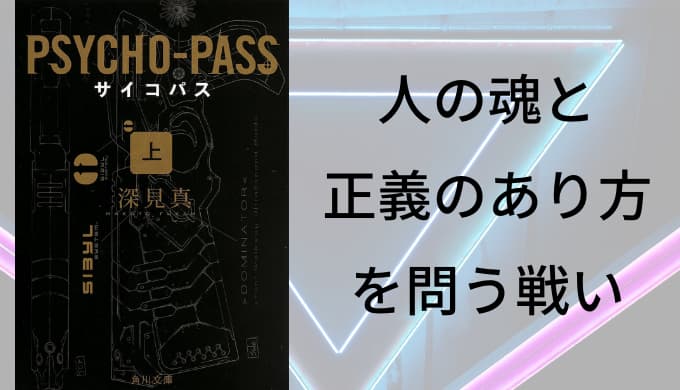
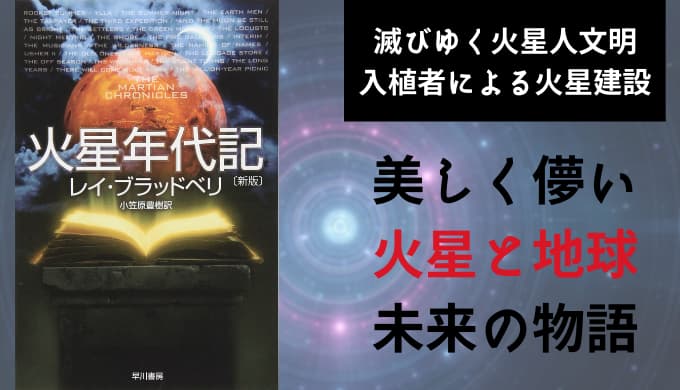



書き手にコメントを届ける