新型コロナウイルス感染が拡大したことに伴い、「食生活」が変わった人も多いだろう。
外食機会が減り、デリバリーや自炊が増えたのではないだろうか。
またお弁当やテイクアウトメニューを出す飲食店も増えたと実感する。
今回紹介する、斎藤千輪さんの『神楽坂つきみ茶屋 禁断の盃と絶品江戸レシピ』は、メインではないが、アフターコロナの飲食店が少し垣間見える小説である。
神楽坂でワインバー開業を目指す若者2人に訪れる、とある変化とともに、その様子を見てみよう。
目次
こんな人におすすめ!
- 料理小説が好きな人
- 江戸時代の料理に興味がある人
- コメディーだけど、少しホロリとする話を求めている人
あらすじ・内容紹介
月見剣士(つきみ けんじ)は、幼馴染の風間翔太(かざま しょうた)とともに、「つきみ茶屋」を改装してワインバーを開こうと計画していた。
つきみ茶屋は江戸時代に神楽坂で創業され、当初は待合(芸者遊びの場を提供するお店。お茶屋の別名)だったが、剣士の祖父の代に割烹へ変え、両親が営んでいた。
しかし、その両親は交通事故で突然亡くなったため、つきみ茶屋は営業を停止。
一人息子である剣士は、幼いころに包丁で手を切る大けがをしてから、トラウマで全く包丁が握れない。
そんなとき幼馴染で料亭『紫陽花亭』の息子・翔太がワインバー開業を誘ってきた。
実家が料亭や割烹を営んでいることもあり、剣士も翔太も和食を敬遠していた。
そのため、新しいお店は洋食をベースにした創作料理を翔太が作り、料理に合わせたワインを剣士が選ぶというコンセプトの元、2人でお店に残っていた日本酒を肴に、自分たちのお店の計画を練っていた。
ところが、剣士が少し目を離していた隙に、翔太は偶然見つけたという、金の盃でお酒を飲んでいた。
その盃は、剣士の両親から使用禁止を告げられていた禁断の盃。
すると、翔太はいきなりマグロのトロをポイ捨てし、口調がべらんべえに。
しかも翔太、、、ではなく江戸の料理人・玄(げん)と名乗った。
『神楽坂つきみ茶屋 禁断の盃と絶品江戸レシピ』の感想・特徴(ネタバレなし)
この世に未練たっぷり!? 江戸の料理人・玄とは?
翔太に憑いてしまった江戸の料理人・玄とは一体誰なのだろうか。
彼が生きていたのは幕末、浦賀沖に黒船が来航したころ。
小石川の水戸徳川家江戸上屋敷近くで兄と一緒に『八仙』という料理屋を営んでいた料理人だった。
玄は頑固でべらんべえな江戸っ子口調をしているが、料理に対しては研究熱心で、作った料理を美味しいと食べてもらうことが生甲斐だった。
ところが、27歳のとき、大名の毒見で酒を飲んだときに、毒にあたり、あっけなく逝ってしまった。
もっともっと美味しいといってもらいたい。
未練があった玄の魂は、剣士の家に保管されていた盃に乗り移っていた。
図らずも、その盃でお酒を飲んだ翔太に憑いた玄は、170年ぶりの世界に、これまでのうっ憤を晴らすように、つきみ茶屋に残っていた食材や庭に生えている草で料理を始める上に、見るものが新鮮に映るため、大声ではしゃいでしてしまう。
仕方なく玄につき合いつつも、本当は翔太を返してほしい剣士。
そうこうしているうちに、酒を飲んだ玄が寝たとき、翔太が戻ってきた。
2人で話して結論付けたのは、禁断の盃でもう一度お酒を飲めば、玄は出てこないだろうということ。
しかし、盃は玄が出てきたときに欠けてしまったため、壊れた器を修理する、いわゆる金継ぎをして貰うまで辛抱することとなる。
素材の味が生きて、実は合理的!?江戸時代の食事事情
盃の金継ぎが終わるまでの間、翔太と玄は、お酒を飲んで寝るタイミングで入れ替わっていた。
正直、剣士は玄が興奮して神楽坂近辺を散策したり、食料品が大量に売られているスーパーを見てはしゃいだりするので、お世話係をするのに疲れていた。
しかしその一方で、時々玄が作る江戸料理を見直すことも出てきた。
それは、玄がスーパーで買いこんだ食料を使い、翔太が料理を作る場面。
季節は秋だったのもあり、カボチャのポタージュ・カプチーノ仕立て、マツタケのクリーム煮・パイ包み、鯖とウイキョウのパスタ、鴨のグリル・マスカットソースを作る。
これだけでも美味しそうなのだが、その後現れた玄は、翔太の料理に対し、こう感想を言った。
味は悪くねぇよ。ばたーとかな、こってり油っこくて確かに旨い。でもよ、どれも素材の味がどっかいっちまってるわな。なんつーかこう、肉も野菜も昔より味がぼやっとしちまってよ。(中略)せっかくの初もんの松茸なのに、香りがくりーむってやつでぼやけちまってる。南瓜の汁物だってそうだ。確かにこってりしててうめぇけどよ、素材が南瓜だが薩摩芋だかわかりゃしねえ。それによ、食材が多いと残り物も多くなる。いわゆる屑ってやつだな。贅沢だとは思わないのかい?
そう言って翔太が使った同じ食材で、玄が作った料理は、鴨と松茸の焼き物、南瓜の安倍川(南瓜に砂糖入りきな粉をまぶした料理)、大根と人参の糠漬け、鯖の船場汁、卵ご飯である。
つきみ茶屋の物置にあった箱膳に入れられた一汁三菜である。
「これが旬の味を活かした江戸料理さ。豪勢じゃねえしそーすとかいうやつもねぇ。だけど季節を存分に感じられるご馳走だ。(中略)みんなが自分専用の箱膳で、一緒に手を合わせてから食う。終わったら一切れだけ残した漬物で器を拭って、その漬物を食ったら白湯か茶を入れて飲む。そしたら、器を清潔な布で拭いて、箱の中に戻すのさ。無駄な水は使わねぇから、今と違って自然にもやさしいだろ。それが江戸の常識ってやつだ」
箱膳とは、中に食器が入った蓋つきの長方形の箱である。
蓋をひっくり返すと膳になり、食事の時はそこに食器を置く。
箱膳は無駄がなく合理的な作りをしている。
これは江戸は火事が多かったこともあり、すぐ持ち出せるよう、考え出されたという。
しかも玄いわく、魚や肉の屑は肥料にし、壊れた食器は修理職人に直してもらい長く使っていたという。
読んでいる私もそうであったが、剣士は江戸時代の食に、目新しさとエコロジーを見出し、段々と江戸料理に興味を持ち始めていた。
剣士と翔太、江戸料理と向き合う
玄と過ごすうちに、江戸料理に興味が出てきた剣士。
翔太とワインバーの開業を目指していたが、これまで見向きもしなかった江戸料理、つまり和食だけでなく、両親が残してくれた膳やのれんの大切さに気付く。
剣士はその思いを翔太にぶつける。
玄の料理はシンプルで地味だ。翔太の洗練された料理とは正反対だよ。箱膳だって古臭い。だけど、それがむしろ新鮮で、特別感があるように感じたんだ。江戸の料理や文化について、もっと知りたくなった。(中略)でね、改めて思ったんだ。古民家風のカフェ、イタリアン、フレンチ、バー。この街にはかなり増えたよね。そんな中で、僕らの店はどう差別化すればいいのか、もっと考えないといけないとなって。逆に、昔ながらの店はどんどん消えつつある。だったら箱膳を出す店でつきみ茶屋の看板を残すのもアリかもしれない。
翔太にとってみれば、自分の知らない間に、幼馴染が玄に肩入れし、和食のお店にしたいと言っているので、寝耳に水な出来事である。
しかも翔太は料亭の息子であるが、親との折り合いが悪く、和食には触れたくもない。
だが、翔太の熱意にも押され、玄が作る料理を見定めようと決意する。
しかし、玄の料理には致命的なことがある。
それは地味であり、SNS映えしないことだ。
剣士と翔太が目指すのは、江戸料理を極めることではなく、飲食店開店。
江戸料理の地味さと集客戦略をどう折り合いつけていくのか、それは読んでのお楽しみである。
まとめ
SDGsという言葉を聞いたことはあるだろうか。
最近はファッション誌でも取り上げられるようになり、言葉を聞いたことがある人も多いだろう。
SDGsとは、国連が掲げた持続可能な社会を実現するための17の目標なのだが、この中には、エコロジーや陸や海の自然を守ることも含まれている。
玄が言っていた、野菜の屑も肥料にする、箱膳のように持ち運びが簡単にできるよう合理的な作りにする、金継ぎのように壊れても直して使うなど、江戸時代に当たり前に行っていたことは、SDGsやエコロジー活動そのものだと思った。
世界中のものや情報が簡単に手に入り、暮らしは便利になったと同時に、失ったものも多くあるだろう。
昔のことを蒸し返すのは古臭いと思うことはあれど、SDGsやエコロジーを考えていく上では、過去にヒントが隠されているのかもしれない。
今一度昔の習慣を見直しても良いのではと感じる。
またここに書けなかったが、翔太の実家『紫陽花亭』の話も奥深いので合わせて読んで欲しい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 歴史漫画おすすめランキング30選!大河ロマンに注目
歴史漫画おすすめランキング30選!大河ロマンに注目









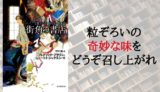
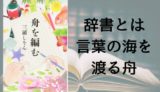
書き手にコメントを届ける