映画『野性の呼び声』をご存じだろうか。
主演はハリソン・フォード。
原作は1903年にアメリカの作家であるジャック・ロンドンが発表した“The Call of the Wild”である。
日本では『野性の呼び声』や『荒野の呼び声』のタイトルでたびたび翻訳され、世界的に見ても同作の映画化は1908年から数えて2020年で6回目であり、原作は現在アメリカ文学において非常に重要な文学作品のひとつと位置付けられている。
あらすじ・内容紹介
作品は犬のバックを主人公に、三人称の視点を用いて描かれる。
セントバーナードとシェパードの血を引いた4歳の雄犬であるバックは、暖かいカリフォルニア州の裕福な判事の家で何不自由なく暮らしていた。
しかしある時、金に困っていた屋敷の家の召使に150ドルで売り飛ばされ、寒さの厳しいアラスカ近くの北方領域で橇犬(そりいぬ)として生きていくことになる。
世間はゴールドラッシュに沸き、橇犬の需要が非常に高い時代だった。
最初は突然のことに戸惑い、怒りを隠せなかったバックだったが、やがて彼は「棍棒と牙の掟」を学び、逞しくしたたかに生きる術を覚える。
他にも連れてこられたほかの犬たちとの覇権争いや、ひとつの旅が終わるごとに入れ替わってゆく主人たちとの関係を通して、バックは次第に自分の中に眠るひとつの本能――「野性の血筋」に気が付いていく。
『野性の呼び声』の感想(ネタバレ)
当時の時代背景と文壇事情
作品の考察に入る前に、まずは当時の時代背景と文壇事情を軽く確認しておこう。
ジャック・ロンドンの生きた時代は19世紀後半から20世紀の前半のアメリカである。南北戦争以降、資本主義化が進む米国では、すでに1890年にフロンティアがほぼ消滅しており、人々は新たな未開の地を求めていた。
そんな折に1896年にカナダとアラスカの国境地帯で発生したゴールドラッシュは、新たな一攫千金の夢として人々の目に映ったのだろう。
富を求め、人々は続々と北へ向かうことになる。
こうした政治的背景の最中、当時の文壇では南北戦争以降、現実をありのままに描こうとする「リアリズム文学」が主流になる。
一方、貨幣経済を中心とする資本主義経済の発展は、「自然主義文学」もまた生み出すことになる。
文学における自然主義とは、自然界における「適者生存」の法則――つまり強者が弱者を淘汰する弱肉強食の法則――を人間の社会に見出す試みのことを指す。
自然主義の作家たちは、遺伝と環境の因果関係を通じて対象を描くことを試みた。
『野性の呼び声』もまた(犬を主人公とした点で多少異なるものの)、飼い犬が文明化された安全な環境から離れ、己の遺伝子のルーツである極寒の地で野性に目覚めてゆく点で自然主義文学の系譜上にある。
橇犬の覇権争いと闘争本能のうずき
先ほどこの物語は、飼い犬が少しずつ野性の本能に目覚めていく話であると述べた。
作品では何度も、このような「本能」について言及されている。
こうしたことを彼は経験から学んだだけではない。長らく眠っていて、いまようやくよみがえってきた本能、それからも学んだのだ。飼い馴らされてきた幾世代もの日々の積み重ね、それが彼から剥がれ落ちていった
では、野性の本能とは具体的に何なのか。
以下の引用を見ていただきたい。
一瞬のひらめきのうちにバックはさとった。今こそそのときがきた。いよいよ死闘がはじまるのだ。いよいよ死闘がはじまるのだ(……)すべてが既視感を伴って感じられる――白い森、大地、月光、そして闘争本能へのうずき
この作品の読みどころはなんといっても、バックのチームメイトである多種多様な犬たちが、人間顔負けの様々な性格をもって描かれ、彼らの覇権争いが臨場感あふれる文体で描かれることである。
例えばバックを敵視する先導犬のスピッツ、仮病と盗みが得意な新入りのパイク、隻眼のソルクレス、自分の職務以外のすべてに無関心な熟練のデーヴ。
作品の後半では、バックととある犬の一騎打ちが描かれるが、その臨場感には思わず息を止めてしまい、ロンドンの人間に対する観察眼と深い洞察力を感じずにはいられない。
人間との絆、ソーントンへの忠誠
一方でロンドンは犬同士の関係だけではなく、犬と人間の絆もまた描いている。
バックが旅の途中で出会う人々は、必ずしも彼を150ドルで売り飛ばした屋敷の召使のような人間ばかりではない。
苦労を共にする犬たちの体調を気遣い、別れの際には涙を流すような人々もいる。
こうした人間たちとの出会いと別れを経て、最終的にバックは彼にとって最後の主人となるジョン・ソーントンと出会う。
彼との出会いはバックにとって人間との最後の絆であり、人間との親密さを呼び起こすものであった。
しかし、彼との別れは突然訪れる。
「激情にかられて、いつもの抜け目なさや理性を忘れたのは、生涯でこのときが最後となったが、それほど逆上したというのも、ジョン・ソーントンへの大いなる愛があればこそだった」
「最後の絆は切れた。人間にも、人間の要求にも、もはや束縛されることはないのだ」
『野性の呼び声』が示すもの
最後にひとつ謎を提示したい。
ソーントンと出会う以前から、作品の所々でバックは
「遠い記憶」の「別世界」に存在する男のまぼろしの夢を見ていた。
暗闇の恐怖に怯え、銛を構えほぼ全裸のその男とともにバックは火のそばに座っている。
「そしてこの毛深い男との幻像とごく酷似したものとして、いまなお森の奥から響いてくる、あの呼び声もあった(……)ある漠然とした、甘やかな喜びを感じるのと同時に、なにやらやみがたいあこがれと、心のうずきをも意識させられる」
この男は文脈的に考えて、人類の遠い祖先であり、銛を携えていることからもアメリカの先住民を指している可能性が高い。
そして作品の最後でバックはインディアンたちを皆殺しにする。
ではこれを一体どのように解釈すればいいのだろう?
まとめ
一般的に『野性の呼び声』は文明批判がテーマなのだと解釈されることが多いが、歴史的に見てアメリカの先住民を迫害したのは、アメリカの入植者たちであり、開拓者たちである。
なぜ人間と対立する存在であるバックに、ロンドンはこのようなことをさせたのだろうか?
こちらについてもぜひ考えながら読んでみてほしい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
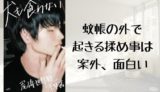 『犬も食わない』あらすじと感想 【蚊帳の外で起きる揉め事は案外、面白い】
『犬も食わない』あらすじと感想 【蚊帳の外で起きる揉め事は案外、面白い】
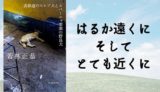
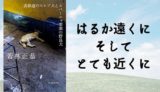
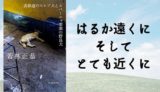






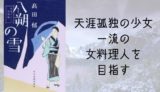

書き手にコメントを届ける