大人気ミステリー作家・東野圭吾。
彼の数多ある作品の中から今回は、死刑制度を題材とした作品を紹介する。
重めのテーマで文庫本でも367ページと、内容も少しボリューミーではあるが、文章は読みやすく、我々読者にしっかりと問題を問いかけてくる内容だ。
※死刑制度の是非等、筆者の個人的な意見を述べている箇所があるが、それが正しいという意味ではない。
※一部過激な表現が含まれているため、苦手な方は先を読まないことをおすすめする。
こんな人におすすめ!
- 死刑制度について考えたい
- 重めのテーマの話が読みたい
あらすじ・内容紹介
中原道正(なかはら みちまさ)と小夜子(さよこ)の愛娘・愛美(まなみ)は、夫妻の留守中、強盗殺人事件に巻き込まれ、小学2年生という若さで命を落とした。
犯人は捕まり、その後の裁判でも望んでいた“死刑”判決を勝ち取った。
しかし、2人は事件を機に離婚し、別々の道を歩むことになった。
離婚し、すっかり疎遠になってから数年が経った頃、道正は愛美の事件を担当した刑事・佐山によって、元妻・浜岡(はまおか)小夜子が何者かによって刺殺されたことを知る。
小夜子を殺害した犯人・町村作造(まちむら さくぞう)はすぐに自供。
町村の死刑を望む小夜子の両親に協力し、裁判の準備を進めていく中、道正はある真相に辿り着く。
本当の償いとはなにか?
死刑制度の是非をめぐる社会派小説。
『虚ろな十字架』の感想・特徴(ネタバレなし)
事件によって被害者遺族が失うもの
殺人事件の被害者となった遺族が失うものの大きさは、はかり知れない。
大切な人の命、思い出、未来……。
周囲の人生を180度変えてしまうのは容易に想像できるが、実際は想像よりも遥かに多くの物を失い、人生のどん底まで突き落とされるのだろう。
「底」と呼べる場所に辿り着くことができるのかも分からない。
「幸せ」とはほど遠く、その時から時計の針が止まった様な虚無感に苛まれ、自分の生きる意味さえ分からなくなる。
「どうして自分ばかりこんな目に遭わなければいけないのだろう・・・」と、世間を妬み、自暴自棄になりそうだ。
人間関係もぎくしゃくしてしまった。多くの人々が気を遣って中原たちには近づいてこなくなっていた。職場での仕事内容も変わった。中原にはもうクリエイティブなことはできなくなっていた。
自分の都合で他人の幸せを奪っておきながら、なぜ犯人は生存することが許されるのだろうか。
自分の大切な人はもうこの世にいないのに…。
ふとした瞬間に、やつが生きていることが脳裏をよぎるだけで苦しいに違いない、と考えていたが、小夜子の言葉から推察すると、事態はもっと深刻だった。
「あの事件のことを考えても、もう感情といえるものが湧いてこなくなっちゃった。たぶん心が死んでしまったんだと思う。」
実際は、犯人に対する怒りや、事件の事を思い出すと辛い、悲しいという感情があるだけまだマシで、「心」を失った生ける屍の様な状態なのかもしれない。
被害者遺族が死刑を求める理由
あらゆる刑罰の中で最も重い位置づけとされる死刑。
犯罪者とはいえ、人の命を奪う刑であり、残虐という理由から制度そのものが無い国や、廃止をする国も多い。
現行法上、死刑制度が存在する日本でも、すべての殺人犯罪において死刑を科せるわけではなく、社会的な影響や犯罪の性質などを考慮し、判決が下されることになる。
制度そのものの賛否や、その理由は個人の考えがそれぞれあって然るべきで、とやかく言うつもりはないが、自分にはどうしても分からないことがある。
死刑制度廃止に賛同される方は、自分が被害者遺族側となった場合でも、犯人にそれを望まずにいられるのだろうか。
『死刑を求めるのは、ほかに何も救いの手が見当たらないからだ。死刑廃止というなら、では代わりに何を与えてくれるのだと尋ねたい。』
あまり考えたくない事だが、もし自分の大切な人が殺害されたら、その犯人には生きていてほしくない、と私は思う。
だから死刑制度を支持する。
経験したことのない出来事なので、実際は違うかもしれないが、「人を殺したのだから同じように死んで償ってほしい」というよりも、大切な人を奪った人間と、この世で同じ空気を吸って生き続けなければいけないことが耐え難く、法の裁きで犯人の命を奪ってほしいからだ。
『仮に死刑判決が出たとしても、それは遺族にとって勝ちでも何でもない。何も得ていない。ただ必要な手順、当然の手続きが終わったに過ぎない。』
どれだけ無残な殺され方をして、殺したいほど憎くても、遺族が敵討ちで犯人を殺害することは許されない。
裁判で罪を問い、裁判官に刑罰の重さの決定を委ねるしかないのだ。
無実の者に罪を着せないよう、公正な裁判で真相を究明し、冤罪事件を防ぐことは必要だが、有罪なのに死刑以外の判決は、殺人者にも生きることが許されたことになる。
国家によって、今世の未来で幸せになることも認められたとも言い換えられる。
加害者を救済するための裁判なのだろうか、と思えるほど、被害者故人の命と殺人者の命が一対一として扱われていない様な感じさえする。
不思議な制度だ。
『人を殺せば死刑――そのようにさだめる最大のメリットは、その犯人にはもう誰も殺されないということだ。』
償いとはなにか?
個人的な意見として、死刑制度の存続には賛成の意を述べてきたが、「死んで報いるべきだ。」という目的での死刑制度には、やや賛成し兼ねる。
後悔や反省の念を感じない者の命を強制的に奪ったところで、それを償いとして受け取ることなんて到底できないからだ。
どんなに凶悪な殺人犯であっても、人権が尊重され、拷問の様な残虐な刑罰は禁止されている。
仮に死刑判決が確定した場合、現在の日本では絞首刑で執行されることになるが、死刑囚が苦痛を感じるのは、踏み板が外れてから息の根が止まるまでのわずか数分だろう。
そのたった数分で被害者本人や、その遺族の味わった苦痛を帳消しにすることなんて到底できない。
それからもう1つ、自分の犯した罪の重さをしっかりと分からせ、償わせた後に刑を執行してほしいという願望もある。
では、何をしたら“償い”として受け止めることができるのか?
考えを張り巡らせてみたが、答えは見つかっていない。
死刑囚は監獄の中で、刑の執行がいつ行われるのか分からない不安と恐怖に怯えながら生活すると言われているが、それが償いなのだろうか?
慎ましく暮らし、善行をすれば償いに値するのか?
本書の(文庫本)343ページから345ページにかけてのシーンで、自己中心的な意見を述べる花恵だが、その考えにも一理ある、と納得してしまうところもある。
「あなたがどういう結論を出そうと文句をいう気はありません。人を殺した者は、どう償うべきか。この問いに、たぶん模範解答はないと思います。」
小夜子は生前、被害者遺族として死刑制度廃止に反対していたが、人生で2度、身近な人を殺人という形で亡くした道正の発言は、ものすごく冷静であった。
彼女の遺志を踏まえた発言でもなく、悟りの境地だ。
まとめ
タイトルの通り、重くのしかかる話であった。
本当に十字架を背負って生きているのは、被害者遺族なのかもしれない。
一人娘を亡くした小夜子の「人を殺めた人間の自戒など、所詮は虚ろな十字架でしかないのに。」という言葉が印象に残っているが、この言葉には愛美を亡くしたときの後悔、虚しさ等様々な気持ちが含まれているのだろう。
東野圭吾作品の中で、本作の様に1つのテーマについて問いかけ、じっくりと考えさせられる作品に興味がる方は、脳移植を題材とした『変身』も、是非読んでもらいたい。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 【2023年最新】東野圭吾おすすめ小説ランキング36選【読書好きが選んだ!】
【2023年最新】東野圭吾おすすめ小説ランキング36選【読書好きが選んだ!】







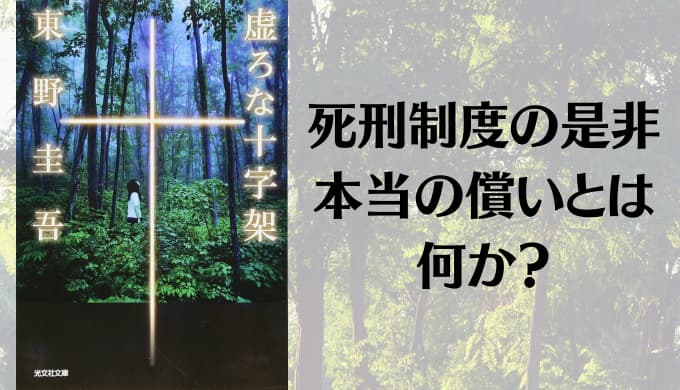


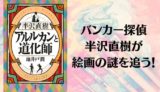
書き手にコメントを届ける