村上春樹が初めて一人称「私」に挑戦した長編小説『騎士団長殺し」は、4枚の絵がつなぐ不思議で少し不気味な物語となっている。
「イデア」と「メタファー」が意味するものを探しに行こう。
こんな人におすすめ!
- 深淵を覗く物語を読みたい人
- 不思議かつちょっと不気味な気持ちになりたい人
- とにかく村上春樹の作品が読みたい人
あらすじ・内容紹介
36歳で絵描きの「私」は、妻に突然離婚を切り出され理由もよく分からないままに家を出た。
東北を旅していたが、車の故障で東京へ帰ることを余儀なくされる。
帰る家もないので、美大時代からの唯一の友人、雨田政彦(あまだ まさひこ)を頼り、山奥の家に腰を落ち着ける。そこは彼の父親である日本画の巨匠、雨田具彦(あまだ ともひこ)の別荘兼アトリエであった。
平穏な日々が続くが、ある日1本の電話がかかってくる。
電話の相手は「私」の絵のエージェントからで、断っていた肖像画の仕事の依頼だった。法外な額の依頼に私は一度は断ったものの、結局はその仕事を受けてしまう。
その後、「私」の家にやって来たのは、免色渉(めんしき わたる)という白髪のハンサムな中年男性だった。免色の肖像画を描いていくうちに、私の身の回りで奇妙なことが起き始める。
真夜中に鳴り響く鈴の音、屋根裏で見つけた不思議な絵、免色が依頼する少女の肖像画、「イデア」や「メタファー」という存在、雨田具彦が体験したウィーンでの事件。
私が行き着いた先に見たものはなんだったのか……。
『騎士団長殺し』の感想・特徴(ネタバレなし)
削ぎ落とされた感情表現の巧さ
読み始めてすぐに、不思議な読み心地だと感じた。
だれも感情を爆発させないからだ。
例えば、絵描きの「私」が妻に離婚を切り出されるシーン。
「とても悪いと思うけれど、あなたとは一緒に暮らすことはこれ以上できそうにない」
と妻に言われるだが、「私」は怒るわけでもなく泣くのでもなく、次のような行動をとる。
彼女のその通告を受けて最初にとった行為は、窓に顔を向け、雨の降り具合を確認することだった。
まったく「私」の感情が読めない、分からない。この後も多少「傷ついた」という言葉があるものの、実際の「私」の感情はついぞ分からないまま読了してしまった。
読み終えてふと考えてみれば、この物語に感情をむき出しにする人はまったく登場しない。
語気を荒げたり、怒鳴ったり、ましてや暴力を振るったりする人もいない。終始、静かな川の流れのように物語は進んでいく。だからちょっと不気味なのだ。
みながみな、冷静でどこか人生を達観しているような人ばかりが出現して、そしてみんな、生きていることにあまり執着しているように見えない。
それでいながら物語が無味乾燥になっていないし、文章が読みにくいわけでもない。
削ぎ落された感情の扱い方が、村上春樹氏はとても上手いのだ。
むしろ、感情だけでは現すことのできないディテールに重きを置いている。
例えば、章の名前はすべてその章に登場するセリフでできている。不思議なセリフが多く、その章をそのセリフで語っていると言ってもいい。
村上春樹氏の心憎い演出に、酔いしれて読んでほしい。
「私」の独白を彩る数々のエピソード
基本的にこの物語は、「私」の手記のような形をとっている。起きたことを並べて書いており、過去をさかのぼる形で進んでいく。
妻から離婚を切り出され、あてもなく東北を旅し、雨田具彦の別荘へ腰を落ち着け、肖像画の依頼があり……と物語はスムーズに進むかと思いきや、割と脱線する。
妻・柚(ゆず)との思い出、柚の父親に結婚を反対されたこと、小さい頃に亡くなった妹・小径(こみち)のこと。
東北の旅で突如一夜だけの関係を結んでしまった名前も知らない女性と、その翌日にファミレスで自分を睨んできた白いスバル・フォレスターの男。
時系列で語っていきつつも、途中途中で脇道に逸れる小話には意味がある。
この物語の主軸は「私」の独白で進み、平面的な構造となるため、「私」が過去を振り返ることで物語全体に厚みが出るのだ。
脱線で厚みと想像を膨らませることで、読者の中の物語を平面から立体にしていく。
行ったり来たりする時系列の自由さがこの物語の主軸であり、小説の技術が光る部分でもある。
「イデア」と「メタファー」は重要ポイント
あまり聞き慣れない言葉である「イデア」と「メタファー」。
「イデア」とは「感覚を超えた理性だけで認識できる、時空を超えた永遠不滅の実在」とのこと。
哲学用語なので、なかなか理解するのは難しそうだ。
一方、「メタファー」とは「隠喩」のことで、聞いたことがあるかもしれない。
「隠喩」とは「~のようである」などの言葉を用いないで表す語法のこと。
これらの言葉がどうこの物語に影響を及ぼすのか。
特に「イデア」は最重要キーワードで、この存在が物語を左右すると言ってもいい。
しかも読み終わってみると、イデアの「時空を超えた永遠不滅の実在」という説明がなんとなく分かってくるから不思議だ。
雲を掴むような物語、空を掴むような読み心地かもしれない。
「イデア」と「メタファー」の存在がこの物語を面白くしている。
「あたしは霊であらない。あたしはただのイデアだ」
さて、イデアとはこの本の何にあたり、メタファーとなっているものはなんのか。
村上春樹氏がこの物語に込めたものはきっと2つの言葉に集約されていると思うのだ。
まとめ
この本を読んでいると、ときどき登場人物たちがうらやましくなってくる。
何が起ころうとも泰然自若としているところ。そして、現実と丁寧に向き合っているところ。
私は少しでも礼儀正しく現実の世界に向き合おうと努めた
「私」の環境に対する順応性、免色の自分に持っていない才能に自信を持っているところもなんだかすごく、うらやましくなった。
ふと、最後に、この人たちは自分に持ってないものをたくさん持っていることに気づいた。
現実から離れたミステリアスな物語でありながら、登場人物たちの息遣いがリアルに書かれている物語だった。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 村上春樹風にマクドナルドで働いてみた【完璧なポテトなどといったものは存在しない】
村上春樹風にマクドナルドで働いてみた【完璧なポテトなどといったものは存在しない】
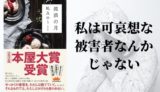
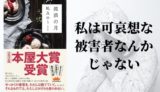
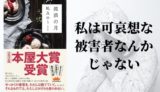
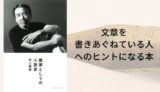
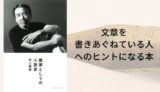
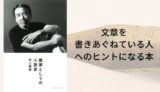

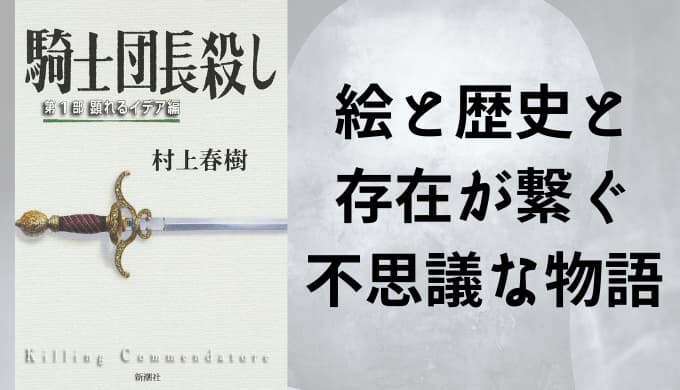

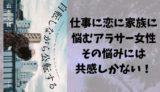
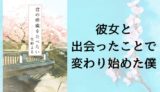
書き手にコメントを届ける