夏目漱石『こころ』はたいへん有名な小説だ。
夏休みの宿題や高校の授業で読んだことがあるかもしれない。
とはいえ、全編を通読した人はそれほど多くないだろう。
あるいは、なんとか読み通したとしても人生経験がまだ浅かったために、登場人物の心情があまり理解できなかったのではないだろうか?
そういう人はぜひ、この機会に読み直してみよう。
名作ほど何度読み返しても新たな発見があるが、『こころ』はまさにそういう小説だ。
あなたが日本人であるなら、グローバル時代の今こそ読んでおきたい本である。
こんな人におすすめ!
- 人間の心の動きに興味・関心がある人
- 現代の社会問題の根本的原因を知りたい人
- 生死・恋愛・仕事など人生の問題を真剣に考えたい人
- 西洋社会による画一的なグローバル化に疑問を抱いている人
『こころ』はその普遍性の高さから日本人のみならず、世界中の人々に親しまれている。
出版されて100年以上経った今なお、国や時代を超えて通底する現代社会の本質と闇を鋭く描き出している。
あらすじ・内容紹介
『こころ』はシンプルな三部構成からなっている。
第一部は「先生と私」。
ときは明治の終わり頃、”私”はふとしたことから海辺で先生と出会う。
人生経験のまだ少ない”私”は先生の含蓄ある言葉に次第に惹かれていった。
まるで親子のような師弟交流を深めるなかで、いつしか”私”は謎めいた先生の過去に疑問を抱くようになる。
第二部は「両親と私」。
大学を無事卒業して故郷に帰省した”私”。
両親との再会を喜んだのも束の間、父は突然病に伏せ、母は”私”の身の振り方を心配していた。
伝手を頼ろうと先生に手紙をしたためた”私”のもとに分厚い封書の返信が届く。
帰京する列車に飛び乗り、”私”は先生からの手紙を急ぎ読み始める。
第三部は「先生と遺書」。
届いた手紙は自らの過去を明かす先生の告白文だった。
生い立ちに始まり、若かりし頃の苦い経験、親友・Kとの出会い、そしてある女性を巡る葛藤の日々――。
手紙の結末は果たしてどんなものだったのだろうか…
夏目漱石『こころ』の感想・特徴(ネタバレなし)
先が気になるミステリー仕立て
物語のクライマックスではキーパーソンである先生の過去が暴かれる。
そこに至るまで、先生にどんなことがあったのか、読者の興味を湧かせるような”私”の巧みな心理描写が続く。
読み進めるほど結末が気になり、あたかもミステリー小説のような展開。
また、登場人物には私、先生、妻、両親…というように固有名詞が一切使われていない。
サスペンス的想像力をかき立てると同時に匿名性を帯びさせ、どこの誰にでも起こりうる普遍性を物語にもたせている。
高い表現力と描写力
かつてはお札の肖像にもなったほど、日本人なら知らない人はいない夏目漱石。
その文章力は言うまでもなく、ピカイチだ。
シンプルな言葉遣いや比喩が実に的確で、どんな場面でも情景がまざまざと思い浮かぶ。
漢字や言い回しの古臭さにもかかわらず、下手な現代の小説よりよっぽどわかりやすい。
目に見える現象のみならず微妙な感情の揺れ動きに対しても、解像度の高い心理描写で登場人物たちの複雑な”こころ”の移り行きを明快に映し出していく。
人間の心と現代社会への深い洞察
人の心は表裏一体。光の裏には影の部分が潜んでいる。
タイトルのとおり、『こころ』は今で言う精神分析的な観点から、そうした複雑な人間心理を克明に描いている。
『こころ』は有名な作品だけに、あらすじや結末をすでに知っているという人も多いだろう。
それでも「登場人物たちがどうしてあのような行動をとったのかよく分からない…」と理解に苦しみ、「よくある恋愛のもつれ?」「今とは時代が違うから…」と短絡的に片付けてしまいがちだ。
本書を解き明かすヒントの一端となる以下の文をみてみよう。
「自由と独立と己れとに充ちた現代に生れた我々は、その犠牲としてみんなこの淋しみを味わわなくてはならないでしょう」
第一章で先生が”私”に言い放ったこのセリフは現代社会を痛烈に批判すると同時に、人間の心に対して一面的な理解をもっていた、かつての自分への自己批判でもある。
どうしてこんなことを言ったのだろうか?
より立体的に読み解くには著者・漱石自身への理解も必要だ。
『こころ』の執筆前、当時の大都市ロンドンに留学した漱石。
いわば日本の未来へとタイムスリップした漱石は、計り知れない精神的ショックを受ける。
そのショックは、肥大した個人主義と競争主義が旧来の価値観を脅かすという危惧からくるものだった。
インターネットもSNSもない時代、人々をずっと支えてきた伝統的コミュニティの破壊はずっしりと重たいものだっただろう。
なぜなら、それはただちに個々人のバラバラな孤立を意味し、その結末はもはや悲惨なものでしかないからだ。
行き過ぎた文明は人々に災厄をもたらす――。
まだ牧歌的だった日本にもたらす影響を漱石はそう予見したのかもしれない。
まとめ
漱石が生涯呈したのは「文明発展が人間の孤独を加速させる」という思想だった。
翻って、私たちは漱石が危惧した未来の只中に生き、深まるグローバル化によって『こころ』が見通した以上に現代社会は混迷を極めている。
さらに思いも寄らない新型ウイルスの感染拡大で人々の争いや絶望は絶えず、世界は悲しみに溢れている。
本書で描かれたような”人間が本来もつ弱さ”が明るみになった今こそ、非日常で平静を保つ心のあり方が問われている。
「人はだれでも状況に応じて変わりうる――(だからこそ手を取り合わなければならない)」。
人間の生きざまを見つめ、未来を看破した漱石のメッセージはコロナ禍の今を生きる私たちの心にも響き渡っている。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 夏目漱石おすすめ作品10選【人の心とエゴに迫る近代文学の巨頭】
夏目漱石おすすめ作品10選【人の心とエゴに迫る近代文学の巨頭】
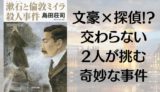
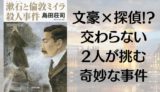
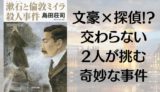
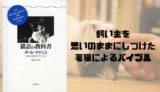
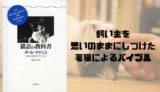
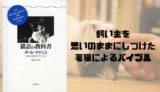

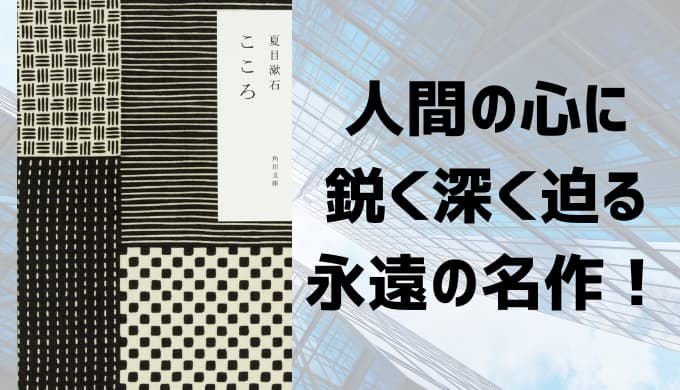

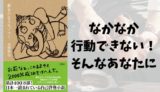
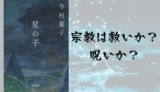
書き手にコメントを届ける