デスゲーム作品は好きだろうか。
ウィキペディアにおけるデスゲームの定義とは「登場人物が死を伴う危険なゲームに巻き込まれる様相を描く作品、および劇中で描かれる架空のゲームを指す」らしい。
『カイジ』『嘘喰い』他、最近ではフリーゲームの『キミガシネ』など、デスゲーム作品の人気は目下とどまるところを知らない。
今回はネットフリックスでドラマ化された漫画、『今際の国のアリス』からデスゲームものの魅力を考察していく。
生きるか死ぬか、密室空間のサバイバル
『今際の国のアリス』の主人公とその友人たちは、突如として東京とよく似た異世界「今際の国」へ召喚され、デスゲームへの参加を強制される。
デスゲームの醍醐味とは密室空間での命がけのサバイバルだ。
本作の場合、主人公たちが飛ばされた今際の国そのものが巨大な密室と化す。
全部のゲームをクリアしなければこの密室を出、現実世界へ帰還することさえ叶わないのだ。
デスゲームにおいて密室は重大な要素だ。
ミステリーと同じ位、否、どうかするとミステリー以上に設定の比重を占める。
彼らが参加するデスゲームの舞台の多くは密室状態となり、わけもわからず閉じ込められたメンバーはパニックに陥る。
これにはちゃんと意味があり、仮にデスゲームの舞台がすぐ逃げられるような場所なら、スリルが半減する。
デスゲームは対人同士の駆け引きや心理戦が肝なので、それを自然な流れで行わせるには、パーソナルスペースにひきこもれない密室の方が都合良いのだった。
タイムリミットが煽るスリルとサスペンス
デスゲームにはタイムリミットがもうけられている。
故に何もせずとも時間が来れば自動終了、参加者は命を落とす。
戦いたくない、殺したくないとビビって何もしないでいたら死ぬしかない。
どんなヘタレやいい子ちゃんも戦わなければ生き残れない。
対人同士の心理戦に時間との戦いが追加され、プレッシャーもひとしおだ。
タイムリミットがあるからこそスリルとサスペンスが盛り上がる。
もしタイムリミットがなければ、仲間内の蹴落とし合いに躊躇する参加者が「じゃあ何もしなけりゃいいじゃん」と開き直り、1日だらだら過ごすだけで終わってしまうかもしれない。
デスゲーム作品がサクサクテンポよく進むのは、登場人物の命に限りがあるからだ。
クリアできなければ明日死ぬ、相手を殺さなければ1時間後に死ぬと言われたら、どんな偽善者だろうと生存本能を剥き出し、本気で挑まざるをえないのだった。
劇的な退場、号泣の群像劇
デスゲームものの醍醐味といえば敵味方問わずアクが強いキャラクターと、彼らの劇的な退場だ。
デスゲーム作品の大半において、主人公の仲間は死ぬ。どうかすると序盤で死ぬ。
人の命は消耗品であり、そこに例外は存在しない。
本作でも主人公の友人が非業の死を遂げるが、それを無駄死にだと嘲る読者はきっといないはず。
というのも、彼らの死にざまが非常に感動的に描かれているからだ。
デスゲーム作品にはもちろん、仲間を助ける為に自ら犠牲になる選択肢も用意されている。
が、それを選ぶ人間は少ない。
デスゲーム作品の登場人物の大半は生き汚く、譲れない信念や目的のもと、ゲームの完全制覇をめざしている。
騙し裏切り殺し合うのが当たり前。
疑心暗鬼にどっぷり浸かり良心が麻痺していくハードな状況の中、友人や恋人、家族を生かす為に死を受け入れるキャラクターの姿はかっこいい。
敗者にもそれぞれ背負うものがあり、志半ばで散っていく無念や未練が読者の涙腺を直撃する。
デスゲームでは様々な人生模様が錯綜し、しばしば群像劇の様相を呈す。
初対面の他人同士が手を組むことで生まれる恋や友情、信頼が新たな悲劇の連鎖を成し、退場に際しては号泣もののドラマを生む。
入場と退場が1ゲーム1セット。
レギュラーキャラなら長生きするかもしれないが、テコ入れを兼ねた不慮の死のサプライズに終始ヒヤヒヤしっぱなし。
このくり返しがデスゲーム作品の基本構造である。
脱落した仲間や好敵手に思いを託され、ずんずん前へ進む主人公を、読者は手に汗握って応援したくなるのであった。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 友達になれる?ニートなおじさんとの付き合い方
友達になれる?ニートなおじさんとの付き合い方
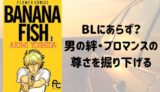
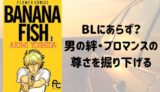
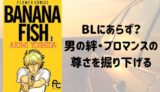
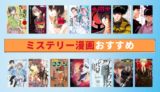
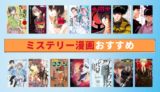
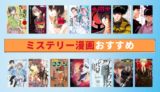
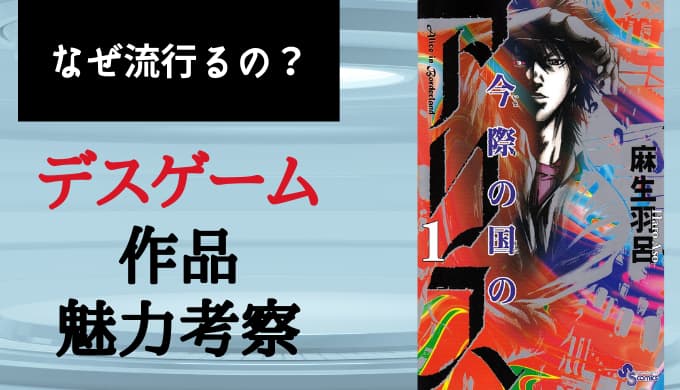
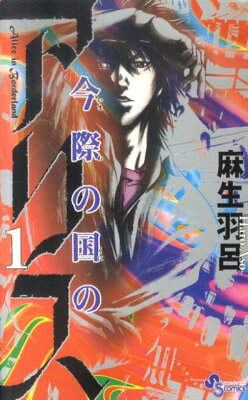
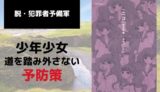

書き手にコメントを届ける