大人の為の残酷絵本を描いてきたエドワード・ゴーリー。
神経症的な描線と独特のシュールな作風は中毒的な魅力を持ち、世界中にファンを獲得している。
彼の作品には常に乾いたユーモアと死の気配が漂っており、読み手を引き付けて離さない。
今回はそんなエドワード・ゴーリーの代表作、『ギャシュリークラムのちびっ子たち』を紹介したい。
アルファベット順に死んでいく
大人の為の残酷絵本を描いてきたエドワード・ゴーリー。
神経症的な描線と独特のシュールな作風は中毒的な魅力を持ち、世界中にファンを獲得している。
彼の作品には常に乾いたユーモアと死の気配が漂っており、読み手を引き付けて離さない。
今回はそんなエドワード・ゴーリーの代表作、『ギャシュリークラムのちびっ子たち』を紹介したい。
アルファベット順に死んでいく
本作は『うろんな客』と並びエドワード・ゴーリーの代表作といえる。
内容は子どもたちがアルファベット順に死んでいく、ただそれだけ。
しかし、死に方のバラエティは凄まじく、焼死・溺死・轢死・墜落死・窒息死etc、およそこの世界に存在するありとあらゆる死因を網羅している。
いたいけな子どもたちが意味もなく死んでいくというあらすじを聞いて嫌悪感を示す読者も多かろうが、本作は悲劇を突き抜けて喜劇的なユーモアが持ち味。
というのも、登場する子どもたちがどこのだれか、どうしてそんな死に方をしたのか、背景がほぼ語られないからだ。
名前はわかっている。
しかしそれは「Who」の回答ではない。
読者に提示されるのは一枚のイラストのみ、そこで彼ら彼女らは死の決定的瞬間を切り取られている。
Aのエイミーはまさに階段から落ちるところ。
Dのデズモンドは橇から投げだされるところ。
Rのローダに至っては火だるまになっている。
裏を返せばそれしか情報を与えられないので、感情移入のしようがない。
たとえるならマザーグースの数え歌と同じで、韻を重んじて物語性を排している。
物語の基調となる「Why」の説明に一切尺を割かず、1ページごとにサクサク死んでいく謎のテンポのよさが、そこはかとないブラックユーモアを醸し出すのは否めない。
残酷なのにおかしい、死との向き合い方
前述したとおり、本作の子どもたちはアルファベット順に次々と変死を遂げる。
斧による斬殺や誘拐など、あからさまに他殺と見られる死に方をした子さえいる。
しかしエドワード・ゴーリーは、彼らの死に悲惨さを持たせない。
本作で扱われる死は実に軽やかだ。
人生は儚い。
運命は残酷だ。
大人だろうと子供だろうと男だろうと女だろうと、生きた年月の長短にかかわらず人は死ぬときは死ぬ。
登場と退場がワンセットになったギャシュリークラムの子どもたちを見ていると、私たちの生と死も、平等に無意味なのかもしれないと思うのだ。
しかし後味は不思議と悪くない。
カラッとした明るささえある。
「どうせ人生は無意味なんだからもっと肩の力を抜いて生きればいいのさ」と、陽気な死神にメッセージをもらった気さえするのだ。
エドワード・ゴーリーのすすめ
本作を読んでエドワード・ゴーリーの魅力にハマった読者には『おぞましい二人』と『うろんな客』をおすすめしたい。
『おぞましい二人』は1960年のイギリスで起きたムーアズ事件に材をとっている。
この事件は、あるカップルが子どもたちを誘拐・監禁・拷問したのち惨殺したものだ
残酷な描写はさほどないが、淡々とした文章とギスギスした絵が相俟って不気味な雰囲気が堪能できる。
『うろんな客』の方は、ある一家が住む屋敷に、異形の生き物が突然訪ねて居座る話。
ゆるかわ系ニートのメタファーである。
エドワード・ゴーリー作品の中では比較的毒が薄く一般向けといえるが、実際こんなトラブルメイカーが転がり込んだら迷惑千万なので早くお引き取り願いたい。
余談だが某美術館で開催されたエドワード・ゴーリー作品展の物販では、うろんな客のマグネットが飛ぶように売れていた。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
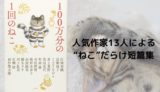 人気作家から“とらねこ”に敬意を込めて… トリビュート短篇集『100万分の1回のねこ』を読んでみた
人気作家から“とらねこ”に敬意を込めて… トリビュート短篇集『100万分の1回のねこ』を読んでみた



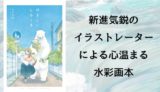
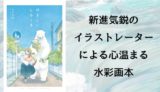
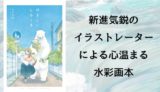
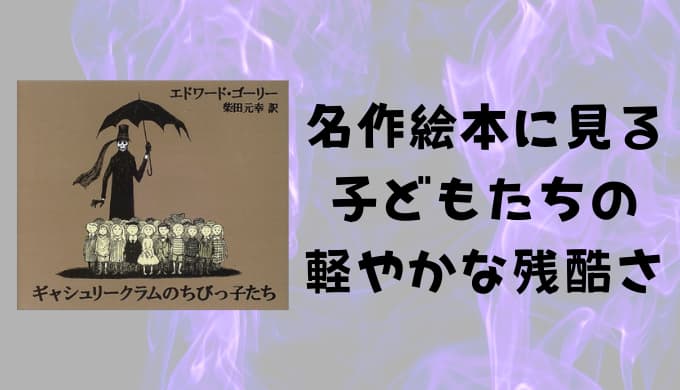


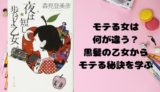

書き手にコメントを届ける