YOASOBIは非常にポップで耳馴染みのいい楽曲を奏でる音楽ユニットだが、彼らの人気を後押しするのが『タナトスの誘惑』という原作小説の存在だ。
二人今、夜に駆け出していく
楽曲『夜に駆ける』の印象的なフレーズも、小説を読んでから聴くと全く別の印象を受ける。
この記事では『タナトスの誘惑』のあらすじ紹介に加え、読むと楽曲『夜に駆ける』の印象がどのように変わるのかについてお伝えしようと思う。
目次
YOASOBIとは?ボーカロイドプロデューサー×シンガーソングライター
YOASOBIはボーカロイドプロデューサーAyaseとシンガーソングライターのikuraによる音楽ユニット。
キラキラとしたピアノの旋律がリフレインする楽曲とikuraの色鮮やかな歌声が印象的で多くのファンを惹きつけているが、人気の由来はそれだけではない。
ソニーミュージックが運営している小説&イラスト投稿サイト「monogatary.com」に投稿された小説を元に作曲しているのだ。
詳細は後述するが、YOASOBIのデビューシングル『夜に駆ける』は、「monogatary.com」に投稿された星野舞夜による小説『タナトスの誘惑』が根元になっている。
続く2ndシングル『あの夢をなぞって』は同サイトのいしき蒼太著『夢の雫と星の花』、3rdシングル『ハルジオン』は「monogatary.com」を飛び出して小説家橋爪駿輝の『それでも、ハッピーエンド』を題材にしている。
この楽曲は5月から発売されたサントリーのエナジードリンク『ZONe』ともコラボしており、その人気ぶりが窺える。
7月4日には4thシングル『たぶん』のティザー映像を公開。
9月18日には短編集『夜に駆ける YOASOBI小説集』の出版が決定している。
今まで本に触れてこなかった読者層を取り込む大きなターニングポイントになるのではないだろうか。
YOASOBI『夜に駆ける』感想と解説【物語の世界へトリップしたような没入感】
再生ボタンを押すとまずはikuraのブレスから始まり、現代的なピアノとギターカッティングへと繋がっていく。
パッと目を惹くマゼンタカラーのジャケットに誘われるが、カラフルに展開されていく楽曲から、その感覚は間違いではなかったと思った。
ボーカルikuraの歌声は基本的には無垢で明るい。
しかし、低音域は寂しさや不安を吐露しているようにも聴こえる豊かな表現力を持ったシンガーである。
プロデューサーAyaseがボカロP出身とあってか、歌声はオートチューンが施されており、現実から離れて物語の世界へトリップしたような没入感を味わえる。
Cメロの転調は非常にリズミカルでインパクトのあるサビに負けず劣らず。
耳馴染みがよく中毒性が高い。
1曲を通して、駆け抜けるようなスピードで真っ先に耳に飛び込んでくるのはピアノの旋律とikuraの声ではないだろうか。
「リリースカットピアノ」とも呼ばれているこのピアノの音色は、曲中で高い存在感を放っている。
それもハイトーンで突き抜けるような存在感があるikuraの歌声と喧嘩することなく共存している。
お互いがお互いの持ち味を理解し、見せ場ではしっかり前に出て主張し、出番でない時には後ろで静かに佇む絶妙なバランス感覚に、プロデューサーAyaseの器量が伺える。
『タナトスの誘惑』あらすじと感想・解釈【通じ合った時の甘美な痺れ】
星野舞夜著『タナトスの誘惑』
「さよなら」
彼女から届いた4文字のLINEを見て、主人公はマンションの階段を駆け上がった。
世の中には2種類の人間がいる。
生に対する欲動──「エロス」に支配される人間と、死に対する欲動──「タナトス」に支配される人間。彼女は紛れもなく後者だった。
息を切らして屋上に向かうと、そこにはフェンスの外側に虚ろな目をした彼女が立っていた。
飛び降り自殺を図ろうとするのこれでもう4回目となる。そもそもの出会いはマンションの屋上で自殺を試みている彼女を助けたのが出会いのきっかけだ。親密になっていくのに時間はかからなかった。ブラック会社に勤めながら独りきりで寂しく暮らしていた主人公にとっては奇跡のような出会いだった。
片思いの醍醐味は一方通行だったものが双方向になった時だろう。
思い通りにいかなかったらいかなかった分だけ、通じ合った時の甘美な痺れは一際大きい。
お互いの理解に齟齬があった主人公と彼女の意見が合致する瞬間、ゾワッとした感じがシミのように心の中を染めていく。
そしてその中には片思いが実ったような快楽も感じられた。
不思議な感覚だった。
好きな人との共通点探しも片思いあるあるだろう。
好きな人とその他大勢は決定的に違うとしながらも、自分と同じ部分はなんとしてでも見つけようと足掻いてしまう。
その共通項は好きな服や好きな本といった一般的なQ&Aよりも、人には公に言えないパーソナルな質問の答えが同じである方がより一層惹かれてしまうものだ。
正しいとされている模範解答よりも、2人にしか理解できない正解の方がはるかに美しい。
この主人公と彼女からはそんなことを痛感させられた。
また『タナトスの誘惑』では自殺がテーマとして扱われている。
著名人の自殺がニュースで流れた時、外から見えている景色と本人の目に映る景色はまるで違っているのだろうなとはっきりと気付かされた。
そんな当たり前のことに気付くのはいつも失った後で、残された側の人たちは悔しさと悲しみでやり切れなくなる。
この作品では自殺をある意味ではポジティブなものとして扱っている。
主人公はブラック企業に勤め、死に物狂いで働いている。
一寸先さえも見えない日々のなか、マンションの屋上で彼女と出会えたことが人生を大きく変えた。
天使のようだったと表現していることから、その喜びが伺える。
彼女がそこで自殺未遂をしていなければ、主人公の人生は物語として描けるほどドラマチックなものではなかっただろう。
幸せが十人十色であるように、誰かにとっての「救い」は、人それぞれ違う。
どんな形であろうと既存の枠に当てはめて推し量ることはできない。
自殺によって救われる人もいると思う。
そしてそれは周囲の人にはほぼ確実に理解されない。
自殺を促す人なんて恐らく居ない。
その人のことを知っていれば知っているほど、残された側になった時の苦しみは深いからだ。
彼女は「死」に希望を抱いていたのだろう。
なるべくならば現状を打破したくて選び取った明るい選択肢を肯定したい。
とは言ってもして欲しいわけではないけれど。
世界保健機関によれば世界のどこかで、40秒に1人が自殺しているという。
本人にしか見えないけれど、終わりから始まることもきっとあるのだろうと思う。
小説『タナトスの誘惑』が『夜に駆ける』の世界をさらに押し広げる
『タナトスの誘惑』を読んだ後に『夜に駆ける』を聴くとまるで聴こえ方が違ってくる。
男女2人の恋愛観のように聴こえていたストーリーが、出口を求めて足掻く1人の人間の物語に見えてくるからだ。
前記したBメロ部分はリズミカルというよりも、言葉や音がギチギチに詰め込まれている印象に変わり、切迫詰まった感情が伝わってくる。
生と死と言うシリアスなテーマでありながら、音楽として昇華された作品は極めてポップ。
この温度差はかなり衝撃的で病みつきになる。
あくまで一体験者としての感想だ。
大いに余白を残して作られている「音と言葉の遊び場」は、人によって抱く感想が全く違うのだろうと思う。
読者の方々にも是非とも体験してみてほしい。
おわりに
言葉で紡がれている作品と、音で表現された作品。
手法が違う2つが重なる部分がお互いの深みをさらに引き出している。
一旦足を踏み入れると、身動きをとっている間にどんどん沈んでいってしまう。
言葉と音の沼だ。
求めれば求めるほど、物語を細部まで味わい尽くせる喜びがある。
コロナ禍でライブができない昨今、音楽業界は危機的状況に直面している。
そのなかで、ライブが出来なくともアーティストの深みを音楽と共に文章で楽しめるYOASOBIは現状に一石投じることできる唯一無二の音楽ユニットになり得るのでないだろうか。
エンターテイメントの新しい可能性を感じた。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 住野よる「音楽」を語る【THE BACK HORN・志磨遼平・sumika・BiSH】
住野よる「音楽」を語る【THE BACK HORN・志磨遼平・sumika・BiSH】



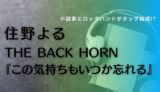
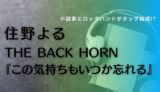
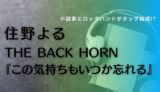
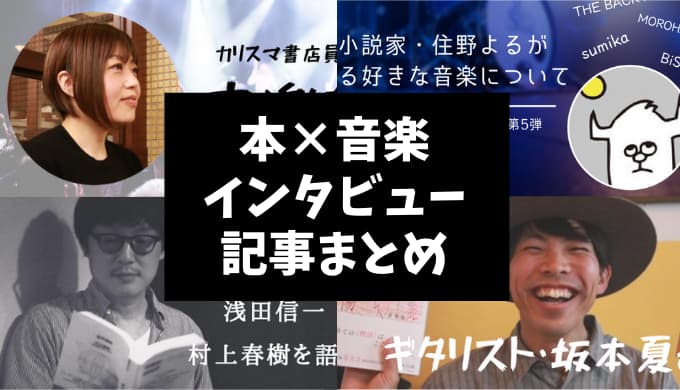
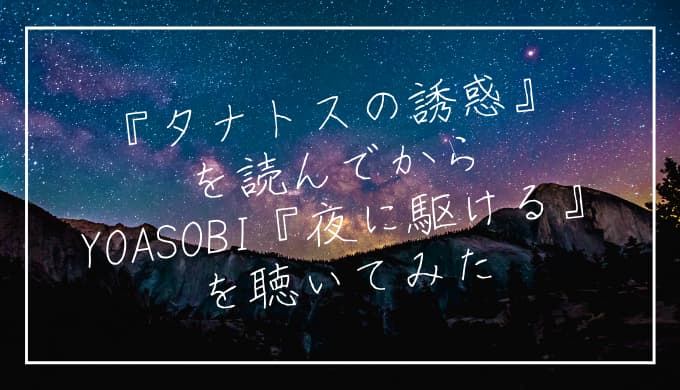

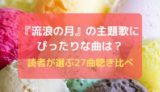
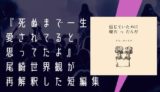
書き手にコメントを届ける