住野よるは自他共に認めるロック好きの作家である。
過去にインタビューをさせて頂いたことがあるが、音楽への愛着は凄まじいものだった。
音楽の話になると目がキラキラとさせ、その様子はライブ会場にいるキッズを彷彿とさせた。
目次
本と音楽というカルチャーを1つにする橋渡し的な役割を担ってきた
2作目として出版された『また、同じ夢を見ていた』は著者が『君の膵臓をたべたい』よりも先に書き下ろした作品だ。
この作品はロックバンド10-FEETの同名楽曲からインスピレーションを得て誕生していたという経緯がある。
『青くて痛くて脆い』ではプロモーションの一環として、本のMVが製作されている。
起用されたのは青とも縁のあるBLUE ENCOUNTの『もっと光を』。
BLUE ENCOUNTは今年9月にリリースされた『ユメミグサ』で劇場版『青くて痛くて脆い』の主題歌も担当している。
『麦本三歩の好きなもの』では表紙にBiSHのモモコグミカンパニーを起用。
ふとした表情が主人公を彷彿とさせたためだと語っている。
さらに音楽へ接近した作品を挙げるならBIGMAMAのシングル『DOPELAND』も欠かせない。
収録されている楽曲『愛はハリネズミのように』を元に作られた書き下ろしの掌編小説が作品の一部として落とし込められている。
『君の膵臓をたべたい』の主題歌に抜擢されたSumikaが2018年にリリースしたシングル『ファンファーレ / 春夏秋冬』の初回限定盤には『君の膵臓をたべたい』のショートストーリー『日々の透き通るもたれ合い』が書き下ろされたことも有名だ。
音楽を愛するリスナーは本を読むきっかけに、本が好きな読者は音楽の入り口として、それぞれのカルチャーを1つにする橋渡し的な役割を担ってきた。
本と音楽による完全共作『この気持ちもいつか忘れる』
上記の作品は住野よる名義の出版物というよりは、アーティストの作品に住野よるが寄稿したという形式に近い。
音楽的に言えばfeat.だ。
しかし、先月発売された『この気持ちもいつか忘れる』は、本と音楽による完全共作である。
先ほどがフューチャリングだとするならば、今作は異色の2組がタッグを組んだスペシャルユニットである。
例えるならばRHYMESTERのMummy-DとSUPER BUTTER DOGの元ギタリスト竹内朋康によるマボロシであり、ハナレグミとフジファブリックによるハナレフジであり、桜井和寿(Mr.Children)とGAKU-MCによりウカスカジーだ。
単なる客演とはまたひと味違った有機的な繋がりが、物語に、そして音楽にさらなる深みを与えている。
今作を共に作り上げるためにディレクションされたのはロックバンドTHE BACK HORN。
THE BACK HORNは1998年に結成されたオルタナティヴロック・バンドで通称“バクホン”と呼ばれている。
メンバーは山田将司(vo)、菅波栄純(g)、岡峰光舟(b)、松田晋二(dr)の4名。
“KYO-MEI”という言葉をテーマに、心をふるわせる音楽を届けていくという意思を掲げており、非常にエモーショナルなロックサウンドを掻き鳴らすバンドだ。
『この気持ちもいつか忘れる』の初回生産分には、なんとTHE BACK HORN の新曲が5曲入ったCDが付いてくる。
住野よるが書いたあらすじに対して、THE BACK HORNが『ハナレバナレ』を書き下ろし、それを聴いた著者が更に小説を書き進め、そこからTHE BACK HORNがまた新たに楽曲を製作するという、ある意味ジャムセッション的な手法で作られている。
”影響”が1つのキーワードとなっていて、異なる2つのジャンルは互いに確かな影響を及ぼし合いながら1つに溶け合っていく。
『この気持ちもいつか忘れる』あらすじ
退屈な日常に飽き飽きしながら暮らす高校生のカヤ。
平凡なクラスメイト達を内心で見下しながら、自分自身も同じくつまらない人間であることを自覚していた。
そんなカヤが16歳の誕生日を迎えた直後、深夜のバス停で出会ったのは、爪と目だけしか見えない謎の少女だった。
突然のあまりに思いがけない出会いに、動揺するカヤ。
しかし、それは一度だけのことではなく、その後、カヤは少女・チカと交流を深めていく。
どうやらチカはカヤとは異なる世界の住人らしい。
2人の世界には不思議なシンクロがあり、チカとの出会いには何かしらの意味があるのではないかとカヤは思い始める。
『ハナレバナレ』の特殊な構成がカヤ・チカの姿と重なる
付属されているCDは疾走感溢れる『ハナレバナレ』からスタート。
エッジの効いたロック然とした楽曲で、『この気持ちもいつか忘れる』を書き上げていく上で非常に重要なポジションを任命されている。
そういう視点から見ても”ハナレ”、”バナレ”という似て非なる文字同士の呼応性はまさにカヤとチカをイメージさせ、字面だけ十分にファンを楽しませてくれる。
基本的に、音楽はAメロ、Bメロ、サビと進行していくのが最も聴きやすいとされているが、『ハナレバナレ』はいきなりサビのようなパートから始まる。
その後にサビが別に用意されていることから考えても、サビでありサビではない
特殊な構成は、やはりカヤとチカの姿が重なった。(便宜上、サビ2と呼ぶ)
Aメロ、Bメロ、サビと王道のルートを通った後に再びサビ2となり、2番に至ってはAメロ、Bメロの後、一度ロック色から離れてドリーミーなCメロに転調していく。
全く予想不可能なドライブ感にリスナーは翻弄されてしまう。
まさに恋愛の持つ絶対的な引力のよう。
そしてようやくサビに突入、そのままサビ2に流れていくという非常にスリリングな楽曲構成だ。
〈爪が心に刺さって〉、〈君という光〉など、歌詞中には小説とリンクしたフレーズが多く潜んでおり、物語の濃度を高めている。
『ハナレバナレ』のみに限らず、この1枚にはそういう作用が随所で見受けられた。
空っぽな世界で 空っぽな心を埋めてゆく
これは作中の物語にも登場している“歌”、「輪郭~interlude~」の1フレーズである。
本文にもある歌の作詞を担当しているのはTHE BACK HORNのドラム松田晋二だ。
著者が書き上げた小説では、著者は神のような絶対的な存在であり、正の世界である。
そこに著者ではない他者による文章が混ざってくることにより、読み慣れた文章とは違った文に触れることから、カヤが感じた”異なる世界”に対する感覚を読者も追体験できる。
さらに「輪郭~interlude~」には映画音楽作曲家でシンガーソングライターの世武裕子がボーカルで参加。
楽曲以前に物語が存在していることにより、世武裕子の深みのある歌声が、圧倒的な没入感を与える。
フィクションを限りなくノンフィクションに近づけてしまう魔力のようなものを感じた。
その一方で「輪郭」のフルバージョンには住野が作詞で参加。
〈産み落とされた〉から続くCメロの4行だけであるが、確かな存在感を放ち、お互いの影響力をより確固たるものにしている。
音楽はリリースが確定すると、事前に収録曲やバンドによっては先行して歌詞がアナウンスされる。
小出しにされた情報によって生まれた疑問は、実際に楽曲を聴き、ようやく「そういうことか」とカタルシスを得る。
『この気持ちもいつか忘れる』でも近いもの感じ取った。
住野よるの持つレトリックは音楽体験にも似た味わいがあると痛感させられる。
主人公・カヤの泥くさい人間性がTHE BACK HORNと重なる
異世界に住む者同士の恋愛を描いたストーリーの背景では、“戦争”が一際存在感を放っている。
戦争と恋愛というコントラスト差もなかなかインパクトがあるが、これはTHE BACK HORNによる影響が大きいのではないだろうか。
彼らの代表曲「コバルトブルー」は特攻隊からインスパイアを受けて作られていることに加え、「罠」や「8月の秘密」など歌詞中に戦争をイメージさせるフレーズが多くあったりと、バンドのなかに戦争がチラリと垣間見える。
また主人公カヤの性格もTHE BACK HORNからインスパイアされているように思う。
端的に言ってしまえば、カヤは心の扉を堅く閉じ、ほぼ全てのものに悪態をつくような捻くれた性格だ。
老若男女、幅広い読者層を持つ住野よるの描く主人公として、ファンから多くの共感を得られる人物とは正直なところ、思えない。
が、著者の作風を考えると、どちらかというと消極的な登場人物が多いなかで、カヤは他のキャラクターに比べてかなり行動的で、一際異彩を放っている。
暴走気味がデフォルトなカヤは、まるでロックの源泉にある破壊衝動をそのまま擬人化させたような人物だ。
過度な暴走っぷりで、真っ向からカヤの気持ちを否定したくなってしまう時もあれば、行動を起こしている姿に爽快感のようなものを感じることもある。
一筋縄ではいかない、そういう泥くさい人間性がロックミュージックひいてはTHE BACK HORNと重なっていく。
カヤとチカの交流は非常に刺激的で、どこか暴力的とさえ感じた。
異なる思考がぶつかりあい、自分の中の確固たるもの、または当たり前過ぎて考えたこともなかった常識(と勝手に思い込んでいたもの)が音を立てて崩れ去り、自身の知力や思考が丸裸になる。
突き放されたような感覚に陥った。
姿も共通の思考もない。
一部分しか分からないからこそ、逆説的に表情や感情が浮かび上がってくる。
爪と目しか見えないチカが、いきいきと躍動できる場所は読者各々の脳裏であり、文章だから成せる表現方法だと痛感させられる。
初めて読んだ時の感動は薄れていっても、初めて楽曲を聴いた時の衝動を忘れていっても、人が愛情を持って生み出した創作物の温もりはいつまでも心の中に残り続けるのではないだろうか。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
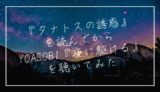 小説『タナトスの誘惑』を読んでからYOASOBI『夜に駆ける』を聴いてみた
小説『タナトスの誘惑』を読んでからYOASOBI『夜に駆ける』を聴いてみた
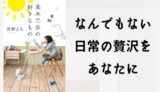
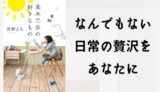
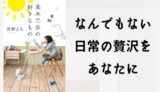



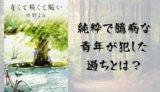
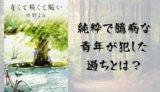
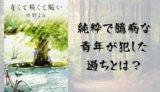
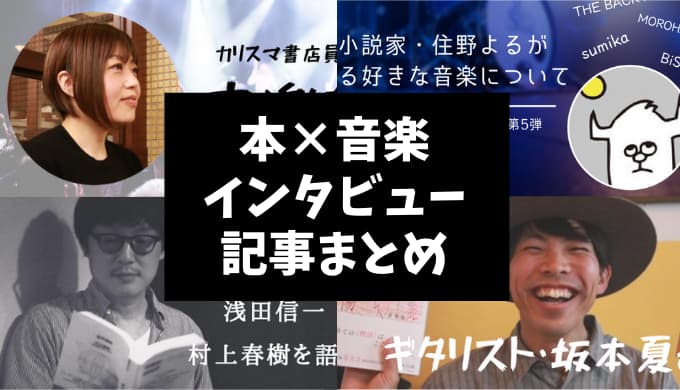





書き手にコメントを届ける