Creepy Nutsは今人気急上昇中の1MC、1DJのヒップホップユニットだ。
MCのR-指定は2012年〜2014年の“ULTIMATE MC BATTLE”の全国大会で3連覇を果たしたラッパー。
バラエティ番組「フリースタイルダンジョン」ではラスボスだった般若からバトンを受け継ぎ、2代目ラスボスに就任している。
トラックメイカーを務めるのはDJ松永。
2019年に行われたDJの世界大会「DMC WORLD DJ CHAMPIONSHIP FINALS 2019」のバトル部門で優勝を成し遂げている。
お昼のラジオ番組「ACTION」では1年半に渡り水曜日のパーソナリティを担当していた。
軽快なトークが人気を博し、バラエティ番組でも多数出演。
日本一のラッパーと世界一のDJが組んだ最強コンビだが、学生時代の部活では2人ともベンチウォーマーだった。
R-指定は遅刻癖がひどく集合時間に遅れることもしばしば。
大阪に住んでいる母親に部屋の掃除をさせることもある。
DJ松永は歯に衣着せぬ物言いで相手を困惑させてしまうことも多く、潔癖症で自宅はサイコ部屋だと揶揄されるほど。
輝かしい成績を残していながら、不完全な部分がある。
Creepy Nutsと“たりないふたり“、相思相愛の関係性
◆TV出演◆
【番組名】
スペースシャワーTV
Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」SPECIAL【放送日時】
9月4日(金)23時~24時【番組H.P.】https://t.co/8ipSDskoO3 pic.twitter.com/sYXwnBFr1S
— Creepy Nuts (@Creepy_Nuts_) August 31, 2020
デビューを飾ったEPは2016年にリリースした「たりないふたり」。
楽曲は自らの不完全な部分をコミカルかつポップに昇華したものであるが、南海キャンディーズ山里亮太とオードリー若林正恭によるコンビ“たりないふたり“に感銘を受け、リスペクトを込めて制作されたものでもある。
R-指定もDJ松永もド級のラジオリスナー。
R-指定は「山里亮太の不毛な議論」を聞いて育ち、DJ松永はリトルトゥースだ。(「オードリーのオールナイトニッポン」のリスナーの呼称)
人見知りで女性が苦手、飲み会が嫌いといったお笑い芸人らしからぬ山里・若林の立ち位置と、不良で重厚なアクセサリーをつけたラッパーが覇権を握るヒップホップ界でのCreepy Nutsの立ち位置はかなり似ている。
ユーモラスなジャケットはラッパー、テークエムによって描かれたもので”たりないふたり”へのオマージュがある。
リリックは自己紹介のようでいて、“たりないふたり“のために書き下ろされたようにも聴こえる。
楽曲はどんどん広まっていき、本人の耳にも届いた。
山里はラジオで掛け、ヒップホップ好きの若林は番組スタッフに口コミするなど、ファンの間で話題になった。
2019年に行われたライブイベント「さよなら たりないふたり~みなとみらいであいましょう~」では「たりないふたり」を”さよならver”と改めた楽曲がテーマソングに抜擢。
非公式にサンプリングされた音楽が正式に番組からオファーを受け、テーマソングになる様子はまさにヒップホップドリーム的でとても清々しいものだった。
また2018年にリリースされた「よふかしのうた」は若林から直接話を受けて制作した楽曲で、ライブイベント「オードリーのオールナイトニッポン 10周年全国ツアー」のテーマソングとなった。
MVは春日が住んでいたむつみ荘で撮影されており、オードリーが準優勝した2008年のM-1の映像がチラリと写る。
楽曲は深夜ラジオがモチーフとして描かれており、オールナイトニッポンでお馴染みの「ビタースウィート・サンバ」をサンプリングしているなど、随所に遊び心がある。
Creepy Nutsは「オールナイトニッポン0」のパーソナリティを務めており、過去には若林をゲストとして自身の番組に呼んでいる。
さらに10月7日に文庫化される若林の著書『表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬』にはDJ松永が解説を担当することも発表された。
Creepy Nutsと”たりないふたり”は切っても切れない関係にある。
ライブの熱量を感じる山里亮太『天才はあきらめた』
山里亮太の名著『天才はあきらめた』はCreepy Nutsの「助演男優賞」を想起させる。
いつ来るか分からないチャンスを物にするには血の滲むような努力が必要だ。ステージ横から虎視眈々と主役の座を狙っているギラつき感と山里が反省ノートに書き綴っていた恨み辛みが絶妙に重なり合う。
言葉数という点でも、幾重に掛けられた意味でもぎっしり詰め込まれたリリックとスピーディーでスリリングなヴァースには現場の熱量を感じ、ライブ映えする楽曲だと分かる。
『天才はあきらめた』の文章には下手に触ったら火傷してしまうほどの熱がある。
その熱っぽさはライブに近く、吉本の劇場に座って目の前で漫才を見ているような、現場特有の焦燥感を感じる。
妬み辛みをこねくり回し歪ませ、1周回った前向きな負の感情が本書の見所でもある。
その筆圧にくらってしまうシーンも多々あったが、その感覚を再び思い出したのが2020年に放送されたお笑い番組「史上空前!! 笑いの祭典 ザ・ドリームマッチ」だった。
コンビをシャッフルし、フィーリングカップル形式で決まった新コンビで芸を披露するという番組だったが、山里が異様なほど春日に執着していて、その姿に怨念のような、おどろおどろしさを感じた。
「たりないふたり」を聞いた山里がR-指定に初めて会った時に放った一言は、
「若林のリリックが多い」
である。
少しゾッとしたのと同時に、細部まで追求する神経質さ、監視ともいえる観察眼が根っこにあるからこそ、人間味豊かな山里の魅力は膨大に広がり続けているのだと感じた。
『天才はあきらめた』の解説は若林が執筆。
そこには山里の魅力がこう綴られている。
日々の仕事や生活で追った傷を、彼は隠さずに見せる。
まさに”たりないふたり”のスタンスだ。
山里の触れて欲しくないところをイジり、逆にイジって欲しそうなところは敢えて触れない。
天の邪鬼な若林が山里に新しく傷を負わせ、生き血が吹き出すからこそ、リアリティーが生まれ、斬新さが生まれ、山里のワードセンスがより輝きを放っていく。
その破壊と再生、または暴走と内省は『天才はあきらめた』のなかでもしっかり描かれていて”たりないふたり”とも地続きになっている。
このユニットは山里がいたからこそ誕生したのだ。
また、本書の中には”オードリー“の文字は1文字も出てこない。
尊敬しているが引き離されてしまう恐怖もある、嫉妬の対象だからこそ出てこないのだという。
若林を今でもライバル視する一方、若林は山里を家族だと思ってる。
解説には、
ワードでは絶対に山里亮太には勝てないから
とも記述されており、お互いの認識の違いが感じられる。
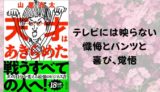 『天才はあきらめた』あらすじと感想【みみっちいのはそれだけ真剣だから】
『天才はあきらめた』あらすじと感想【みみっちいのはそれだけ真剣だから】
ラジオの熱量を感じる若林正恭『ナナメの夕暮れ』
笑いどころが巧妙に計算されていた山里のエッセイに対して、若林のエッセイ『ナナメの夕暮れ』は文章に余白があり、読者に考える時間を与えているようにも感じ取れた。
熱すぎず冷たすぎず、良い距離感で接してくれる。
山里がライブの熱量ならば、こちらはラジオの熱量と言っても良いだろう。
本書を読む前に『天才はあきらめた』を読むと、若林が自身を描くことによって、対照的に山里の人格が浮き彫りになっていくのが分かる。
試すってすごく楽しいことなんだ。何かがうまくいく喜びには、それまでうまくいかない苦しみが必要不可欠だ。
成功の喜びのためにミスを楽しむ若林とは対照的に、山里はミスを楽しんでいるようには感じられなかった。
取り憑かれたかのように完璧を求め、その結果としてトライアンドエラーを繰り返しているようだった。
もっと完璧になるために敢えて試される環境に身を置き、自ら退路を絶ち、自分を追い込んでいく。
ある意味ストロングスタイルである。
その副産物として生まれたのが”たりないふたり”でもイジられていた”SMプレイ”なのだろう。
若林によって綴られている『天才はあきらめた』の解説にはこんな一幕がある。
こんな天才が(あ、最後に言おうとしてたのにもう言っちゃった)
最後に書こうとしていたのに、早速もらしてしまうこのポロリスタイルは、”たりないふたり”で情報解禁日を待たずフライング告知してしまう暴走若林の片鱗を感じてニヤついてしまう。
バラエティ番組「あちこちオードリー〜春日の店あいてますよ?〜」や「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。」などオードリーの番組にはゲストが来ることが多いが、誰と共演しても嫌な空気になることが全くない。
ゲスト目当ての人はもれなくオードリーも好きになってしまうし、オードリー目当ての人はゲストを好きになるピースフルな魔力がある。
それは春日の力やコンビの空気感など様々な要因があるだろうが、ここでは若林の持つ、度量の広さに注目したい。
『ナナメの夕暮れ』には若林が誰かに質問を投げかけている描写が非常に多く見受けられる。
自分と誰かが交わり、そこで生まれたものを誠実に掬い取って改めて自分の意見を述べる。
長年自身の内面を見つめ続けることで自然と培われた掘り下げ力と、疑問という苦しみから解放されたくて身についた質問力が、ここに来て最大限に活かされているように感じた。
また、「ズレ漫才」という新しい笑いが発明された経緯については下記のように綴られている。
ぼくらの漫才で、相方が遅れて出てくるのは、元気よく袖から出てきて「よろしくお願いしまーす」なんて丁寧に挨拶する漫才師への青いアンチテーゼだった
Creepy Nutsもヒップホップシーンに対するアンチテーゼが感じ取れる。
筋骨隆々じゃないナードな奴でもヒップホッパーになれることを知らしめたのだ。
そこにはオードリー、更に言うなら当時は珍しかった男女コンビであり、困惑に近い新しいツッコミを開発した南海キャンディーズのシルエットを感じずにはいられない。
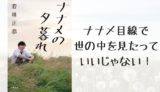
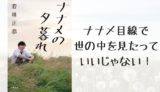
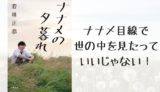
次のページ
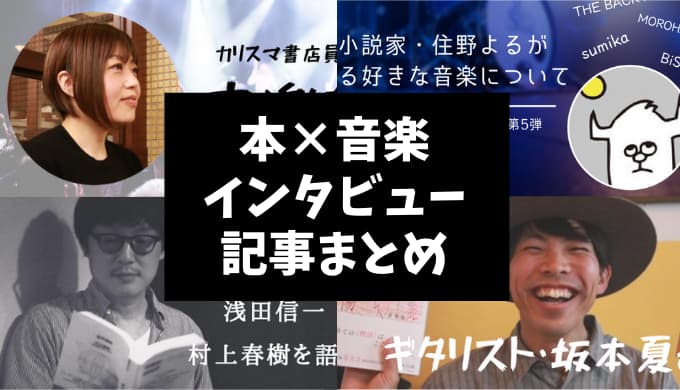
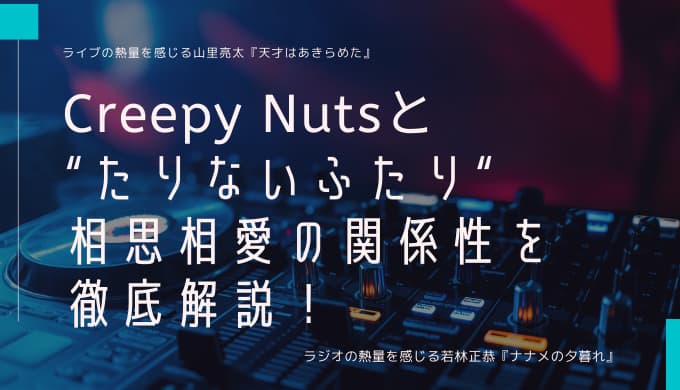
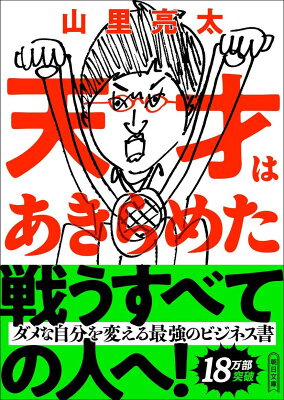
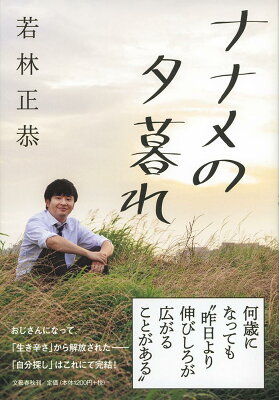
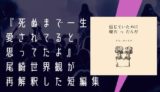
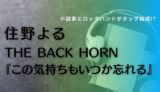
書き手にコメントを届ける