表現者というものは脳内にあるイメージを形にする仕事だ。
それは文章や音楽だけには限らない。
この企画は本来、本と音楽の親和性を発見し紹介する企画である。
今回はその企画を拡大解釈し、内なるものを表出する生業をアーティストとして括り、多方面で活躍を見せている紗倉まなにフォーカスを当てた。
アーティストとは、芸術家、美術家の他に、その道のプロフェッショナルという意味を持つ。
誤解を恐れずに言えば、紗倉まなはAV女優、文筆家、タレント、アイドルして活躍するアーティストである。
紗倉まなとは?
1993年千葉県生まれ。工業高等専門学校在学中の2012年にAV女優としてデビュー。15年にはスカパー!アダルト放送大賞で史上初の三冠を達成する。
著書に映画化もされた初小説『最低。』、『凹凸』、エッセイ集『高専生だった私が出会った世界でたった一つの天職』、『働くおっぱい』、スタイルブック『MANA』がある。
アイドルとしての表現
昨年も変わらずおとといフライデーを応援頂きありがとうございました!
令和2年もおとといフライデーらしさを全面に出して、新しいステージに向かって全力で頑張ります。応援よろしくお願いいたします! pic.twitter.com/9dbZ5QB8xx— おとといフライデー(OTOTOY FRIDAY) (@otome_f) December 31, 2019
幅広い活躍の1つとして、「おとといフライデー」というユニットでアイドル活動が挙げられる。
紗倉まな、同業者である小島みなみで結成されたアイドルユニットだ。
アイドルという形式を持ちながらも、全裸まで知ることが出来るという点でいえば、非常に型破りなアイドルと言えるだろう。
「私ほとんどスカイフィッシュ」の作詞は、タモリ倶楽部でもお馴染みのトリプルファイヤーの吉田靖直が手掛けていたり、「ENIGMA」はライブハウスで存在感を放ってるバンドHave a Nice Day!の浅見北斗がプロデュースに参加しているなど、知る人ぞ知るディープなアーティストが制作陣として参加していることでも話題だ。
小島みなみ、紗倉まなによる肩肘張らないボーカリゼーションは、かなり自然体でPUFFYを彷彿とさせる。
それはバラエティー番組などで見せる親しみやすいキャラクター性にも引っ張られている影響だと思うが、歌唱という基本的には肉声だけで形成された表現に培われた、女優としての表現力が活かされている。
AVでの表現
AV女優とはセックスを演じる女優のことだ。
紗倉まなは下町っぽい親しみを込めてエロ屋と呼んでいる。
“演じる”は自身の存在感を消し、作中でのキャラクターを表出させることが基本的に求められるが、AVにおいてはかえって自分を出すことが求められる条件だろう。
その上で指定された役柄を自分自身に纏い、設定にいくら無理難題があっても、リアリティある作品に仕上げられるかが必要不可欠となる。
江戸時代に浄瑠璃、歌舞伎の作者だった近松門左衛門が唱えたとされる芸術論に、虚実皮膜(きょじつひまく)というものがある。
実と虚の境に微妙なラインに存在し、その狭間にこそ真の芸術があるとする論法だ。
彼女たちが演じている内容は往々としてどこまで本当なのかかなりグレーゾーンである。鑑賞して楽しむ作品であるため台本や演出も存在しているだろう。
全て本当に見えるが、そうではないところもあることと思う。
紗倉まなは見事に役柄になり切っていて、鑑賞者に没入感を与え、虚実のラインを曖昧に濁していく。
どうすれば視覚的に最も興奮材料になるか研究し尽くされた演技に加え、文字通り体当たりのアクションは視覚だけでなく聴覚の刺激も生み出している。
演者と鑑賞者同士が間接的でありながらも近い温度感でなければいけないため、その両者には高度な感度を要する。
ある意味では飛躍を遂げて発展したカルチャーとも言えるのではないだろうか。
非常に娯楽性が強い世界で活動する紗倉まな、およびAV女優たちは紛れもなく芸能の一端を担うアーティストである。
音楽業界に似てシビアなAV業界には次々に新星が現れ、その一方で人気が落ちた人物は淘汰されて舞台を去る。
第一線で活躍をする人物の偉大さを実感してしまう。
エッセイでの紗倉まな
著者のエッセイ『働くおっぱい』では普段見られない内情が曝け出されている。
ロジカルな思考で紡ぎ出される数々の言葉は、圧倒的に説得力があり読者に新しい発見をさせてくれた。
時に重く、時にかるーく、変幻自在なウェイトで綴られているため、心地よいリズム感で楽しめる。
ちなみにタイトルである「働くおっぱい」とは、おっぱいを出して働いている著者の様子を表していると同時に、”胸”を動かして働いているというニュアンスも含まれているのも面白い。
この面倒くさいという感情を乗り越えるほどの熱量が、お金の使い道には必要だったりする。自分がどうしたら心と体が満たされるのかが明確にわかっているからこそ、注ぎ込む対象が決まってくるわけで、所謂、自分という会社の必要経費でもあったりする。
様々な要素で構築されている自分を分解していくと、自由な時間の過ごし方や息抜きという色味が必然的に織り交ぜられ、その糸が案外太く絡まっていたことに気が付くのではないだろうか。その自由な時間のために、その息抜きの行為のためにも、働くことに意味がある。
引用部分は、著者がネイルにときめくも、「めんどうくさい」という壁にぶつかってしまった時の文章だ。
モヤモヤした感情を解体し、丁寧に洗い出すことで、見にくかったものが水のように飲み込みやすく変容されている。
自身が本当に思っていること、周囲からの自分と自分自身の乖離、求められている人物像としての役柄など解像度の高い分析結果が多く見受けられ、それらとしっかり向き合う真面目な性格が滲み出ている。
そのためには根気も必要だからこそ、タフな一面も持っているだろう。
負の願望が、AVというフィルターを通すことでフィクションとして成立して、現実世界において抑制されているなら万歳!ってなるけどさ、それを鵜呑みにされたり女性側に強いてしまうことになってしまったら、という恐怖感もあるのだよな。
一般的にタブーとされている作品がAV業界では人気であることに対して著者が感じた率直な気持ちも綴られている。
表現者として、AV業界内のマジョリティーに受ける人気作品を作ることは大事なのだけれど、紗倉まなである以前に、1人の女性としての心情に彼女ならでは葛藤が見受けられた。
『働くおっぱい』は読者の心身の性別で刺さる部分は大きく異なるだろう。
女性が働くこと、生きることについて本音が吐露されている部分もあれば、ファンサービスに近い”紗倉まなならでは”の表現で男性を掴む文章もある。
バラエティに富んでいて読み手を選ばないポップさが感じられた。
エッセイとは活字に起こされた裸体である。
聡明な頭脳を持っている彼女だからこそ、打算的に書いている部分もあるかもしれないが、基本的に著者の本心が垣間見える。
映像での表現の源泉を知ることが出来る潔いエッセイだ。
映像でのパフォーマンスは先天的な感性によって引き出されているのだとばかり思っていたが、著書を読むとそれは間違い(ある程度の正解はあるかもしれない)で仮説に基づいた、理知的な思考と勤勉な姿勢から生まれた武器なのかもしれない。
最新作『春、死なん』
2020年2月に刊行された最新作『春、死なん』は第42回「野間文芸新人賞」の候補作品にも選定されている。
本作は二部構成になっており、そのうちの一編が以下のあらすじだ。
「春、死なん」
妻を亡くして6年の70歳の富雄。
理想的なはずの二世帯住宅での暮らしは孤独で、何かを埋めるようにひとり自室で自慰行為を繰り返す日々。
そんな折、学生時代に一度だけ関係を持った女性と再会し…。
富雄はライフステージの最終段階に突入し、無味乾燥の生活を送っている。
それどころか、自身の老いに対して体がついて行かず周囲の人から困った人として扱われてしまう。
小説における紗倉まなの表現は非常に生々しいものがある。
ぞわぞわとする嫌悪感のある描写は脳裏に映像として容易に焼き付く。
二十代半ばである彼女は、当然ながら老人男性の苦悩なんて経験しているはずがないのに、読者のメンタリティーを70歳男性に引き上げ、主人公の抱えてる苦しみを読者にも味わせてしまう魔力を持っている。
人生の幕引きが確実に迫っている底知れぬ苦々しさ、息子夫婦との二世帯住宅に抱えているわだかまり、自分と世間との溝。
途方もない現実の数々が、時に死の気配すらも孕みながら圧倒的な孤独感を痛感させられた。
映像作品で様々な女性像を演じ、培われた想像力がこうして全く別次元で活かされていることに驚かされる。
枯渇した生活に潤っていく解放感ある描写では前述したものが逆説的に効力を持ち、生きる喜びを体感する。
そしてその表現方式にまんまとやられてしまうのだ。
生きることと死ぬこと、その狭間にある老いること。
性を通じて人生そのものを感じる。
性をテーマにしていながらも作中でフォーカスされているのが、若い男女ではなく、欲求のピークを過ぎた、旬ではない人物だからこその輝きがあった。
雌と雄の生物学的な区別を示す性(せい)と、生まれつきの性質、持って生まれた運命を意味する性(さが)。
この物語を読んで、その2つに同じ漢字を当てられていることに対して妙に納得した。
生殖器官というとても厄介なものと死ぬまで向き合わなければならない徒労と、存在証明の権化とも言える性衝動の圧倒的なパワー。
その表裏一体が、良し悪し全てひっくるめた巨大な渦になって飲み込まれそうになってしまった。
そのとき、開けられた窓から入ってきた羽虫が一匹、壁に止まった。里香はしばらく、何かを考えるようにその黒い小さな一点を見つめた。しゃがんで、床に転がっていたティッシュ箱から一枚しずかに引き抜き、たたんで重ねた。息をひそめ、そーっと、獲物を狙う獣のように滑らかに近づくと、壁を汚さないように羽虫を摘み取り、手の中にまるめてつぶした。ぞっとするような穏やかさだった。
個人的にこの表現は震え上がった。
たわいのない行為に過ぎないのに、そこに狂気の匂いを感じさせてしまうほど緻密に練り上げられた構成と、どこか暴力性を持った文章に紗倉まなの筆力を感じる。
紗倉まなという表現者の底が全く見えなくて恐怖すらも覚えた。
次のページ
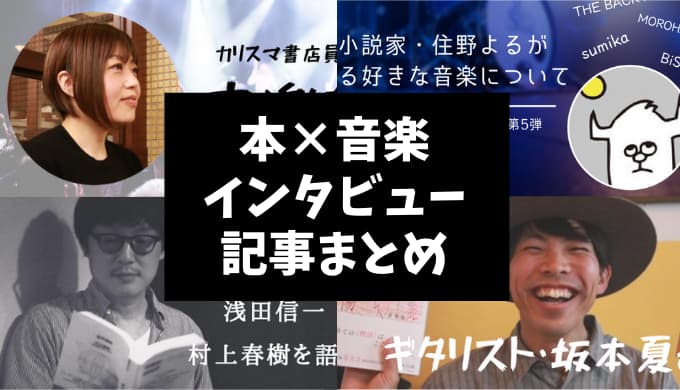




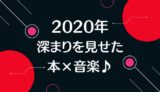
書き手にコメントを届ける