目次
『夜行秘密』に見られた前作とは違うカツセマサヒコの新たな挑戦
前作『明け方の若者たち』とは、細かい変化が見受けられる。
実際の場所や固有名詞を巧みに使うことによって、作品の評価をより確かなものにしてきたが、今回の小説は架空の街が舞台になっている。
例えば、燃え殻著の『ボクたちはみんな大人になれなかった』や映画『花束みたいな恋をした』など、固有名詞を多く盛り込んだ物語が人気を博している。
それは近年顕著に見られる傾向ではなく、ずっと使われている、ある意味王道的なやり方だ。
それに抗うかのように『夜行秘密』では特定の場所は表れない。(唯一出てくるのは東代田駅のすぐ近くライブハウスは新代田Feverを捩ったものであると思われるが、架空の駅である)
実在する場所を用いると必ず制限がつくし、読者全員が分かるとは限らない。
その点、架空の街ならば、誰しもが自由に描くことができる。
前者がA4の塗り絵に色を塗っていくことだとしたら、後者は6畳の画用紙に自由に街を書くというくらいフレキシブルさが違う。
しかし、塗り絵の題材が細部まで描かれた良く知っている場所であれば、それだけで楽しい。
読者がそこに自分の思い出、自分の色を重ねることができるというメリットもある。
非常に便利な小技であるが、前述した通り、分からない人も少なからずいる。
言うなれば諸刃の剣とも言えるだろう。
今作において、カツセはその手法に頼らず、素手を選んだ。
まっさらな画用紙を使うことで、読者一人ひとりに背景を委ねた。
小さなことかもしれないが、なかなか勇気がいる決断だと思う。
実際の街を使えば、刺さる人にはより鋭利に刺さるし、indigo la Endと東京の情景の相性が良いことは明白だからだ。
それらを削ぎ落とすことで、物語に集中してもらいたいという想いがあったのだろう。
背景を架空の街にしたことで、余白が生まれ、読者だけのオリジナルな世界が完成された。
そこに時代性や自身の思考をブレンドすることによって、新境地が開拓され、indigo la Endも予期していなかった楽曲の新たな可能性が生まれている。
indigo la Endのアルバム『夜行秘密』
『夜行秘密』は今年2月にリリースされた通算7枚目のアルバムである。
川谷絵音はこのアルバムについて、改めて“バンド”であることを見つめ直したと明かしている。
スタジオで集まって楽器を演奏せずとも、パソコン1台あれば音楽が完成させられるこの時代に、indigo la Endはスタジオに入り、バンドとして音楽を作っている。
今作はストリングスアレンジが抑えられており、バンド内で完結している曲が多い。
川谷は
やりすぎるのはよくないから、ちょっと余白を残しておきたかった。
とコメントしている。
人によって様々に解釈できる散文的な歌詞と、余白のあるサウンドアレンジだったからこそ、小説化された時に予想外の空路が開けたのではないだろうか。
indigo la Endの高い表現力
生の楽器はチューニングや、プレイ、環境によって音が微妙に異なる。
それが、リードギター、リズムギター、ベース、ドラムなどそれぞれの楽器に起こるため、理想のテイクを取るのは簡単なことでは無い。
一方で音楽ソフトに登録されている音は常に正しく、強弱も簡単に付けられる。
打ち込み楽曲の方が、当然作りやすいし、強い音がはっきり聴こえるためCDよりも音質の劣るサブスクでも聴きやすい。
それらを踏まえた上で、indigo la Endはバンドとして鳴らしている。
昨今の流行などを考えるとオールドスクールなスタンスではあるが、彼らの鳴らす音は無骨さも繊細さもあり、アルバムとしてかなり魅力的な作品になっている。
それは楽器隊の表現力の高さによるものであることは明らかだ。
彼らは昨年、結成10周年を記念して人気楽曲25曲のインスト音源をベストアルバムとしてデジタルリリースした。
『藍楽無声』と名付けられた1時間45分の作品は様々な視点から、時代の流れとは逆行している。
まずボーカルがなければ分かりにくくて聴く人は少ない。その上、昨今のアルバムは1時間以内にまとめられたものが多い。
ただ、普通のベストアルバム(どこかのタイミングで出すだろうけど)としてリリースしない辺りが尖っているなと思う。
インストでも全く違和感はないほど完成度が高く、楽曲がどれだけ緻密に構成させているのかが分かる。
インタビューにて楽器隊のメンバーは今作のプレイについて下記のように語っている。
ドラムの佐藤は
「夜光虫」は自分の青春のJ-POPを意識していて、「加爾基 精液 栗ノ花」のときの(椎名)林檎さんの、ミステリアスで切ないんだけど、グチャグチャな感じ。
ギターの長田は「たまゆら」について、
イントロのギターのファジーな感じ、サビ裏の歪んだサウンドでメロディを弾くのはWeezer(Thank God for Girls)をイメージ。実はラストサビ直前の1小節半に効果音的ギターが5、6テイク入っています。
ベースの後鳥は
シンプルかつ口ずさめるようなフレーズができたらいいなというのはずっと考えていて。「夜風とハヤブサ」はもともと全然違って、途中からスラップにしてすごくよくなったんですけど(中略)口ずさめて、なおかつ曲に馴染むようなフレーズをたくさん入れたいというのは意識していました。
(ナタリーインタビューより)
楽曲に対する想いは演奏の端々に表れている。
アルバム『夜行秘密』でその表現力が分かりやすく出ているのは『晩生』だ。
この楽曲は戦争がテーマになっている。
イントロ、アウトロはグランジ感ある荒っぽいサウンドで、テーマともしっかり結びつく。アウトロでは加速的にカオスを極めていき、最後には残響を残して終わっていく。
『晩生』の章に、戦争がモチーフの夢が用いられたのは、このことが起因しているように思う。
やがて夢の話だった戦争は、現実のネットの炎上と重なり、主人公が感じている何とも言えない居心地の悪さが伝わってくる。
おわりに
この小説は賛否が大きく割れている。生粋のindigo la Endファンには独自性が強すぎるのだろう。
彼らが求めていたのは恐らく、歌詞を補完してくれる物語だ。真っ暗な夜に、ファンたちの目を盗んで、ここでは無い新たな場所を求めて逃げ出そうと試みているようにも思える。
ファンを貶しているのではない。indigo la Endがバンドスタイルを貫くように、ベストアルバムをインストでリリースしたように、カツセにも、1作目とは異なる世界に飛び出したい、音楽のPRの一部だと思われたくないという反骨精神があったのだ。
そういう意味ではカツセの小説からも音楽愛の片鱗が垣間見えた。
どちらか片方がさらにポップだったら、こんな気持ちにはならなかっただろう。
『夜行秘密』は極めてバンド的で、ロックな作品だと思う。
この記事を読んだあなたにおすすめ!
 Creepy Nutsと“たりないふたり“、相思相愛の関係性を徹底解説!
Creepy Nutsと“たりないふたり“、相思相愛の関係性を徹底解説!



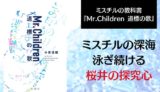
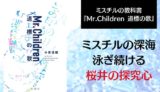
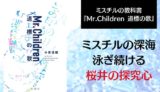
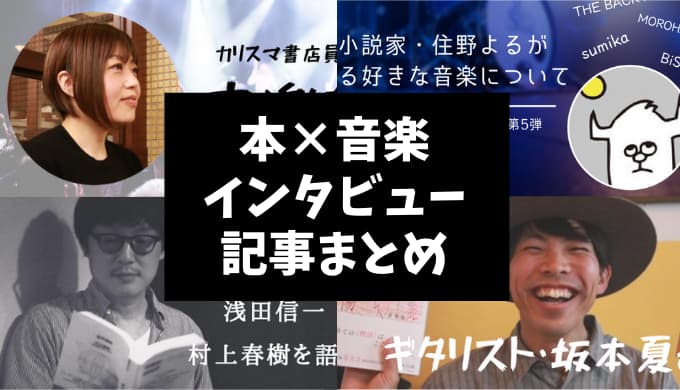




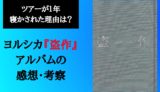
書き手にコメントを届ける