『夜行秘密』はindigo la Endのアルバムであり、カツセマサヒコの小説でもある。
同名アルバムを聴いて文字を紡いだという小説はindigo la Endの楽曲観を超えて独自の物語に昇華されている。
音楽と重なる部分と独立した部分が共存した、カツセマサヒコ2冊目の書籍『夜行秘密』を掘り下げていく。
目次
小説『夜行秘密』のあらすじ
物語は彼氏からのDVを受けて傷付いた岩崎と、母が不倫していることを知る高校生、松田の出会いから始まっていく。
駅の待合室でたまたま一緒になり、「帰りたくない」という気持ちから2人とも何本も電車を見送る。
やがて松田は岩崎に声をかけ、交流が始まる。
映像作家として人気の宮部あきらはストイックな仕事人間だ。仕事が出来ない人間を嫌い、クリエイティブに欠けるものを嫌う。
そんな彼の元に、新人バンドのブルーガールからMV製作の依頼が届いた。SNSから突如ブレイクした彼らの依頼を宮部は承諾した。
そのオリエンの帰りに、以前共に仕事をした映画プロデューサーに誘われ、ナイトクラブに向かう。
宮部はバーテンダーを自宅に連れ込むための戦略を考えていたところで、並んでいた女に声を掛けられた。
富永早苗と名乗るその女は宮部と近いものがありそうだった。話が盛り上がり、自宅に連れ込んだが、服を脱がしたところでやんわりと断られてしまう。
しかし、一度だけキスをした。そのキスで相性が良いことを宮部は直感する。富永も気付いたみたいだった。
2人はその瞬間、確実に戸惑って、少し怖がっていた。
少なくない数の異性と関係を持ってきたはずなのに、たった一度唇を重ねただけで、全身に電気が走るような感覚は宮部にとって初めてだった。
翌日、ブルーガールからデモ音源が送られる。試聴した音源は宮部にとって劣悪に思えた。
「耳どうかしてるって。こんな曲のMV作ってもダセぇもんしかできねえよ。俺に恥かかせるなって言ってるじゃん。なあ。得意先との適当な伝言ゲームさせるために雇ってんじゃねえんだよ。頭使えよ、少しは。顔ばっかり良くてもキャバ嬢とかにしかならねえだろ? それとも枕営業でもしてくれんの? なあ」
とマネージャーに怒鳴り散らしてしまうほど宮部は苛立った。そのタイミングで富永から連絡が届く。
やがて宮部や富永は、岩崎や松田と接近していくのだった。
本書は14の物語で構成されており、章ごとに主人公が切り替わっていく。
それぞれが迷い、悩み、嫉妬し、決断をしては、傷つき合う。激しい後悔が描かれた、鮮烈なラブストーリーである。
『夜行秘密』で描かれた想定外の物語
予想外の飛び方をする小説だった。
作中にはネットの炎上にフォーカスした描写があり、それが物語の鍵となっているが、楽曲を起こした小説に炎上が入ってくるとはアルバムを単体で聴いていた時点では全く想像できなかった。
indigo la Endは恋愛ソング、それも失恋の名手である。アルバム『夜行秘密』の中でも、それが中心として描かれているのは明確だ。
ジャケットはフランス映画のポスターがモチーフで、このアルバム自体は情景が脳裏に浮かぶ映画的な作りになっている。
つまり、楽曲を聴いていれば物語が浮かんできて何となく、この空路で進んでいくと、ある程度予想できるのだ。
しかしページを捲るにつれて、その範疇から少しずつズレていき、予想していた着地点を超えて飛び続けていく。
音楽と調和する部分と、それを拒む部分のバランス
もちろん楽曲の歌詞も小説に登場してくる。
アルバム『夜行秘密』以外の、彼らの楽曲を彷彿とさせる言葉が登場し、ファンサービス的な側面はしっかりと存在している。
それらのワードが”満を辞して”の登場ではなく、あくまでも自然と、さらりと差し込まれているため、詩を無理やり小説にしたような違和感はない。
誰かが抱えた憎しみや悲しみが誰かに伝播し、連鎖的に繋がっていく。
前の章(曲)の影響を受けて、展開されていく様子は”アルバム”という枠組みとも重なる。
作品に出てくるバンドのブルーガールにも『自転車』という楽曲がバズった描写があるが、indigo la EndもTikTokでバズり、『夏夜のマジック』が桁違いに再生されている。
アルバムではなく、曲単体でバズっている様が今の音楽シーンをリアルに描いているとも言えるし、全編が呼応し合い、読み切って始めて繋がる点に、コンセプトアルバムのようなものを感じる。
アルバムに収録されている曲順と本書での曲順は大きく異なる。
出発地が『夜行』、着地『夜の恋は』である点だけは共通だが、それ以外は物語に沿った曲順になっている。
まるで物語のBGMとして、後から楽曲が作られたような、絶妙な曲順だ。
小説の曲順でプレイリストを作ってみても面白いかもしれない。
小説は『夜行』、『左恋』、『夜風とハヤブサ』、『フラれてみたんだよ』、『夜漁り』と続き、『夜行』から『フラれてみたんだよ』にかけては比較的楽曲のイメージ通りに展開されていく。
大きく変化を遂げていくのは『夜漁り』だ。
会えない
もう会えない
夜を漁るあいにくの御心で
燃えない
もう超えない
恋はそこに寂しく転がってる
楽曲では切ない別れが描かれており、本書でもその部分は描かれているが、その上で、ブルーガールと宮部の対立関係がメインとして描かれている。
この関係の小さな歪みが、やがて小説の流れを大きく変えていく。
”カツセマサヒコ”といえば…を打ち破る、小説にとっても、彼にとっても、ターニングな章である。
ネット社会の良い面を切り取ると同時に、悪い面もしっかりと切り取った、皮肉的でリアルな作品である。
社会的弱者が自分よりもさらに弱い者を見つけ、適当な理由を正当化してフラストレーションを発散させる。
本書で描かれている、被害者が別の被害者を生む連鎖は、アルバムと大きく乖離してはいるが、作品として読み応えがある。
バンドに近い感覚で呼応するindigo la End×カツセマサヒコ
このコラムでは今までにも音楽と本について記述してきたが、今回の作品はそれらともまた異なる。
例えば、YOASOBI『夜に駆ける』は原作の小説『タナトスの誘惑』を音楽に落とし込んだもの。本作と近いものがあるが、コラボではなく、『夜行秘密』とは真逆のやり方である。
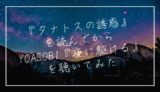 小説『タナトスの誘惑』を読んでからYOASOBI『夜に駆ける』を聴いてみた
小説『タナトスの誘惑』を読んでからYOASOBI『夜に駆ける』を聴いてみた
住野よるとTHE BACK HORNのコラボ、『この気持ちもいつか忘れる』はTHE BACK HORNと共作だ。住野よるが書いたあらすじにTHE BACK HORNが曲を書き下ろし、さらに書き進めるという手法をとっている。
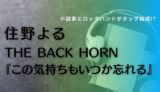
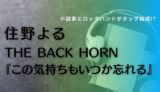
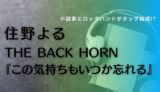
クリープハイプの『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』を小説に落とし込んだ副読本『信じていたのに嘘だったんだ』はボーカルの尾崎世界観が自分たちで作った曲に、自身で小説を書き下ろしたもの。
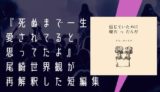
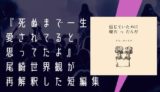
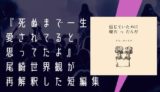
『夜行秘密』は完全パッケージとして出来上がったアルバムに、カツセが独自の解釈で物語を彩ったものである。
乱暴な言い方をすれば、バンドが作った音源を、全く土俵の違う人間がリミックスしているような、不思議な関係性の上に作品が成り立っている。
内情を知らないからこそ、想像の斜め上のもの作り出せる可能性がある。
『夜行秘密』はindigo la Endとのコラボ小説ではあるが、共著ではない。
互いに異なる考えを持っているが、同じものを扱う。他人の気配が混ざるからこそ面白い。
それは”バンド”というスタイルにも同じことが言える。
一人ひとりにバックグラウンドがあり、大なり小なり音楽性の違いがある。発想の掛け算でアイデアを膨らませたり、逆に削ぎ落としたり、バンドという小さな社会で起きた刺激が音となり、作品の深度を深める。
人それぞれにある考えのズレこそが、互いの魅力を相乗効果的に引き出すマジックではないだろうか。
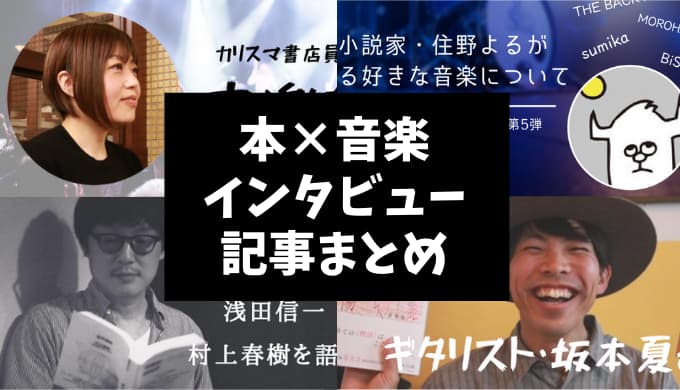



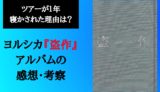
書き手にコメントを届ける