『OTOGIBANASHI』は5つの歌と5つの小説を一つにまとめた作品である。母体となるのは、いきものがかりの水野良樹が2019年に始めた「HIROBA」という企画。”考える場、つながる場、つくる場”をより豊かにするという実験的なコンセプトだ。
今回「HIROBA」のリスタートに合わせて始動したのが『OTOGIBANASHI』である。トーク番組やエッセイなどもプロジェクトの一環であり、音源もリリースされている。1stシングルでは水野が敬愛する小田和正とコラボし、2ndシングルは同世代である高橋優を迎えた。編曲はいきものがかり作品ではお馴染みの亀田誠治と、布陣こそ豪華であるが内容としては実験的な事柄が多い。
水野がJ-POPど真ん中のいきものがかりとは異なるアプローチでポップスを奏でた『OTOGIBANASHI』について解説していく。
こちらの記事もおすすめです!
 いきものがかり×亀田誠治『今日から、ここから』の背景を読む
いきものがかり×亀田誠治『今日から、ここから』の背景を読む



『OTOGIBANASHI』の中で、「最もポピュラーな作品」と「最も振り切った作品」を紹介!
『OTOGIBANASHI』には個性豊かな面々が参加している。ドラマ、映画でお馴染みの俳優から、TVでは見かけずとも音楽好きなら知らない人はいないアーティスト、書店でよくみる作家など。この章では、そのうち2つを物語のあらすじを含めて紹介する。
『OTOGIBANASHI』に収録されている5つの短編小説とそれに当たる楽曲は以下の通り。
短編小説
- 『みちくさ』彩瀬まる
- 『南極に咲く花へ』宮内悠介
- 『透明稼業』最果タヒ
- 『星野先生の宿題』重松清
- 『Lunar rainbow』皆川博子
楽曲
- 歌唱伊藤沙莉、アレンジャー横山裕章の「光る野原」
- 歌唱坂本真綾、アレンジャー江口亮の「南極に咲く花へ」
- 歌唱崎山蒼志、アレンジャー長谷川白紙の「透明稼業」
- 歌唱柄本祐、アレンジャートオミヨウの「ステラ2021」
- 歌唱吉澤嘉代子、アレンジャー世武裕子の「哀歌」
作詞は小説を書いた作家が手掛け、楽曲の大本は全て水野良樹が担当している。
最もポピュラーな組み合わせ「綾瀬まる×伊藤沙莉×横山裕章」
この中で最もお茶の間に近い組み合わせは、綾瀬まる×伊藤沙莉×横山裕章のものだろう。
アレンジャーの横山はYUKI、ビッケブランカなど様々なアーティストに楽曲を提供しており、吉澤嘉代子のツアーにはキーボードとして参加している。
綾瀬まる『みちくさ』のあらすじと、作詞を担当した「光る野原」の感想
『みちくさ』のあらすじは次のようなものだ。
近くで昔好きだった相手が死んだと聞きつけ、会いにいくことにした。
主人公は病気で亡くなり、相手は交通事故。不本意な死と生きる苦しみを憂い、転生を拒絶する相手。その手を引き、消える場所を探しに2人で”道草”を食っていく。
この小説は「むかし、ずいぶんむかしに好きだった相手が、近くで死んだようなので、見にいった。」という衝撃的な一文で始まる。
死後の舞台でありながら、決して暗くはない”道草”は独特な雰囲気を持ち合わせていて、引き込まれる。
綾瀬まるは2010年にR-18文学賞で読者賞を受賞。『くちなし』は直木三十五賞候補、高校生直木賞を受賞している。2021年11月には最新作『新しい星』が発売された。
作詞は綾瀬まるにとっては初めての経験だったが、語感もよく、ポップスの歌詞として全く違和感のない。
歌詞中に登場する”私の魔物”と、”光る野原”が天使と悪魔のように感じられ、主人公の心の動きが分かりやすい。
「光る野原」を歌う俳優、伊藤沙莉の特徴
「光る野原」を歌うのは伊藤沙莉。
距離感を感じさせない人間性で、コミカルな演技に定評があるが、映画『ボクたちはみんな大人になれなかった』ではヌードも公開し、親しみやすさだけでは無い一面を覗かせた。
ハスキーでときに不安定な伊藤の歌声は、人間の生々しさを伝えてくるようでもあった。美しいだけでも残酷なだけでもない、作品に滲む二面性を巧みに表現している。
ミュージックステーションにも出演し、”俳優”として知っている人たちをその歌唱力で驚かせた。
最も振り切った組み合わせ「最果タヒ×﨑山蒼志×長谷川白紙」
逆にお茶の間から最も遠く、シーンに最も近いのは最果タヒ×﨑山蒼志×長谷川白紙の組み合わせではないだろうか。
崎山蒼志は「風来」を水野と共作していたり、「感丘」で長谷川白紙とコラボしている。
また、Little Glee Monsterの「夏になって歌え」は水野が作曲し、最果タヒが作詞を担当。それぞれの関わりはあるものの、全員が関わりあうのは今回が初だ。
最果タヒ『透明稼業』のあらすじと感想
なんでも透明にする仕事を請け負う主人公が、相方の銅くんと一緒に様々なものを消していく。その中で主人公はある秘密に気付いてしまう、というのが物語のあらすじだ。
たった8ページの短い小説だが、透明と無は違い、見えないだけで確かにそこに存在することが小説にも歌詞 にも描かれている。
音源「透明稼業」は、﨑山蒼志のビブラートの効いた存在感ある歌声が活きる、物語同様に独特なサウンドだ。無機質なビートとサンプリングされた動物や赤子の声がアンバランスかつ、丁寧に積み上げられている。
プロデューサーの長谷川白紙とは?
かなり乱暴な言い方をすれば長谷川白紙は、現代音楽に限りなく近い大衆向けのミュージシャンである。
2016年頃よりSoundCloudなどのインターネットシーンで音楽活動をスタートさせた彼は、2018年に初の流通盤ミニアルバム『草木萌動』をリリースし全国デビュー。同年11月にリリースしたファーストフルアルバム『エアにに』は第12回CDショップ大賞に入賞した。
楽曲提供なども精力的に行っており、chelmicoの「ごはんだよ」の作曲・編曲、
KID FRESINOの「youth (feat.長谷川白紙)」の作詞・作曲・ボーカルを務めている。
ポップミュージックでは馴染みのないメロディーが多用され、親しみやすさは薄いかもしれないが、そのインパクトは強烈だ。そこに崎山蒼志の独特なハーモニーが混ざると、「斬新さ」と「人懐こさ」が絶妙に入り混じった不思議な音楽が出来上がる。
一方で、水野の作る楽曲は基本的に耳馴染みが良い。
それは”老若男女問わず楽しめるポップス”を目指しているからだろう。
歌声を主体とし、歌声を邪魔しない演奏で成り立っている楽曲は覚えやすく、つい口ずさみたくなる。その一方で、ポップスに飽きている人にとっては退屈なものになってしまう。この楽曲には、いい意味で”水野くささ”が無い。
作家とアーティストを刺激する巨大な広場
様々なアーティストが名を連ねて賑やかな分、ごちゃごちゃしているというデメリットもある。昨今の映画や音楽では、分かりやすいものがトレンドだ。その中で『OTOGIBANASHI』はなぜそうしなかったのか。
『OTOGIBANASHI』はジャンルの枠を超えた多くのアーティストが参加している。1つ1つの物語に小さなコミュニティが形成され、それが集まって街になっていく。
作品を解釈し合い、バトンを繋いでいく過程は、地の固まったいきものがかりの1人としての水野にとって、新鮮でかなり刺激的なものだっただろう。自分でやるわけでは無いからこそ、予想外な方に転がっていく面白さがある。
『OTOGIBANASHI』が意外と知られていない理由は?
魅力的な作品であることは間違いないのに、正直なところ、あまり知られていないように思う。
『OTOGIBANASHI』は作家、音楽家だけでなく、プロデューサーもハイライトとして挙げているため、見どころが多く、どこを見れば良いのか迷ってしまう。
企画の参加者が多ければ多いほど、情報が過多で全貌が分かりにくいというデメリットも孕んでいる。
年々分かりやすいものが好まれていく傾向を鑑みると、この情報量は時代の流れとは反しているのかもしれないと思う。
しかし、「広場」というニュアンスではかなりしっくりくる。
新橋のSL広場も渋谷のハチ公前広場も、多くの人が行き交い、人間関係が渦巻き、ごちゃごちゃしている。そういう観点からも「HIROBA」とネーミングしているならば、巨大な広場となり得るだろう。
まとめ
このプロジェクトに関わったのは、ここで名前が挙げられている人だけではない。ジャケットを手掛けた人、レコーディングスタッフなども物語の一端を担った者として挙げられる。
そして、これを読んだ人に繋がり、呟いた感想が誰かに繋がる。そういう意味では、『OTOGIBANASHI』は永遠に完結しないのかもしれない。
この記事を読んだあなたにおすすめ!






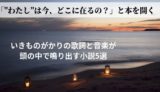
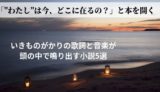
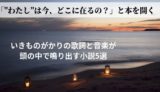
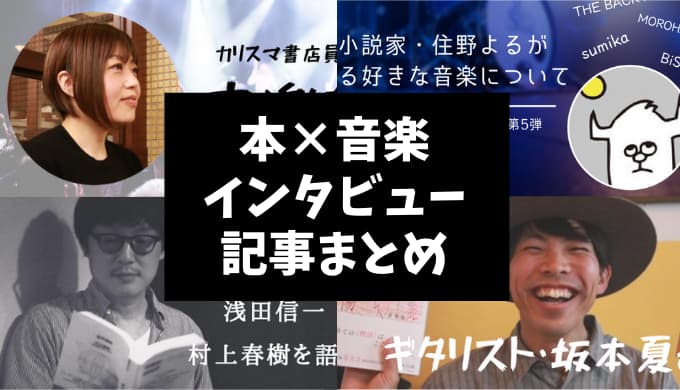
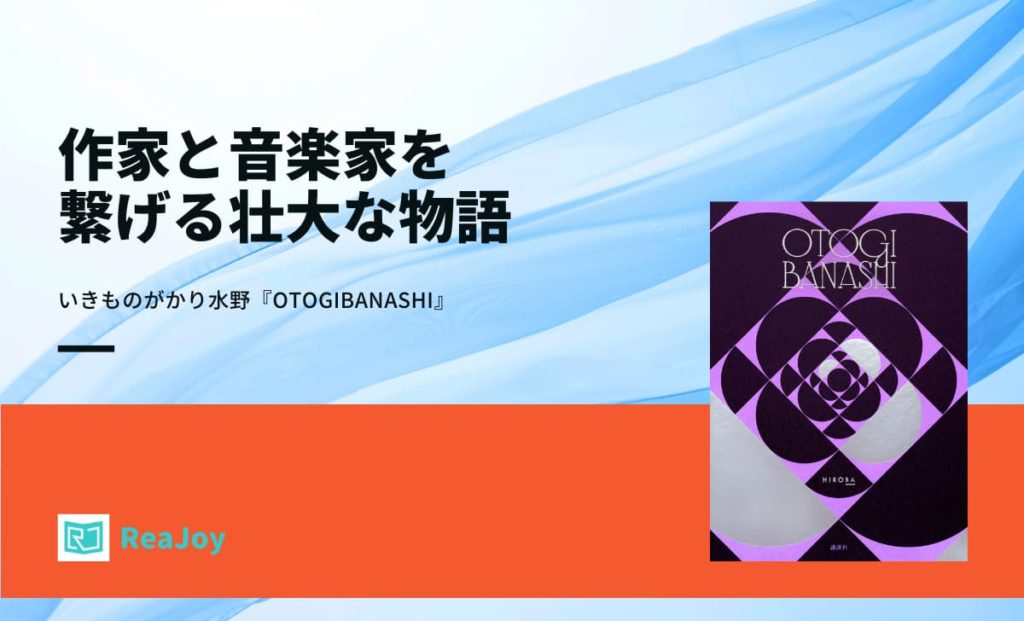



書き手にコメントを届ける